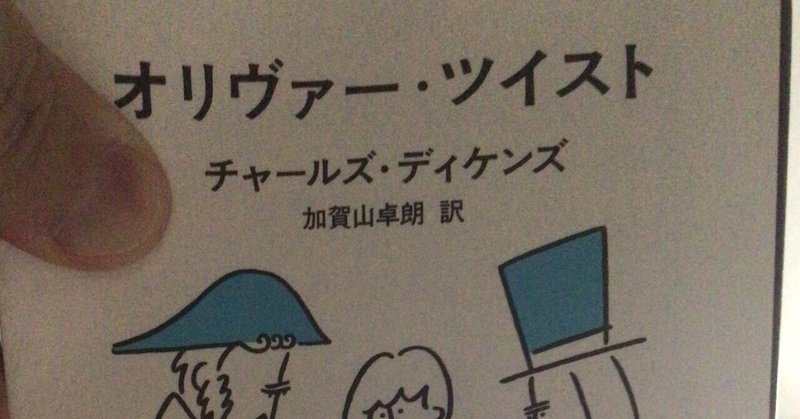
チャールズ・ディケンズ『オリヴァー・ツイスト』 1
俺たち前衛的なものに憧れた学生時代を経て、それらを批判する理論的なものを吸収しつつ、仕事をし出すとやっぱり疲れて、前衛からも理論からも離れてしまう。
そこで、大衆的なものにうまく着地できればいいんだけど、気持ちこじらせたまま政治的なもの、社会的なもの、あれやこれやと探しながら、ああでもないこうでもないと生きてきた。
別に本を読まなくても生活はできるんだけれども、何もしないと味気なく、刺激がない。脳が冬眠したみたいね。
本を読んでいるということを、人に対するコミュニケーションのチャンネルとして使っていた若い頃と違い、今は読んだ本を他者に提示する場などなく、自分で読みたいものを読めばいい。
もちろん、こういうWebの中で、不特定多数に読んだ本を提示してはいるわけだけれども、それはかつての対人コミュニケーションとは異なる。だから、やっぱり、読みたいものを読んでいいといえる。
でも、実は、読みたい物語なんて、もうないのかもしれないと思い、本屋の棚を眺めると、それでも毎年そこそこの分量の小説は出版されているし、読書習慣が衰退しつつあると言っても、それでもなお読むべき本はそれなりにあるように思われる。
と、まあ、そんな自問自答はここまでにして、理論的、前衛的なものに傾倒していたころには、19世紀の大衆小説家ですよねと、読んでもいないくせに読んだつもりになっていたチャールズ・ディケンズ。そもそも、それなりに長い小説ですからね。これを読みたくなって、今日を迎えた。
昔、某文学者のセミナーに3年間くらい参加していたときにみんなで読んだユゴーの『レ・ミゼラブル』。なげーよ、と思って、全然手に取らなかったものを、大人になって読むと、これがなるほど、面白い。
きっとディケンズも面白いんだろうという想定のもと、まずは、この間ちょっとした関係で購入せざるを得なくなった新潮の新訳『オリヴァー・ツイスト』を、読むことにした。
構成
全部で51章で構成されている『オリヴァー・ツイスト』。1章ごとにやっていったら、ネタも尽きてしまいそうなので、あらすじの紹介は、読んだところくらいまで、という形にして、気楽にやっていこうと思う。
それぞれの章に概括的な見出しがついているので、物語の中での位置づけのようなものは、読み手の方で考える必要はない。そういう親切さが、前衛的かつ理論的なワナビーにとってはむしろ有難迷惑だったのだけれども、もうそういう気持ちにならなくていいよね。呪いというのは、いつまでも、俺を縛るものになっています。
つい読みながら、新しいものを探そうとしてしまう、そんなモードな読み方はもうやめて、単純に物語を楽しみたいのである。なーんて、もうそういう場所には戻れないことはわかっているんですが、とにかく、ナチュラルにやっていきたいと思います。
あらすじ(1のみ)
救貧院で、オリヴァー・ツイストが生まれた。
死にそうだった。賢い医者だったら、速やかに処理されていたかもしれない。そうでなかったのが、オリヴァーの幸運だった。
母である若い女は、すでに生きる力を失いかけていた。
「赤ちゃんを見せて。それから死なせて。」
若い女は、赤ん坊の額にキスをして、死んだ。
若い女はどこから来たのかわからない。とにかく、遠いところから歩いてきたらしく、どこへ行こうとしていたのか、誰にもわからないという。
産婆の婆さんは、さっきから飲んでいた酒を飲み、赤ん坊に服を着せた。
オリヴァー・ツイストは、こうして孤児として生まれた。
たびたび使われて黄ばんだ綿布のローブに包まれると、彼は烙印を押され、札をつけられたも同然で、たちまちいるべき場所に落ち着いた──教区の子──救貧院の孤児──餓えた卑しい働き手──どこへ行っても叩かれ、殴られ──みなに蔑まれ、誰からも憐れまれることがない子になったのだ。
感想
暑いですね。
孤児というと、小さい頃の学童の友達だった勝浦(仮名)くんを思い出します。親がどちらも蒸発して、一人残された勝浦(仮名)くんは、泣きながら学童を後にし、施設へと移動していったことがありました。私は小学1年、勝浦(仮名)くんは2年、もう一人岡田くんというおそらくハーフの6年生でよく遊んでいました。
この3人には事情があって、単純に仲間はずれにされていた3人だったわけです。勝浦くんも一人になってしまいましたが、岡田くんはじきに卒業し、私も一人になってしまいました。
なんで私もこんなに遠ざけられているのかな、と思わないこともありませんでしたが、その理由を理解するのは後年。理解してみれば、ああなるほどという理由でした。岡田くんは、当時珍しいハーフでしたし、勝浦くんにはおそらく微妙な障害があったのでしょう。
3人で山にタケノコを取りに行った記憶があります。今の世の中では窃盗なのかもしれません。ただ、子どもすぎて、この竹林が誰の所有なのかはよく分からず、そこに出ていたタケノコを掘り出して、一つ拝借してしまいました。
勝浦くんも、岡田くんも、私も当時の水準から言うと貧しい部類に入ったでしょう。岡田くん家も、ボロアパートに家族で住んでましたし、勝浦くんの家は、後年理解するのですが、新聞屋の2階を間借りしてしたものでした。その配達人だった勝浦くんのでオヤジが逃げ出したってわけです。
だから僕らは勝浦くんにそのタケノコを全部あげようとしました。そもそも三つに分けられないし、勝浦お前一番貧乏だから全部持ってけよとも言えない。岡田くんは最後そう言ったのかもしれないけど、勝浦くんからしたら、お前らだってまあまあ貧乏じゃんと言うはずでした。
いずれにしても、勝浦それやると言って岡田くんと一緒に、帰ってきちゃった。そんな記憶が残っています。
勝浦くんは底抜けに優しい人でした。生意気な一年生の私と一緒に遊んでくれ、揶揄っても寛大に許してくれました。彼が施設に行く日、岡田くんと一緒に見送りに行きました。何度も振り返って、泣いている勝浦くんの姿は、なんとも頼りなかったです。岡田くんと帰りに、ああアイツ行っちゃったな、とトボトボ歩きましたが、その後も岡田くんは陰口を叩かれる私を庇ってくれました。
私も素質としてはその後不良グループに入ってもおかしくないような状況でしたが、優等生と不良の二極の間に、岡田くんや勝浦くんのようなニッチなカテゴリーがあるということがわかっていたので、従順と反抗の出来レースには興味が抱けなくなってしまったのです。ヤンチャなるものが最終的に更生することですべて許されると思っているじゃないですか。
とまあ、吠えてみたところで、『オリヴァー・ツイスト』読んでみたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
