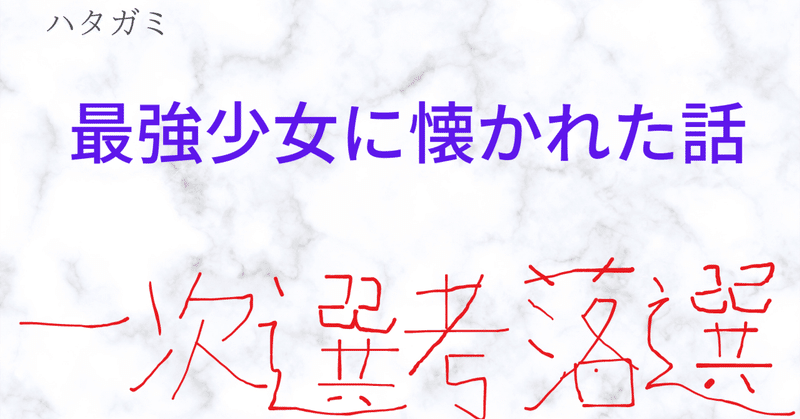
「最強少女に懐かれた話」ハタガミ|第36回後期ファンタジア大賞 一次選考落選
どうも、ハタガミです。今回は新人賞に落ちた作品を載せます。
そのまま載せていくつもりですので、すぐ完結すると思います。
取り敢えず序章と第一章を載せました。(1万2千字程度)
反省を兼ねて、皆さんの参考になれば幸いです。
序章
「んー……センセー、次いってください」
「待て、俺がまだ読んでる」
ソファでうつ伏せに寝転びながら漫画を読むのは、黒髪黒目の黄色人の男――早瀬 幸一(はやせ こういち)だ。そしてその上には、一人の華奢な赤毛の白人少女が同じくうつ伏せで乗っかっていた。
「というか、いつまで乗ってるんだ? 降りろよ」
「やです」
幸一は少女とソファにサンドイッチ状態だが、少女はあまり重くないらしく、窮屈そうな様子はない。
何せこの少女――ミリアム・エイダンは、まだ十二歳の子供だ。
人種は違えど、傍から見れば親子に見えるだろう。
だが、二人の関係は少々特殊だった。
「奴隷ならもうちょっと主人に気を遣うべきだと思うぞ?」
「私はセンセーと一緒に読みたいんです」
「……生意気なやつめ」
そう、二人は主従関係なのだ。
だが奴隷とその主人とは思えない程に、二人はフランクな距離感だった。
幸一は漫画のページをめくりながら呟く。
「最初はあんなによそよそしかったのに、図々しくなりやがって」
「……センセーが、そうさせてくれたんですよ?」
そう言ってミリアムは、幸一の首元に顔を埋めて体をこすりつける。
「すりすりするな。……鬱陶しい」
「でもセンセー、女の人にこうされたいんでしょ?」
「アホか。お前は女じゃねぇよ、ただのガキだ。……つーか、どこでそんなこと覚えた」
「センセーのベッドの下」
「……」
幸一は気まずそうな顔をする。
その横顔を見て、ミリアムは微笑んだ。
「ふふっ」
「おい、響子には内緒だぞ? また俺が怒られる」
「何が内緒ですって?」
そんな仲睦まじい二人に、声がかかる。
「……」
幸一は気まずそうに漫画でその女性の視線を遮る。
「まぁそれは後で問い詰めるとして……もうお昼ですよ。二人とも」
まるで母親のような小言を言うのは、メイド姿の黒人美女――真田 響子(さなだ きょうこ)だ。
今はその上からエプロンをしており、どうやら料理中らしい。
「昼食ができていますから、顔を洗ってきてください」
「……別にこのままでよくね?」
響子は幸一に近づいて、子供を諭すように指を立てる。
「先生? あなたはもう少しミリアムの保護者としての自覚を持つべきです」
「保護者じゃなくて主人なんだし、別にいいだろ」
ふてぶてしく寝ころんだまま告げる幸一に、響子は手刀を振り下ろす。
「こら!」
「あだっ!?」
ちなみに響子は元軍人なので、とても痛い。
まるで分厚い本の角で殴られたかのような衝撃に、たまらず幸一は漫画を落とす。
「いってぇ……!」
「センセー、大丈夫……?」
ミリアムは心配そうに、幸一の頭を撫でる。
「ちゃんと聞いてください、全く……今日はミリアムと買い物に行く約束をしていたじゃありませんか」
立場的には響子は幸一のメイドなのだが、響子は強気に説教をする。
「あぁーそういや、んなこと言ってたな……」
「センセー、行くの……お嫌ですか?」
明らかに面倒くさそうな顔をする幸一に、ミリアムは不安そうに聞いてくる。
その顔は、主人の気が変わったことを恐れる、奴隷の顔だ。
「……先生?」
その顔を見た響子は、釘を刺すように手刀を構える。
辛うじて笑顔だが、目が笑っていない。
「ふ、ふん……まぁ、約束だしな。ついてってやるよ。……だから叩くな、マジで」
幸一は両手で頭部をガードしながら、焦ったようにミリアムに返事する。
「……分かったら、早く身支度をしてください。ミリアムもですよ。降りなさい」
「はーい」
ミリアムは返事をして、幸一の背中から降りる。
「えへへ……」
そして嬉しそうにトタトタと洗面所へ向かう。
「……ったく、元気なやつだ」
そんな歳相応の姿のミリアムを見て、幸一はため息をつく。
「……よかった」
一方、響子は心から安堵したように目を細めていた。
「あん?」
「ふと、出会ったときのことを思い出していました……」
「あぁ……まぁやんちゃだったな、あいつ」
傍から見れば、三人の姿は奇妙に映るだろう。
黄色人の主人に、黒人のメイド、そして白人の奴隷。
そんな三人が家族のように暮らしている。
「最強の少女兵を、やんちゃなんて言えるのは先生ぐらいですよ。……でも、ちゃんと先生に懐いてくれて、安心しました」
「そう、だな……」
あの頃のミリアムでは、あんな無邪気な笑顔はあり得なかった。
「……俺も不思議だよ。……なんでこんなに懐かれてんだか……」
幸一は、ミリアムと出会った頃を思い出す。
第一章 最強少女兵がやってきた話
一九七五年。アメリカ合衆国、カルフォルニア州。
都心からは少し離れた街の一角に、幸一は屋敷を構えていた。
門扉にはローマ字で「HAYASE」と書かれた看板を吊っており、門扉を潜ると広々とした芝生が広がる庭の中に舗装された歩道がある。歩道は屋敷の玄関に繋がっており、それだけで金持ちの家というものを認識させる。
この屋敷は、マンションのような直方体の上に方形屋根がついており、豪邸のような見栄えは無いものの、中の広さを十分に感じさせるつくりだ。
屋敷の中は、調度品や美術品は一切見受けられず、玄関から屋敷の中心を通る長い廊下は、カーペットすらない閑散とした光景で、家主の合理的な性格が見て取れる。
廊下は各部屋に繋がっており、最奥には二階へ続く階段が見えた。
「ありがとうございます……! 先生!」
幸一は玄関から見て一番手前の扉に位置する部屋、応接室で三人の客と話していた。
今はスーツ姿であり、白のブラウスの上から青いネクタイを締めている。ワックスで黒の短髪を綺麗に塗り固めており、誰が見ても優秀なビジネスマンの恰好をしていた。
この応接室は扉から見て右手に幸一用のソファがあり、左手に客用の長いソファが設置されている。向かい合う二つのソファの間には書類の散らばるガラスのローテーブル、奥には縦長のキャビネットが置いてある。そしてこの部屋も、それ以外の家具や調度品は一切ない。シンプルなつくりの部屋だ。
客用のソファには、大人と見間違う程の体躯をした少年と、その両親が座っていた。
「息子が先天性巨人症と診断されたときはどうなることかと思っていましたが……先生がいてくれて本当に助かりました……!」
両親は必死に幸一への感謝の言葉を送っていた。
「いえ、礼には及びません。子供は平等にチャンスを与えられるべき存在です。そして子供の未来を守るのが、大人の務めですから」
幸一は実に爽やかな笑みで対応している。
目の前の少年は、先天性巨人症という奇病にかかっていた。僅か十歳の子供だというのに、身長は既に百七十センチを上回る。しかし顔だけは歳相応の童顔で、アンバランスな見た目が彼を見る者に絶えず不快な違和感を与える。また顎や手先が過剰に発達したせいで妙に太く、歪な輪郭をしていた。
そんな少年に、幸一は特効薬を打ち込んだのだ。
「カリフォルニアに、奇病難病を専門とするアジア人の薬剤師がいるとは聞いていましたが、まさか本当に治せるとは……町のどの医者も相手にされなかったというのに」
「あはは……大したことはありませんよ」
愛想よく笑いながら、幸一は二回手を叩いた。
すると程なくして、扉が開かれる。
入ってきたのは、響子だ。
「「「……」」」
その姿に、親子三人は息をのんだ。
理由の一つは、響子は見る者を圧倒する絶世の美女だからだ。黒人特有の抜群のスタイルでありながら純白のエプロンを豊かな乳房が押し上げ、団子に結い上げた黒髪はフリルのついたメイド服とマッチしており、否応なく周囲の視線を惹きつける。
しかしそれ以上に目を引くのは、彼女に備わる凶器。
すらりと伸びる美脚にはスパッツを履いており、その上から両の腿にホルスターを巻いている。ホルスターには拳銃とナイフが刺さっており、それ以外にもベルトや袖など、服の合間にちらりと見える凶器の数々。
淑女めいた所作から伝わる、優秀な仕事人の気配。運動能力の高い黒人であることも含め、親子三人は響子を見た瞬間に響子との戦力差を理解した。
「響子、会計を頼む」
「はい」
ローテーブルに散らばる書類を整理して、響子は手早く領収書を作成する。
「……では、こちらへサインをお願いします」
「はい……え」
響子の差し出した書類に、サインをしようとした父親が固まった。
見つめるのは、その数字だ。
「あの……これ、請求額……間違っていませんか?」
「ん……?」
父親の言葉に、幸一は書類を見る。
書類に記載されている請求金額は、約二万ドル。
この時代のドルは、一ドル約三百円ほどだ。つまり、単純計算で、六百万円もの治療費を請求しているのだ。
ぼったくりを通り越している金額に、父親は冷や汗を垂らす。
「いえ、この金額で間違いありませんよ」
「そ、そんな……たかが薬にこんな金額、どう考えてもおかしいでしょう……!」
納得のいかない父親は取り乱したように抗議する。
「いえ、この金額で間違いありません。お支払いは現金、カードの他にローンも組めますが、どういたしますか?」
先程の人の良さそうな笑みはどこへやら、幸一はどこまでも冷徹に話す。
「っ……」
幸一の事務的な対応に、父親は歯を食いしばる。
「父さん……別に無理しなくていいよ」
「あなた、払うべきよ。彼以外にこの子を治せる人はいないわ」
「だが……くっ……!」
この時代、一般家庭で二万ドルを支払えるのはそう多くないだろう。
(……全く、この人は……)
家族のドラマが繰り広げられる中、響子はため息をついた。
「……お支払いが難しいようでしたら、私が立て替えましょうか?」
「……へ?」
思わぬ申し出に、三人は固まる。
「……おい」
その提案に、幸一は不快そうに響子を睨む。
だが響子は幸一の視線を無視して、親子に笑みを向ける。
「全てとは言えませんがそうですね……三割程度ならば、私個人が治療費を立て替えることなら可能です」
「い、いいんですか……!?」
背に腹は代えられず、父親は縋るように響子を見る。
響子は少年を見て、安心させるように微笑んだ。
「はい……子供の未来にこそ、金銭は使われるべきですから……」
「あ、ありがとうございます! これならローン決済で、支払い可能です!」
響子は嬉しそうに微笑んで、請求書の金額に射線を引く。
そしてキャビネットから新たに領収書を取り出した。
「かしこまりました。それでは手続きしますので、改めてサインをお願いします」
「はい……! ありがとうございます!」
響子は領収書に書き込んでいく。
そして会計が終わり、無事に請求書も作成して、親子は幸一の屋敷を出た。
「ありがとうございました!」
「お大事に」
笑顔で親子を見送った響子が、屋敷へ戻る。
「……行ったか」
「はい」
「ふぅ……はぁ~あ~……つ~かれた」
廊下で大きくため息をついてから、幸一はネクタイを緩めて、緩慢な足取りでリビングへ向かう。
リビングは応接室の一つ奥の部屋だ。この屋敷の中央にあり、広々とした空間でキッチンと食卓、そして本棚がある。
中央のソファに、幸一はどかっと座り込む。
「つーか響子てめぇ、なんで立て替えたりなんかしたんだよ」
服を脱ぎ散らかしながら、子供の様に文句を垂れる。
これが幸一の、普段の姿だ。
「別に先生は金に困っていないでしょう。それに、立て替えたのは私です」
響子はそんな幸一に見向きもせず、キッチンで料理を始める。
「それに、あんな法外な金額はいけませんよ。いつも言っているでしょう。きちんと相手に寄り添った価格設定で、顧客を増やす努力をしないと……いつか誰にも薬を買ってもらえなくなりますよ?」
子供じみた幸一に、響子は母親のように小言を告げる。
「うるせぇなぁ。どうせああいう薬は俺以外、調剤できないんだからいいだろ」
そう。巨人症という指定難病の特効薬は、幸一しか作れない。
少なくともこの時代のアメリカでは幸一以外に作れる薬剤師はいない。
だからこそ、あれほどのぼったくりが成立していた。
「……というか俺、久々に仕事して疲れた。昼飯何?」
「二ヶ月に一度あるかないかの予約に、何を言っているんですか。……今日はコーンスープとローストビーフです」
「おっ、そうか。今日は肉の日だったな」
それを聞いた幸一は、嬉しそうな顔つきでシャツとパンツ以外を脱ぎ捨てる。
「いいですか? 薬が先生にしか作れないということは、先生にしか救えない命があるんですよ? いつも漫画読んで最新のゲーム機に大金を使ってぐ~たらしているんですから、せめて社会貢献を……って、聞いていますか?」
「聞いてなーい……あ、立て替えた分は響子の借金として返済してもらうからな」
階段を上りながら、幸一は一方的に告げて自室へ閉じこもる。
「もう……!」
聞き分けの無い幸一に、響子はつい愚痴る。
「……全く、先生は怠けすぎです……」
元軍人の響子がメイド兼ボディガードとして雇われてから早数年。幸一はずっとこんな生活を続けていた。
わざわざ日本の漫画を取り寄せては、読み漁る。さらには最新の家庭用据え置き型のゲーム機を購入して、それに入り浸る。おかげで幸一の自室はとうの昔にパンクして、空き部屋には一昔前の漫画や娯楽小説、ゲーム機が敷き詰められていた。
当然それらを整理するのは、メイドである響子だ。
たまに予約が入り、仕事をしたかと思えば、こうしてぼったくりで信じられない金額を稼ぐという体たらく。
幸一の不健全極まりない生活に、生真面目な響子は気が滅入る。
「はぁ……ん……?」
どうしたものかとため息をつきながら響子がテーブルにナイフとフォークを並べていると、突如として視界がぼやける。
膝をつき冷や汗を垂らしながら、響子は懐をまさぐる。
「う……! ……んっ」
響子はその急激な眩暈に苦しみながら、手早く懐から取り出した錠剤の薬を飲む。
すると眩暈は収まり、身体は落ち着きを取り戻した。
(……ふぅ……全く、先生だけでも手一杯なのに、この体は……)
響子が自分の持病に嫌気を覚えていると、インターホンが鳴らされる。
「?」
念のためキッチンの火を止めてから、響子は玄関へ向かう。
「やぁキョーコ。久しぶりだね」
響子が玄関のドアを開けると、そこには美青年が立っていた。
「……エヴァさん……お久しぶりです」
エヴァを見た響子は、驚きつつも嬉しそうな顔で歓迎する。
「あぁ。コーイチに合わせたい子がいるんだが……上がってもいいかい?」
そう言ってエヴァは、後ろを振り返る。
エヴァの後ろには、エヴァと手を繋いでいる小さな白人の子供がいた。
虚ろな目で、俯いている。
「……もちろんです」
響子はその子供のことは聞かずに、二人分の来客用スリッパを用意する。
「こちらです」
「相変わらず真面目だね。もっと雑にもてなしてくれてもいいのに」
エヴァは子供の手を引きながら、響子の案内に応じる。
「エヴァさん相手に、そうはいきませんよ」
響子はエヴァをリビングに案内した。
「おや、料理中だったのか」
「はい、先生の昼食を作っていました。……ソファでくつろいでいてください。昼食を用意しますので」
響子は食材を取り出そうとするが、エヴァはそれを止める。
「いや、昼食はいいよ。僕は長居するつもりはないんだ」
「……分かりました。では、先生を呼んできますね」
「あぁ。頼む」
響子が出て行ったタイミングで、エヴァはソファに腰かけた。
「ほら、君も座れ」
「はい……」
子供は俯いたまま、遠慮がちにエヴァの隣に座った。
程なくして、幸一は響子に連れられて階段を降りてきた。
「んだよ。客は帰ったんだろ? なんで服なんか」
どうやら響子が無理矢理スーツを着せたようで、堅苦しいスーツが嫌いな幸一の不機嫌そうな声が階段から聞こえる。
「……いいから、ちゃんと着て下さい。それから、社会人としての振る舞いをしてください。いいですね?」
「あん? なんでそんな……」
響子に手を引かれ猫背のままやってきた幸一は、リビングの入口でエヴァと目が合う。
「……やぁコーイチ、相変わらず元気そうだね」
「……エヴァか」
幸一はエヴァを見て一瞬固まり、うんざりしながらため息をついた。
エヴァは金髪のマッシュルームヘアに、輝く碧眼を持つ絶世の美青年だ。真っ白のスーツに包まれた九頭身の身体は彫刻のようなプロポーションを誇っており、その相貌は同性であっても直視すれば立ち眩みを起こす程整っていた。エヴァに見つめられた者は、否応なくエヴァに意識が釘付けとなり、思考が止まる。そんな魔性の美貌の持ち主だ。
「今日は君に用があってね」
「断る! 響子、昼食はよ」
「……用意はしますから、聞いてあげてくださいね」
響子は幼稚な対応の幸一に呆れながら、料理を再開する。
幸一はエヴァの言葉を遮りながら、ドカッと食卓に座る。
「……せめて用件を言わせてくれないか?」
「ダメだ! お前が持ってくる用件なんて、ロクなものがない。おい響子、昼食はよ」
「はいはい。ちょっと待ってください」
幸一はナプキンを首にかけながら、響子を急かす。
エヴァは仕方ないとため息をついてから、話し始める。
「……実はこの子を預かってほしいんだ」
幸一は無視を決め込もうとするが、不可解な言葉に座ったまま振り返る。
「……あん? この子?」
ソファは食卓に背を向けて配置されており、子供は幸一から死角にいた。
「ほら、立ちなさい。彼に挨拶なさい」
エヴァに言われて、子供はソファから立ち上がり、ぺこりと頭を下げた。
「……子供?」
「……ミリアム・エイダンです……よろしく、お願いします」
声から少女と判別できる子供――ミリアムは小さな声でそう言った。
「ミリアムはテロ組織の少女兵だったんだが、うちの部隊と衝突してね。そのときに捕虜として捕らえられた」
いきなり壮絶な経緯を聞かされて、幸一は顔をしかめる。
「少女兵……? なんだそりゃ」
「知らないかい? 少年兵の女性名詞さ」
「……マジかよ」
冷戦中とはいえ、二度の世界大戦が終わったというのに、未だにそんなものが存在していることに幸一は驚きを隠せない。
「それで、ミリアムはすごい能力を持っているんだ」
「聞きたくない」
「人体発火現象……君なら知っているだろう?」
幸一はその言葉に納得したように、少女の姿を見た。
「……ふん。そうかよ」
白人特有の雪のように白い肌だが、顔を含めて見えている体表には無数の火傷の跡がある。また毛髪と呼べるものが一切存在しておらず、頭部には焦げ付いた黒い産毛のようなものがいくつか点在するだけだ。その下にはパープルの瞳を持ち、今は見るからに安物と分かる灰色のワンピースと運動靴だけを身に付けていた。
言われるまでもなく幸一は確信した。
ミリアムの抱えているものは、病院では治せないと。
「……俺にこいつを治せと?」
幸一は面倒くさそうに頭をかきながらエヴァに尋ねた。
「いや、君にはミリアムを引き取ってほしいんだ」
「引き取る? ……なんでだよ」
幸一は子供が好きではないし、養育の心得など皆無だ。
そもそも幸一は社会人として目指してはいけない部類の人間だ。とても子供を預かれるような大人ではない。まともな親ならば、幸一に子供を近づけたくはないだろう。
エヴァはミリアムの頭に手を置いて、理由を話す。
俯いたエヴァの顔つきは、涙を誘うように感傷的だった。
「この子はね。最強の少女兵なんだ」
「……ふーん」
「普通は子供の兵士なんて半年持てばいいくらいの、消耗品だ。だがミリアムは、戦場で何年も生き永らえてきた。敵を殺す日常に、適応してしまった。……それほど彼女の【人体発火】は人殺しに有用過ぎたんだ」
「ふーん」
「君は戦場を離れてから、色んな娯楽を知っただろう? 今を満喫しているだろう? だからその世界を、ミリアムにも知ってほしいと思ったんだ」
「ふーん」
「……って聞いてるかい? コーイチ」
同じ返事しかしない幸一に、エヴァが怪訝に思い、顔を上げる。
食卓では、幸一が山盛りのローストビーフにフォークを突き立てていた。
「んむ……聞いてなーい」
暢気にローストビーフを食べながら、幸一は呟いた。
「コーイチ……!」
本気でどうでもいいような声色に、流石のエヴァも少し声を荒げる。
「んむ。響子、わさび取ってくれ……つーか……んっ……嘘だろ? それ」
「え……?」
だが、唐突なその言葉にエヴァは固まる。
「何年の付き合いだと思ってんだよ。お前がそんなことでガキを助けるわけないし、そんなことで俺が動かないのも、お前は知ってんだろ?」
「……」
幸一の言葉に、エヴァは少し固まっていたが、やがて肩を震わせる。
「……ふふ。そうだったな。君はそういう男だ」
先程の感傷的な空気はどこへやら、エヴァは無邪気に笑って白い歯を見せる。
「分かったら帰れよ。俺はもう『軍用薬剤師』じゃねぇんだ」
幸一はそう言って、ローストビーフを三枚まとめて口に入れる。
そんな幸一に、エヴァは立ち上がって歩きながら話し始める。
「すまなかった、コーイチ。本当の事情は、この捕虜をどうするかで話し合いになってね。本来、テロ組織の捕虜は情報を吐かせればその場で処刑するか、警察へ引き渡すのが通例だ。だがミリアムには面白い能力がある。兵士としての才能もね」
エヴァの口調は、まるで新しいおもちゃを見つけたかのような、どこまでも無邪気な好奇心に満ちていた。
「……だから、ここで警察に渡すのは惜しいと思ったんだ。幸いミリアムにはアメリカの市民権はない。どこにいて何をされても問題にはならない。だから君に託そうと思ったんだ。君なら、この子の能力を引き出せるだろう?」
そう言ってエヴァは、幸一の肩に手を置く。
「……相変わらずだな。社長」
エヴァの幼馴染である幸一は、エヴァの好奇心の正体をよく知っている。
エヴァ・ヘンリー・メイデンホール。アメリカ最大級の財閥であるメイデンホール財閥の御曹司であり、アメリカ最大手の軍事警備会社『ソリッド・シールド』の社長。そして幸一の薬の、研究開発の出資者でもある。
彼は【特別】な存在が大好きだった。【特別】な力というものに、憧れのようなものを持っており、【特別】な人間が寄り集まる幸一のことを、誰よりも気に入っていた。
「市民権も無いから、ミリアムには人権が保障されることはない。雑用として使ってもいいし、コーイチにそっちの趣味があるなら、ミリアムをおもちゃにしても――
「ぶっ飛ばすぞ」
流石に聞き捨てならない言葉に、幸一がエヴァを睨む。
エヴァはやっとこっちを向いてくれたと言わんばかりに嬉しそうに目を合わせる。
「……ミリアムの【人体発火】は不完全だ。いつも自分の体ごと燃やしているせいで、火傷が絶えないんだ。それを何とかしてほしい。そして将来、我が社の兵士として雇用することになるかもしれない。そのために一般的な読み書きを教えておいて欲しい。……【人体発火】の安全運用と基礎教養の教育……この二つを頼みたい」
そしてずいっと顔を近づけてエヴァは幸一に頼み込む。
ふわりと香る香水の匂いを振り切るように、幸一はローストビーフを口に入れる。
「あむ……嫌だと言ったら?」
「君にキスして、口の中のローストビーフを頂くよ」
「んっ!? ゲホゴホっ! 響子! 水!」
幸一は酷くむせた。
ガシャン!
さらにはキッチンから、響子が皿を割る音が響き渡る。
「ご、ごめんなさい……はい、お水です」
顔を赤くしている響子が、か細い声で謝罪しながら、幸一に水の入ったコップを渡す。
「けほっ……相変わらずだな。ホントに」
エヴァはこの時代には珍しく、同性愛者であることを公表している男だった。
「……報酬は?」
「八万ドル」
羽振りの良さも相変わらずなエヴァに、幸一はため息をついてから告げた。
「……分かった」
その言葉を聞いて、エヴァはやはり無邪気に笑った。
「ありがとう! コーイチにならミリアムを任せられるよ」
「うるせーよ……あむ」
話はお終わりだと言わんばかりに、ローストビーフを頬張る幸一。
そんな幸一に、エヴァは笑顔のまま近づく。
「……それじゃあ僕は行くよ。またね、コーイチ。……チュッ」
そして唐突に、頬にキスをした。
「んぅっ!? ゴホッゴホッ!」
幸一は酷くむせた。
ドガシャンッ!!
さらには、響子が皿を割る音が響き渡る。
「す、すびばせん……」
鼻血を垂らしながら響子が、か細い声で謝罪する。
「それじゃ、バイバイ」
「て、てめぇ……!」
幸一を含め、たとえ同性愛者でなくとも、目も眩む絶世の美青年であるエヴァにキスをされるとほとんどの人は動揺するだろう。女性ならば失神することもある。
幸一とて、動揺せずにはいられなかった。
そしてエヴァは、満足そうな顔でリビングを出ていった。
「……お、お送りします」
響子はそんなエヴァを見送るために、急いで鼻血をふく。
色んな意味で騒がしかったエヴァが去り、少し静かになる。
「んく……ぷはっ。ったく、あのやろう……ん?」
幸一は水を飲んで落ち着いてから、気付いた。
「……」
ミリアムが、音も無く隣に立っていた。
「なんだ? 欲しいのか? まぁ響子のことだろうし、お前の分も作ってくれるだろうから、少し待って――」
幸一が暢気に話している最中、突如としてミリアムは動き出した。
「ふっ!」
ミリアムは幸一の持っていたフォークを奪い取り、幸一の手にぶっ刺した。

さらに流れるような身のこなしで、幸一の背後をとる。
「あだあああああむぐっっ!?!?」
間抜けな絶叫を上げる幸一の口を、ミリアムは後ろから手で塞ぐ。
「動くな、動けば殺す」
「んぅ……!?」
いきなりの脅迫に幸一は理解が追い付かない。
(テーブルにあったナイフ!? いつの間に!?)
だが首に当てられたナイフの冷たい感触が、脅迫が本気であると示していた。
「……お……おちおち、おちゆけ。早まるなよ……!」
口から手をゆっくり離された幸一は、ミリアムを宥めようと必死になるが、ほとんど言葉になっていない。
ミリアムは少女とは思えないほど低い声で、簡潔に告げた。
「要求は二つ。一つはあのメイドの女が帰ってくるまでに、私をこの場から逃がすこと。もう一つは、二度と私に関わらないこと」
「わ、分かっひゃ……!」
幸一は滝汗を流しながら、凄まじい速度で首を縦に振る。
ミリアムは幸一が嘘をついていないことを確信して、ナイフを首から離す。
「裏口から逃げるから、手伝え」
そして幸一の首を握りながら移動を始めようとした矢先、声が掛けられる。
「それはいけません」
いつの間にか、響子がリビングの入口に立っていた。
ミリアムはリビングの入口に背を向けており、背後を取られた状態だ。
瞬間、ミリアムはナイフを動かした。
幸一を人質として使うため、もう一度ナイフを幸一の首に当てようとしたのだ。
「っ!?」
だが、飛んできた包丁によって、ナイフは弾かれてミリアムの手から落ちる。
金属音を響かせながら、ナイフと包丁が転がっていく。
(動きを読まれた……!?)
ミリアムは冷や汗を垂らしながらも、即座に作戦を立て直す。
「食事中はお静かに」
「おい響子、遅いぞ! ぐえっ!?」
ミリアムは幸一の背中を蹴り飛ばす。
ミリアムの蹴りはとても少女とは思えない威力で、幸一を椅子から吹っ飛ばした。
そして幸一の座っていた椅子を片手で投げ飛ば――
「っ!?」
――そうとしたところを、響子に手首を掴まれた。
「大人しくしなさい」
ミリアムの前には、いつの間にか響子が立っていた。
凄まじい握力で、ミリアムの手首を握り締めている。
「くっ……はぁっ!」
鋭く吠えると同時に、ミリアムの腕が突如として燃え上がる。
【人体発火】。
人体発火現象。人間の身体が突如として燃え上がる現象。様々な学説が提唱されるものの、未だに完全に解明できていない正体不明の現象だ。瞬時に自分の腕力では響子の握力を振り切れないと悟ったミリアムは【人体発火】を発動した。
「っ」
熱反射。熱いものを触ったときに火傷をしないように、熱いものから遠ざけようと体を引っ込めてしまう人体の反射行動。
響子は突如として燃え上がったミリアムの腕から手を放してしまう。
同時にバックステップで後ろに下がる響子に、ミリアムは踏み込んだ。
「やぁっ!」
ミリアムの作戦は、肉弾戦。
【人体発火】を用いた格闘術は、戦場で武器が無くなっても、ミリアムを支え続けた。
(倒せなくてもいい……武器を奪うだけでも十分……!)
ミリアムは吠えながら渾身の肉弾戦を仕掛けようと、燃え盛る拳を繰り出した――刹那。
コンッ
「……?」
そのままミリアムは、顎を打たれて意識を失った。
「……ふぅ……流石は最強の少女兵」
とさり、と拳を振り抜いた体勢で響子がミリアムを抱き留める。
「素晴らしい状況判断です。まるで歴戦の兵士を相手にしているようでした……」
意識の無いミリアムに、響子は素直に賞賛を送った。
「先生? 大丈夫ですか?」
そして、先程から静かな主人の無事を確認する。
「……先生?」
「うぷっ……さっき食べたばっかだから……吐きそう……」
「……子供に蹴られた程度で、全く情けない……」
情けない主人の姿に、響子はため息が出た。
序章と第一章はこれにて終了です。
今見ると、主人公のピンチが全く存在せず、これでは読者が引き込まれないと反省しております。また、エヴァや屋敷の描写はカットしてよかったかもしれません。最初の戦闘で活躍したのも響子ですし、序盤から主人公をもっと掘り下げるべきでした。
これを改良して、他の賞に応募しようと思っています。
第二章からの物語も載せていきますので、よければ見て行ってください。
では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
