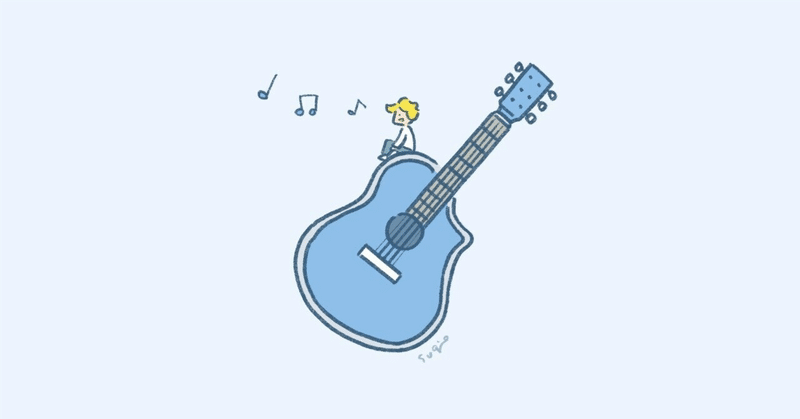
手話通訳者全国統一試験「ボランティア活動」2020過去問⑬解説〜ボランティア活動の特徴とボランティア政策〜
2020年度手話通訳者全国統一試験の過去問について、参考文献をもとに独自に解説をまとめたものです。
問13.ボランティア活動
ボランティア活動における変遷について述べています。下記の(1)〜(4)の中から正しいものを1つ選びなさい。
(1)1981(昭和56)年の国際障害者年を一つのきっかけとして、ボランティア活動は大きく広がりを見せたが、若者が中心であったため地域での高齢者分野の活動までは発展しなかった。
(2)1970年代以降一貫して進められてきた国のボランティア政策によって、ボランティアが医療や社会福祉現場での担い手として組み込まれることで、「豊かさ」の幅が広がっていった。
(3)国の指針や社会福祉審議会の意見具申による活動の奨励もあって、1998年(平成10)年には、特定非営利活動促進法が成立し、NPO及びその支援センターが相次いで設立・設置された。
(4)今日のボランティア活動の新たな特徴として、情報発信ツールの活用、拡大に加え、NPOやNGOなどの営利法人として発展していることがあげられる。
問題解説
(3)が正しい。今日のボランティア活動の特徴、ボランティアの理念や意義、社会福祉と政策の関連について整理しておきたい。市民が自主的で主体的に行うボランティア活動と、国・自治体が責任をもって行う福祉施策とは根本的に異なることも理解しておきたい。
今日のボランティア活動
今日、ボランティア活動は私たちのくらしにとって身近な事柄となってきた。多くのボランティアは、人との関わりで自らを成長させつつ、さらに社会に働きかけ、自分たち自身のくらしに関わる内容について改善を勝ち取ってきている。
ボランティア活動とは、社会の中で生み出される問題や課題に対し、基本的には個人の意志によってなんらかの行動をすることを指す。その行動は、社会の中で生きる人としての個々の成長を促し、同時に、社会的諸課題の解決に向けた動きとなる。1995(平成7)年の阪神・淡路大震災、2011(平成23)年の東日本大震災などの大災害では多くの人がボランティア活動に参加した。ボランティア活動は、一人ではできなくとも、みんなで一緒になればなにかできる。協力することで成しうることが広がることが示された。同時に人との関係で進める活動は、情報を集め状況を理解し、配慮や気遣い思いやりといった心配りが不可欠であることや、ボランティアセンターなどが状況、活動内容について説明し、結びつけていく案内役として重要な役割を発揮することも明らかになった。
90年代に迎えた大きな変化
ボランティアという言葉を我が国で最初に紹介したのは戦前のセツルメントと運動といわれているが、それ以前から奉仕活動や慈善活動、相互扶助活動など類似する言葉は存在していた。
一般的にボランティアという言葉と活動が広がりをみせるのは第二次世界対戦が終わってからである。青少年活動によるボランティア活動や子ども文庫活動、平和運動、公害運動や障害者運動などの社会運動と結びついた活動が発展していく。特に1981(昭和)年の国際障害者年を一つのきっかけとして障害児・者に関わるボランティア活動が大きく広がりをみせるとともに、そのすぐあとには、地域での高齢者分野の活動が発展するなど、その時々の社会の動きによって様々な活動がわき起こってきた。
ボランティアの基本理念とボランティアの拡大
政府は、1992(平成4)年の文部省(当時)からだされた「今後の社会の「動向に対応した生涯学習の「振興方策について」(答申)において、ボランティアを自発(自由意思)性、無償(無給)性、公共(公益)性、先駆(開発、発展)性の四つの基本理念で表現した。そこからボランティア活動を進めるため学校教育における体験的活動を積極的に位置づける方針を打ち出した。
1993(平成5)年には厚生省(当時)が「国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針」及び「ボランティア活動の中長期的な振興方策について」(意見具申)を出した。これにより、市町村にボランティアセンターの整備並びにボランティアコーディネーターの配置が積極的にすすめられるようになった。
その後、1998(平成10)年には特定非営利活動促進法が成立し、NPO及びその支援センターがあいついで設立・設置されていった。2001(平成13)年にはボランティア国際年といった国挙げての拡大・促進政策が進められた。
社会福祉とボランティア政策の関係
なぜ、1990年代にボランティア活動が積極的になったのか。背景の一つには医療現場や社会福祉現場での担い手不足の問題があったことである。国のボランティア政策の基本は高齢化社会への対応がある。「社会福祉への活動参加」が「豊かさ」という言葉とワンセットで進められてきた国の政策は、本当に「豊かさ」につながったのか、きちんとした評価は出されていない。
ボランティア活動に対しては、経済活動や行政サービスなどの型にはまった社会システムとは関係なく、自由で豊かな人間関係の構築や発展が期待されていることは確かである。しかし、「市民の力」と「民間の力」が行政サービスなどの制度の担い手として組み込まれることは、一見すると前進面があるように思えるが、「安あがり」な内容に留め置かれることに加え、基本的な問題への対応があいまいにされるという点で注意する必要がある。
そもそも社会福祉は、雇用・労働などのくらしの基盤がぜい弱である、あるいはない、さらにはくらしを営む上で必要な公共的な施策やサービスなどの整備状況が進んでいない、あるいは使えないなど、個人や家族では対応できない生活上の困難の一部に対応している制度である。つまり、くらしを支える土台の部分を社会的にきちんと整えないと根本的解決につながらない。
市民が自主的で主体的に行うボランティア活動と、国・自治体が責任もって行うサービスとは根本的に異なるのである。社会福祉問題の解決に対して何かの役割を分担しあうという関係ではない。社会福祉に関する基本的な責任は憲法に明記されている通り、国(自治体)にある。
ボランティア活動における情報発信
今日のボランテジア活動の特徴として、第一に、自分の関心あるテーマや問題に対しインターネットなどの情報発信ツールを活用し直接なんらかの働きかけを行う。あるいは、見えやすい、わかりやすい情報を発信し、さらにつながりを広げていくという傾向がある。
第二に、このような情報発信ツールの拡大に加え、個人の思いや悩みを活動やアクションに結びつける支援センターや団体も数多く立ち上がっている。これまでなかなか発信や行動ができなかった個人が、様々な活動を進め、個人の活動の広がりがNPOやNGOなどの非営利の市民活動団体として拡大してきている。
第三にこれまでのボランティアにありがちだった枠が設けられた活動から脱皮・脱却を望む傾向が強まり、より自主的で主体的な面が強まっている。
よって(3)が正しい。(1)は「高齢者分野の活動までは発展しなかった」が間違い。1981(昭和)年の国際障害者年を一つのきっかけとして地域での高齢者分野の活動が発展した。(2)は、「豊かさ」の幅が広がっていったが間違い。国の政策では、「社会福祉への活動参加」が「豊かさ」という言葉とワンセットで進められてきたものの本当に「豊かさ」につながったのかきちんとした評価は出されていない。(4)のNPOやNGOなどの「営利法人」が間違い。NPOやNGOなどは非営利の市民活動団体である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
