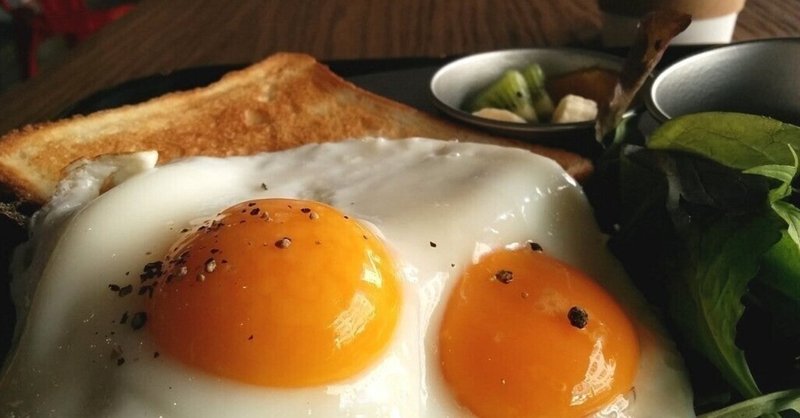
目玉焼きに何かける?【短編小説】
「みんな、目玉焼きには何をかける? しょうゆ? ソース?」
小学生のとき、先生がふいにそんなことを聞いてきた。
授業中のたわいもない雑談だったと思う。
身近な話題に教室は大盛り上がり。みんな一斉に口を開き始めた。
「ぼく、しょうゆ!」
「わたしはソースかな」
「おれ、マヨネーズ!」
「えー!? ほんと?」
「うちはねえ、ケチャップかける!」
醤油とソースに続き、他にもいくつかの答えが飛び交う。
楽しそうに答えるみんなの声を聞きながら、私は何も言わずじっとしていた。
授業の後、友だちの一人がそっと私の傍へと近付いてきた。
周りを気にするように声を潜めて話しかけてくる。
「みちるちゃん。あのさ、さっき、先生が言ってた話……」
「目玉焼きのこと?」
「うん……。あのね、私は、塩コショウで食べるんだ」
「え⁉ わ、私も!」
嬉しさと驚きで私は思わず大きな声を出した。
さっきは誰も塩コショウを挙げる人がおらず、最後まで言い出せなかったのだ。そう伝えると、その友だち――杏はほっとしたように笑った。
「そっか、一緒だね」
「うん、一緒!」
「よかったー! 塩コショウ派がいて」
「ね! 誰も言わないから、もしかして変なのかと思っちゃった」
「私もー!」
二人で顔を合わせ、けらけらと笑い合う。
杏と仲良くなったのは、これがきっかけ。
彼女はもう覚えていないと思うけれど、私にとってはとても印象的な出来事だった。
あれから二十年。
「お待たせ! ごめん、遅くなっちゃった」
息を切らせながらやって来た杏が向かい側の席に座る。
急な残業で抜けられなかった、と詫びる彼女に、私は「いいよ。大丈夫」と声を掛け、メニューを渡した。
「残業おつかれさま。なに飲む?」
「うーん、ビール! ……と言いたいところだけど、明日も早いからウーロン茶で」
「あれ、明日仕事なの?」
「そう。地獄の休日出勤」
「大変だねえ」
金曜の夜。二人でよく行く焼肉屋は大勢の客でにぎわっていた。
周りの席から漂ってくる肉の匂いに空腹を刺激される。
ちょうど通りかかった店員を呼び止め、まずはウーロン茶を二杯注文した。続けて肉も注文する。
「塩タンひとつ」
「あ、私も」
「……じゃあ、塩タン二つ。それから、ロース」
「私はカルビで。……ねえ、みちる。スライストマトも頼んでいい? 半分ずつにしよ」
「いいよー。トマト好きだし」
「知ってるー」
杏が楽しそうに笑う。
「あ、キャベツ盛りもお願いします。……杏、キャベツ盛りも半分ずつね」
「いいよ。キャベツ好きだし」
「知ってるー」
注文を終え、私はそう言って彼女に笑い返した。
彼女と一緒に食事をするときは、それぞれ好きなものを好きなだけ食べる。
半分ずつにしたりもする。
そうして、お互いに近況報告をするのだ。
今の私と杏は、よく一緒にご飯を食べる友だち。
高校からは別々になってしまったけれど、彼女とは変わることなく仲良くしていた。まずはウーロン茶で乾杯し、牛タンを網の上に並べていく。すでに温まっていた網の上で肉がジュージューと音を立てて色付き、いい匂いが広がった。
「……今日、みちるの旦那さんは?」
「向こうも飲み会だって」
「そっかー」
「杏はどう? 最近」
「それがさ、聞いてよー! うちの会社、また人が減るんだって」
「また? 先月も何人か辞めたって言ってなかった?」
「そう、先月は二人。今月も二人……もういや」
自分の好きなタイミングで肉をひっくり返し、私はちょうど良い焼き加減になった肉を皿に取った。杏の方の肉はまだ網の上だ。
彼女は一番いい頃合いを待ち、じっくりと様子をうかがっているように見えた。
次々と網に肉を並べ、焼いては食べながら仕事の愚痴や近況について話していく。ふと話題が途切れたところで、杏が改まったように切り出してきた。
「……あのさ。次はうちで鍋食べない? 来週末とか、どう?」
いつもとは違う雰囲気になんとなくピンとくる。大事な話のようだ。
でも、自分からは言いたくない。出来ればどうして?と聞いてほしい。
杏はそんな顔をしていた。彼女の意図を正しく読み取り、私は口を開く。
「それはいいけど……どうして? 何かあるの?」
「……うん、あのね、私の彼氏も一緒に、何人かで鍋をしようと思って」
なるほど、杏の恋人に会ってほしいということらしい。
昨年頃からその恋人の話は聞いていたけれど、まだ会ったことはなかった。
年上で、背が高くて、優しくて、頼りになる、公務員の彼氏。
彼女がその彼に惚れ込んでいるのは分かっていた。なにせ、付き合い始めたのをきっかけに、実家を出て恋人の近所で一人暮らしを始めたくらいだ。
「彼とは、そろそろ結婚を意識してるんだ」
デザートのチョコレートアイスをゆっくりと口にしながら、杏は幸せそうに微笑んだ。
今日は馴染みの店が臨時休業だった。
シャッターの降りた店前でスマートフォンを操作し、検索した別の店へと向かう。初めて入る店だ。
こちらへどうぞ、と案内された奥の座席には私たちしかお客がいなかった。
杏がメニューを眺めながらうーん、とうなる。
「最近シンプルな方が好きでさ。お好み焼きって、具が少ない方が美味しいと思うんだよね」
ふうん、と頷いて私もメニューを吟味する。
テーブルに置かれた呼び出しボタンを押したが、ちっとも店員が来ない。
もう一度押して少し待ってみたものの、やはり反応がない。
仕方なく、私は席を立って直接厨房の方へと声を掛けに行った。
いやあ、ボタンの調子が悪いみたいで、すみません、と誤魔化すように笑う店員に注文を伝える。杏は、メニュー表の一番上を指さした。
「私、イカ玉で」
そして、そのままメニューブックをパタンと閉じてしまった。
思わず「あ」と声が出てしまい、彼女の方へと手を伸ばす。
「ごめん、あの、メニュー、見ていい?」
「あっ! ごめん……」
杏から手渡されたメニューをパラパラと開く。彼女は少し気まずそうな表情を浮かべていた。今日は色々なことがどうにも噛み合わない。
「私、ミックス玉で。トッピングにチーズと……明太子も追加してください……あ、お餅も」
気分のままに頼む私の向かい側で「入れすぎ!」と杏が笑い、ふっと空気が緩む。けれど、穏やかになったのはその一瞬だけだった。
運ばれてきたタネを細長いスプーンでかき混ぜる。私も杏も無言だった。
温度を上げた鉄板がジリジリと音を立て始める。
「……もう、焼いてもいいかな」
「……うん、いいかも」
小さく確認し合い、一気にタネを流し込む。
ジュワー!という大きな音と共に生地の焼ける匂いがあたりに広がった。
鉄板から舞い上がる熱気が顔に当たる。軽く形を整え、あとは焼けるのを待つばかり。
「……どうだった?」
視線を目の前のイカ玉に向けたまま、ぽつりと杏が言う。
来た、と思った。
なるべくその話題に触れたくなかったけれど、やっぱり聞かれてしまった。
杏が聞きたいのは先週の鍋会について。つまりは杏の恋人についてのことだろう。
「……うん」とだけ答え、私は黙り込んだ。
杏が、ちらりとこちらを見る。
「あんまり彼と話、弾んでなかったみたいだけど、なんか、あった?」
「うーん……そういうわけじゃ、ないんだけど」
言葉を濁し、段々と火が通っていくお好み焼きを見つめる。
黙ったままの私にしびれを切らしたのか、杏ははっきりと言葉にした。
「ねえ。彼のこと、どう思った?」
その一言で分かってしまった。
杏とはもう長い付き合いになる。だから、分かる。
彼女の望む言葉が。背中を押して欲しいと思っていることが。
杏は、恋人を誉めてもらいたいのだ。
「優しそうで良い人だね!」「かっこいいね! お似合いだと思う」
「年上で、頼りがいがあって、本当にしっかりした人だね、あの人となら幸せになれそう!」
きっと、そんな言葉で。でも、私は言えなかった。どうしても言えなかったのだ。
正直にいうと、その人の印象は、よくなかった。
よくないどころか、悪かった。
けれど、大事な友だちの恋人を悪く言いたくはない。
だって、まだ一度会っただけだ。
緊張していたのかもしれないし、私との相性がよくなかっただけかもしれない。
大事なのは私の印象よりも杏と合うかどうかだ。
余計な口出しをすべきではないと思った。
けれど、誤魔化して褒めたりすることも出来なかった。
「……しっかりしてそうな人だなって、思ったよ」
そう答えるのがやっとだった。煮え切らない私の態度に杏が眉をひそめる。
「なに? 何かあるなら言ってよ」
「……そう言われても、まだ一度会っただけだから」
「本当に? 何かさっきから嫌な感じ」
「…………」
「みちる、鍋会のときもちょっと態度が変だった。もっとあの人と喋ってくれたらよかったのに」
「……なにそれ。私はちゃんと最初に挨拶したよ。……返事はなかったけど」
「それ、気のせいじゃない? みちるの声が小さくて聞こえなかったとか」
「……そんなことない」
「…………」
「…………」
焼けた豚肉から落ちた油が跳ね、ジリリ、パンッと音を立てる。
ハッとして鉄板を見れば、生地の端が焦げていた。ヘラを手に取り、慌てて裏返す。
いつもならお互いに「やった! うまく返せた!」とはしゃぐ場面なのに、そんな雰囲気ではなくなってしまった。
片面を焼きすぎたお好み焼きを食べ、ぎこちない会話を交わす。
杏はそれ以上恋人の話には触れず、私も何も言わなかった。
「しばらく忙しいから、落ち着いたらまた連絡するね」
店を出ると、杏は私の方を見ずにそう言った。
なんとなく、もう連絡は来ないかもしれないと感じた。
けれど引き留めることも言葉を掛けることもせず、ただ「うん」とだけ答えて。そうして、私たちは別れた。
それから三か月後。
共通の友人から杏が引っ越したことを聞いた。
あの恋人と一緒に住むことになったのだろうか。
私と杏は、あれから一度も会っておらず、メッセージのやり取りも止まっていた。
どうしよう。今更ながら一度連絡してみようか、とスマホのメッセージ画面を開く。
「久しぶり。よかったら、また、近々ご飯でも行かない……?」
散々悩んだ末に短いメッセージを打つ。
そして、そこからまた延々と迷い、ようやく送信ボタンを押す。
杏から返事が来たのは、その日の深夜だった。
いらっしゃいませ、おひとりですか?と微笑む店員に「待ち合わせです」と答え、店内へ入る。休日のファミリーレストランは家族連れや学生たちでにぎわっていた。
奥の席に座る杏の姿を見つけ、緊張しながら一歩ずつ近寄る。
彼女には聞こえないようにそっと咳払いをし、私はなるべくいつも通りに話しかけた。
「……杏。久しぶり」
「……みちる」
私の顔を見た杏がほっとしたような、泣き出しそうな顔をする。
向かい側の席に座り、何を言えばいいのか分からずにいると、杏はメニューを差し出した。
「ねえ、何頼むか決めよ。お腹すいちゃった」
「うん」
呼び出しボタンを押すと、すぐに店員がやって来た。
「煮込みハンバーグのランチセットに、コーンスープ。あ、ドリンクバーも付けてください」
「香味野菜の豚しゃぶ定食を。私もドリンクバー付きで」
注文を済ませ、ドリンクバーを取りに行く。
杏は氷をたっぷり入れたコップにメロンソーダを入れていた。唐突に、そういえばずっとメロンソーダだと思った。彼女はここへ来ると必ず最初にメロンソーダを飲むのだ。
飲み物をついで席へ戻ると、私のコップを見た杏があはは、と笑う。
「みちる、いつも最初はアイスコーヒーだね」
なんだかその言葉が無性におかしくて、うれしくて、ふいに泣きそうになって。私はガムシロップを取り忘れた、と言って、もう一度席を立った。
杏が頼んだハンバーグの上には、目玉焼きがのせられていた。
「目玉焼きがのってるのっていいよね」
「分かる。それだけですごく豪華に感じるもん」
「私、焼きそばの上にのせるのも好き」
「いいなあ、それ」
たわいもない会話をしているうちに、私の注文した定食も運ばれてくる。
いただきますと箸を手に取ったタイミングで、杏が小さく声を発した。
「……彼とさ、別れちゃった」
それだけ言い、彼女は勢いよくハンバーグを食べ始めた。
そっか、とだけ答え、私も豚しゃぶへと箸を伸ばす。
目玉焼きを綺麗に半分に割り、杏があのさ、と口を開く。
「小学生のとき、授業中に目玉焼きの話になったの、覚えてる?」
「……覚えてるよ」
びっくりした。だって、もう二十年も前の話だ。杏も覚えているとは思わなかった。
驚きを隠し、話を続ける。
「……何をかけるか聞かれたやつでしょ」
「それそれ」
頷いて、杏がおいしそうに卵を頬張る。
彼女はゆっくりとそれを呑み込んで、そして泣き笑いのような表情を浮かべて私の顔を見た。
「今思うと、あれ、別に何をかけたっていいんだよね。おいしく食べられるなら、それで」
「そうだね。好きなものをかけて食べればいいと思う」
「ね。しょうゆでもソースでも、塩コショウでも。恋人の好みが自分とは違ってても、別にいいじゃんね」
「うーん……。その時はさ、相手の味を試してみるのも楽しいよね。意外とこっちもいいね、ってなるかもしれないし」
「……うん。本当にそう。私も、そういうのがいいな」
杏は何度も頷いて、手にしていたフォークとナイフを置いた。
「実際はさ、私が塩コショウをかけておいしい!って食べてるのに、勝手に人の皿に醤油やソースをドバドバかけて、こっちの方がうまいから食べろよって押し付けてくる奴だった」
「それは、嫌だなあ」
「でしょ。あの人、いつも全然こっちの話を聞いてくれなくて、嫌になっちゃった」
「……そっか」
「そうなの。ただ一緒に楽しくご飯を食べる。まず、それが出来なかったよ」
「そっかあ」
無言で食事を進める。定食を残すことなくすべてたいらげ、私は杏を見た。
「……また、次のご縁があったらさ、俺は醤油が好きだけど、塩コショウもいいね。試してみようかなって言ってくれる人だといいね」
「そうだねえ。……まあ、しばらくそういうのはいいや」
それから、彼女はぽつりと「あの時は、本当にごめんね」と告げた。
「いいよ。私もごめん」と答え、アイスコーヒーを飲み干す。
水分がなくなり、コップに当たった氷がカラン、と軽やかな音を立てる。
仲直りの後は、いつだって少し決まりがわるくてそわそわする。
面映ゆさを誤魔化すようにして私はメニューを手に取った。
「デザートも頼もうかな」
「いいね。私も食べる。この期間限定のパフェが気になる!」
「んー。おいしそうだけど、入るかなー」
「喋ってたら、すぐお腹減るんじゃない?」
「いやいや。それは高校生のときの話だから」
期間限定のパフェは予想以上に量が多かったけれど、甘くておいしかった。
「一緒に行くの? 二人で?」
「うん」
「……それ、デート?」
「違う違う。引っ越しを手伝ってもらったお礼だよ。ご馳走するから何がいい?って聞いたの。そしたら、珈琲とケーキの美味しい店に行きたいっていうから」
どこかおすすめのカフェを教えてほしい。
突然電話で杏にそう言われ、私は珍しいね、と返した。
杏は珈琲も紅茶もあまり飲まないので、自分からカフェには行かないのだ。
聞けば、引っ越しを手伝ってくれた会社の後輩へのお礼だという。
その後輩くんとは普段からよく話す間柄で、引っ越しの手伝いも彼の方から申し出てくれたらしい。そういえば最近、杏の近況報告には後輩くんの話題がよく出ていた。
「いつ行くの?」
「都合が会えば今週末かな……。向こうはいつでもいいって言ってる」
「……ねえ、杏。その後輩くんと、いい感じとかではないの……?」
「えー? 違うよ。私、社内恋愛はちょっと……。そもそも全然好みじゃないし」
「ふうん」
「……みちるも一緒に来てよ」
「なんで」
「……なんか、話してたら、二人っきりっていうのは気まずい気がしてきた」
「いやいや、お礼なんでしょ? 私が混ざるのはどう考えても変でしょうに」
尚も食い下がる杏をなだめ、私はおすすめの店を紹介した。
飲み物の種類もケーキの種類も多い、落ち着きのある店だ。
私がとても好きな場所。
今まで自分から人に紹介したことはなかったけれど、なぜか今回は勧めたくなった。
三週間後。
杏からその店で会おうと連絡があった。
「アップルジュース。パンケーキとセットでお願いします。メープルシロップで」
「ブレンドを。季節のタルトとセットで。……あ、プチシュークリームもお願いします」
注文を済ませ、先に運ばれてきた飲み物に手を付ける。
私は湯気の立つ珈琲に砂糖を一杯入れてスプーンでぐるぐるとかき混ぜた。
「それで? どうだったの、お礼のお茶会は」
「普通に終わったよ。ここ、教えてくれてありがとうね。気に入っちゃった」
「それは何より」
シンプルなプレートに綺麗に盛り付けられたケーキが運ばれてくる。
杏はパンケーキにたっぷりとシロップをかけた。
「……後輩くんがさ、」
「うん」
「私があれも食べたい、これも食べたいってずっと迷ってたら、『じゃあ、また次にここに来た時に食べましょう』って」
「……次」
「そう。『よかったら、また次も一緒に来たいです』って」
「……それで?」
気になって先を促すと、杏は照れくさそうに顔を逸らした。
「……それで、また一週間後に一緒に……」
「え? そうだったの? ん? つまり先週もここに来てたってこと?」
「……うん」
「えー!?」
朗らかに笑いながら幸せそうにケーキを頬張る彼を見て、彼女は雑談がてらに聞いてみたのだという。
「……ね。目玉焼きに何かける?」と。
そう話す杏がとても楽しそうで。可愛くて。
まだ話の途中なのに、私は思わず「へへへ」と笑ってしまった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
