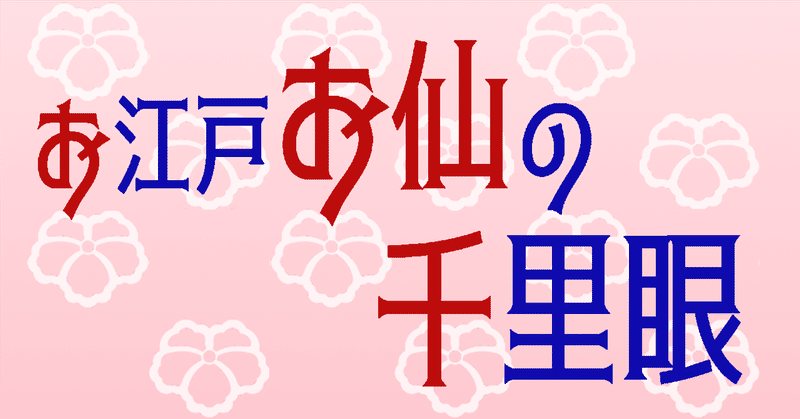
お江戸お仙の千里眼【第一話 出会い】
【あらすじ】
江戸中期。「明和三美人」のお仙・お藤・お芳が千里眼(=彼岸識)を駆使して活躍する。田沼意次・平賀源内・長谷川平蔵など史実の人物達との関りを通して江戸庶民の生活を描き、真の人の幸せを探求する。三人は同い年。幼い頃に浅草寺で出会って江戸の人々の幸せを龍神に祈った。数年後、臨死体験でそれぞれの千里眼(お仙は過去・未来を読め、お藤は空間を俯瞰でき、お芳は人の心の声を聞ける)を獲得、成長する中でそれに磨きをかける。だが江戸の町に、全てを灰燼に帰す大火が迫る。三人の彼岸識と人々の力で江戸の町を守れるのか。燃え盛る炎を前にお仙は最後の決断をする。その時、予想もできない奇跡が起きる。
【本編】
― 向こう横丁のお稲荷さんへ
一銭あげて ざっと拝んで お仙の茶屋へ
腰をかけたら 渋茶を出した 渋茶よこよこ
横目で見たらば 米の団子か 土の団子か お団子 団子 ―
宝暦十年、一七六〇年十一月のことである。六歳になった谷中笠森稲荷門前の水茶屋・鍵屋の娘お仙は、父親の鍵屋五兵衛に左手を引かれて浅草の浅草寺門前まで来ていた。五兵衛は水茶屋・鍵屋を営む商魂逞しい男であった。人の道に外れるようなことは決してしないが、結構な頻度で人の道の定義の輪郭が曖昧になることがある男であった。あるだけの金儲けの機会はどうしても逃したくない男であった。そのための努力は決して惜しまぬ男であった。だが彼が商魂を燃やす時に心の中でつぶやく言葉はいつも一つ。それは「コイツのため、お仙のため…」である。小さくはその日お仙に少しでも良い物を食わしてやるために、大きくはなるべく良い家に嫁がせて、自分がいずれ死んだ後もお仙が末永く幸せに暮らせるようにと、可能な限りの金を稼ごうとしていた。時として愛娘のための金もうけのために愛娘を微妙な商売の道具にするという、目的と手段とが混乱を来たすことも無いでは無かったが、兎にも角にも五兵衛は良き父であった。お仙もそんな五兵衛のことを「信頼する」とも「大好きだ」とも意識しないほどに父として信頼もし、大好きでもあった。つまり父と娘は十分に幸せであった。
その五兵衛がお仙の手を引いて浅草寺まで来たのは、数え七つになった娘の無事な成長と商売繁盛とを観音様に祈願するためだ。谷中と浅草の距離である。現代の感覚なら電車で何分、バスで何分という近さだが、庶民の足は徒歩しかないこの時代、それは子連れなら片道半刻(一時間)近くかかる行程である。五兵衛は行く道々で出会う顔見知りやお得意さんに片っ端から笑顔を振りまき会釈をしながら歩いた。その五兵衛に手を引かれて、時々足をもつれさせなどしながらお仙も歩いた。
お仙はものに動じない質の子供であった。同じ年頃の女の子と比べたらあまりしゃべらない方であった。子供らしくない、どちらかと言えば何を考えているのかうかがい知れないような子供であった。そして何より、お仙は奇跡の珠ように美しい女の子であった。姿かたちの美しさは、目鼻や口や手足などの顔や身体を構成する各部分の形、大きさ、配置、バランスで決まるものであるが、お仙のそれ等は、奇跡的に一つの例外もなく完全であった。物事に頓着しないお仙は大抵無愛想な顔をしていたのであるが、それは十人がすれ違えば十人が振り返るほどの美しい無愛想顔であった。お仙が生まれて三年も経った頃にはその美しさは疑い得ないものとなり、日々我が子を見るにつけ五兵衛がうわ言のように言う言葉は、「こいつはヤベェ…」であった。そうして五兵衛はそのお仙の美しさをできるだけ隠すように心がけた。無論親としては自慢の一人娘を綺麗に着飾らせて誰彼構わず見せびらかして自慢したい気持ちはあった。だが道理が引っ込み無理が通ることの多いご時世である。考えも対策もなく目立ったって良いことなど一つもないに決まっている。五兵衛は意識してお仙の美しさを目立たせぬように育ててきた。だがこの日は晴れの日であり、神前に出る日である。裕福ではないので大したことはできないが、それでも普段と比べればはるかに綺麗な格好をさせて連れてきたのであった。
浅草寺の仲見世に入った所で五兵衛は鍵屋で出す団子の米粉を卸す高田屋と出会った。五兵衛は前々から米粉の仕入れ値を少し抑えたいと思っていたので、速足の歩みをとめ、お仙の手を放して高田屋と商売の話を始めた。もちろん長話をする気はなかったのである。こんな往来の立ち話で値引きが取り付けられると思うほど五兵衛は愚かではなかった。ただこういう小さな機会をしっかり活かすことの積み重ねが、店を少しずつ大きくする礎になるのだという信念のようなものが五兵衛にはあった。そうして五兵衛が高田屋と話している間、お仙は五兵衛の後ろで五兵衛とは逆の方を向いてぼぉっと突っ立っていた。ところが浅草の人込みの直中である。よそ見をしながら歩く見知らぬ男が悪気もなくお仙の肩にドンとぶつかった拍子に、お仙は二三歩よろめいて道の真ん中の人の流れの中に押し出されてしまった。押され押されて随分動いてしまい、気づけばそばに五兵衛はおらず、さらに大分押し流されてようやく人の流れの淀んだ場所に弾き出され、来たと思しき方を向いてぴょんぴょん飛び跳ねなどしてみたが、五兵衛の背中はとんと見つからない。お仙はさすがにしまったと思った。どうせすぐに五兵衛を見つけられるという根拠のはっきりしない確信のようなものがあり、このまま父親と二度と会えなくなったらどうしようという、お仙くらいの年頃の子供が抱くような不安は全く感じなかったが、見つかってみた時のバツの悪さを思うと、なんともやりきれな気持ちになった。目を閉じて探そうにも人が多すぎてままならず、やむなくお仙はもっと人通りの少ない方へ移動することにした。横道に入り少し歩き、人影はなく銀杏の大きな木があって、ふんわり散った落ち葉が辺り一面を覆っている場所に出た。黄金色に輝く銀杏の葉が秋風に揺れていた。その鮮やかな黄色に少し楽しい気分になって落ち葉を蹴って遊んでいると、足元に一寸ばかりの白くて丸い綺麗な石があるのに気付いた。鍵屋で出す米のお団子にそっくりだと思い、左手で拾い上げて少し泥を払ってから袂の中に入れた。さて、五兵衛を探さなくてはとお仙が思ったちょうどその時、後ろで「ほら、いた」という声がした。振り返ると自分と同じくらいの年恰好の女の子が二人立っていた。
一人は見るからに裕福な身なりをした美しい少女だった。子供なのに上等な鼈甲の櫛を髪に挿していて、手には緋色の手毬を持っていた。ツンとした顔はやや気が強そうではあったが、それがある種の気品となって美しさをさらに引き立てていた。もう一人の少女は身なりはごく普通であったが、やはり極めて美しい顔形をしていた。帯に小さな鯉の根付をぶら下げていた。不思議なのは、この子の顔の表情であった。確かに美しいには違いなかったが、目が合っただけで心の奥まで暖かく優しい陽光が差し込むような色をしていた。お仙は数秒の間、まじまじとその顔を見つめてしまった。「ほら、いた」と言ったのは、ツンとした方だった。
「あなたたち、誰?」とお仙が聞くと、鼈甲の櫛を着けた方が真っすぐお仙と目を合わせながら、
「あたしはお藤。柳屋お藤。むこうで楊枝屋をしている柳屋の娘よ。よろしく。こっちの子は…」
と言ってもう一人の少女の方を振り返ると、
「あたし、お芳。二十軒茶屋の蔦屋の娘。よろしくね」といって根付を揺らしながらにこっと笑った。
お仙もつられるように「あ、あたしは谷中笠森稲荷の鍵屋お仙」と名乗った。誰かに聞かれたらそう答えろと、いつも五兵衛に言われていたのである。
「さっき、『ほらいた』って言ってたけど、どういうこと?」お仙は二人の顔を交互に見ながら聞いてみた。
「それはね」お藤が右手の人差し指を立てて当然と言った顔で説明を始めた。ツンとした表情が一々美しい。
「知らない女の子がここでぼぅっと突っ立ってるのが見えたの。あたし、そういうの得意なの。分かる? お芳ちゃんと会ったのも、実は今日が初めてなんだけど、なんか仲良しになれそうな気がして、そしたらあなたが見えたでしょ。それで会いに来たの。分かる?」
お仙はお藤の子供らしい稚拙な説明が分かろうはずがなかったのだが、なぜかそれを前から全部知っていたような気がした。また横からお芳の目に見つめられていると、不思議だなぁと思いながらもお藤の話を何となく納得してしまっていた。お芳はというと「あたし、二人いるのかと思っちゃった」と言って舌を出して微笑んだ。
「ね、あなたたち、毬つきは得意? あたし、けっこう凄いわよ? 競争する?」お藤がそう言うと、お芳が「やるやる! でも、あたし身体使う遊び、全然だめ!」と言って明るく笑った。その笑顔に引き込まれてお仙も「あ、それじゃ、あたしもやる」と答えた。お仙はこの二人から、今までに誰からも感じたことのない不思議な親しみを感じていたのだった。
物心ついた時から大人に「可愛い可愛い」と言われて育った。だから自分はきっと「かわいい」のだろうと思ってはきたが、お仙にとってそれはどうでも良いことの一つであった。そもそも母親は早くに死んでしまっていて家にはろくな鏡もなかったから、自分の顔をまじまじと鏡に映して見たこともない。大人は子供をみれば誰にでも「可愛い」と言うのだろうというくらいに思っていた。実際、大人は大抵の子供には「可愛い」と言っていた。だがお仙は、今、お藤の輝くような美しさを間近に見て、初めて世の中に美しい人、可愛い顔というものがあるということを納得した。こういう子のことを「可愛い」と言うのだと、初めて実感をもって理解した。それはお仙にとって小さからぬ発見であった。そしてもう一つお仙をびっくりさせたのは、お芳の醸すえも言われぬ心地よい雰囲気だった。お藤の美しさ、可愛らしさは誰が見ても一目で分かる。お藤の顔を見れば、誰でも「可愛い」「綺麗だ」という言葉を心の中で呟くだろう。だが、お芳の顔と表情とからは何の言葉も浮かばないのではないだろうか。何らかの言葉が浮かぶ前に、人はきっとぼぅっとなってしまうに違いない。確かにお芳の顔も美しく可愛らしくはあったが、単純に比較すればきっとお藤の方が勝つだろう。だたお芳の目に見つめられた時に感じる、春の暖かい陽の光と澄み渡る秋の木犀の香りとに同時に包み込まれるような喜びは、一体何と表現したら良いのだろう。そんな気持ちになったことが、そしてただ一瞥でそんな気持ちを自分に抱かせる少女がいるということが、お仙には正に驚愕であった。
三人輪になって交互に毬をついた。お藤が一番上手かった。お芳が一番下手だった。お仙もそこそこ普通にやれた。三人とも、上手くつけて笑い、失敗してまた笑った。ところが何回目かの番が来てお仙がついている時に、毬が小石に当たって思わぬ方に転がった。お藤とお芳は屈託なく笑った。お仙も一緒に笑いながら銀杏の落ち葉の上を転がる毬を追った。毬に追いつきぴょんとしゃがんで拾い上げようとした時に、落ち葉の隙間から薄汚れたそれの一部が見えた。「あれ?」と思ってその場でしゃがんで見ていると、お藤とお芳が走って来た。
「何やってるの?」お藤が聞く。
「…ここに何かある」お仙が答えた。お藤に追いついたお芳も「ほんとだぁ」と言いながらお藤と前後してお仙のそばにしゃがんだ。お仙は毬を落ち葉の上に置くと、両手で落ち葉をかき分けてみた。するとそれは、半分近く土に埋まった古い石の祠の屋根であることが分かった。お藤とお芳も一緒になって三人で落ち葉を払いのけてみると本体の方も出て来て、倒れ崩れてしまった古く小さな石の祠が現れた。
「神様だ…」お芳が言うと「神様ね」とお藤も言い、さらにお芳が「何の神様かしら?」と続けて言った時に、お藤が祠の朽ちかけた前面に、うっすらと鱗のような模様があることに気が付いた。
「龍か蛇の神様みたい…」そうお藤が言うと、「龍神様かな?」とお芳が言った。「…八歳くらいかしら?」とお仙が何気なく言うと「龍の神様がそんな子供の訳ないでしょぅ?」とお藤が言って苦笑いした。
谷中に住むお仙なら知らなくて当然であったが、不思議だったのは比較的近所に住むお藤とお芳もこの祠の存在を全く知らなかったことである。「もっとちゃんと綺麗にしてからお参りしましょうよ」とお藤が提案し、お仙とお芳は頷いて積もった銀杏の葉を寄せ始めた。やがて一間四方ほどの落ち葉をきれいに払い除け終わると、今度は半分埋まった祠の屋根を、手を泥で真っ黒にしながら掘り出した。最後に、三人力を合わせて崩れた重い屋根を本体に乗せ、小砂利の擦れる音をさせながら少し屋根の向きを直し、元はこうであったであろうという姿にした。そしてその前に三人一列ちょこんとしゃがんだ。みな汚れた手で額や頬の汗を拭ったので顔が泥で汚れている。
「それじゃ、お供え物をしてお参りしましょ」とお藤が言った。
「お供え物?」お仙が聞くと、
「そうよ。神様だもの、お供え物くらいしなくちゃ失礼よ。お供え物をしたら、三人それぞれ、心に思っている一番大事なお願いをするの」とお藤は言った。その子供っぽい提案を大人びたものに感じたお仙とお芳は素直に従った。お藤は髪に挿してあった鼈甲の櫛を髪から抜いて祠に供えた。お芳は帯に吊るしてあった鯉の値付けを供えた。その場に至って、お仙は自分が神様に供えるべき物を何も持っていないことに気付いた。唯一あるのは、今履いている下駄であるが、さすがに下駄を供えてしまっては帰ることができない。これは困ったと袂の中に手を入れてみると、先ほど拾った米の団子にそっくりな白くて丸い石が指先に触れた。他にしようもなかったので、お仙はその石をお芳の根付の隣に供えた。お藤もお芳もそれぞれの理解の仕方でお仙のお供え物がただの石ころだということを咎めなかった。
「それじゃ、拝みましょう。いい? 今心の中にある、一番大事なお願いをするのよ?」お藤の言葉にお仙とお芳も頷いて、三人目を閉じ泥に汚れた小さな手で柏手を打ち、心の中でその石の祠の神様に一番叶えてほしいお願いをした。子供らしく、決して大人にはできないほど純粋に願った。そしてそれは奇しくも三人ながら同じ願いであった。
江戸の町が平和で、みんなが幸せでありますように……
その時、強い風がふわっと吹いて払い除けた辺りの落ち葉を舞い上げた。そしてその瞬間、石の屋根を上げた時に祠の本体との間に挟まった小砂利が弾けて飛び、祠が「ゴト…」 と音を立てた。三人ははっとして目を開いたが、やがてお互いに顔を見合わせると可笑しそうに笑い合った。
「お仙! こんな所にいたのか。ずいぶん探したよ。話に夢中になっちまったおとっつぁんが悪かったけど、お前もしっかり… あれ、その二人は?」
五兵衛が来た。お仙が何か言うより前に、お藤が説明した。
「あたしたち、近所の子です。ここで迷子になったお仙ちゃんを見つけて、お父様が探しにくるまで遊んで待っていました」
「あぁ、そうなのかぃ。それはありがとね。この子はどうもぼぉっとすることが多くてね。ゆっくりお礼を言いたいんだけど、お参りがまだなんで、もう行くね。お仙、お礼を言いな」
五兵衛は初めて見る二人の少女に笑顔を向けながらそう言ってお仙の手をとった拍子に、それがザリっとした泥で汚れていることに気付いて少しぎょっとし、懐の手ぬぐいを出してまずお仙の手と顔とを、次いで自分の手を拭いながらお仙にそう言った。
「お藤ちゃん、お芳ちゃん、今日はありがとう。今度谷中の方にも遊びに来てね。」
「うん。行く行く。また会おうね」そう言ったのはお芳だった。お藤も「また会いましょ」と言って、二人とも手を振った。お仙も二人に左手を振って応えた。お仙の右手を引きながら歩きだした五兵衛が「あとで二人のお家にもお礼に行かないといけないな。名前は聞いてあるのかい?」と聞くのが二人に聞こえた。「うん。柳屋仁平次さんのところのお藤ちゃんと蔦屋心平太さんのところのお芳ちゃん」遠ざかりながらそう言うお仙の声も聞こえる。
「可愛い子だったわねぇ…」と言いながら父娘を見送るお芳が、同じく二人を見送るお藤の気持ちのわずかな動揺を聞いたような気がした。
「ん? お藤ちゃん、どうしたの?」
「お芳ちゃん、あたしたち、自分のおとっつぁんの名前、お仙ちゃんに言ったっけ?」
「う~ん… 言ってない気がする」
「それじゃなんでお仙ちゃん、あたしたちのおとっつあんの名前が分かったんだろぅ?」
「たしかに…」
お仙は五兵衛に手を引かれながら、なぜ先ほど祠を拝んだ時に、鍵屋の商売繁盛を願わなかったのだろうと思った。あの時はそんなこと、少しも頭に浮かばなかったのだ。お藤に「一番大事な願い事」と言われて真っ先に思い浮かんだのが江戸の平和とみんなの幸せだった。だが「おとっつぁんだって江戸のみんなの中の一人だ」と思いなおしてまぁよしと納得した。そしてお藤とお芳とには明日にでも会いたいと思った。二人と遊んだ時に、それまで感じたことのないような深い安らぎがあったのだ。だがそれが叶うのには四年の時が必要であった。不思議な縁で結びついたお仙・お藤・お芳の三人は、四年後に思いもよらない所で再会するのである。
それは、うだるような暑さの、ある夏の日のことであった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
