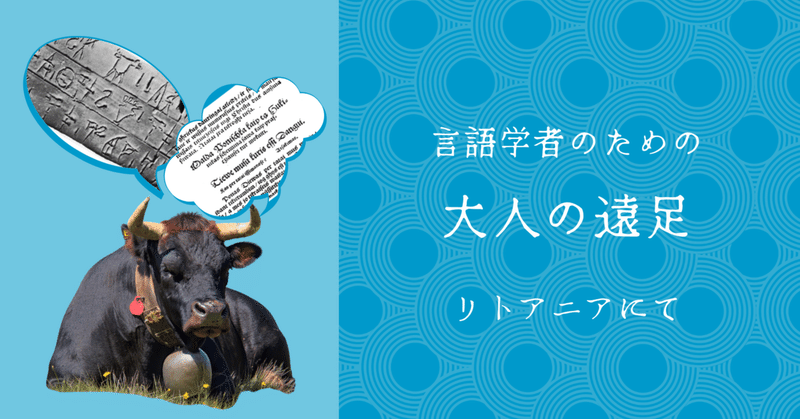
リトアニア、言語学者のための大人の遠足
私Yamayoyam、一応今のところ本業は言語学の博士研究員でいられてます。
いつまで続くかわからないけれど(汗)
先々週は、リトアニアのヴィリニュスで開かれたバルト語学の学会にご招待いただいて、ちょっと言語学者っぽいことをしてきました。
コ○ナ禍をはさんで3~4年ぶりにリトアニアに行ってきましたので、印象に残ったことを綴ってみたいと思います。
ストックホルムから、ラトビアのリーガ経由でヴィリニュスまで、バルティックエアという航空会社の便で飛んだのは、9月21日水曜日の夜。
夜遅いフライトで、ヴィリニュス到着は午前様、大学のゲストハウスに到着したのは午前1時頃。
それでも容赦なく翌日朝からヴィリニュス大学のバルト語学科で学会。
私は午前の部の3人目の発表者で、寝ぼけた頭でなんとかこなした、といった具合。せっかく質問をいただいたのにその真意がちゃんと腹落ちしたのは次の日のコーヒーブレイク中、というテイタラク。
辛抱強く議論に付き合ってくれた人たちに感謝。
対面式の学会のコーヒーブレイクの大切さを思い知りました。
私と同じような分野の印欧語比較言語学や歴史音韻論・形態論的な研究の他に、リトアニア語の動詞の語法、方言形式、ラトビア語の17世紀のテキストの分析、などなど、いろんなトピックがありました。
2日間ぎっちりな学会の合間、ゲストハウスから学会の会場に行く途中で、かわいい佇まいのKmyninė というパン屋さんを見つけました。
ところで、パン屋さんはリトアニア語で kepykla といいます。「-kl-」はもともとは行為者名詞や道具の名詞を作る接辞(*-tl-)に由来しますが、ここでは何かが行われる場所を表しています。他に、mokykla 「学校(mokyti「教える」)」leidykla「出版社(leisti「許す」)」など色んな言葉に使われています。
語根にあたる kep- は「焼く」という意味。合わせて「(生地が)焼かれる場所」=「パン屋」というわけですね。
ところでこの語根、何故か k と p が入れ替わるという珍現象が起きています。他の言語では、例えば 古教会スラブ語 pekǫ (pešti)「焼く」、サンスクリット語 pácati「調理する」、トカラ語B pakṣäṃ「調理する」などがあり、印欧祖語の語根は *pekᵂ- であったと考えられています。
こういう古い言葉が町の看板に普通に掛かってたりするのが、たまらないです。
さて Kmyninė に戻って、たくさんの惣菜パンや菓子パンが並んでいるショーウィンドウが圧巻。思わず写真を撮らせてもらいました。

朝ご飯に私が注文したのは、kopustėlis と表示してあった、小さな惣菜パンとコーヒー。炒めたキャベツなどの野菜の具が詰まったパンで、野菜が不足しがちな旅行中にありがたい一品。
暖かいコーヒーで寝不足のアタマに喝を入れてもらいました。
パン1.7ユーロ、コーヒー0.69ユーロ、合計2.39ユーロ。ストックホルムとかベルンなどの物価が辛い場所から来た身としては、ビックリ。
ほかにもかわいらしい雑貨やお土産用の šakotis という樅の樹みたいなクッキー、マカロン、チョコレートが売られてました。
最終日24日の遠足は、バスに乗って Zarasai というリトアニア北東の地域へ。今回の学会名にも冠してある Kazimieras Būga の出身地であるDusetos という町がある地域です。
言語学者のための大人の遠足、といったプログラムでした。
Kazimieras Būga(カジミエラス・ブーガ 1879-1924)は、リトアニア語・バルト語の歴史言語学に重要な功績を残した言語学者です。
リトアニア語の方言を詳細に聞き取り・書き取りし、たくさんの単語カードやノートにまとめて残しました。それらのデータを元に、リトアニア語のアクセント論、方言論、語源、地名の研究についての多くの論文を発表し、1902 年には Lietuvių Kalbos Žodynas (LKŽ) の編纂を始めました。
LKŽ は今ではオンラインでも公開されています。
私もLKŽをはじめ、Būga の metatony の論文や語源研究の論文にたくさんお世話になりました。
途中、Dusetos の教会(Dusetų Švenčiausios Trejybės bažnyčia)に寄ったり、お昼には Vasaknų dvaras のビール工場へ行って工場見学、そのままビールとお昼ご飯。


とはいえ、このIPA,すごく美味しかったです。
その後、いよいよ Būga の生家でもある記念館(Kazimiero Būgos memorialinio muziejus)へ。

こんなふうに、Būga の自伝を引用しながら、Būgaの生涯が展示されていました。

Būga は学者一家に生まれたというわけではなく、農家の出身でした。
パネルには、「父に初歩的な読み書きを習い、Šiauliai 出身の祖父と祈祷書を読みながら冬を二回(2年)過ごした。1892 年に(両親が)サンクトペテルブルク(大学)へと従兄弟と一緒に送り出した。」
とありました。
当初は神学部に入学したらしいのですが、一年で辞めて紆余曲折の後、なんとか言語学科に入学。言語学者としてのキャリアを始めたのだそうです。想像以上に苦学者。

Būga の人生についてはまったく知らなかったので、私が今まで読んでお世話になってきた論文や辞書を、彼がどんな思いで書いたのかの一端を知ることができて、良い機会でした
「Būga は、人生は自分の能力次第だということを示す良い例だよね」と知り合いが言った言葉が印象に残りました。
そうは言うもののもちろん、サンクトペテルブルクに留学させてくれた両親の後押しがあったから、Būga の才能も花開いたんじゃないかな・・・?
でも、留学先での本人の踏ん張りは並大抵のものではなかったようです。
なかなかに人生はたいへんなもので、ビールは飲めるときに飲んでおかねば、と思ったのでした。
行きのバスの中では、Vilnius 大学の先生方の庭で採れたというりんごや、途中サークルKで買ったホットドッグなどを食べながら、歴史音韻論やアクセント論の話をしたり元気でした。が、帰りは疲れてみんなウトウト。

そこらへんも含めて、楽しい遠足でした。
結局、大人の遠足の感想で終わってしまいましたけれど、
また次回まで、ご機嫌よう♪
Yamayoyam
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
