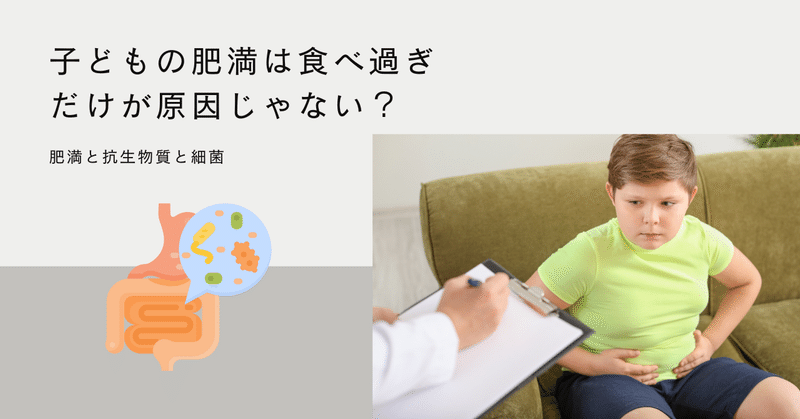
腸内細菌が乱れると子どもは太るのか? 抗生物質と肥満の関係
私たちは、毎日ものを食べる。
肉、魚、野菜、ご飯などの穀物、それからいくばくかのおやつ。
毎日同じものだけを食べる人もいるかもしれないし、一日たりともメニューのかぶらない人生を送ってきた人もいるかもしれない。
それでも、私たちの体はブロッコリーを食べたからといって緑になるわけでもなく、もも肉を食べたからといって太ももにだけ肉がつくわけでもない。
それは、まったく別物に見える食べ物が、消化管のおかげである程度共通した小さな構造になってから体に取り込まれるからだ。
食べたものは消化管の各部位を通過しながら順番に消化酵素の洗礼を受け、だんだんと小さなパーツに分かれていく。そして、小さくなった栄養分を小腸が効率的に体に取りこむ。
この消化吸収のプロセスには、腸内細菌たちの活躍が欠かせない。(※参考 腸内細菌の働きを、不躾ながらあっさりまとめます)
この事実は、日々体がぐんぐん成長する子どもたちにこそ重要な事実かもしれない。
前に見たように、赤ちゃんはビフィドバクテリウムという細菌によって母乳から栄養を得ることができる。
赤ちゃんが離乳し、だんだん大人と同じような食事を摂るようになるにつれて、莫大な種類の細菌たちがこの消化吸収運動会に参加する。
ある細菌はブドウ糖を利用し、ある細菌は乳糖を利用し、またある細菌はより高分子の多糖類を分解する。
リレーをするように他の細菌の仕事を引き継ぐ細菌もいる。
かれらの活動の結果、私たちヒトは大腸からも余さず栄養を吸収できる。食べ物を得ることが難しかったヒトの歴史において、細菌とヒトが共進化してきた賜物だ。
では、何らかの原因でマイクロバイオームの生態系が乱されてしまった場合、体の成長にはどのような影響があるのだろう。
※本記事は「腸内細菌は何歳までに決まる? 赤ちゃんから子どもへの成長とともに歩む菌たちのこと」シリーズの一部です。
別のシリーズ「全プレママ&パパに届けたい、妊娠・出産とマイクロバイオーム全まとめ(腸内細菌、膣細菌を中心に)」と併せて読むことを推奨します。
・本文中のカッコ付き番号は、記事下部の参考文献の番号を表しています。
・用語解説はこちら(随時更新)
・主要記事マップはこちら(随時更新)
肥満と抗生物質、そして腸内細菌の相互関係をもっとも研究している人物のひとりが、Martin J.Blaser氏(当時ニューヨーク大学教授、現ラトガーズ生物医学および健康科学先端バイオテクノロジーおよび医学センターの所長)だ。
彼はもともとピロリ菌の研究をしていた微生物学者で、2007年に発足したヒト・マイクロバイオーム・プロジェクトのリーダーだった。
彼は、腸内細菌と肥満や糖尿病などの疾患の関連を研究する過程で、子どもたちに対する抗生物質の使用が細菌の構成、さらには代謝に大きな影響を及ぼすことを見出した(1,2)。
細菌とアジア人の高身長化は関係がある?
彼はまず、人々の身長が高くなっていることに気がついた。
1975年に東京に滞在していたBlaser氏が地下鉄に乗ると、身長187cmの彼の眼下には黒髪の海が広がっていた。
その光景はその後東京を訪れるたびに変わっていった。
ちらほらと抜き出た頭が見えるようになり、特に若くて背の高い人が増えた。
ヨーロッパよりも、アジアでこの高身長化が顕著らしい。
栄養条件がよくなったというだけでは、この高身長化を説明するには不十分だった。
そこで彼は、細菌感染の減少が高身長化に貢献しているのではないかといういくつかの証拠を「身長の生態学ーー微生物がヒトの身長に与える影響」と題して発表したが、記事は注目を集めなかった。
彼はその続編「体重の生態学」も構想していたが、別のもっと面白そうなテーマが見つかった。それがまさしく、抗生物質と肥満の関係だった。
抗生物質は太る?
細菌感染の治療薬である抗生物質は、ある種の細菌を殺してしまう。
当然、腸内細菌の生態系は変わる。これがなぜ肥満と関係するなどと考えたのだろう?
実は、抗生物質が太るという事実は、当時の酪農家たちにとってほとんど常識になっていた。
抗生物質は益こそあれ害はないと信じられていた時代、低用量の抗生物質投与が家畜の成長促進に役立つことを彼らは知っていた。
抗生物質は同時に、家畜の感染症も防いでくれるので、使わない理由がなかった。
近年になって規制は進んでいるものの、まだまだ畜産や水産業における抗生物質の使用は残っている。
これはつまり、薬として抗生物質を飲まなくても、日々の生活で私たちの体には抗生物質が入り込む余地があるということを意味する。
肥満の原因は抗生物質そのものではなく、その結果だった
Blaser氏らのチームは、一連のマウス実験によって肥満の原因が抗生物質そのものではなく、抗生物質によって変えられたマイクロバイオームであることをつきとめた。
治療用量以下の抗生物質を与えられたマウスたちは、例外なく肥満した。
そのマウスの糞便を移植されたマウスたちも。
同じように、治療用量での抗生物質を断続的に数クール投与する実験でも、同じ結果が得られた。
つまり、日常生活からの低用量の抗生物質摂取も、治療としての抗生物質摂取も、肥満リスクを高めるということだ。
興味深いと同時に深刻な事実もある。
抗生物質の投与を中止すると、マイクロバイオームの構成は多くの場合もとの状態に回復した。
にもかかわらず、抗生物質を一度投与されたマウスは太ってしまったのだ。これは、一時的な抗生物質への暴露が、代謝系を長期的に変えてしまったということを示唆している。
この素晴らしく緻密な実験の詳細は『失われてゆく、我々の内なる細菌』13章をぜひご覧いただきたい。
この実験群には、現代の子どもたちが肥満傾向にある理由が隠されていた。
まず強調しておきたいのは、この肥満効果は生後早いうちに抗生物質が投与されるほど大きかったという事実だ。
抗生物質を処方されすぎている子どもたち
多くの先進国の子どもたちは抗生物質を処方されすぎている。
1991-1992年にイギリスで生まれた子どもたちは、生後半年以内にその3分の1が、生後二年以内にその4分の3が抗生物質治療を受けていた。
デンマーク(3)、イギリス(4)、カナダ(5)、アメリカ(6)の疫学研究では、抗生物質と肥満の関連がマウスだけではなくヒトにも当てはまることが示された。
日本では、薬剤耐性菌への対策として2018 年 4月に小児抗菌薬適正使用支援加算が新設され、医療機関での抗生物質過剰使用を適正化しようと試みられている。
私の2歳半になる娘も、ウイルス性の風邪では抗菌薬(抗生物質)が処方されないかわりに、この点数が加算されている。
さて、肥満の原因が抗生物質そのものではなく「乱されたマイクロバイオーム」であるなら、他にも肥満に影響をあたえる要因はたくさんある。
これまで見てきたように、妊娠中の母親のマイクロバイオームや、分娩方法、母乳の有無は生後間もない赤ちゃんのマイクロバイオームを決める重要な因子だろう。
成長とともに共生マイクロバイオームを獲得していく過程で、現代的な生活がどれほど影響しているのか、世界中で研究が進んでいる。
次回の記事では、マイクロバイオームが乱れることで逆に低体重になってしまうケースを考えていきたい。
1. Cox LM, Blaser MJ. Antibiotics in early life and obesity. Nat Rev Endocrinol. 2015;11(3):182-190. doi:10.1038/nrendo.2014.210
2. マーティン・J・ブレイザー. 失われてゆく、我々の内なる細菌. みすず書房; 2015.
3. Ajslev TA, Andersen CS, Gamborg M, Sørensen TIA, Jess T. Childhood overweight after establishment of the gut microbiota: the role of delivery mode, pre-pregnancy weight and early administration of antibiotics. Int J Obes 2005. 2011;35(4):522-529. doi:10.1038/ijo.2011.27
4. Trasande L, Blustein J, Liu M, Corwin E, Cox L, Blaser M. Infant antibiotic exposures and early-life body mass. Int J Obes 2005. 2013;37(1):16-23. doi:10.1038/ijo.2012.132
5. Azad MB, Bridgman SL, Becker AB, Kozyrskyj AL. Infant antibiotic exposure and the development of childhood overweight and central adiposity. Int J Obes 2005. 2014;38(10):1290-1298. doi:10.1038/ijo.2014.119
6. Bailey LC, Forrest CB, Zhang P, Richards TM, Livshits A, DeRusso PA. Association of antibiotics in infancy with early childhood obesity. JAMA Pediatr. 2014;168(11):1063-1069. doi:10.1001/jamapediatrics.2014.1539
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
