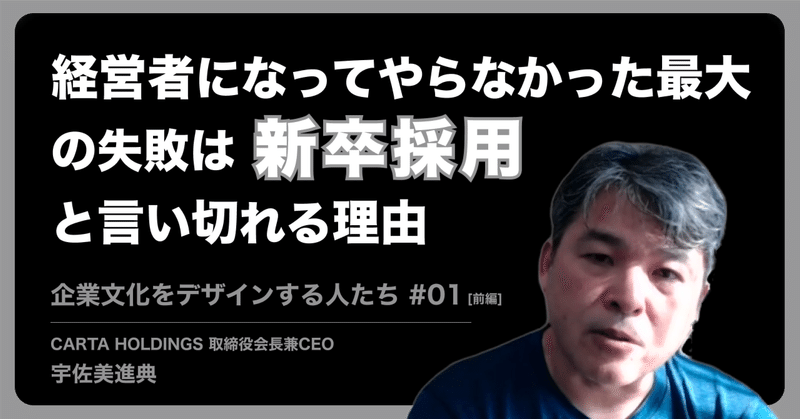
経営者になってやらなかった最大の失敗は「新卒採用」と言い切れる理由|企業文化をデザインする人たち#01[前編]
2023年6月1日に出版される「企業文化をデザインする」を執筆する過程であらためて実感した「企業文化」の底知れぬ奥深さと影響力。
そんな「企業文化」をさらに深め、多くのビジネスリーダーにとって「デザインする価値があるもの」にすべく、「企業文化」と常に向き合ってきたIT業界・スタートアップのトップランナーにインタビューする企画をスタートさせました。
ーー「企業文化をデザインする人たち」

今回がそんな連載企画の第1弾。トップバッターは私自身が自らのキャリアで多くを教わってきた、現CARTA HOLDINGSの宇佐美さんとの"カルチャー対談"です。
前後編2回にわたって公開する前編です。
後編はこちら
話し手|CARTA HOLDINGS 取締役会長兼CEO 宇佐美進典

1996年、早稲田大学商学部を卒業後、トーマツコンサルティング(株)(現デロイトトーマツコンサルティング)に入社。大手金融機関の業務改善プロジェクトやシステム化プロジェクトにコンサルタントとして従事。その後ソフトウェアベンチャー企業への転職を経て独立を決意し、1999年に(株)アクシブドットコム(現当社)を創業。取締役COOに就任後、2002年には代表取締役社長兼CEOに就任。2005年には、(株)サイバーエージェントの取締役に就任。メディア部門副統括、技術部門担当役員として、既存事業の立て直しやアメーバの成長に携わり、幅広く経営の実務を経験。2010年からは、当社の成長にフルコミットし、MBOやCCI社との経営統合を経て現在に至る。
聞き手|株式会社ラントリップ 取締役 冨田憲二

2006年、東京農工大学大学院(ビークルダイナミクス)卒、株式会社USENに入社。その後ECナビ(後のVOYAGE GROUP、現CARTA HOLDINGS)に入社し複数の新規事業を担当後、子会社として株式会社genesixを創業、スマートフォンアプリの制作とプロデュースを行う。2013年に創業期のSmartNewsに参画し、グロース・マーケティング・セールス事業立ち上げを経て当社初の専任人事となり50名から200名への組織成長と企業文化形成を担当。現職は株式会社ラントリップで事業・組織推進に従事しつつ、複数社のスタートアップで企業文化・人事組織アドバイザリーを担当。2023年6月1日に初の著書「企業文化をデザインする」を出版。
今、「企業文化」をテーマにする必然性とは

冨田憲二(以下、冨田)|本日は旧VOYAGE GROUPの卒業生として、宇佐美さんと「企業文化」をテーマに話せることを楽しみにしてきました。宜しくお願いします。
宇佐美進典(以下、宇佐美)|トミーが卒業してもう10年も経つのか、今日は宜しく。インタビューの前に、そもそも何で本を出版することになったの?
冨田|「企業文化」に関してこのnoteで発信していたのが直接的なキッカケですが、より本質的なキッカケはSmartNews時代に初めて人事・組織を管掌することになって初めて、自ら「企業文化を意識的にデザインする」ことをやったんですね。
そこで良い部分も悪い部分も含めて本当に強烈な思いをしたので、それがnoteに発信する原動力になりました。「企業文化」の奥深さや力強さを、もっと多くの人に知ってもらわねばという謎の衝動ですね(笑)
卒業してからもしばらくSmartNews社にはアドバイザリーとして残ったり、他のスタートアップでも企業文化・人事/組織のアドバイザリーで関わることでさらに自分の中で深まっていきました。
出版の声はたまに頂いていたのですが、その中でも優秀な編集者さんが私のnoteを読み込んでくれて「目次」まで作ってくれたんです。「これで本を出版しましょう!」と。
本当はスタートアップの経営者が本業の側で本を書くなんてやるべきではないと思っていたんですが、現職(ラントリップ)代表の大森、チームが後押ししてくれたので、色々とお言葉に甘えさせて頂いた形です。逆質問ありがとうございます。
「なぜこんなに差がついたのか…」サイバーエージェント傘下で学んだ"カルチャー"の力
冨田|まず最初の質問なのですが、起業してから、はじめて「企業文化」を意識したのはいつのどんなタイミングですか?
宇佐美|最初に起業したのが1999年の5月で、これは社員を採用してっていうよりも個人会社としてだった。その次にアクシブドットコムを99年10月に作った。最初は当然「企業文化」に対する意識なんて全く無かったよね。
ただ、最初に就職した会社がコンサルティング会社で、その社会人1〜2年目の時に「経営破壊/トムピーターズ」を読んだんだよね。そこでこれからの時代は「ネットワーク型の組織」だと。そこから「こういう組織を作りたい」という観点を漠然と持つようになったかな。
「ネットワーク型組織」
特定のリーダーを設定せずに、チームメンバーがフラットな立場として、チームの皆でアイディアを出し合いながらひとつの仕事に取りくむ組織のこと。 特徴としては、自由な意見が言いやすいことや、素早い意思決定、また立場に関係なく業務に取り組みやすいことがあげられる。
そして一番の転機はやはり2001年9月にサイバーエージェントの傘下に入ったこと。そこで「企業文化」の違いを強烈に学んだよね。
サイバーエージェントの設立が1998年3月、社長の藤田さんも僕と近い年齢だった。同じようなタイミングで起業した年齢の近い経営者の会社。それなのになぜこんなに差がつけられてしまったんだろうと。
冨田|自社のDNAと異なる会社を深く知ることは、逆に己を深く知ることに繋がりますよね。自社の「企業文化」が良い意味でも悪い意味でもクリアになったということですね。
宇佐美|そうだね。そして「企業文化」における最大の失敗もその過程で学んだ。それは、やったことの失敗より「やらなかった失敗」なんだよね。
それが「新卒採用」だった。
「企業文化」ってキャリアと一緒で、入社時からゼロベースで一緒に作っていったほうが確実に育みやすい。
ITベンチャーや今時のスタートアップだと、どうしても中途・即戦力が中心になってしまうのだけど、自社の文化を育む強い意志と覚悟を持って会社を経営するという視点に立つと「新卒採用」というのは、やっぱり欠かせない。
藤田さんは最初から「企業文化」という観点で意識していたわけでは無いだろうけど、新卒採用を中心にそれをもの凄くうまくやっていた。
結局僕たちが新卒採用を本格的に実施できたのが2004年〜2005年ぐらい。そこから徐々にあるべき方向の「企業文化」を作れてきた気がするね。だから、それまでやれてなかった「新卒採用」というのがやらなかった最大の失敗経験。
冨田|サイバーエージェントさんのいわゆる「プロパー」を中心とした文化醸成は本当に学ぶべきことがたくさんありますよね。今回の書籍でも学ぶべき生きた事例として深掘りさせて頂いています。
他にサイバーエージェントや藤田さんから学んだ「企業文化」の凄みはありますか?
宇佐美|あとは「言葉」の力だね。例えば「21世紀を代表する会社を作る」とか、そういった「経営理念」もそうだし、採用における「素直でいい奴」とか、未だに根付いている言葉の捻り出し方、使い方が当時から絶妙にうまかった。
そういった「言葉」と浸透している実際の「企業文化」がかなりシンクロしてるんだよね。経営陣だけが「俺はこういう会社にしたい」と思っていても、現場では全然そんなことが起きてないってことがよくあると思うんだけど、経営陣の「言行一致」の徹底が凄い。そして当然、そのための巻き込み力が半端ない。
魂の入った言葉、それを「言行一致」で浸透し続けないといけない。経営だけが言っている言葉ではなく「自分たちの言葉」で語れる魂の入った言葉をちゃんと作るということだね。
企業文化は事業内容によって変わる。
冨田|私がVOYAGE GROUP(当時のECナビ)に入社したのが2008年で、実際「混在した企業文化」という印象の元に、サイバーエージェントの「人材」も一定存在していた印象があります。「企業文化の輸入」において、やはり「人」そのものが大事だったのでしょうか?
宇佐美|当時の僕の印象で、サイバーエージェントって「狩猟民族的」カルチャーがある一方で。その当時ECナビは「農耕民族的」なカルチャーだった。これは事業内容によって組織のカルチャーが変わると思っていて。メディア中心の会社は農耕民族的なカルチャーになるし、一方で営業が強いと「狩猟民族的」カルチャーになる。
当時「ウェブ2.0」的な大気のトレンドの変化があって、そういった外部環境が目まぐるしく変わっていく中で、その環境に合わせて自分たち自身のビジネスモデルはもちろん、企業文化も変えていかないといけないという危機感があった。このまま農耕民族的な企業文化やり方だと、その世の中や環境の変化についていけないんだろうなって。
冨田|人に紐づいた企業文化の違いって、DNAや血液型みたいなものだと思っているので。自社のDNAや血液型とは明らかに違う人材を輸入してカルチャーを変えていくというのは、結構勇気がいることだと思うんですけど。
宇佐美|もちろん覚悟の上でではあったよね。でも結局変えていかないと会社がもう生き残れないっていう、そういう時間軸的な危機感もあったから。
あの当時は色々な変化があった。まず主力事業の「MyID」をビジネスモデルから「ECナビ」に転換。これは環境変化に合わせたビジネスモデルの陳腐化に対する適応。
次に農耕民族型のカルチャーから狩猟民族型のカルチャーへ移行しつつ、組織形態を機能別組織から事業部制に移行した。
血の入れ替えを中心とした覚悟のカルチャーアップデートの真相
冨田|組織形態まで、ものすごい外科手術をしたんですね。
宇佐美|当時機能別の組織で120人ぐらい。外部環境のスピード感に対して、色々なスピード、いわゆる意思決定のスピード感がすごく遅くなったんだよね。何か新しいことをやろうとしても他の部署とちょっと調整してからみたいな。
恐竜が絶滅した時みたいなね。そんな感じで凄く大きな図体になって環境の変化に対応しにくい組織になっていた。こういう環境変化がある時に哺乳類がでてきて次の時代を作ったわけで。その当時は「やばい。俺らいつの間にか恐竜になってる」みたいな感覚だったね。早く哺乳類に進化しなくちゃみたいな。
冨田|外部環境のマクロ的な変化やスピード感、事業モデルの陳腐化サイクルと組織の整合性。そういったものをメタ認知できていたのも凄いし、認知した上で実行にまた落としていくのはかなり難易度高いですよね。
宇佐美|覚悟を決めてたっていうのもそうだし、生きた事例としてサイバーエージェントができてたから。
こういうやり方をすればっていう、ある意味理想とする部分が見えたのは大きいよね。現実の自分たちがやってる部分と、あとはこのギャップをどう埋めますかって話。だから迷いも無く、あの当時は事業も文化も大きく変えていけたんだと思う。
冨田|私のユーザー体験でいうと、当時のECナビには「狩猟民族」的カルチャーを背負った人材に惹かれて入ったんですよね。実際入ってみたらそんな人たちばかりではなかった。そういった「異文化」が混在している状況を経験できたのは貴重な体験でしたね。
目の前で違いが見えるから、逆に自らを知ることができるわけで。そこから本業以外にも社員総会の総合プロデューサーを3回担当したのですが、そういった文化のグラデーションがハッキリと存在する中で、全社的にカルチャーをアップデートしていく過程は強烈でした。
宇佐美|当時の総会プロジェクトは狩猟民族的なメンバーが多かったからね。僕が思うに狩猟民族って「寂しがり屋」多いんだよね。だから一人、二人だけ入れても直ぐに辞めちゃう。ある程度の規模で固めてあげないと。お互い切磋琢磨できたり、刺激が足りないとダメなんだろうね。そういうところは割と意識してやってたな。
画期的な社内バー「ajito」が企業文化にもたらした本当の恩恵
冨田|企業文化が完全に「狩猟型」にコンバートしたと思ったのはいつぐらいですか?
宇佐美|いや、結局「ミックス」されたっていう感じだね。僕のイメージで言うと、思いっきりこっち側に振ったというよりは、いい感じに「らしさ」を作れた感覚はあるな。社内バーの「ajito」とかはその象徴だったよね。
冨田|「ajito」は私も相当使いました。あれは本当に「生きた福利厚生」でしたね。あらためて設置の経緯や、企業文化観点での恩恵などを教えてもらって良いですか?
宇佐美|サイバーエージェントの役員に入ったのが2005年からなんだけど、当時Jリーグの「ベルディー」出資してスポンサーになったり、原宿にアメーバのスタジオを作ったりしたタイミングだったんだよね。当時は正直、なんでそんなことにお金使うんだろうと。
だたその一年後、二年後っていうのをこう見ていた時に、そういったところ取り組みがやっぱりいろんなところに効いている感覚があった。
それで、自分自身やっぱり事業をものをすごく「P/L」で考えたなと。それだけではなくて、いかに「B/S」をうまく使っていくか。ここに経営のセンスが表れるなと。
それでB/Sを戦略的に活用していく意識がすごい芽生えた。
冨田|なるほど。確かに「企業文化」の話も、基本「P/L」ではなく「B/S」的な視点ですよね。
宇佐美|そうそう。またその話とは別で、当時社内のコミュニケーションを活性化させていきたいという全然別の課題意識があった。
さらに会社の知名度をどうやって上げていこうか。戦略的に福利厚生で考えようとなった時に、見た瞬間に「なんじゃこれは!」って思わるものが良いんじゃないかと。その当時の時点で「社内バー」やってる会社はあったんだけど、当時思ったのはなんかワインセラーがあったりスノッブな感じで、社長のエゴっぽい感じだったんだよね、本当に社内で皆んなが使ってるの?っていう(笑)
それよりも小学生の頃、秘密基地作ってみんなで遊んでるみたいなワクワク・ドキドキ感、遊び心があった方がITベンチャーのカルチャーだなって。
これは絶対「新卒採用」にも効くし、そいうった色々なニーズが合致したんだよね。
あとは当時サイバーエージェントの役員をやっていて、サイバーがやらないことをやろうと。他の会社がやっていないこと。これはその後の「Frontier」などの「学生インターン」もそうなんだけど、他社がやっていないことをむちゃくちゃ凄いレベルでやって初めて「凄い」って言われるんじゃないかと。期待を超えないと驚きは生まれないし、覚えてももらえない。
それでいて、実際に意味があって利便性があるもの。それでああいったコンセプト・形の社内バー「ajito」が生まれたんだよね。

冨田|私は本当にあの場で採用イベントに参加して学生さんとたくさん交流したり、やっぱりカルチャー叩き込まれたイメージありますね。当然普段はフラッと寄るといろんな人と斜め横で繋がれたんで。当時はそこを自分がデザインする側ではな無かったので気づかなかったのですが、今振り返ると巧妙に仕組まれたなって(笑)
宇佐美|当然だけど、めちゃくちゃ考え抜いた結果あの形にになったよね。そして、それが結果的に他社が真似できない独自の「企業文化」や「らしさ」に繋がっていったんだろうね。
ーーー
後編へ続く。
編集後記|新卒採用は"トレードオフ"なのか。
スタートアップを経営していると、それは「時間軸」との戦いでもあり、ゆえに「即戦力」をいかに採用するかという視点にフォーカス当たりがちです。ただし、企業経営という長い旅路に想いを馳せると、揺るぎない自社の「企業文化」に投資をし続けること。そのために「新入社員」を採用し、育成して自社のコアメンバーに育てることの合理性が自然と湧き上がってきます。
今回のインタビューで宇佐美さんの口から何度も語られた「覚悟」という言葉。ファーストキャリアの人材を見出し、採用し、同じ船に乗せ、一緒に自社のカルチャーを創り、カルチャーを自らの言葉で語ってもらうこと。このカルチャーの循環を何度も何度も繰り返すことによって、ようやく本物の「自分たちだけのオリジナル」が磨き上げられるのかもしれません。同時に事業を創り、事業を修正し、必要とあれば人材・カルチャーという「血」の入れ替えも厭わない。そうやって共に熱くなれる仲間を育て、外部環境の変化や外圧に負けない「コア」を覚悟を持って築き上げていく。
企業文化というものは、そんな「内部の熱狂」と「外部の濁流」に揉まれながら磨き込まれていくものだと思います。そして、常に内外から問われるのは、組織構造上の上位にあたる経営トップや幹部の日々の言動や行動。「言行一致」がこれほどまでに重要なのは、新入社員を含めた多くの視線がトップの背中に集まり、組織全体はトップの生写しになるから。企業文化が正しくデザインし続けられるかは、結局はそんなトップの「覚悟」次第なのかもしれません。
本書の「はじめに」と「序章」を無料公開しています。
#01 |CARTA HOLDINGS 取締役会長兼CEO 宇佐美進典
#02 株式会社マネーフォワード People Forward 本部 VP of Culture 金井恵子
#03 ex-SmartNews, Inc. Head of Culture Vincent Chang
#04 株式会社グッドパッチ People Empowerment室 人事 高野葉子
応援が励みになります。頂いたサポートは、同僚にCoffeeとして還元します :)
