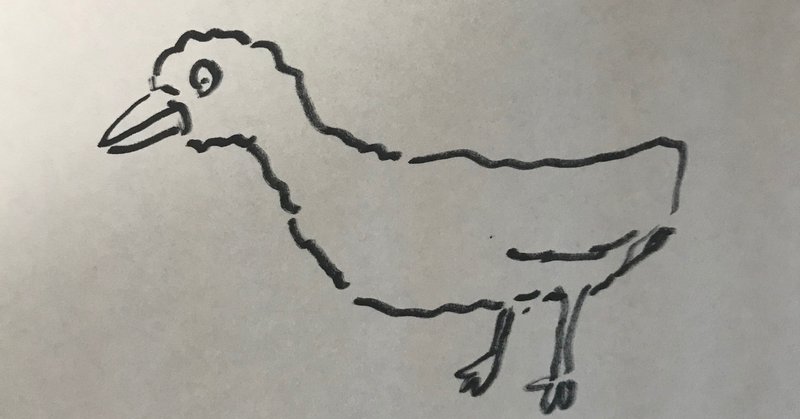
生命倫理についてのメモ、フォアグラ、カント、孟子
急に生命倫理について考えたのでメモ。
生命倫理における同一化の問題。例えばフォアグラ。フォアグラは動物愛護の視点から強く批判されるのは有名な話。そこでその議論の中心にあるのはその製造過程のグロテスクさ。拘束され強制的に餌を食わされるガチョウ。そこでの争点は「苦痛」。苦痛の問題。伝統的な哲学観でいうなら、動物は「水のなかに水が存在するように存在する」(ヘーゲル)とされる。動物は言語を持たないのだから苦痛を意志において分離できない。分離という操作がないのだから、時間という機能が存在せず、よって知覚もない。要は「苦痛」なんて人間の物差しに過ぎないという話。このようなオーソドックスな批判が可能である。で、この批判は伝統哲学のノリに加えてリバタリアニズム的な自己責任とも共振する。人はそれぞれがそれぞれの責任を自らで負い自らで行動する。個人主義と自己責任。ガチョウの苦痛はガチョウのものである、というわけ。
さてこのガチョウへの共感VSガチョウへの同一化の不可能性という図式。ガチョウへの共感サイドは自らの食べるものは自らで全て理解しなければならないという倫理、及び苦痛には人間も動物も関係がないという倫理に支えられている。対してガチョウへの同一化は不可能であるという別の倫理がある(「倫理なし」についてはここでは触れない)。しかしこの視点は極めて西洋的な二元論をその根底に持つ双子にすぎないとも言える。理解できるか理解できないか、全面的な関係か全面的な無関係か。
ここで孟子を引いてみる。孟子はこんなことをいっている。供物にされる牛が通りかかるのを見かけた王様。そこで王様がいう。「その牛なんか可哀想だから助けてやってよ。供物とかやめてさ」で従者はいう。「おっけーっす!」、そして別の牛が供物に捧げられる。これを孟子は肯定する。カントなら激怒りする。カントならば一頭の牛を助けるなら(牛が供物になるのが倫理的に許されないなら)、全ての牛は助けられなければならない、そういうだろう。カントの有名な定言命法ってやつだ。「あなたの意志の確率が、つねに同時に普遍的立法の原理として妥当しうるように、行為せよ」。要は道徳や倫理は時間や空間、TPOに「一切」関わってはならない。多分哲学やってない人はそんな無茶な!と思うだろうけど、一見不可能に見えたり、潔癖に見たりするこの原理の強度は途轍もない(そしてそのカントの定言命法こそが、前半部分で書いた全面的な関係か全面的な無関係かという二分法を作り出す)。
でも実際、頑固親父カントが怒り出す通り、この救済にどれほど意味があるだろうか。結局「その牛」が助けられても別の牛が代わりに死ぬ。そして動物愛護の観点からしてもこの世界の苦痛の総量は減っていないので無意味。リバタリアンからしても余計なお節介。カント的にはそんな判断は一時的な判断(気まぐれ)に過ぎず、普遍的な判断(道徳律)ではないので倫理的ではない。ではここにどんな意味を見出せるか。
フランソワ・ジュリアンというフランスの思想家の論を引こう。孟子の判断の根底にあるのは、普遍的な法に遡行して機能するような道徳ではなく、ある種の情動、「憐れみ」を基点としてのみ機能する道徳である。逆にカントの道徳はいつでも普遍的な法が参照されてからその判断/行為がなされる。孟子の道徳はそうではなく、その場その場で情動的に、悪く言えば気まぐれに機能する。つまりそれ自体が道徳そのものであるような行為。だから孟子の道徳は苦痛の総量とか、道徳律とかそういう眠たいことを考えない。は?でも普通に意味なくね?とお思いでしょうか(孟子は実はそのその場その場の道徳、善意は他の人に波及して、善いことをする人が増える、みたいな面白いことも言っている。なので単に「その場その場」の話だけではなく、普遍的なものを頼らずに「その場その場の道徳」が拡大していくというところもセットで孟子なのですが、その話は置いておきます)。ここにぼくなりの調整を加えてみる。
カントと孟子の対立は、普遍と経験の対立である。もっとわかりやすく言い換えると、「悪」の現場に「立ち会う」ことで機能する道徳を支持するか、立ち会わずとも機能する普遍的道徳を支持するかという対立。またさらに別のレイヤーを重ねてみると、悪を探しまわり精査する監視型の道徳か、悪を探しはしないけど見かけたら「怒る」道徳かともいえる。権力と自治。
柔らかい言葉で客観的な論証のみで書くととっても回りくどくなるので、論証なしの話でいうと、ぼくは後者の方が好き。カントの道徳の「無力さ」は「見かける」という観点がないことに起因している。カントは「その場その場」という感覚を捨象して、しかし同時に客観的に定義できる「苦痛」という事実を採取することでやっと機能する。実は動物愛護的な「苦痛」は主観的な感覚というよりも、「証明」の道具立てとして用意されている。つまりは「苦痛があるなら助けなければならない」のための「苦痛」。普遍的な法に適うから助ける。しかし孟子の道徳的判断にはその「苦痛」という内面の事実性すら必要がない。「苦しそう」なら助ける。もっというなら「苦しいように見えるなら」その事実性を確かめるまでもなく助ける。これは一般的な言葉でいう「共感」に近い。しかしこの「共感」には強い意味での同一化という操作がない。そして何よりも、この共感は節度を知っている。「製造過程」をすべて理解し、監視し、把握し、なおかつ苦痛の総量を勘案するような道徳とは違う。カント的道徳は苦痛の真実性/普遍的な意味にこだわる。「苦しそう」は「苦しい」という事実とは完全に別のものである。それは「そう見える」ことにすぎない。そして主観的な情動であるのだから普遍化もできない。
フォアグラの話に当てはめてまとめてみる。カントは個別の判断を認めないので、フォアグラを認めるなら認める、認めないなら認めないのどちらか。そしてカントの応用であるところの苦痛論における苦痛は、全てのフォアグラの製造を批判するために機能する。苦痛はガチョウの内面の問題なので、個別の「出会い」とは関係がない。ガチョウへの「虐待」は誰かに目撃されようとされなかろうと批判されなければならない。かくしてガチョウの主観的な苦痛が、普遍性に裏返る。対して孟子は裁く相手を探さない。でも見かけた時共感したら助ける。その際、一切の同一化の手前で、勝手に、自己の判断で助ける。ガチョウとの「出会い」を基点とする偶然的に起動する道徳。
ぼくは孟子の「中途半端な」道徳律を支持するのでフォアグラを食べる。でもフォアグラの製造過程を見たら耐えられないかもしれないし、怒るかもしれない。「見かけたとしたら」、この仮定法を生き残らせること。この「余裕」が生き残ること。カントの善意は社会を圧迫し、監視する。他者に普遍的な判断を求める(動物愛護団体の話法、「フォアグラを作らせている社会で黙っているならそれは肯定していることと同じ」という話法は今やリベラルの得意の話法になった。他人に意見の提示を強制する話法)。孟子の善意。社会や関係性のダイナミズムを圧迫しない善意。いや、むしろそれ自体が社会のダイナミズに寄与するような善意。
ところで社会のダイナミズムとは、普遍化不可能な「その場その場」の判断の集積であるような、全面的な無関係と全面的な関係という二分法のあいだ、一時的な関係と一時的な無関係のなかでこそ編まれるものである。
なんだ結局書き終わったら社会論になってしまった。社会の「機能」として道徳を考えるなんて!というカント大先生の怒声が聞こえるようだ。あとガチョウめっちゃ可愛く描けた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
