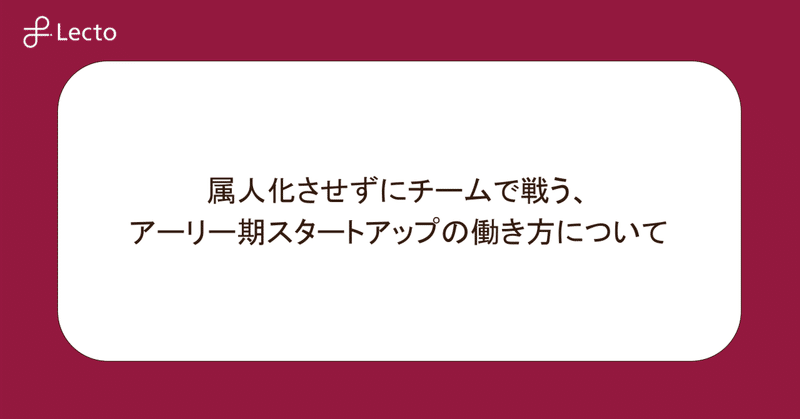
属人化させずにチームで戦う、アーリー期スタートアップの働き方について
こんにちは、takです!
このNoteでは、「金融の摩擦を解消し、人の無限の可能性を解き放つ」をミッションに掲げ、"債権管理・督促回収プラットフォーム Lecto"を提供するLecto株式会社のカルチャーや働き方についてご紹介します。
Lectoの事業については取締役COOのKeisuke.SerizawaのNoteをご覧ください!
自己紹介
改めまして、takです!
Lecto株式会社で事業開発ポジションを担当しています。
Lectoではポジションに囚われず事業全般に関われるため、自分や他のセールスメンバーも含め、マーケ・営業・カスタマーサクセス・採用人事など色々な業務に携わっています。
趣味は犬猫・ギター・息子のサッカー応援です。
Lectoに入社したのは2021年6月となり、現在3年目に突入しました。
子育てのしやすさと全力で仕事に挑戦できる環境を求めて、初めてのスタートアップに飛び込み、目まぐるしい日々を楽しんでいます!

Lectoでどんな人が働いているのかイメージしていただくために、簡単に自分の経歴も紹介させていただきます。
大学では情報科学を専攻し、プログラミングや音声信号処理を学びました。
高校から趣味でギターをやってたことから、ゼミでは音源データを入力して楽譜を自動出力する雑プログラムを作ったりしていました。
今でもこっそりギターを弾いています。
社会人になってからは、映像・音響製品を扱う会社で法人営業を1年間経験しました。企業の会議室やカンファレンスホールなどの映像音響空間を作る仕事をしていました。六本木あたりのビルにはよく足を運んでおりました。
社会人2年目になるタイミングで、IT業界へ転職し、金融領域に強い一部上場SIerでシステムエンジニアとして保険業向けのシステム開発に従事しました。後半では10名ほどのチームも持たせていただきながら4年ほど働き、webシステムやプロジェクトマネジメントを学ぶことができました。
その後社内異動によって経営企画部所属となり、全社の予算管理・決算対応・IR対応・M&A・経営会議体運営などを行なっていました。
代表直下で各事業部長と連携しながら、2000人ほどの組織をマネジメントするためのプロセスを回したり、世間に開示する間違えられない資料をひたすら作ったり、社内で2例目のM&Aにクロージングまで携わらせていただくなど、とても貴重な経験をさせていただきました。(心身ともになかなかハードでしたが、良い思い出です。)
上場企業の経営企画として千人規模の組織をマネジメントするプロセスを体感することができましたが、当然ながら大きな組織であるが故のしがらみも多く、今度は逆に「ゼロに近いフェーズのスタートアップで事業・組織作りをやってみたい」と考えるようになってきました。また、「子供が小学生に入るタイミングで子供に向き合う時間を増やしたい」といった仕事と家庭のバランスの最適化にも意識が向くようになりました。
そんな中、当社株主であるALL STAR SAAS FUNDさん主催のウェビナーをたまたま見た際に、タレントパートナーである楠田さんとご面談の機会をいただき、出資先のスタートアップ数社をご紹介いただきました。
何名かのスタートアップ経営者や社員の方々とご面談させていただき、その中で事業フェーズが一番若く、経営者・既存メンバーとのフィーリングが一番あったLectoに入社させていただくこととなりました。
Lectoが大切にしている文化について
Lectoと接点を持ち始めたのは2021年2月末頃で、まだ事業を始めてから2ヶ月経ったくらいの時期ですが、当時からすでに大切にしたいValueやCultureが言語化されていました。
今回はそんなCultureについて、いくつか紹介していければと思います。

カルチャーの1番目に掲げているのが"家庭優先の意思決定ができる"です。
私の転職理由の一つに「子供と向き合う時間を増やす」という目的があったので、当時はフルリモートが可能かつ自分の経験が活かせる環境を探していました。
※後者については複数職種に就いてきた経験を活かしたく、総合格闘技と呼ばれる創業期スタートアップに興味が湧いていました。
そんな中、"家庭優先の意思決定ができる"ことをCultureの1番目に掲げているLectoに興味を持ちました。実際に創業者である小山・芹沢や、後にCTOになる八木と話しをすると、家庭優先の意思決定ができる組織を本気で作ろうとする気概を感じました。
「仕事と違って家庭に関することで自分の代えは効かないから」と、話としてはよくあるセリフを言っているものの、Cultureを言語化する上で一番優先したい項目として"家庭優先の意思決定"を選んでいて、組織作りを行う上で根幹にある思いなんだろうなと素直に受け止められました。
自分もそういった組織作りを行いたいと強く共感しましたし、まさにこれからCultureを体現した組織を作る段階であることにとてもワクワクしました。
※ちなみにここでは家庭という表現をしていますが、配偶者・子供の存在は関係ありません。ご親族である場合もありますし、自分自身が仕事以外で大切にしているものもこの言葉には含まれています。Cultureの表現や項目をアップデートしよう、といった活動も最近進み出しているので、別途記事にできればと思います!
背中を預け合いながら、属人化をなくしていく
"家庭優先の意思決定ができる"ようにするためには、特定の誰かしかその仕事がわからない または できない状況を避けなければいけません。いわゆる属人化ですね。
家庭を優先した意思決定をするためには、その人が抜けた穴を補完しなければいけません。
そのために、Lectoでは"透明性の最大化"もCultureとしており、公開しない情報を定義し、それ以外は全てをメンバーにオープンにしています。
事業計画や営業案件の進捗状況、プロダクトの開発状況から個人の日記に至るまで、あらゆる情報が社内でオープンになっています。
またメンバー個々人を見ても、自分の次の人がその仕事に取り掛かった時に困らないよう、情報をアウトプットして残していくことの重要性を理解して、日々行動しています。

このような環境を意識して組織を運営することで、業務が人に張り付く状態を極力避けています。
また、新機能の設計方針や営業施策の検討状況など、今後やろうとしていることもドキュメントとコメント機能の中で検討が可能なので、働く時間が被らない場合でも一緒に仕事を前に進めて、意思決定を行える環境となっています。
働く環境やツールについて
Lectoは現在、フルリモートでの働き方を前提として組織作りを行なっています。一都三県に在住のメンバーが現時点では多いのですが、栃木や愛知で働いているメンバーも既におり、また地方在住の方との採用面談も増えてきています。
そのため、上述しているようにチャット・ドキュメントでの非同期コミュニケーションを重視しています。

ただ、会話によるコミュニケーションを軽視している訳ではなく、オフィスにいるようなコミュニケーションの取りやすさ・楽しさも再現したいという意見も出てきました。そこで現在はGatherというバーチャルオフィスを導入して、基本的に稼働時間はGatherに出勤する同期・非同期のハイブリッド型で働いています。
こんな方にLectoはオススメです!
2023年12月現在、Lectoは正社員・業務委託など含めて20人ほどの組織になっていますが、さらに多くの仲間を増やしていきたいと思っています!
今後シリーズA、シリーズBといった拡大期に進んでいきますので、まだまだ組織作りの醍醐味を味わい尽くせる状況です。
30人の壁、50人の壁、100人の壁など、スタートアップとして組織拡大に伴う課題が待っているはずですが、組織作りに本気で向き合いたいと思っているメンバーばかりなので、正直ワクワクしかありませんw
営業、CS、開発といったご自身のご経験を軸としつつ、会社を成功させるために組織作りにもチャレンジしたい方にはオススメの環境です!
ご興味をお持ちいただけた方はぜひ一度カジュアル面談等でお話しできると嬉しいです!
Lectoのnoteアカウントはこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
