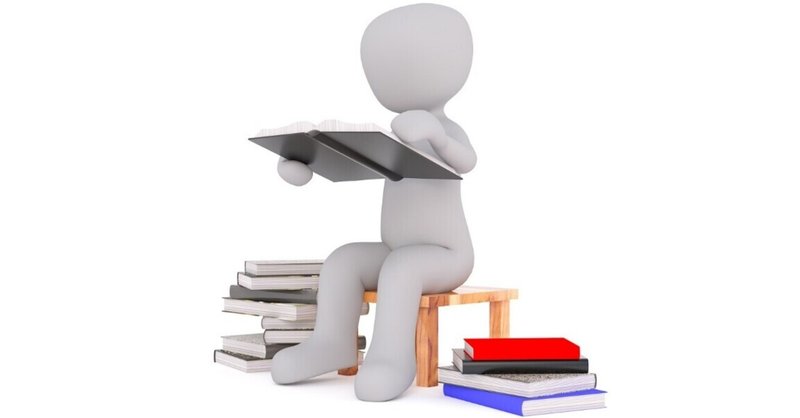
イラスト制作に役立つおすすめ書籍21冊
自分が持っている本の中でイラスト制作に役立つおすすめの書籍を紹介したいと思います。
ただ、本の内容は自分に関係のある話でないと頭に入りませんので、内容の適正ごとに
[ビギナー(初級)][ミドル(中級)][アドバンス(上級)]の3種類に分けて紹介させていただきます。特にビギナーの方はそもそもどんな知識から学べばいいのか迷う場面も多いかと思いますので是非参考にしてみてください。
▼ビギナークラスにおすすめの5冊
個人的には[技術]より先に正しい[心得]を身に着けておかないと、間違った考え方や練習を続けてしまい、結果として学習効率が良くないのではと考えています。
ですので、今からイラストの勉強をしようと思うけど、なにから始めようか迷っているという方におすすめの書籍を下記に4冊紹介します。
もちろんある程度経験のある方でも「そうだったわ。。」となる内容の多い良書です。
1.アニメ私塾流 最高の絵と人生の描き方
■小手先のテクニックより、まずは正しい考え方の土台作りから!
「「真似しちゃだめ」「見ちゃだめ」「個性が全て」という考えがなぜ間違っているのか」「絵がうまくならない理由とは」「絵がうまくなるための最強の3ステップとは」などなど。。
絵を描いた経験のある人であれば一度は悩むであろう問題とその対策が数多く書かれています。
今から絵の勉強をしようと思っている方や、始めたものの壁にぶつかって困っている方などにおすすめです。
ただし、「ブラシは〇〇を使おう」や「髪の毛の描き方のコツは〇〇」などの具体的なテクニックが掲載されているわけではないのでご注意ください。
2.うまく描くの禁止-ツラくないイラスト上達法-
■さいとうなおきさんの記念すべき一冊目の書籍!
さいとうなおきさんに関しましては説明不要かと思いますので割愛いたします。
上記で紹介した[最高の絵と人生の描き方]が上達の際の悩みや解決方法に特化しているのに対し、こちらの本は[SNSでバズるには?][やりたい仕事をもらうには?][本業と副業どちらを選ぶべきか?]など、上達したその先で絵を仕事にすることを前提とした疑問の解決方法なども掲載されているのが大きな違いです。
また、カラーイラストで考え方を図解したり、内容の詳細を解説したYou Tubeの動画のリンク等もありますので「ノウハウ本って読むの大変そう」という方でもサクッと読むことが出来ると思います。
3.絵がふつうに上手くなる本
■悩みの解決の糸口がきっと見つかる!
370ページ以上あるので、上記2冊の1.5倍程度のボリュームがあります。
その分内容も多岐にわたっていて、基本的な考え方や概念の記載の他に、実際に制作する上でのテクニックやチップス的なこと、SNSやウェブサイトを作る際の注意点まで掲載があります。
ですので、初心者であればとりあえずこの本を読んでみて、特に気になった項目を発見したとき、それ専用に特化した専門書を別途入手する流れがおすすめです。
4.アニメーターが教える線画デザインの教科書
■[線]を通じて物体、空間の捉え方を幅広く学べる!
[線画デザインの教科書]とあるように、線で物体、空間をどう捉えるかが中心に書かれているノウハウ本です。
サイズに関して、上記3点が[A5判]程度なのに対しこちらは[B5判]で一回り大きく、その分線画での実例がかなり多く掲載されています。
また、それらの解説もかなり理論的で分かりやすいです。
美大系出身の方などは、線で捉えるより塗りのほうが得意な方も多いかと思いますので、線でのノウハウを中心としたこの本の概念をインストールすると何か良い変化が生まれるかもしれません。
5.さいとうなおきのもったいない!イラスト添削講座
■ノウハウを活かすとこんなに変わるのか!が見える本
自分の絵を良くしたいけど、どうすれば良いか分からない人へのアドバイスと改善案の具体例が掲載されている本です。
特に良いなと感じた点は、他の添削系の本と異なり、ちゃんと作者のテイストを活かしながら更に良くなる案を提示しているところです。
こちら以外にもイラスト添削系の本はいくつか持っているのですが、どれも
線画だけでの直しが中心で、元絵の全てに直しを入れてしまっているものが多く[何を活かして、何を直せばいいのか]が不明確で
[直した結果の完成イメージ]は具体的にどう変わるのかが分かりづらいなと感じていました。
その点、この本では、線だけの直し(赤入れ)ではなく、塗も含めた完成イメージとしてビフォア・アフターを比較していますので、元の絵の魅力をが活かしつつ、更に良くなっている様子が具体的にわかるのでおすすめです。
ビギナーであればきっと自分と同じ悩みとその解決方法のヒントが見つかると思いますし、内容の詳細を解説したYou Tubeの動画のリンク等もありますので合わせて確認することでより理解が深まると思います。
▼ミドルクラスにおすすめの8冊
色、光、構図はイラストを制作する上では欠かせない構成要素です。
それらの法則性を知らずに、センスや感覚値だけで勝負するには限界があり、むしろ天才たちに挑むためにはこれらの知識を確実に駆使する必要があると思います。
ご紹介する下記8冊は技術や原理原則の内容が中心となりますので、ある程度絵を描いた経験や心得は既にある方向けとして紹介できればと思います。一応ミドルクラスとしましたが、これらの内容を把握していれば十分プロとして活躍出来るレベルで有用な良書だと思います。
6.カラー&ライト
■学生時代に出会っていれば人生変わっていた
自分がもし一冊だけおすすめを紹介してと言われたら、この本を選びます。
イラストや絵画を制作する上で、色、光の扱いは避けて通れません。
この本は絵を描く上で欠かせないそれらの法則に関するノウハウが網羅されています。
初級者には難しいかもしれませんが、中級者から上級者まで末永く役に立つ素晴らしい本だと思います。
私の感覚ですが、会社や専門学校の学生でこの本を持ている人は
周りと比べ頭一つ抜けて上手い傾向があるように思います。
7.デジタルアーティストが知っておくべきアートの原則
■イラストレーションの総合風邪薬
[ライティング][色][構図][遠近法][解剖学]など、イラストだけでなく写実的な絵画を描く上でも必要になる[原則]が数多く掲載されています。
もし予備校や専門学校、大学の教授らから抽象的で漠然とした好評しかされたことない方がいれば是非読んでほしい一冊です。
恥ずかしながら、私は20代の前半にこの本に出会い、そこで初めて絵を作る際には有効なルールがあることを知りました。
それからは、今まで感覚知的に知っていたことが理論として頭の中で整理され、より計画的で高いレベルのアウトプットをコンスタントに行えるようになりました。
8.Vision ヴィジョン ーストーリーを伝える:色、光、構図ー
■作品の基礎工事はこれでバッチリ
[構図]と[色]を使って見ている人にストーリーを伝えるための土台となる考え方や構成要素の説明が書かれた本です。
逆に[〇〇の描き方]などテクニック的な内容は書かれていません。
確かに[目の書き方][手の描き方]などの練習のほうが成長している感覚を得やすいのですが、[構図]と[色]という絵のメッセージの土台となる部分が失敗すると、いくらディティールが多少上手の描けたとしても意図した内容はうまく伝わりません。
そのような失敗を減らすためにも、まずはメッセージ(絵)の[土台作り]のための教本として大変おすすめです。
9.キム・ラッキの人体ドローイング
■人体構造を徹底的に学べる1冊
解剖学的な本は数多くありますが、中でもこの本がおすすめな理由としては、人体の構造や可動領域を簡略化し分かりやすく解説している点と、[よく間違えるNG例]と合わせて390ページ近くにわたり様々なアングルでの実例が掲載されているため、参考にしたい動きや角度が見つけやすい点です。
この本に限らず[人]を描く際の[筋肉][骨][関節]の構造に対する疑問を調べる本やフィギュアなどのツールが常に手元にあると大変便利ですので、その中の候補としてご検討頂ければと思います。
10.画角ノススメ
■画角とパースの悩みをサクッと解決!
背景を専門に描かれている人であれば、画角やパースの話は必ず身につける必要がありますが、キャラクターをメインに制作されている人だと、このへんのノウハウは避けて通ってきたという方も結構多い印象です。
特に「迫力のあるイラストをキャラクターを使って描きたい」と思った場合、カメラからの距離に合わせてオブジェクトの見え方や構図に変化をつけないと迫力のある画面にはなりませんので[広角][望遠]「パース」のノウハウを駆使する必要があります。
もしそれをこれから学びたい方がいればとても役立つ本だと思います。
11.安達洋介アートワークス
■カードゲーム、ユニットイラストを仕事にしたいならマストバイ
上記で紹介した本は[心得]や[原則]にまつわる内容が中心でしたので、「じゃあ実際に絵を描くときはどんな順番で何をすればいいのか」と疑問が出るかと思いますが、その際におすすめなのがこの本です。
[アートワークス]とありますが、イラストの構想(ボツ案の掲載)から完成までの各工程で、何を考えどうしたのかが細かく書かれており、画集的な側面以上にメイキング集としてとても勉強になります。
特に印象に残ったのは99Pの[キャラのモーションを6段階に分けて考える]という方法で、私はこの考え方は一生使うと思います。
12.COLOR DESIGN カラー別配色デザインブック
13.配色スタイル ハンドブック
■色の理論とか知らなくても良い感じの配色を探せちゃう本
私は色のセンスが全く無いので、これらの本にとてもお世話になっています。
この2冊が便利なのは、配色が円グラフ形式で掲載されているので、
なんの色をどれぐらいの割合で使えば良いかがひと目でわかる点です。
色選びほど感覚とセンスに頼るのが危ない項目も無いと思いますので(完全に私の主観です)、もし配色に関するツールを何も持っていない方がいれば、このどちらかだけでも入手をおすすめします。
◇COLOR DESIGN
メインカラーごとにページのカテゴリーが分かれているため
[赤][黄色]等のベースカラーを1つ選べば、それに合う配色を瞬時に探せます。「青色に合う配色って何があるのかな〜」など、漠然とした構想の段階からでもヒントを探せます。
◇配色スタイルハンドブック
[マジカル][トレンディー][ノスタルジア]など、色を見たときに感じる印象ごとにページがカテゴリー分けされているので
配色バランス全体の雰囲気の想定から、それをイメージさせる組み合わせのパターンを探せます。「なんとなくポップな色の組み合わせないかな〜」など、感覚的な構想から事例を探せます。
▼アドバンスクラスにおすすめの8冊
今までご紹介した書籍以上に脳科学的な知見や理論的な内容が多くなるので、イラストレーター向けというよりは、アートディレクターや、専門学校の講師の方など、人に理論や概念を明文化して説明する必要のある仕事をしている人以外は直接的には役に立たないかもしれません。
個人のイラストレーターであれば理論の明文化より成果物のクオリティが重視されるので、正直上記の12冊だけでも十分だと思います。
この本を読んだから上達するというより、感覚値や経験則的に理解しているが明文化できていないノウハウを整理したり、補強するためのエビデンス集として参考にしてみてください。
14.画づくりのための光の授業 CG、アニメ、映像、イラスト創作に欠かせない、光の仕組みと使い方
■[カラー&ライト]の補足に
物体と光の原則についてCGや写真を使って説明されている本です。
[カラー&ライト]と似た部分もありますが、こちらのほうが科学的な側面からの解説がより強い印象です。
個人的に面白かった点として、私はプラスチップ等の非金属素材はツルツルでも金属のように鏡のような反射をしないのはなぜだろう思っていたのですが、本書で[それは表面の光沢ではなく分子レベルの問題だ]と解説がされていて驚きました。
ただ、どちらか1冊だけをオススメしろと言われたら[カラー&ライト]かなと思います。
15.アイデアの力
■イケてるデザインの89%に共通する法則性とは?!
人の心にアイディアを印象づけるために必要な[6つの条件]が書かれている本です。
広告媒体を想定した内容ですが、人の印象に残るメッセージを作るという点ではイラストにも応用できる点が大変多くあります。
私も自分が描いたキャラのテーマやデザインがあまり良くないと感じた際には、この本に書かれている[6つの条件]をチェックリスト的に使っています。
16.場面設定類義語辞典
■設定のディティールアップに
イラストでストーリーを表現する際[5w1h]を用いると思いますが、
この本はその中の[W:Where(場所)]の想定を全225場面掲載し、その各場面にありそうな[目に見えるもの][聴こえるもの][匂い][味][質感、感覚][物語の展開][登場人物]の設定をそれぞれ580p以上で記載した[辞書]です。
ストーリー性のあるイラストや漫画での場面設定を作る際に役立つと思います。他にも[感情類義語辞典][性格類義語辞典]等のシリーズもあります。
17.ナショナル ジオグラフィック プロの撮り方 構図の法則
■被写体を[語彙]とするなら構図は[文法]である
写真を撮る際の構図に関する法則や注意点が視覚認知のメカニズムを元に大変ロジカルに説明された本です。
あくまで写真を撮る上での考え方として書かれていますが、根本的な構図の考え方は写真もイラストも共通なので、どちらを極めたい方にもおすすめです。ただ構図に関する本をまだ持っていない方には[ヴィジョン]の方をおすすめします。
18.デザインを科学する 人はなぜその色や形に惹かれるのか?
■デザインに科学的なアプローチをした1冊
表紙の可愛らしさとは裏腹に、デザインが生まれた背景や、人間の認知の特性の解説など、勉強になる内容が多く掲載されています。
特にイメージの根拠を探る章の[かわいい]と感じる形状の特徴の分析や、[おしゃれなデザインとは何か]を傾向として定義している部分が面白かったです。
私はこの本を読むまで「暗い場所や影の中の色の彩度はどうして低く見えるのだろう」とずっと疑問だったのですが、この本の28pの[桿体細胞]と[錐体細胞]の関係の説明部分で長年の謎が溶けました。
19.要点で学ぶ、色と形の法則150
■こんなにルールってあるのか、、ってなる本
人は目から入った情報を都合よく脳で処理して認識していますが、これはその認識の法則を150個も掲載してある本です。
全てが制作に応用できる内容とは限りませんが、何か1つでも発見があれば、作品を通じて相手に感じさせたい感情を逆算し、狙いをもった表現ができるようになるかもしれません。
20.配色の教科書-歴史上の学者・アーティストに学ぶ「美しい配色」のしくみ-
■[色]の視点から歴史を見れる本
私達が制作をする上で当たり前に使っている色のノウハウも、そこに行き着くためには様々な紆余曲折があったのだなと染み染み感じることが出来る本でした。また、それだけではなく現在でも実用されている配色の法則等も掲載されているので、配色規則の勉強とそのバックボーンにも興味のある人におすすめです。
21.芸術的創造は脳のどこから産まれるか?
■脳科学の観点からクリエイティブを科学的に検証した本
クリエイティビティに関して、科学的なエビデンスがまとめられている書籍です。
自分は「〇〇するといい感じになります!」と説明されても
「いい感じってなんだろう」と考えてしまうタイプですので、この本の内容はとても楽しめました。
難しい内容も含まれますので、ある程度のことなら人に教えることが出来るくらい経験値を得ている人でないと面白くないかもしれません。
ただ、そのようなレベルに達している人であれば
既に知っている知識のさらなる理論的な強化や、感覚的に把握していたことを言語化する際のヒントを多く発見出来ると思います。
下記に書かれている一例を記載しますので、もしその内容に興味のある方はぜひ手にとって見てください。
・創造性が生まれる4段階の定義とは
・基礎を固めることが大切である科学的根拠
・知識と創造性は協力体制
以上になります。
また良い書籍を見つけたら随時更新しようと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
