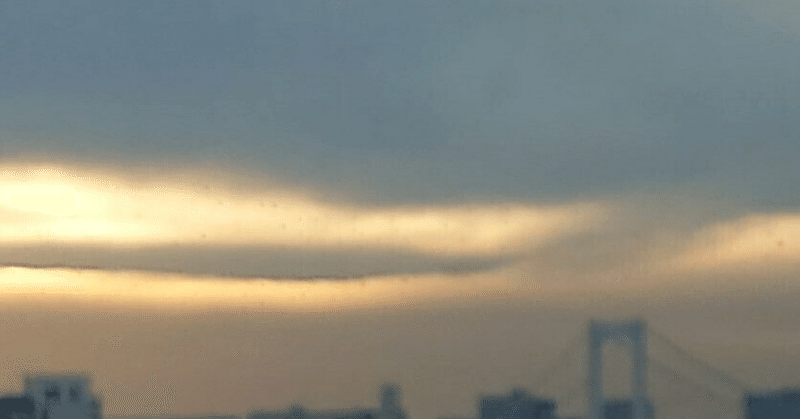
相続時精算課税の利便性向上に関するガイド
2023年の税制改正により、贈与税の取り扱いにおいて利用者にとって大きな改善がもたらされました。具体的には、贈与税の計算方法に関する選択肢「暦年課税」と「相続時精算課税」に関するルールが変わり、後者がよりアクセスしやすくなりました。今回は、この相続時精算課税に焦点を当て、その概要と2024年1月1日以降に適用される改正内容について解説します。
相続時精算課税の基本
相続時精算課税は、特定の条件を満たす親子間の贈与に適用可能な制度で、最大2,610万円までの財産を贈与税の負担なしで譲渡できる特典があります。ただし、この制度を選択した場合、贈与者の死去時には、贈与財産が相続税計算の基礎に加えられます。この選択は一度行うと、暦年課税への戻りは不可能です。
改正点の概要
対象者の明確化: 60歳以上の贈与者と18歳以上の受贈者(直系卑属)がこの制度の対象です。
計算方法の改善: 特別控除2,500万円を含む計算式が設けられ、より多くの贈与が税の負担なしで可能になりました。
手続きの簡素化: 贈与額が基礎控除額以下の場合の申告不要化、および不動産の災害による再計算の導入があります。
利便性の向上
2023年度の改正は、基礎控除の創設や不動産に関する災害再計算の導入など、ユーザーにとっての利便性を大幅に向上させました。特に、基礎控除額以下の贈与に対しては、以前必要だった税務申告が不要になり、相続時には基礎控除分の加算が不要となる点が大きな改善です。
注意点
利用しやすくなったとはいえ、相続時精算課税を選択することは、将来の相続税負担に影響を及ぼすため、慎重な検討が必要です。また、贈与者自身の生活資金を考慮し、過剰な贈与を避けるべきです。
まとめ
改正により、相続時精算課税制度はより使いやすくなりましたが、制度選択にはその影響を十分理解した上で進めることが重要です。老後の資金計画を優先し、その上で贈与の検討を行うことが賢明です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
