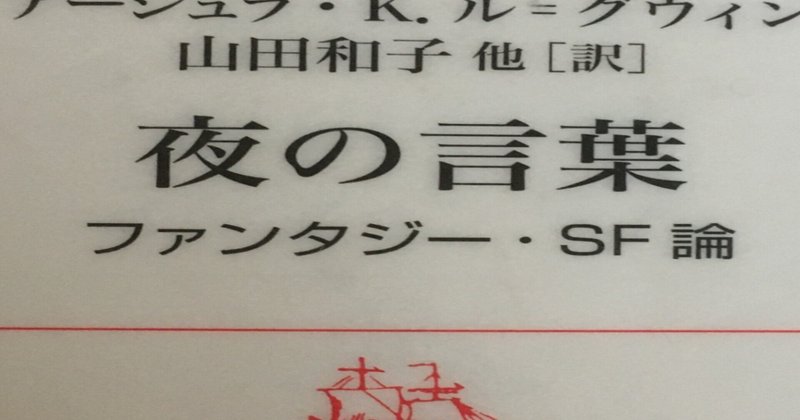
いつも薄暗い皆へ
この状況で、ゴールデンウイークにも図書館が開いていると知り、行った。たまたまル=グウィンのエッセイ集『夜の言葉』を手に取った。『ゲド戦記』はおろか彼女の作品は一つも読んだことがなかったが、呼ばれたのかもしれない。ファンタジーとSFについてのエッセイ集である。そして、時代がフェミニズムの時代だったこと、そして、そのジャンルでの女性作家が非常に少なかった中で、SFやファンタジージャンルの性差別的な問題についても繰り返し発言しており、今むしろ読まれるべき本ではないかと思う。
そもそもファンタジーやSFというジャンルは、(今は変わってきた部分もあろうが)一段低いジャンルとして認識されている。当時のアメリカのそうした傾向を手繰って行ったル=グウィンは、以下のような結論に達する。
わがアメリカ文化においては、この反フィクション的な態度は基本的に男性のものだ、と思うのです。
彼らは想像力を抑圧し、なにか女々しい、子どもじみた、益のない、そしておそらくは罪なこととして拒絶することを学んできました。
想像力をおそれるように、と教わってきたのです。それを訓練することを学ぶのではなしに。(5 アメリカ人はなぜ竜がこわいか)
これが書かれたのは1974年とのこと。前年には『エクソシスト』、この年に『悪魔のいけにえ』が製作され、B級映画を超えて、ホラーがジャンルとして確立され始める頃である。ル=グウィンはこのエッセイでホラージャンルについて言及していないが、恐らくこの男性的な価値観に照らして、「テレビの血なまぐさい推理ものか三文ウェスタンやスポーツもの、はては『プレイボーイ』誌以下諸般のポルノグラフィティ」と批判するのではないだろうか。
ル=グウィンは、そのようなものについて、
これらのジャンルの作品群の不毛なこと、救いがたく不毛なことは、彼に取っては欠点どころかむしろほっとできる点なのです。
と言っている。この『彼』とは、アメリカの多くの男性のことである。ホラー映画を観て「ほっとできる」というのは変だが、そこにこそホラージャンルの存在意義があるとも思う。『悪魔のいけにえ』がそうかと言うと何とも言えないが、『エクソシスト』は、四方田犬彦やロビン・ウッドなど、色々な人が指摘したように、家父長的な保守性に帰っていく物語である。ただし、私には、『エクソシスト』は意図された保守性の殻を突き抜けて、こちら側の安堵を覗き込んで嘲笑うような嫌な映画になってしまっているようにも読める。
一旦彼女の論に戻る。彼女は「ポップアートなるもの」を缶詰スープに例えて述べている。
真の新しさ、本当の独創性は怪しまれる。慣れた味を温め直したり、形の上では実験的試みだが中身は取りあげる価値なしか皮肉なものでなければ安全にあらず、というわけだ。そう、なんと言っても安全でなくてはならない。消費者を傷つけてはならないのだ。消費者を変革(「変革」に傍点あり)してはいけない。…<中略>…ショックを与え、揺さぶり、じらせ、身をくねらせ悲鳴をあげさせろ――だが、考えさせるな。もし考えたりしたら、消費者は再びスープを買いにもどって来なくなるかもしれないのだ。(12 魂のなかのスターリン)
私の観るところ、ハリウッド映画はまさにそれ(安全であること)を追及してきたのだと思うし、当然アメリカのホラー映画はそうなっていると私も感じる。今日の「ソーシャル・スリラー」も同様である。
彼女がポップカルチャーを非難する理由は、私のみならず多くのホラーファンがホラージャンルを消費できる理由でもあるのかもしれない。我々はホラー映画を観るとき、あり得ない描写によって、思考が止まっているのかもしれない。戸田山和久は、人間は、怖さを快楽として消費する力を獲得したと『恐怖の哲学 ホラーで人間を読む』の中で述べている。恐怖は娯楽であり、産業化されてもいるという点は重要だ。
「安全」「考えさせない」。さもなくばもう「売れない」。これを彼女は、旧ソ連における言論の自由を圧殺した検閲に対し、「市場の検閲」と呼んでいる。
売れないものは作られないのだ!!ある画家の詐欺行為を焦点として、旧来の芸術がポップアートに変化ないしは劣化していく五十年代アメリカを描いた映画『ビッグ・アイズ』を観ると、以下の論も分かる気がする。
にっこり笑いさえすれば万事うまくいく、世界中が幸せになる。…<中略>…この希望的観測、痛みや敗北や死が存在すると認めることを拒む鈍感さは、非常に成功しているアメリカ人の書きもののなんたるかを如実に示しているだけでなく、ソビエトの”成功した”作家たちのことをも典型的に示している…<中略>…人はひとたび、なぜ、と問うのをやめ、スターリンを魂のなかにはいりこませるなら、あとはただ、にっこり笑う、ただにこにこと笑う、だけとなる。(12 魂のなかのスターリン)
これは70年代に書かれており、アメリカの中では「もう深刻に悩むのいやだよう」という雰囲気が溢れていたのかもしれない。「にっこり」笑いたかったのかもしれない。SFは、終末的世界を描いていることに意味があるわけではない。もしそれが読み手にとって「真の思考、真のコミットメントを要求するものではない」なら、「絶望を描く小説は、たいていは警告の意図をもつものだが、わたしが思うには、ポルノ同様、しばしば現実逃避である」とばっさり。
彼女はSFと併せてファンタジーを書いた(『ゲド戦記』読んでない…)が、ファンタジーについては、このようなことを書いている。
ファンタジーは旅です。精神分析学とまったく同様の、識域下の世界への旅。精神分析学と同じように、ファンタジーもまた危険をはらんでいます。ファンタジーはあなたを変えてしまうかもしれないのです。(4 エルフランドからポキープシへ)※太字箇所は傍点
「あなたを変えてしまうかもしれない」。この部分は、ホラー映画の中ではしばしば描かれていると私は思う。我々は時々大きく変異する。それはホラー映画的な体験なのではあるまいか。「自分や近しい人が別物に変わってしまうこと」をホラー映画は繰り返し描写して見せ、疑似体験させてきたとも言える。だが、どうやって変わるのか?の部分が重要なのかもしれない。
「6 子どもと影と」の章もとても感銘を受けた。アンデルセンが描いた物語についての批評だ。自分の影を主人、自分を従として旅した学者が、最後、影による逆襲に遭い悲劇に見舞われるお話。これは知らなかったが、ル=グウィンは、「屈辱と死のうちに終わる、狂気の物語」であり、「アンデルセンの残酷さの一部は理性のもつ残酷さ」だと言っている。そして、それが何故子供のための物語であるのかを力説する。
主人公は文明化された人間を象徴する一方、影は文明化された世界では抑圧されざるを得ない「怪物」を象徴しているという。そして、この怪物と主人公=文明化された我々は、本来一つのまとまりを成しているのであって、「怪物」を全否定してはならないのだと言う。
これを彼女は10歳で読んだときは、「嫌い」だったと言っている。でも、「あの物語が語りかけたのはここ、つまりわたしのなかの未知の深みに向かってだった」と書いている。「無意識から無意識に向かって」語りかけるのだと。
影とはわたしたちが自我として意識するもののなかに入れたくないもの、入れられないものすべて、わたしたりの内にありながら、抑圧され、否定され、とりあげられることのなかった性質および傾向のすべてなのです。
別の言い方で言えば、人が自分の影を見ることが少なければ少ないほどその力は強くなり、ついには一種の脅威、耐えがたい重荷、魂のうちなる恐怖の種ともなりうるのです。
意識に受け入れられない影は外側に、他人に投影されます。わたしはなにも悪いところはない――あの人たちが悪いのだ。※太字箇所は傍点
おのれ自身が悪と深い関係をもっていることを否定する人は自分自身の現実性を否定する人です。(6 子どもと影と)
ユングの論を引きながら上記のようなことを書いている。
ところで、ル=グウィンの刺激的な世界を見せてくれる本と同時に、エーリッヒ・フロム『悪について』(渡会圭子訳、ちくま学芸文庫)も読んだ。1930年代にドイツからアメリカに亡命した彼の論は全く違っており、それが、ホラーやファンタジーを否定したがる、また別の想像力の否定行為のようにも思われた。
彼にとって「悪」というのは何よりもまずナチズムである。そして「いま私たちの生を支配する官僚制的産業主義に対して、ヒューマニズムの産業主義をどうつくっていくか」(第3章 死を愛すること 生を愛すること)と書いている。欧州の美徳を再建しなければならないと考えたのだと思うし、多くの欧州の知識人がそのような気分でいたのだと思われる。それは少し遅れて日本にも輸入された考え方である。なんとなく懐かしい。
あらゆる差別や対立は、個人のナルシシズムが肥大化して集団のナルシシズムにまで成長したときに起こるものであるので、科学とヒューマニズムによって高い次元に上がり、普遍主義によってナルシシズム乗り越えんとする意図が読める。ル=グウィンが、自分個人の体験として向き合うことを強調しているのとは全く違うアプローチである。そして、こちらはあまり怖くない。特にこのように書いているのは印象的だ。
ルネサンスのヒューマニズム、ブルジョア革命、ロシア革命、中国革命、植民地革命――これらはすべて、ある共通の思想に基づいている。すなわち、人間は平等であるということだ。(第4章 個人と社会のナルシシズム)
2021年から見て、「ロシア革命」「中国革命」を挙げていることに驚かされるが、知的雰囲気が左寄りであった戦後の感じがよく伝わってくる。これが書かれたのが1964年ということだから、上記のル=グウィンの論考とは10年位しか変わらない。
しかし「悪」の捉え方がまるで違う。フロムは、個々人の中に育ちかねない「悪」に言及しているが、それを暴走させないためのツールとして、欧州の普遍主義と科学(それも欧州の産物)を信じきっている、或いは希望をかけているところがある。
対するル=グウィンは、「誰でも悪を持っているのだ」と警告し、内なる悪、言い換えれば影と向き合い「あなたを変えてしまう」と言い、あくまで個人の体験として捉えている。私にはル=グウィンの方がよく分かる。また、時代性なのだろうが、フロムの論にはどうしたって「男」で人類を語ってしまうところがある。
ル=グウィンは、同書「8 性は必要か?」で「性別というものがない世界」をSFとして描いた『闇の左手』についてこう結んでいる。
もしわれわれが社会的な両性存在であるとしたら、男性と女性が社会的役割において本質的に完全に同質であるとしたら、法的にも経済的にも平等で、自由においても責任においても、そして自己評価においても同等であるとしたら、社会はまったく異なったものとなるはずだ。そうなった場合にいかなる問題が現れてくるかは皆目、見当がつきません。わたしにわかるのは、ともかく問題が生じるだろうということだけです。ただその中心的な問題は、まず間違いなく、現在の問題と同じものではありますまい。現在の中心的な問題は搾取です――女性に対する搾取、弱者に対する搾取、そして地球に対する搾取。(8 性は必要か?)
今ある問題は無くなるだろうが、完全無欠になるとは考えていない。その点で、既にある人類の叡智で乗り越えんとするフロムよりも社会の捉え方がラジカルなように感じる。
ル=グウィンとフロムの両方が、ユングに触れているのも面白い。ル=グウィンは積極的にユングの論を引いて、上記のアンデルセンの「影」を論じている。
他方、フロムは、ユングのことをあまり買っていない。フロムはユングを「ネクロフィリア」的傾向の人物として挙げている。「ネクロフィリア的な傾向を持つ人は、生きていないもの、死んでいるものすべてに惹かれ心奪われる。そこには死体、腐敗物、排泄物、汚物なども含まれる」(オッオー)「ネクロフィリア的な人間は殺す者を愛し、殺される者を見下す」(Really?)「ヒトラーやスターリンは…<中略>…ネクロフィリア的な人々に愛される」(第3章 死を愛すること 生を愛すること)とまで言っている。ホラー映画なんて、まさにネクロフィリア的である。しかし人間はそんなに単純なものだろうか。なぜ、『ザ・クラフト』で描かれたように、孤独な十代の少女たちが悪魔崇拝的なもの(同作は、白魔術としてお茶を濁しているが、八十年代アメリカのサタニストパニックを下敷きにしているのは間違いない)に居場所を見出すのか、多分何も分かっていないのは、『エクソシストコップ』と大変似ている。
また、ネクロフィリア的な性質は、「一見害のないかたちで」あらわれる人がいるとしてこう言っている。
子どもの病気や失敗、暗い将来を常に気にしている母親である。そのような母親は、好ましい変化には心を動かさず、子どもの喜びに応えない。子供の内に新たに育っているものに気づかない。その夢には、病気、死、死体、血が出てくることがあるかもしれない。彼女は子どもを目に見えるかたちで傷つけることはないが、子どもの生の喜びや成長への信頼をゆっくりと抑圧し、やがて母親自身のネクロフィリア的な性質が子どもへと感染することもある。(第3章 生を愛するもの 死を愛するもの)
この記述を読むと、彼は「母親」という存在に大きな期待と願望と責任を求めているのではないかと感じる。このあと彼はユングのネクロフィリア的傾向について述べた後、彼は創造的な方向でネクロフィリア的なものを乗り越えたと論じている。そしてフロイトの論に走って行く。フロイトはユングのそのような傾向を見抜いていたとまで持ち上げている。
フロムは人間はネクロフィリア(死を愛する)傾向と、バイオフィリア(生を愛する)傾向の両方を持っているものだとしつつ、ヒトラーやスターリンをネクロフィリア的人物の代表として挙げている。そして、何かを作り出す行為そのものに意義を見出す。
なお、フロムは、「インポテンツ=ポテンシーの欠如」という言葉を使って人間の本来の性質についてこう書いている。
(前略)人は完全な服従には耐えられないという事実がある。人は変容、変化させられるばかりでなく、世界を変容、変化させて、自分の足跡を世界に刻みたいと切実に思っている。そのような欲求は、古代の洞窟壁画をはじめ、すべての芸術、生産活動、性衝動に表れている。…<中略>…そのように自らの力を行使できる能力こそがポテンシーである(性的ポテンシーはその一つの形態にすぎない)。(第2章 さまざまな形態の暴力)
フロム的な論では、ル=グウィンのように、積極的に、自分の中にある避けられない死や闇や悪に向かって旅を続けるというのは、世界に足跡を残したいと考え、世界を変容させる行為ではない以上、ポテンシーの欠如なのかもしれない。
フロムのマルキシズム的な価値観は、確実に、私の親の世代の思想を支配した。私はホラー映画なんて意味が無いと言ったり、ファンタジーを全く理解しない親の子供として育った。しかしどうだったか。フロム的な思想の方が都合の悪い辻褄の合わない現実に目を瞑り、世界は正しい方に向かうはずだと思い込んでしまうことに陥りやすかったように思うし、未だにそうではなかろうか。自分の中の都合の悪いところを覗き込むことは、やはり必要なのではないだろうかと今なら言える。
社会や人の内面に対するラジカルな目を以て、アメリカの「偉い人」が陥りがちなアメリカ普遍主義にも陥らず、ひたすらファンタジーとSFの質を高めることを追及したル=グウィンの思想から見て、その後の八十年代ホラーの全盛や、さらにその後のファンタジー映画の大流行はどう読めたのだろう。中には、『あなたを変えてしまうかもしれない』闇や悪と向き合う様子を描いたものもあると思う。
最近の作品の方では、『怪物はささやく』『バーバラと心の巨人』は、明らかに、自分が変わってしまう怖さを描いたル=グウィン正統派のファンタジーであろう。イッサロペスの『ザ・マミー』、ジュリア・デュクルノーの『RAW』も、社会と個人のぶつかり合いの中で自己を確立していく凄みに触れている。また、スティーブンキングの世界は、時折自分の闇の部分と交信しているようなところがある。
大概、自分の闇と向き合うと楽しくない。自分が一番嫌い憎んでいるものが、自分の中にあると知りたい人はそんなにいない。大概は他人を憎んだり攻撃したりするものだ。それは自分が怖いからだ。
自分の中にもある暗い都合の悪い部分に触れてくるホラーは、優しい気がする。あなたも私も、勿論違う個人だが、そこはおんなじなんだと教えてくれる。変なものに惹かれることは恥ずかしいことではないと言ってくれる。勿論少数者なわけだが、薄暗く生きていく者たちには、一人ではないのだと教えることや、それでも自分で戦わねばならないと教えることで充分ではなかろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
