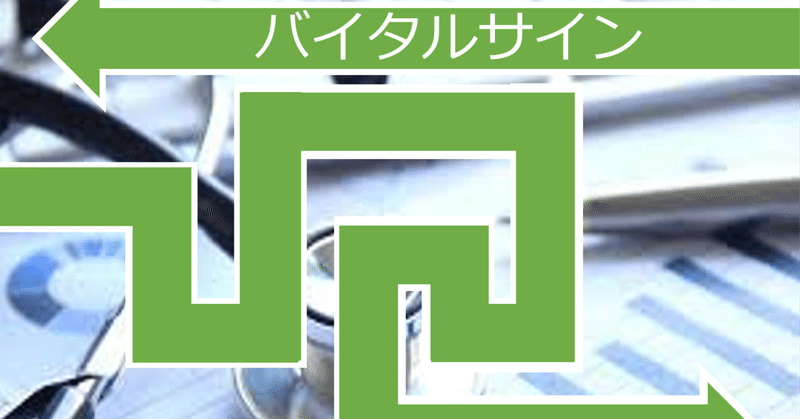
バイタルサインって何?
【はじめに】
初年度の経験から、急性期と慢性期におけるリスク管理の違いを考えさせられました。急性期では症状が激しく変化するため、病院での機械的なモニタリングやデータ収集が可能ですが、慢性期では症状が安定しているためにリスク管理がそれほど重要ではないという風に考えていました。
しかし、慢性期でも適切なリスク管理が必要であることを学びました。慢性期ではすぐに検査やデータを取ることが難しいため、訪問リハビリやNSの活動が重要となります。これらの活動を通じて、患者の状態変化に早く気づき、適切な対応をすることができます。慢性期でも十分なリスク管理が行われれば、危険性を減らすことができることを理解できます。
今回は、バイタルについて少し触れていきたいと思います。
【そもそも、バイタルとは?】
バイタル(Vital signs)は、人体の生命活動を評価するために測定される基本的な健康指標のことです。一般的なバイタルサインには、体温、脈拍、呼吸数、血圧などが含まれます。
これらは、検査機器を用いないものです。つまり、SpO₂は検査データとなるわけです。
これを聞いて血圧は?と思う人もいるかもしれませんが、血圧もおおよそは触診で知ることができますよね?

つまり、バイタルとは検査機器を使わず測定できるものを指しています。
まず、呼吸について触れていきます。
【呼吸の役割】
呼吸は、酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出することで体内の細胞に酸素を供給し、新陳代謝に必要なエネルギーを生産するために重要な役割を果たしています。具体的には、以下のような機能があります:
酸素供給: 呼吸は、肺で酸素を取り入れ、血液中の赤血球に酸素を運びます。この酸素は、体の各部に送られ、細胞の代謝で使用されます。
二酸化炭素排出: 代謝によって生じる二酸化炭素は、血液中に溶解し、肺に運ばれて呼気として体外に排出されます。二酸化炭素の排出により、体内の酸塩基平衡が保たれます。
酸塩基平衡の調節: 呼吸は、血液中の酸素や二酸化炭素濃度を調節し、酸塩基平衡を保つ役割も果たします。これにより、体内の生化学的プロセスが正常に機能します。
発声と表現: 声帯や気管、口腔などの器官を通じて、呼吸は発声や表現にも重要な影響を与えます。声を出すためには、適切な呼吸が必要です。
【呼吸はなぜ大事?】


酸素は常に体内外で交換を繰り返されています。これが絶たれれば栄養や体温より早期に死に至ることは明白です。優先されるべきは、酸素供給で最初に見ていかなくてはいけないものになります。
【呼吸の逸脱はリスクが高い】
呼吸数が24回/分越えは、6~8時間以内に重篤症状を起こすリスクがあります。 症状の不安定な患者はHRやBPより呼吸数に現れやすい 正常に図るなら、のど元に聴診器を当てて、「スー、ハー」と空気の出入りを数える。

呼吸数が増えるとなぜ危険なのかというと、上記の図のように結果的に分時肺胞換気量が減少してしまいます。
呼吸数が多いから、十分酸素は送られている!とはならないですね。
【呼吸リズム】

【音を聞いて換気を見る】


簡単に言うと、呼吸音が低いと管の直径が太い。つまり、気管異物(痰とか)があまりついてない状態。
呼吸音が高いと管の直径が細くなっている状態です。つまり、気管が痰などで細くなってしまっているので、酸素が入りにくい状態ですね。
細くなっている場合は、吸引を行ってください。
【臨床で考える事】
臨床では、バイタルやデータを複合的に考える必要があります。
呼吸で考えることは、離床を図れる状態なのかどうかです。
呼吸数が30回/分を超えている状態で起こすことは死につながるリスクであることを考えてください。この上、異常呼吸のパターンも示していれば、起こすことで、患者を殺してしまう恐れがあります。
リハビリが死につながってしまうことを避けるためには、呼吸数、呼吸パターン、呼吸音を見て離床を進めていくことが重要です。
呼吸音 ⇒ 高い ⇒吸引
呼吸数 ⇒ 多い ⇒その他バイタルとの相互関係を見る。
(バイタルサインツインズといいます。)
呼吸パターン ⇒ 異常 ⇒バイタルサインツインズ+既往の確認。
【最後に】
離床の前にふと立ち止まって考えてほしいです。
起こしてよいのか?Drの指示を完全に信じていいのか?
死に直結するリスクはないのか?
リスクを回避してより安全で質の高い臨床を展開していきましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
