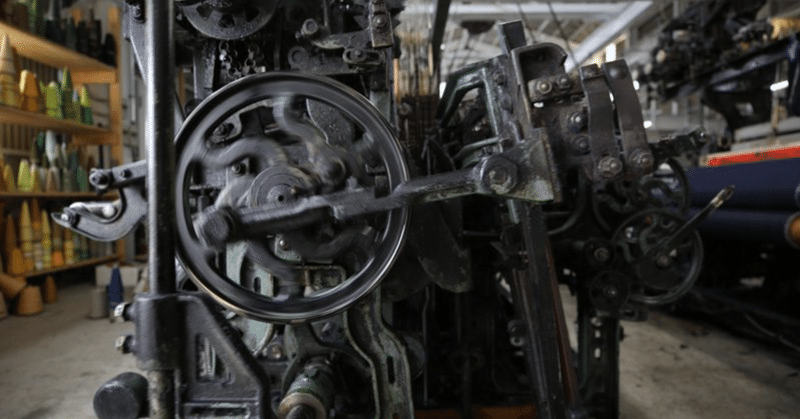
#06 玉木と酒井によるディスカッション、そしてクリエーションの本質。
2018.06.15
東京の展示会での織物職人西角博文さんとの出会いが玉木と播州織を結び付けた。「素材としての生地の完成度を追求していけば、面白いものになるという確信があった。磨けば光る価値を感じた。」そう玉木は回想する。播州織という“原石”を見つけ、玉木は何ら自分を縛る事なく、デザイナーとして妥協の無いクリエーションの試行錯誤を続けてゆく事になる。 確かな目的を携えてモノづくりに邁進し、作品として磨き上げてゆく事を得意とする玉木。そして荒削りではあっても、何も無いところから予想のつかないアイデアを発することが出来る酒井。 真逆な個性を持つ二人による言葉のキャッチボール、遠慮の無い意見のぶつけ合いが、今に至るまでtamaki niimeをどんどんと進化させるエネルギーを生み出してきた。
玉木新雌
「ウチのモノづくりのほんとの原点っていうのは、マニアック目線でこんなんあったら面白いな。と思ってる私と、消費者目線で、いや、そんなんあっても着ないやろ。という酒井、真逆の対立した意見をどうやったらどっちもがOKっていうモノを創れるか?っていうところで、そこにもの凄く注力したんです。その結果がショールで。あ、これは売れるし、私も更に面白いモノづくりの追求が出来ると確信が持てたんですよ。」
酒井義範
「そんな感じやな。」
玉木
「ショール誕生以前は、お互いの役割分担も定まってなかったし、色んなことを試行錯誤でやってました。酒井の方はウェブづくりにハマっていてそこで色んな表現をしていたり。それぞれが全然違うカタチで好き放題にモノづくり、コトづくりしていて。その中から自分たちが本当に目指すべきところを探ってた。」
酒井
「側から見れば何がしたいの?って感じやったと思います。」
玉木
「まだゴールがしっかりとは見えてなかったから。」
酒井
「当時は着地点の無いモノづくりやったので。大体普通のブランドやメゾンって、おぼろげにでも着地点が見えてて、その中でバーンと上辺だけのクリエーションがされてて、それに対して皆ワーッとなって、いかんせん僕らにはそれが無かったし、当時はそれを求めてなかったから。でも、開発した生地自体はエキセントリックだし、パターンの形も面白いし、良い感じではあったんですけど、いい意味で宙に浮いた様な状態で。ショールに行き着くまでは、着地しない飛行機みたいな感じでずっと飛んでましたね。」
玉木
「モノづくりそのものというよりは方向性の面で、どこに向かって歩いてるのかがよくわからなかったし、わからないことが愉しいみたいな。でも、周りにはお前たち一体何がやりたいんだ?って言われてしまうという。」
「その実験的な動作を理解してもらえなかったなぁ。ま、理解してもらおうとも思ってないんやけど。」
― その頃のウェブサイトっていうのはtamaki niimeのブランディングとかを意識してましたか?
酒井
「もう全く無しですね。商売とか関係なく、人の評価なんてクソ喰らえで、ただ単に好きなように暴れてました。着地点が無いからああでもない、こうでもないと。ある意味制限が無いから、もの凄くたのしかった時代です。ここっていうところに収まらないっていうか。皆んなが理解出来ないところにいたっていうか。」
玉木
「西脇に来た当時もまだまだそんな感じだったんですよ。ただほんと“ヘソ曲がり”なので皆んなと同じことはしたくないっていうスタートやったから、アパレルだったらこうするとか、ブランディングだったらこうしなければいけない、という様な縛りをことごとく否定してきたので、本当にぐちゃぐちゃやったんやな。でも、それがすごく嬉しかってんな。全然食べれてなかったけど。(笑)」
心地よく洗練された現在の姿からは想像し難い、始動時のある意味原初的でカオスな状態。そこで自由に培われたものが、やがてショールを誕生させ、方向性が定まった事でtamaki niimeのモノづくりは一気に開花してゆく。玉木と酒井、それぞれの異なる能力が組み合わさって余すことなく発揮され、お互いの役割も明確になっていった。
玉木
「最初に悶々と考えてるのは私やな?会社をどういう方向に導いていこうかとか。こういう風に改善したらどうやろうか?とか。私が発案して酒井に投げかける、で、それに対してドーンとダメって返ってきたり、いいやん!ってなったり。そこからディスカッションが始まるんです。こういう事をやりたい。っていう芯の部分は決まっていて。自分で解決策が閃く時は良いんですけど、分からない時はどんどん投げる。すると酒井の方からこういう方法があるんじゃない?とか、こういうアプローチをしたらどう?とか、返ってきて。あ、でもそれはちょっと違うとか、それに対しては言い返したりして(笑)んで、また考えてもらって、じゃそっちで行ってみようか。って、採用実行したりして。そんなやり取りが多いかな。」
酒井
「そんな二人の間の言葉のバトルが半端なく凄いから。それに対して、ミーティングでのウチのスタッフのやり取りは“正論”ばかりっていうか、いい子ちゃんの戯れっていうか。そうゆうのをぶっ壊してやりたいって思うんですよ。」
玉木
「まだスタッフがディスカッションに慣れてないのよね。二人の間のバトルを見せる様にはしてるんですけど、皆んな引く(苦笑)。まあまあ落ち着いて…みたいな。いや、これを真似て欲しいねん!って言って。本音で話すというかね、良い悪いじゃなくて、世の中のひとがどう思うかとかじゃなくて、思ったことを口に出す。それによって相手を否定するわけじゃなくて。更に良いアイデアを導き出すためのディスカッションやから。」
酒井
「僕ら二人のディスカッションっていうのは小手先じゃなくて凄く躍動感があるし、全力投球ですごく体力も消耗するけど、だからこそやり甲斐があるし。だけどウチのスタッフはまだまだ“産みの苦しみ”が無い。それをスタッフから感じ取れないのが僕は凄く不満。」
玉木
「だから“対策”として、なるべく私たちはディスカッションしないようにする、酒井とわたしの二人でディスカッションしちゃうと全部決まっちゃうから。私たちは黙っておいて、スタッフでディスカッションするのを見守るっていうポジションに今してる。もちろん最終的なジャッジはするんやけど、先ず自分たちで考えて自分たちでディスカッションして、その上でこちらに上げて来てくださいとお願いしてる。その習慣の繰り返しが今の私たち二人やし。小さな事から先ず話し合って決めていく事で習慣化されてゆくので。スタッフが1時間かけてミーティングして決めた事をそれは無いでしょと私に却下される事もいっぱいあるんですけど、でも1時間ディスカッションしたその事実、経験が大事やし、次はこうしようというアイデアに繋がってゆくし。それはやっぱり経験やね。数をこなさないとディスカッションも習慣化しないし、掘り下げられないから。」
酒井
「極端に言えば、そこに自分の全存在がかかっていて、それが出来なければ自分の全てが壊れてしまうくらいの意気込みで取り組んでほしい。そう僕は思いますね。」
玉木
「だからこそ、まだ現在のshop & Labのカタチのtamaki niimeが確立してなかった頃は、やっぱり中途半端なモノは出しちゃいけないと思ってるから、スタッフに対して、これでもか!ってくらい口を挟んだり、基本二人で考えてたんですよ、デザインにしても。これまでの経験値を踏まえて、今お客様に提供するべき新しいモノっていうのを従来通り私たち二人で生み出してたんですけど、これからはそれじゃダメだから。今はスタッフもデザインを考えてるじゃないですか。最初はね、すごく苦しかったんですよ。作品のクオリティとしてダメだろこんな中途半端じゃ。とか思ったり、自分の経験からして、もうちょっとこうした方が良いんじゃない?っていうのが見て取れるから歯痒かったんですけど、やっぱり産みの苦しみを知ってもらうためには、それが売れないって現実も経験してもらわなくちゃならないという事なんですよ。売れるっていう成功体験ももちろん必要やけど、売れないっていう“失敗体験”はもっと大事。そのプレッシャーや、そこから生まれるフラストレーションがあるからこそ、こう変化させたらもっと良くなるんじゃないか?っていう、洗練された濃いアイデアが出て来るから。そこを私たちが全部端折っちゃって売れるモノに変えちゃったら、スタッフは成長出来ないから。もちろん着地点は何でもアリではないですけど、最低限私たちの基準を満たしていれば、まだちょっと改善する余地があるなと思ったとしても、もうゴーする。」
― ブランドとしては少しリスキーな面もあるのではないですか?
酒井
「0から1を生み出す、創造するという意味では、さっき玉木が言った様に自分が着たいモノや自分が欲しいモノを、スタッフは全力で生み出していかないと全く意味が無いですからね。自分で創って出来上がって、自分が心の底から楽しめないモノを作ったところで全然意味が無い。昔僕らが試行錯誤していた頃の、人がどう思うかじゃなくて、それに対して自分が心の底から喜びを感じる、そうゆう高揚感や躍動感をスタッフ皆んなが持たなきゃいけない。だから、多少リスキーであっても、どんどんやらせます。」
玉木
「それはデザインスタッフだけじゃないな?販売するスタッフ、営業チームもリスクを理解した上で全力でやるっていうか。」
酒井
「そやな。全力で没頭する。」
玉木
「自分が楽しんで販売をする、言われたからやるんじゃなくて、こういう接客されたら面白いやろうな。とか、自分たちで能動的に考えて、創り出していくっていう。」
酒井
「そう、皆んなの様子を見てると、資本主義という枠組みの中でやるビジネスってなると、なぜか?皆最初“論理”から入るんですよね。そうじゃなくて、もっと自分の躍動感っていうか、バーンとした心意気っていうかを直感的に表現すれば論理なんて後から付いて来るし、論理なんていうのはその表現を受け取った側が勝手に構築するもんやから。」
― 意味性や理屈は後から付いてくると。
酒井
「そう、まずはダイレクトに自分の想いを伝えるとか、そういうところに注力すべきなんですよね。小手先じゃなくて、そこが僕は、0から1を生み出す、創造するって事の本質やと思う。僕らはそうありたいし、スタッフにもそうあって欲しいと思います。」
ショールというカタチに結実するまでの、方向性が決まらない中で、制約を設けずに自分たちの可能性を、日々楽しみながら広く捜し求めていた玉木と酒井の模索の時期には、掛け替えのない価値があったのだと思えた。
酒井
「線引きがされていない、サッカーに例えれば、ゴールがいくつもあって、どこにゴールしてもいいんですよ。全然縛りがなくてどこにドリブルしてもいいし…っていう風な状況やったから。すっげぇ愉しかったよな?」
― ルール度外視、みたいな。
酒井
「色んなゴール目掛けてシュートしたよな。」
玉木
「その当時はね、未だ方向が決まってないから。ただ最終的にショールに行き着くだろうという事は何となく分かってたっていうか。具体的にショールというカタチだとはまだ分かってなかったけど。絶対目指す処にはたどり着けるから、なんせ一生懸命に…それまでの会社勤めではなく、しがらみのない中で自由に考えたい、それには時間もお金も投資して。でも本当に自分たちがやるべき事は何なのか?っていうのを、本当に追求したいと思って実行した最初の3年間やったな?」
酒井
「だからそういう時期を経て、この今のtamaki niimeの表現の仕方というか、打ち出し方というかは、そういう過程を経てるからこそなんで、全くなんも無しで、今流行ってるからやっちゃえみたいな輩とかいっぱい存在しますけど、そういうのと比べるつもりはないけど、そこを経てるか、経てないかでは、全く雲泥の差がある訳ですよ。」
玉木
「今のスタッフはもしかしたらそっちになりかねないって事なんですよ、試行錯誤抜きでもう環境が出来上がってるから。」
酒井
「流行ってるからやろうとか。ドロッと沈殿したところを知らずに、上澄み液だけを掬うっていう感覚がくだらないから僕は嫌なんですよ。」
玉木
「あ、簡単にデザインって出来ちゃうんだ、って風潮もホントくだらんもんな。」
― ショールに結実するまでの過程でたまった“沈殿物”というか蓄積があるわけですよね。
酒井
「そう、それこそが0から1を生みだす創造の基やというか。」
玉木
「だからこそ、スタッフ個人個人がデザイナーとしてモノづくりするのなら、もっとこのtamaki niimeの環境を活用して、教えてもらうんじゃなく自分から調べろよ、質問して来いよ。と思うんやけど全然。興味無いんかな?って思っちゃうな。」
酒井
「ヘンにカッコつけて皆いい子ちゃんぶるんですけど、そういうキチンとした常識的な側面も持ちつつ、皆んなが型にはまらずに自由な表現が出来たら、もっとtamaki niimeは深いブランドになるわな。」
玉木
「明治維新じゃないけど、世を変えたるで!くらいな集団でないとあかんと思うけど。なんやろう?」
酒井
「だから良い意味でもっと闘わないといけないし…なんかちょっと、いい子ちゃん過ぎるんですよね。ホントに。それは否定ではなくて、彼らにそうなってほしいという僕らの希望を込めてね。」
玉木
「今後のヴィジョンとしてね。そこはほら、自分が専門学校出て企業に勤め出した頃に、なんて世の中つまんないんやろう、世の資本主義ってなんてしょうも無い、何のためのデザインで、何のための服づくりなんやろう?ってすっごい疑問を持って。その時にある人に言われたんですよ、自分好きな事を仕事にするなって。ガッカリするから、趣味で取っておいた方がいいと。とことん追求出来るのは趣味の時間であって、ビジネスにした時点で色んな制約が出てくるから、絶対面白く無くなって息詰まるから、趣味で取っておけという事を言われた事があって。何で駄目なんやろう?趣味に使える時間なんてちょっとしか無いやん、って思ったし、そこも天の邪鬼やから、迷わず好きなことを選んだな。」
酒井
「結論、好きな事を仕事にしないと全身全霊を込められないもんな。」
玉木
「今ここにある設備っていうのは全部、自分が専門学校卒業した時にガッカリした社会や、社会人じゃなくて、ワクワクする社会人になるためには、こんな会社あったら良いなヴァージョンなんですよ。だから今新卒も採り始めたり。」
― 実際外から観てもワクワク出来る空間ですからね。
玉木
「だからこそもっとぶっ飛んで欲しいなっていう。」
― これだけの環境を整えてるから、と。
玉木
「そういう意味では面白い状態になって来てるかなと思います。専門学校や大学で考える事とか実験する事をやってきてる子たちがそのままここに来てるから、こっちのやり方次第ではもっともっと花開くだろうし。いわゆる、世の中の社会人とはこうしなきゃいけないよという常識はある程度持って来ちゃってるからまだまだ鎧を外せないところはあるけど、それを剥がしていくというのも私たち二人の仕事やと思うし、“ぶっ飛んで”もらうためにはソフト面も含めて更によりクレイジーな環境を作っていかなくちゃと思ってます。」
酒井「そやな。」
「0から1を生み出すっていうのを一言で言うと“世間体”というところから逸脱する事やと思うんですよ、大前提として、世間の目とか、世間はこうやから、とかに縛られてたら、いい意味で逸脱したクリエーションは出来ないから。」
「常識なんて後から教えられるけど、逸脱した生き方は若い時にしか出来ない。大人になるとどんどん頭が固くなるから。だからこそ今、産みの苦しみと一緒で、苦しいかもやけどそこをぶっ壊していかないと。そうでなければ、これからtamaki niimeをもっともっとリニューアルしていこうとする時には難しいでしょうね。」
「ないからつくる」。彼らのモノづくりを象徴する言葉のひとつだ。何かを真似るのではなく、自分が欲しいモノが無いからこそ、たのしみながらそれを全力で創造する。方向性が定まる以前の、型にはまらず、ある種混沌とした試行錯誤の時期を経て来た深い経験が、現在の玉木と酒井によるモノづくりの確かな基礎となっている。
酒井
「だから創って壊して、また創って壊して創って。そうやってここまで、徐々に積み重ねてきたというのがあります。あえて、まっすぐ構築してこなかったから。」
玉木
「天邪鬼かもしれないけど、簡単にtamaki niimeを理解されたくないっていうところがあって。とにかく、いつでも無我夢中で考えてるし、たのしすぎるから、これからもどんどん変化していきますよ。」

書き人 越川誠司
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
