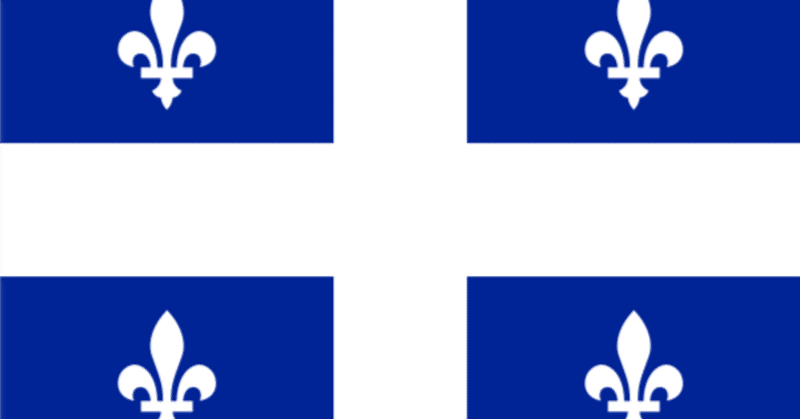
ケベックの歴史と独立運動の発展
カナダ・ケベック州は、カナダ東部の大西洋に面した地域で、カナダでも有数の大都市モントリオールを抱えます。
約150万平方キロの広大な土地に約770万人の人々が暮らしています。

ケベックはフランス系住民が建設した北アメリカ植民地ヌーヴェル・フランスが元となっており、イギリス系とは長年に渡って対立、時には戦闘状態にあった歴史があります。カナダ連邦の一部ですが、現在でもケベックでは英語に加えてフランス語が公用語で他の連邦諸州とは異なる独自路線を採っています。
1970年代以降は2度、独立の可否を問う住民投票を実施し、二度とも反対が大勢を占めましたが、現在でもわずかながら独立派が存在します。
単に歴史的に相容れない部分があるだけでなく、経済的利害が絡んだセンシティブな問題ですが、作家のイボン・デシャン曰くケベックの独立問題は「欲しいものは何でも与えられ甘やかされた子供が、それ以上欲しがっているかのよう」だそうで、そもそもの主権や国民意識自体からして対立が根深そうです。
今回はケベック人、通称「ケベコワ」が、民族自決の認識を抱くに至った歩みを見ていきたいと思います。
1. ヌーヴェル・フランスの発展

フランスは大航海時代の後発国で、探検家を各地に派遣する余裕が出始めたのはようやく16世紀前半でした。
1524年、フランソワ1世の援助を受けたイタリア商人ジョヴァンニ・ダ・ヴェラツァーノがガスペ半島からフロリダまで探検し、大西洋岸一帯を「フランシスカンヌ」と呼び国王に報告しました。
次いで1534年にジャック・カルティエがシャルル湾に上陸し、先住民族に倣って現地を「カナタ(先住民族語で村という意味)」と呼ぶことにしました。
フランス人は豊富な鱈の漁場と毛皮交易の利権を求めて北アメリカにやってきて、セントローレンス川流域に住居を立ててここを「ヌーヴェル・フランス(新フランス)」と呼びました。フランス人は現地のアルゴンキアン語諸族、ヒューロン族と関係を築き、五大湖周辺のイロコイ族と闘いながら毛皮交易網を拡大していきました。
1661年、ルイ14世が親政を開始しフランスは絶対王政のまっただ中にありました。1663年にヌーヴェル・フランスは国王の直轄植民地となり、貿易は西インド会社の管轄下におかれました。これにより、ヌーヴェル・フランスから西インド諸島に農産水産物を、西インド諸島から本国へ砂糖を、本国からヌーヴェル・フランスに工業製品を送る三角貿易が構想されました。
ヌーヴェル・フランスでは本国に倣った統治機構が整備され、行政・立法・司法の機関が作られフランスの法律が導入されて法体系も整備されました。それまでヌーヴェル・フランスは人口の少なさが悩みの種でしたが、本国での積極的な移民奨励策が功を奏し、1663年から73年の間に2000人以上の移民がやってきて、人口は二倍になりました。漁業や毛皮だけでなく農業が発達し、農産物を運ぶための道路・水路などのインフラの開発も進みました。
こうして順調にフランス植民地としてのカナダは発展していくのですが、同時にその真横で、イギリスもまた北アメリカ植民を活発化させており、英仏抗争を経てやがてヌーヴェル・フランスはイギリスの支配下に入っていくこととなります。
2. イギリス支配下の「ロワー・カナダ」

イギリスの北米植民地は現在のアメリカ合衆国の東海岸が主要でしたが、17世紀半ば以降に徐々にハドソン湾にまで拡大し、フランス人と毛皮貿易で競合の関係になっていきました。
イギリスは北米でのさらなる植民地と権益の獲得を目指し、ヨーロッパ大陸で発生した戦争に乗じて、ヌーヴェル・フランスを攻撃していきます。
1702年に始まったスペイン継承戦争では、北米ではアン女王戦争と呼ばれイギリス軍とフランス・先住民連合軍が戦いますが、イギリス軍がポール・ロワイヤルを陥落させました。
次いで起こったオーストリア継承戦争では、北米ではジョージ王戦争と呼ばれ、いくつかフランスの要塞が落とされますが後に返還され、イギリス系住民は反発します。
そして、ヨーロッパの七年戦争が起こる2年前から起こっていた、フレンチ・インディアン戦争は決定的にイギリスの優位とフランスの転落を意味づけるものとなりました。
優位な武器と戦力を持つイギリス軍は、人数的に劣勢で先住民の同盟が上手く機能しないフランス軍を各地で打ち破り、とうとう1757年のアブラム平原の戦いでフランスは決定的な敗北を喫し、フランスの北米植民地の拠点ケベック・シティが陥落。これにより、ヌーヴェル・フランスはイギリスの支配下に置かれ、新たに「ロワー・カナダ」と呼ばれることになりました。
ケベックを獲得し敵対的なフランス系住民を抱え込むことになったイギリスは、イギリス支配に対して彼らの支持を得る必要がありました。そこで1774年に成立したのが「ケベック法」です。
これはフランス系住民に旧来の領主制を認めさせ、カトリックの十分の一税も認め、フランス民法の使用も認めるという大幅にフランス系住民に譲歩した内容となっており、言わば「民族的特権」をケベックに与えたのでした。
その一方で、ケベックへのイギリス系住民の植民と議会の掌握を図り、徐々にフランス系住民をイギリス系へ「リプレイス」する計画も進んでいました。
1776年アメリカがイギリスから独立すると、共和制を嫌った王党派イギリス系住民が多数カナダに逃げてきて、その一部はケベックにも住み着きました。
彼らは本国イギリスとの連携という強みを活かし、徐々にフランス系を脅かしていき、1790年までにケベックの毛皮取引の1/4以上をイギリス系が支配するようになっていきました。
急激なイギリス系移民の増加はフランス系住民の反発を招き、イギリス系が支配する議会と対立するようになりました。すでに行政や立法のエグゼクティブは少数派のイギリス系に支配されていました。フランス系住民の不満を吸収し、フランス革命の継承と共和制を主張し絶大な支持を受けたのが、ルイ=ジョゼフ・パビノーという男。

パビノーとケベックのナショナリストである愛国者党は、フランス系が多数を占める議会の権限強化を求めますが、イギリス系はこれを拒否。
これにさらに反発を強めたパビノーは、1837年に「自由の息子たち」と呼ばれる軍事組織を結成し、モントリオールとケベック・シティの暴力的な制圧に乗り出した。しかしすぐにカナダ政府軍に鎮圧され、パビノーはアメリカに亡命し、反乱は失敗しました。
その後、トロントなどイギリス系が占めるアッパー・カナダでも保守派に対する不満から改革派による反乱が起こり、すぐさま鎮圧されたものの本国イギリスは相次いで起こったこれらの反乱に衝撃を受けました。
そこで植民地カナダを調査し、よりよい統治方法に関して研究すべく派遣されたのがダラム伯爵。彼は5ヶ月ほどのカナダ滞在から得た見聞から1839年9月に有名な「ダラム報告書」をまとめイギリス政府に提出しました。
この中でダラムは
1. 総督ではなく議会に対して責任を有する行政評議会を有すべき
2. アッパー、ロワー両カナダを統合すべき
という提言をまとめています。前者についてはいわゆる植民地カナダに「責任政府」をもたせよ、という急進的なもの。後者については政治統合により究極的にフランス系住民をイギリス系に同化させることを目的としたものでした。これを受けてイギリス政府は、前者の責任政府は時期尚早としながらも、後者の両カナダの政治統合には踏み切ることにしたのでした。
1841年2月、アッパー、ロワー両カナダは「連合カナダ」内の行政区分「西カナダ」「東カナダ」となり議席が統合されました。議席数は両方42議席割り当てられましたが、当時の人口は東カナダのほうが多かったので明らかにイギリス系に有利で、財政面でも西カナダが大きな利益を得たのでした。
3. 歴史的な「ケベック決議」

連合カナダが成立したものの、西カナダのイギリス系と東カナダのフランス系は鋭く対立し、新首府の場所の選定もイギリス系は西カナダ、フランス系は東カナダと主張して譲らず、最終的に中間地点のオタワに落ち着くまで毎年東西交替で首府が移動していたほどでした。さらに東西カナダそれぞれで保守系と進歩系政党に分裂し、議会は機能不全に陥っていました。
さらに経済的には鉄道建設の限界からこれまで順調だった連合カナダ経済も失速し始めており、政治・経済共に行き詰まりをブレイクスルーさせる「何か」が必要だった。
タイミング良く発生したのが、「アメリカ南北戦争」でありました。
イギリス本国は南部連合に好意的な中立を宣言したことで、北部連邦はイギリス領北アメリカに対する敵対心が燃え上がり、「武力によるカナダ併合論」が主張され始めた。
アメリカの北進阻止が緊急課題となり、これまで対立していたイギリス系改革派のジョージ・ブラウン、イギリス系保守派のジョン・マクドナルド、フランス系保守派のジョルジュ=エティエンヌ・カルティエの三者による大連立が成立。
1. 北アメリカ全体での連邦制成立
2. 議会選挙での人口比例代表制導入
3. 西部のカナダ編入と大陸横断鉄道の建設
を共通目標とすることで合意しました。これはまさに政治・経済で行き詰まりを見せていた東西カナダの問題をブレイクスルーさせるための方策でありました。新たに誕生したマクドナルド大連立政権は、1864年10月に連邦結成の大綱となる「ケベック決議」を採択しました。
これによって連合カナダは西カナダがオンタリオ州、東カナダがケベック州として再分割され、連邦政府は「財政・軍事・鉄道・金融」といった権限を集中させ、州には「教育・民法」といったローカルな事項の立法権のみを認める高度な中央集権体制が確立されました。
ケベック決議によって「連邦政府は州政府に対し、本国イギリスが植民地に対して有するものと同じ地位を占める」とされ、州は連邦の植民地という位置づけがなされることになりました。
中央集権的連邦制国家の成立で、対米防衛を中央主導で強化しつつも、未開の西部と太平洋岸を国内植民地化して経済開発を進めていくための準備が整ったのでした。
このケベック決議体制は現在のカナダの地域主義や連邦に対する州の反発の遠因となっていくのです。
4. 連邦制への疑問

1867年11月、連邦制国家となった新生カナダ自治領の議会が開会され、初代首相にイギリス系保守派のジョン・マクドナルドが就任しました。当時の連邦カナダの人口比は、イギリス系が約60%、フランス系が約33%、先住民が約7%と推計され、東にフランス系、西にイギリス系、先住民は辺境に暮らす構図は変わらず、分裂のリスクを抱え込んだままの船出でした。
国家の方針として西部の開拓が進められていくのですが、フランス系住民はイギリス系住民が西部に入ってバッファローなどの資源を根こそぎ奪ってしまうのを恐れた。
西部フロンティアのレッドリヴァー植民地に住むフランス系住民は、1869年11月にレッドリヴァーの連邦への無条件移譲に抗議し、ルイ・リエルという男を首班に臨時政府を立ち上げ、レッドリヴァーを「中央カナダと同等の州として連邦に参加させるよう」に主張しました。
放っておけば、レッドリヴァーにイギリス系住民がやってきて、自分たちの資源を奪い去られると恐れたのです。

ルイ・リエルはオタワ政府と交渉し、先住者の保護措置を認め、英語フランス語の両方を公用語とし、カトリック系学校の設立を認めるなどの譲歩を勝ち取り、レッドリヴァーをマニトバ州として連邦に参加させることを認めさせました。
ところが、マニトバ州の成立から間もなく、イギリス系が大挙してやってきて政治・経済・社会生活を支配するようになり、先住者の保護はなし崩しになった。フランス系は失望してマニトバ州から逃れていきました。
レッドリヴァー蜂起を受けて、ケベックのフランス系住民はイギリス系の非道に憤り、ルイ・リエルを自分たちの文化・伝統の守護者であると祭りたてました。フランス系の多くは自分たちの国はローマ教皇に忠実なカトリック国家となるべきだと望んでいました。
一方でイギリス系はフランス系を国家分裂主義者として敵意を向け、北方の気候に適したアングロ・サクソンこそが新生カナダの担い手であるとして、イギリス系主導の国家統一と西部進出を主張していました。
レッドリヴァー以降フランス系住民は先住者の保護をオタワ政府に訴えますがその度無視され、再び実力行使を図り始めます。現在のサスカチュワン州のフランス系住民は、アメリカに亡命していたレッドリヴァーの英雄ルイ・リエルに懇願し再び抵抗運動に立つように求め、リエルはそれに応えることにしました。
1885年、臨時政府がバトーシェで創設され、フランス系住民の民兵に加え、中央政府に抑圧され続けていたインディアンの部族の中から、クリー族のビッグ・べアートパウンドメーカーが参戦。一時は政府軍を押し返すも、物量に劣った反乱軍は4日後に崩壊。
反乱軍の中心人物ルイ・リエルは処刑されました。
この出来事は特にフランス系住民に衝撃を与え、「愛国者リエルがフランス系の大義のため死んだ」と受け止められました。
ケベック州では民族主義政党が台頭し、「州権の強化」を主張するにようになりました。これはマクドナルドが進める中央集権体制への異議申し立てであり、同様の主張はケベックだけでなく他の州でも州権論が盛んに叫ばれるようになっていきます。
5. 分裂の中の発展

1896年7月に首相に就いたウィルフリッド・ローリエは、カナダを新たな発展に導くことになります。
彼はカナダ初のフランス系首相で、「いずれ本国=植民地関係は消滅すべき」と主張するカナダ独立論者でした。ローリエはフランス系ながら「ヌーヴェル・フランスの征服こそが今のカナダを作ったと認めるべき」として、「イギリス系やフランス系という対立ではなく、カナダ人として協調すべきである」と訴え続けました。国際的にも本国イギリスではなく、アメリカとの関係を強化すべきという立場でした。
当時はまだイギリス系住民の間ではイギリスとの結合を求める声が強く、その妥協の中でローリエは大英帝国との枠組みの中で地位を高め、将来的な離脱を目指すという方向に向かっていきます。
20世紀初頭から小麦価格が上昇し、西部開拓に対する期待から本国イギリスから大規模な投資が投下されたことで、カナダは空前の経済発展を遂げることになります。西部に大規模な移民が流入し、またオンタリオ州を始めとしたオールド・カナダでは工業化が進展しました。
一方でケベック州でも工業化は進んだものの、伝統的なカトリックの価値観が根強く、フランス系起業家はイギリス系に比べて投資や産業振興に不熱心でした。「工場や金を持つと、他の連中と同じように、フランス系カナダ人はアメリカ人になってしまう」として保守的な経済発展がなされ、イギリス系住民が多い州に比べて経済的な差が生まれる要因が作られました。
実際にこの時期にはカナダに対するアメリカからの投資はめざましく、額自体はイギリスよりも劣るものの、投資の先が工業や鉱工業・林業に集中し、鉄・パルプ・ニッケルなどの重要な資源を支配しました。この時代にカナダの対米依存は一層強まっていきます。
1914年8月4日にイギリスがドイツに宣戦布告し第一次世界大戦が始まると、カナダはイギリス とともに「正義を守るため」の戦いに突入していきます。当時のイギリスは国力の低下が著しく、インド、オーストラリア、南アフリカなどコモンウェルスの国々の兵の協力なしには戦争を戦えない状態になりつつありました。
カナダ軍はイギリス軍の一翼として獅子奮迅の活躍をし、ヴィミー・リッジの戦いでは英仏軍が総崩れになった後、カナダ軍が孤軍奮闘したおかげで山稜の重要拠点を奪取。各国にカナダ軍の誇りと威信を見せつけたのでした。
ところが戦争が長期化すると、イギリスからさらなる増兵の要請が来るようになります。フランス系はこれに反発し、「欧州の戦争は我らには関係ない」とまで言い放った。これにイギリス系は「戦争の非協力者」として反発を募らせた。
第二次世界大戦でも、カナダ世論の大勢はイギリス支持で「断固参戦すべし」「徴兵もやむなし」でしたが、ケベックのフランス系住民は「中立」を主張し、あくまで「州の自治、英仏系カナダ人の平等、家族重視の社会改革の実現」を要求し続けていました。
戦争を通じてカナダはアメリカと軍事同盟国になり、アメリカからの軍需品の注文が殺到し、政治的だけでなく経済的にもさらに対米依存が強まることになりました。
6. ケベック独立運動の展開

カナダは第2次世界大戦からイギリスから自国を自立化させ、印璽法(1939年)、カナダ市民憲法の制定(1946年)、君主大権移譲の勅令(1947年)を相次いで行い、首相の任命・罷免・議会の招集・解散権などが、英国王からカナダに移譲され、名実ともにイギリスの支配が終結しました。
一方でアメリカとの関係はますます緊密化し、東西冷戦下に置いてソ連に対する北方の守りとしての重要性から軍事的な連携を強化。共産化阻止のための地域戦争にも積極的に参加しました。また経済的には、アメリカ資本が投下され各地に工場が建ち工業化が進展。カナダはアメリカ資本の「子会社」のような構造になっていきました。
過度のアメリカ依存は、カナダ独自の企業が育ちにくくなるという弊害も生み、実際にカナダは「国産自動車メーカー」を保有していない珍しい国です。
このように、イギリスからの自立、経済発展に伴う対米依存の深化の只中にあった中で、唯一ケベック州はカトリック教会の伝統的価値を保有していた保守的なデュプレシ州政権の下で停滞を続けていました。
経済発展の恩恵にはあずかっていたものの、失業率はカナダでも最悪で、温情的な人事や企業慣行から汚職が蔓延。社会的に閉塞感が漂っていました。
危機感を抱いた若者グループは、ケベックの古い社会・政治・経済に問題があるとして、フランス系カナダ人の体質そのものの刷新を主張しました。
1959年にデュプレシが死亡すると、州選挙で元連邦官僚のジャン・ルサージュ率いる自由党が勝利を治め、改革に乗り出しました。

ルサージュ政権は州内の企業を育成するための公的投資機関を設立して投資を促進し、カトリック教会の手から教育の管理を州立のカレッジに移行させ、コネ人事の廃止など一連の腐敗撲滅策を進めました。また、労働基準法を改正し、男女平等を進め、病院を増設しました。
これらの改革は見事なほど成功を治め、人々はフランス系である自分たちの誇りを取り戻すに至った。ルサージュ政権はフランス系である自分たちの文化を保護育成するため文化省を設立し、カナダ放送公社の中でもフランス語放送網はほぼ独立した存在となった。
そのような社会の動きの中で、「ケベック・ナショナリズム」を訴え自らを「ケベコワ人」として自らのアイデンティティをより鮮明にする者が現れました。
彼らはケベコワ人やフランス語の地位が低く、イギリス系から差別されているとして、政治的な独立すら主張するようになりました。より過激的にケベックを武力をもって独立させようとする勢力も現れました。
それがケベック解放戦線(FLQ)で、自らを「植民地化された民」であるとし、「ケベックの土地に寄生する帝国主義者たちを排除せよ」と訴えました。

彼らは爆弾をしかけたり、拉致をして身代金を要求したり、VIPを殺害したりなどのテロ行為を行い、連邦政府と武力対決する姿勢を見せました。ケベックではナショナリストの圧力が増し、ルサージュは連邦政府に対し「ケベックの特別な地位」を認めるよう要求。
連邦政府はケベック州に譲歩し、連邦の年金の費用分担からケベックを外し独自の年金制度を創設したり、外交権も一部認めるなどしました。
連邦政府はケベックが要求して立ち上げた「ニ言語・二文化調査委員会」の報告勧告に元、フランス語を英語と同じ公用語に認定し、連邦政府の議会や裁判所、行政などでフランス語を使用することを義務化しました。
フランス系カナダ人の公務員が積極的に採用され、フランス語教育が補助金を使って大々的に行われました。しかしケベックのナショナリストからすると、連邦政府の対応は「ケベックの自治という本筋を覆い隠す偽善」としか思えなかったし、西カナダの住民からしたら「フランス系住民にまたしても特権を与えた」と見なされたのでした。
1970年10月、ケベック解放戦線(FLQ)のメンバーがモントリオール駐在商務官ジェイムズ・クロスと州労働大臣ピエール・ラポルトを誘拐し、獄中にいるFLQのメンバーの解放と宣言文放送を要求しました。連邦政府は戒厳令を敷き軍隊を派遣して鎮圧に乗り出しますが、結局ラポルトは死体で見つかり、メンバーの一部は逮捕、一部はキューバに亡命しました。

FLQの過激派は一連の行動を「ケベックの労働者を解放するための人民革命」と称しましたが、当然大多数のケベコワの支持は得られませんでした
。
多くのケベコワは「カナダ連邦内の主権」の確立を目指すルネ・レヴェックのケベック党に期待を寄せました。ケベック党は1976年の選挙で勝利し、法律制定権、課税権、外交権などを含む政治的主権の確立と、金融制度や関税制度などは連邦に依存する国家連合を目指しました。
なんというか、「いいとこ取り」という感じです。
レヴェックはフランス語をケベックにおける「唯一の公用語」として、州内のフランス語化を推し進めたため、ケベックに本社がある企業が逃げ出し、イギリス系住民20万人もケベックから脱出していきました。
1995年、ケベックでは「主権連合」の可否を問う住民投票が実施されました。
カナダとの政治・経済の連携を維持しつつ、主権国家となるか否か。
結果、賛成が49.42%に対して、反対が50.58%。
僅差で反対派が勝利しましたが、連邦政府はさらにケベックへの譲歩をせざるを得ず、当時のクレティエン政権はケベックを「独特の社会」と認め、ケベックに憲法修正拒否権を与えるなどして図りました。
その後は州の景気が悪化して中央政府からの支援が必要になったこともあり、分離独立論は沈静化しました。住民投票はその後実施されず、最終的な分離独立を目指すケベック党も無残に落ちぶれてしまいました。現在もケベック州の平均収入は低く失業率は高く、仮に分離独立を行ったところですぐに経済的に苦境に立たされることは目に見えています。
当面はケベックの分離独立の可能性は低いと思いますが、今後
どのように転ぶか予想もつきません。
まとめ
宗教の問題や言語の問題など色々あるのでしょうが、フランス系カナダ人の「イギリス的 」に対する拒否感と抵抗の歩みは壮絶というか、感心を通り越して呆れてしまいます。表には出てきませんが、フランス系住民はイギリス系に対して「文化的民族的優越性」を抱いており、奴らに下るのは死んでも嫌だし、というかイギリス系が自分たちフランス系に下るべきだ、くらいに思っていそうな感じです。
そうでも思わないと、経済的政治的恩恵を充分受けて様々な譲歩も得ているのに、「美味しいところはありがたくもらっとくけど、皆と同じ負担を負うのは嫌だからね」なんて言えませんよ。
とまあ、日本人的な価値観で見るとそう思っちゃいますが、きっと話はそう単純でないのでしょう。
日本から見ると羨ましいほど公平公正で心が豊かな社会に見えますが、その内情は中央と地方が互いに疑心暗鬼に満ちて結束は脆く、産業はアメリカ頼みでハイリスクだし、人種差別も一部は根強い、結構大変な感じなようです。
参考文献・参考サイト
『カナダ史(新版 世界各国史)』 細川道久, 吉田建正, 木村和男 山川出版社
History of Quebec - Wikipedia, the free encyclopedia
有料マガジン公開しました!
はてなブログで公開していたブログの傑作選をnoteでマガジンにしました。
1記事あたり10円でお安くなっています。ぜひお求めくださいませ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
