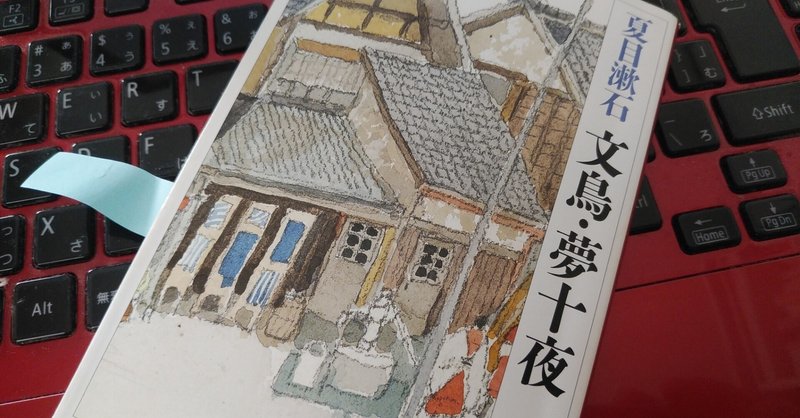
落ちこぼれシニアのリベンジ読書~『文鳥』夏目漱石著~
いろいろな書評にもあるように、この作品は小説というより随筆のように思う。
ある意味で、漱石の人間性がにじみ出ているといえるだろう。
さすがと思ったのはその細やかな描写。極めて知覚的であるところが、とても興味深い。
例えば「嘴の色を見ると紫を薄く混ぜた紅の様である。その紅が次第に流れて、粟をつつく口先の辺りは白い。象牙を半透明にした白さである」(新潮文庫 P16)という視覚表現。
「紫を薄く混ぜた紅」「象牙を半透明にした白さ」。目の前に文鳥がいるかのような錯覚さえ覚える。
同様に「菫程な小さい人が、黄金の槌で瑪瑙の碁石でもつづけ様に敲いている様な気がする」(P16)。さすがにこうしたシーンは見たことも聞いたこともないが、マルっとした、スピードとリズム感あふれる様子なのだろうか。漱石が文鳥を見る微笑ましい姿が目に浮かぶようだ。
しかも文鳥の表情から、昔好意をもった(!?)女性を思い出す。
(引用はじめ)
水道の水を汲んで、籠の上からさあさあと掛けてやった。(中略)文鳥は絶えず眼をぱちぱちさせていた。(中略)裏二階から懐中鏡で女の顔へ春の光線を反射させて楽しんだ事がある。女は薄紅くなった頬を上げて、繊い手を額の前に翳しながら、不思議そうに瞬きをした。この女とこの文鳥とは恐らく同じ心持だろう。
(引用おわり P22)
この表現も漱石ならではの微に入り細を穿つところであると思う。
いずれも素晴らしい写実性である。
その一方で、後半は漱石の内面を疑うようなところも多くなる。
仕事も忙しく文鳥の世話が面倒くさくなる。手抜きする。下女が気が付いた時に世話をしてくれる。それをいいことに放置プレイ。そして徐々に文鳥に関心を示さなくなる。
遂に文鳥が死んだ時には下女のせいにして、文鳥の亡骸を放る。さらに三重吉に対して「家人が餌を遣らないものだから、文鳥はとうとう死んでしまった」(P26)と手紙を書く。
なんと冷たい人。リアリストとしての漱石の一面を垣間見る。
あんた、どういう人!? それでいいと思ってるの!? そう言ってやりたい。
まさに漱石の人間性がよくあらわれた作品である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
