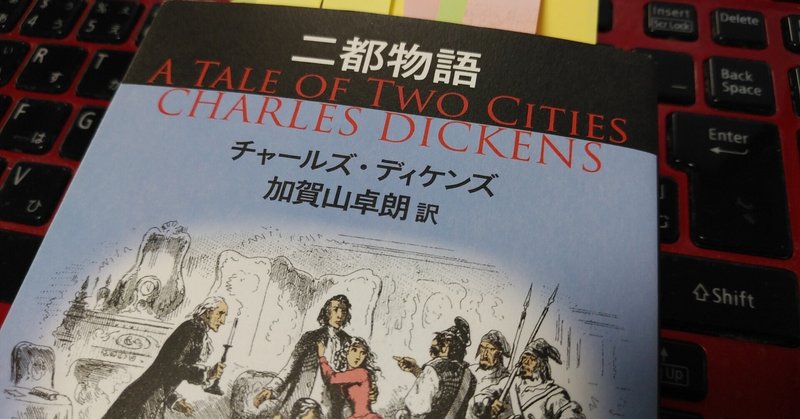
落ちこぼれシニアのリベンジ読書~『二都物語』チャールズ・ディケンズ著 加賀山卓朗訳~
<<感想>>
フランス革命の背景を正しく理解していないとなかなか難しいかもしれない。
著の中での市民の会話(会話の最後に「市民」という言葉をつける→「また歩いていますね 市民」)。いまのわれわれからすると、どこかの国のようなまったく奇異な世界だ。しかも「スパイ」が横行。内部告発も多発。自分を守るために相手を蹴落とす・・・・・・・・。当時のフランス社会の息苦しさがうかがえる。
ロベスピエールの「恐怖政治」は、国内の反革命分子を徹底的にギロチン処刑するものと理解していたが、もはやフランス社会全体が「恐怖」の中にあったようだ。「恐怖政治」ではなく「恐怖社会」となっていたように思う。
そんな中での「悲劇の恋」の物語。
常に革命の爪痕を感じる。
召使いに対する悪行三昧の貴族であったダーネイの父・叔父。
当時の貴族はみなそうだったのか。権力を手にすると勘違いしてしまうものか。
さらには、正しいものを事実として正視せず、すぐにギロチン処刑。しまいには風物詩としてそれを楽しむかのような大衆の様子。1日に数十件も処刑されるにあたって、大勢集まった回りの見物人(席取りまでしている)は1人処刑されるたびに「イチ」「ニィ」「サン」・・・・・・・とみんなで唱和する。(ちなみにギロチンを「刃先鋭い女『ラ・ギヨティーヌ』」としていたようだ)
革命という名のもとに常軌を逸していた社会がそこにあった。
「自由・平等・友愛」というフランス革命の理念。
その実現ために、大衆がある意味、革命指導者に洗脳されてしまった。
憲法を作って、僧侶・貴族・王族の腐敗した封建社会を打倒する。そこまでは正しいと思っていたが。
どこで歯車が狂ったのだろうか。
その後も「行き過ぎ」と「揺り戻し」を繰り返しながら、ようやく今日のフランスになったようだ。
それにしても「悲劇の恋」という話の一方、その裏側で「大衆(大衆社会)とは何なのか」「何が彼らをそうさせる(洗脳させる)のか」、と改めて考えさせられた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
