
松本清張「半生の記」読書感想文
以外だった。
松本清張と太宰治は、同年生まれだ。
1909年の、12月21日と6月19日。
松本清張は、昭和の小説家。
太宰治は、戦前の小説家。
そんなイメージがあったが、同じ明治42年の生まれだった。
読書ノートを見ているうちに気がついた。
2人は、活動時期が入れ替わった格好である。
太宰治は10代半ばで作家を志望して、あれこれ作品を発表して、1948年(昭和23年)に38歳で死去。
そのあとの1951年(昭和26年)に、42歳の松本清張は、はじめて書いた小説が懸賞小説に入選する。
1953年(昭和28年)に芥川賞。
1955年(昭和30年)から推理小説を書きはじめる。
1966年(昭和41年)に「半生の記」発刊。
1992年(平成4年)、死去、82歳。
作家デビューまではなにをしていたのか?
松本清張は、その42歳の作家デビューまで、一体なにをしていたのか?
5作ほど読んだ中には、そのあたりのことは全く書いてない。
想像としては、その時代に文学をやる人だから、裕福な家に生まれて育っている。
となれば、定番の女中は登場してくる。
大学は卒業しているだろう。
美しい恋愛だってあるに決まっている。
卒業してからは、文学志望の書生でもやって、実家に戻ってから若旦那でもやって、でも文学が諦めきれず書いて、文壇デビューしたのだろうなというもの。
そしたら、ちがうらしい。
極貧だったらしい。
女中は登場するが、極貧すぎて祖母が60をすぎて女中に出ているという逆パターンだ。
それも、ただの極貧じゃない。
暗い。
ただ暗い。
恋愛だなんて一切ない。
文壇界の交友なんてのも一切ない。
自虐なんてものではない。
斜に構えているとか、穿って見ているでもない。
鬱屈、屈折、卑屈、恨みつらみ、といったあたりか。
松本清張の暗部を知ったような読書だった。
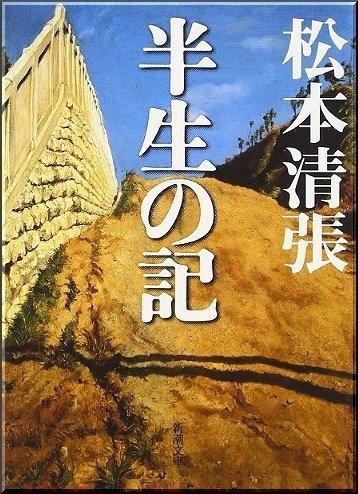
初出:1966年 河出書房新社より発刊
ネタバレあらすじ - 解説風
16歳で扇風機のメーカーの給仕に
松本は、16歳から働きはじめた。
生活のためだった。
父と母は、飲食店をやっていたが立ち行かない。
不器用で無計算な父は、何をやっても成功する見込みがない人間だった。
ちょっと儲かると、すぐに調子に乗って、身なりと整えて、肩で風を切るようにして歩いたりする。
在学中には、進学の説得のために先生が家まで来たが、ナメクジが這う土間にびっくりして、それ以来、受験勉強のことは言わなくなっていた。
松本は、扇風機のメーカーで、給仕として働く。
給料のほとんどは、家に入れなければならない。
役に立つ給仕ではなかった。
私におもしろい青春があるわけではなかった。
濁った暗い半生だった。
役に立つ給仕ではなかった。
・・・と、松本はひたすら暗い。
19歳のときには、解雇され、無職となる。
肉体労働をするには虚弱すぎた。
特別高等警察に逮捕される
この頃、松本は、地元の工場の青年たちが主催している文学同好会にも入る。
小説家の素養があったのだと思っていると、この年代の少年がよくやることで取るに足らないこと、と記している。
しかも、とばっちりで逮捕されている。
非合法となっていた共産党に関係していると “ 特高 ” に目をつけられたのだ。
警察に連行されてからは「仲間を吐け!」と調べられるが、関係がないので吐きようがない。
拷問は竹刀だけだった、とあっさりと書いてある。
留置場の房内では、排泄物の匂いになれなくて、官弁を3日食べれたかったとある。
そこに10数日入り、釈放されている。
松本清張の作品には、留置場が度々出てくる。
実際とはちがうなと思っていたが、それは時代がちがうだけで、あれらは実体験から書かれていたのかと知った。
20代は印刷職人として働く
松本は、生活のために、すぐに働かなくてはだった。
小さな印刷所の見習いとなった。
印刷が機械化されてない頃で、手作業が多かった。
熟練も技も必要で、職人になれば食うに困らないと思ったのだ。
そして、広告図案、・・・デザインとするが、そのデザインというものに目がさめた。
こき使われたが、やる気を持って仕事に取り組んでいた。
23時まえには、家に帰ったことがなかった。
帰ってからも、遅くまでデザインの練習をした。
家業の飲食店は、いよいよ閉店した。
父親は60歳に近かったが、体力のいる魚の行商をはじめた。
楽天家の父親と悲観的な母親
松本の父親のことである。
その出生は、隠さなければならない事情があった。
生まれると同時に養子に出されているのだ。
この父親の出生のことを、松本は「父系の指」という小説にしていると明かす。
読んでみたい1冊だ。
で、その父親は、17歳で米子市から家出。
広島で結婚。
松本は1人息子。
地元から、養父と養母を呼び寄せてもいる。
その2人も極貧だった。
汗を流して働くことを極端に嫌う父親だったという。
いわゆる “ 弁が立つ ” ほうで、示談屋をやったりしている。
無尽をやったり、米相場をやったりもしていた。
下関で餅屋をやって潰してから、一家は小倉へと移った。
理由としては、なにか向こうのほうが景気がよさそうだという程度だろうと、松本は記す。
逆境ばかりの父親だったが、恐るべき楽天家である。
松本が幼少のころから、なにかをやっては失敗したり、愛人をつくって見限られたりしているが、深刻に悲しんでいる姿を見たことがないという。
落ちぶれたようにして行商のリヤカーを引く姿を、かつての愛人に見せても全く気にしない性格だった。
借金とりに粘られたときに、いくらか困った顔をしたくらいだったなどと、父親についての文面には悲壮感はない。
楽観的な父親に対して、母親は悲観的だった。
気が強くて、夫婦ゲンカばかりしていた。
こんな不幸な夫婦はなかった。
その母親は、文字が読めずに、字も書けなかったという。
が、母親についての文面には、どこか逞しさを感じさせる。
松本清張の結婚の謎
印刷の技術を身につけた松本は、職人らしい給料を得るようになった。
生活を確立させたいだけで、楽しみなどなかった。
文学のことなど考えてなかったと、またウネウネと暗く記している。
そして、すさんだ生活をしている渡り職人も目にしたりして、職人の世界に身を置く恐ろしさもわかってきた。
両親も、魚の行商が無理なくらいに老いてきていた。
行末を考え込まずには、いられなかった。
このとき松本は28歳なのだが、いきなり結婚をしている。
経緯については、まったく書かれてない。
以降にも、妻については、さほど書かれてない。
このあと軍隊に召集されたときには、泣く両親のことは考えていたが、子供を抱いている妻の影は薄かったともある。
妻に好意があるのか、なにかしら負の感情があるのか、それすらもわからないほどに書いてない。
たぶん、妻については、全部で5行もないのでは。
28歳で独立の転機がくる
転機が訪れたのは、勤めていた印刷所が潰れたことだった。
版下屋、・・・いってみれば、デザイン事務所で独立をしようと思ったのだ。
そして、朝日新聞の支社が、小倉にできることを知る。
なにかデザインの仕事があるのかもしれない。
でも、どうやって営業したらいいのかもわからずに、手紙をかいたら面接となって採用となったのだ。
が、よくよく確めてみると、広告の図案を1枚描いていくらという下請け契約だった。
松本は、3年間の下請けをやる。
それから、朝日新聞だけの仕事にして、待遇は雇員と変わっていく。
下請けから含めると、小説家になるまでの約20年間、途中で兵役の2年間があるが、朝日新聞の広告部で仕事をする。
・・・ 一見、いい待遇のように思える。
が、松本の鬱屈は果てしない。
雇員と準社員と社員の階級があった、営業の社員の態度が鼻持ちならなない、図案係と校正係は見下されていた、現地採用の者は寂しい、風に散っていく木の葉のよう、と自虐というよりも卑屈にまみれている。
日中戦争が激しくなっていく頃でもあった。
松本は「皇軍!北京入城!」という図案も描く。
松本清張ではじめて泣いた
松本は、33歳で軍隊に召集される。
集合場所の兵舎では、1時間ほどで、出征先がパプアニューギニアだと漏れ伝わってくる。
兵隊たちは運命に敏感で、絶望感が広まっていく。
古い召集兵ほど「今度は駄目らしい」と青い顔をしている。
5日後の未明に、招集兵は出発する。
面会禁止されていた中での極秘の出発だった。
隊列を組んで、博多港まで歩きで向かう。
雨が降るなか、兵舎を出て、人のいない街を進んだ。
が、極秘のはずの出発の日時は漏れていたのだった。
強い雨のなか、女の影が何人も現れて、隊列を執拗に追った。
夫の姿を探している妻たちだった。
が、暗いので顔がわからない。
隊列は、押し黙ったまま進む。
女たちは、警戒の憲兵に阻まれたが、隊列に遅れないように小走りで駆けた。
人数も次第に増えていった。
雨は強い。
どの兵隊も、顎から雫を垂らしていた。
・・・ 檻の中で読んでいるからか。
松本清張の小説ではじめて泣いた。
一切の感情も描かれてない。
静かに書かれているだけなのに泣ける。
そのとき松本は、妻の小さな叫びも聞いたかもしれない。
泣いている兵も、見たのかもしれない。
昭和18年、朝鮮の京城での軍隊生活
全国の招集兵は、朝鮮の京城に集まり、兵団に編成されてからパプアニューギニアへ向かう。
京城に着いてからは、途中で輸送船が沈んだ場合の訓練ばかりしていた。
先発した輸送船も、撃沈されたとのことだった。
先発した部隊には見知った顔もいたが、とても生きているとは思えない。
松本は、死を覚悟した。
撃沈されすぎて、輸送船がなくなったらしい。
そのまま終戦までの2年間、松本は朝鮮に留まる。
衛生兵として、炊事や洗濯という雑役ばかりだった。
演習もないし、訓練をやるのでもない。
空襲は1度もなかった。
戦争など、どこで起きているのか疑いたくもなった。
一切の思考は死んでいた。
頭脳は動物化していた、ともある。
が、この2年間、それほど怠けた兵隊ではなかったという。
妙な生き甲斐もあったというのだ。
軍人精神ではなく、新聞社の職場の反動だったと、松本は自己分析する。
新聞社では、どうあがいても、差別的な待遇からは抜けきれなかった。
歯車のネジという例えがあるが、私の場合はそのネジにすら値しなかったのである。
ところが、兵隊生活では、社会的な地位も、貧富も、年齢の差も帳消しになる。
上官のご機嫌取りでもなんでも、なにかに励むことで、個人的顕示が可能なのを見出したのだ。
軍隊は人間性の抹殺だという人が多いが、私の場合は逆の実感を持った。
・・・ と全否定ではない。
以外だった。
終戦直後にホウキの仲買人をする
終戦のち日本へ帰還。
喜びはさほどない。
またあの両親に頼られるのか、また生活に追われるのか、と気が滅入っている。
妻の実家の、佐賀の村に疎開していた家族と合流する。
知らせることもなく帰ると、妻は畑を耕していた。
姿を目にしてからは何も言わずに、ただ涙を流していたとあって、以降は妻の記載はない。
もしかしたら松本は、妻のことを書くのが照れくさいのかもしれない、とうっすら思う。
で、その家族は、祖母、両親、妻、子供2人の6人になる。
他に同居の5人家族もいて、人間地獄に飛び込んだとある。
家族は農家の手伝いをして、作物を譲ってもらっていた。
なにか物品があえば、米などにも交換してもらえるのだが、そんな物品も持ってなかった。
村の寄食者のようだった。
2年ぶりに小倉の新聞社にいったが仕事がない。
広告もない。
印刷する紙もないという物不足だった。
週に2日の “ 買出し休暇 ” も認められていた。
佐賀の村にいる家族を救い出す義務があった。
松本は、小倉でボロ家を借りる。
そのとき、あることに気がつく。
掃除をしようと思っても、ホウキがないのだ。
市中の荒物屋を回ってもない。
が、佐賀の村の農家には、藁でつくったホウキが、軒先にたくさん置いてあった。
あれを持ってくれば、売れるのではないのか?
試しに見本のホウキを荒物店に持っていって、2割ほどかけた値を言ってみると「いくらでも送ってくれ」という。
利益は薄いが、家族を食わす収入にはなりそうだ。
そう思った松本は、小倉、門司、八幡の店を回る。
予想とおり、ホウキは出回ってないのだ。
モノ不足とインフレだった。
日曜日と、買出し休暇の2日は、ホウキの売込みに回った。
リュックサックに見本のホウキと握り飯を入れて、立ちっぱなしで夜行列車に乗って、大阪、京都、大津、奈良も回った。
今度は、ホウキの製作者の農家が、材料の針金と竹が足りないと言いだす。
松本は、材料の買出しに各地にいく。
昭和23年になると、インフレも食糧不足もモノ不足も収まりかけて、買い手のほうが強くなってくる。
支払いも延ばされたする。
松本は、ホウキの仲買をやめたのだった。
ホウキ商売の総決算としては、貯金まではできなかったが、あのインフレのなかで家族を食べさせることはできた、と満足そうである。
明らかに充実もしていた。
松本にしてはめずらしい。
少年時代からたびたび書かれているのは「あの山を越えてみたい」「1回見てみたい」「あの先に行ってみたい」「まだ行ったことがない」という好奇心である。
遠くまでホウキを売りに行きながら、現地の遺跡や仏閣も見て回っている。
それについては、楽しそうに記している。
削除されている部分がある不思議
この文庫には不満がある。
削除されている部分があるのだ。
この「半生の記」は、他の松本清張の本で紹介されていた。
その本の題名は、なんだったか忘れたが、あとがきに抜粋があったのだ。
ところが、その読みたかった部分が、この本にはない。
どうみてもない。
削除されているのだ。
その抜粋は、おおよそ以下である。
ホウキの仲買人をしていた松本は、あるとき旅館に泊まる。
向こうでは、儲けている闇屋がどんちゃん騒ぎをしている。
ホウキの仲買人が、いかにも小さな商売に思えた。
でも家族のためには、やらなくてはいけない。
そのとき松本は、ある小説を思い出す。
・・・ ここがうろ覚え。
たしか井原西鶴か近松門左衛門あたりの古い小説で「働けど働けど我が暮らし楽にならず」とつぶやく主人公の泥棒を挙げる。
以下は、しっかりと覚えている。
私はこのときほど、この泥棒の気持ちがわかったことはなかった。
経験は以上である。
・・・ といった内容である。
このくだりが、そっくりそのままないのだ。
まさか、泥棒の気持ちがよくわかった、というのが犯罪を助長するとでもされたのか?
実際に、そこで犯罪者となったなら問題だけど。
とにかくも、このときの松本があったから、それからの小説も書けたのかなと多少の推測もして、いちばんの楽しみにしていた場面だったのに。
その泥棒の小説の題名を知りたかったのに。
ただ、不思議。
焦燥、後悔、虚無、
40歳となった松本は、新聞社の広告部で働いている。
当然のようにして、充実などしてない。
子供も3人になっている。
8人家族の、足の踏み場がない狭い家。
ポスター書きなどのアルバイトをしなければ、生活費が足りない。
とぼとぼと家に帰る途中で、夜空のオリオン座を見上げる。
ああ、こんなことではいけない。
なんとかしなければ。
焦りとも後悔とも虚無感ともつかないものが、胃に落ち込んでくる。
・・・ 書き忘れていたけど、松本が子供のころになりたかった職業とは新聞記者である。
父親が新聞を読んで、さまざまなことを話すのに、憧れがあったようである。
10代のころに新聞社に面接にいって、学歴がないから面接すらなく帰らされたことも書いてあった。
その憧れの新聞社で働いているのに、仕事は決まっていて、出世などには関係なく、このまま定年を迎えるという鬱屈が、全編の根底にあるのは伝わってくる。
で、松本は、わけもなく腹が立っている。
家族の多い家に帰るのがうんざりしていた。
外に出ても行き場がなかった。
浜辺に腰を下ろして海を眺めたり、松林を歩いたりもした。
もし、私に、もっと直接的な動機があったら、そのときに自殺を企てたかもしれない。
だが、そういう強いきっかけさえ身辺になく、ただ苛立たしいい怠惰の中に身を浸していた。
脳髄は腐っていた。
・・・ ここまで、小説の “ しょ ” の字も出てこない。
いい年ぶっこいて、ふて腐れているただのオヤジだ。
昭和26年、42歳で突然に小説を書く
あるとき、松本は、必要があって辞書を引く。
“ 西郷札 ” という語句に目が止まった。
そのときに、一気に空想が生まれたというのだ。
1等30万という懸賞金つきの小説の募集があるのも知る。
そして20日間で「西郷札」という小説を書き上げる。
3等に入賞して10万円を手にする。
その10万は生活費で消えた。
が、はじめて書いた「西郷札」は直木賞候補になる。
これが、私に野心を持たせた。
・・・ にわかには信じられない。
本当は、こっそりと書き溜めていたのではないか?
そんなにも書けてしまうものなのか?
とにかくも、ここから終盤になっていく。
ラスト5ページほど
次に書いた小説も売れた。
一家8人で東京に引っ越す。
昭和29年のことで、松本は45歳になっている。
その1年半後に、母親は76歳で死去する。
祖母と同じように、最後には目が見えなくなっていた。
その4年後。
父親が89歳で死去した。
長女の嫁入りが、もう少しのところだった。
もっとも息があっても、どこまで見えたのかはわからない。
死ぬ半年前から、その瞳は、気味がわるいほどに、きれいな灰色になっていた、と終わっている。
