
司馬遼太郎「項羽と劉邦 中巻」読書感想文
文庫版のカバーの紹介文が変だ。
上巻には『劉邦は人望があり天下を制した』とある。
中巻には『劉邦は仁徳で将に恵まれた』とある。
この紹介文を書いた人は、本文を読んでいるのだろうか?
余計なお世話だけど、この紹介文と本文はチグハグである。
パッケージと中身が違うような、せっかくの小説を粗悪品まがいにしている。
『人望』という語句が美質だとすれば、どのように読んでも、司馬遼太郎が描く劉邦からは、美質さは感じられない。
『仁徳』が高等な振る舞いだとすれば、同じように劉邦からは、とても高等さは感じられない。
ともかく、以下を抜粋した。
すべてが劉邦の装飾語として、一挙手一投足に対して付けられたものである。
『人のおだてに乗りやすい・百姓のおやじ・道楽は色しかなかった・生まれ故郷の農民からは嫌われ・実家の長兄から無視され・兄嫁から露骨に厄介者あつかいされていた人間・身ひとつで逃げるというのは劉邦の得意芸・ただの土俗人』
これらはすべて、登場人物を介して発しているのでない。
しっかりと、司馬遼太郎が、劉邦の人物像として描いている。
劉邦とは不思議な人物
司馬遼太郎は、この長編を書いておきながら『どうして劉邦みたいな男が皇帝にまでなったのかわからない。』とも書いてあるので、読んでいるこっちがずっこけてしまう。
『人間は予測不可能で、すべてが運命である。』と身も蓋もないことを書いてある。
まだ途中だった。
司馬遼太郎から劉邦への、悪意の装飾語の抜粋はまだまだ止まらない。
『自分の弱みについては正直・臆病で戦下手で身動きがにぶい・ろくに文字を知らない・役立たずの男・遊び人あがりなだけに体力や根気がない・配下にとってじつに話しやすい男・危機について鈍感な男・彼は戦っては負ける名人』
劉邦は、偉業を成し遂げている。
無名の農民から帝国を建設した人間は、中国史上においては劉邦しかいない。
司馬遼太郎はそうも書いてはいる。
が、どうしても劉邦だけは嫌いらしい。
後の明の時代となり、卑賤の出から皇帝となった朱元璋がいるにはいるが、彼には学問があった、劉邦とはちがう、と無残に突き放している。
まだまだある。
あの優しそうな司馬遼太郎は、劉邦への悪口を続ける。
『人に対して無礼で傲慢・無作法で知られた劉邦・両眼は聡明という印象から遠い、厚い唇はいかにも欲深そうだ・愛すべき愚者である・農民あがりであるだけに表情が素朴・ただの田舎のごろつきではなかった・百姓唄をうたっておおはしゃぎ』
司馬遼太郎から、劉邦への悪口はまだまだ続く。
まるで、タイムスリップでもして見てきたようだ。
『沛の町の女で劉邦という年中町をごろついている男を好きだとおもっている者など居なかったといっていい・法螺ふき・身なりも田舎の大公といった感じで泥臭く・仕事きらいの怠け者・銭なし・平然と自分自身の値踏みをできる男・能無し男の巨大な徳』
もしかしたら、自分は『人望』とか『仁徳』という意味をとり間違えているのだろうか?
劉邦の長所は4つほど
司馬遼太郎は、劉邦の長所もあげてもいる。
でも、数少ないから、驚きを持って発見することになる。
本書で劉邦の長所として発見できたのは、たった以下の4点だけである。
気前がいいこと。
褒めるのが上手なこと。
愛嬌があること。
人の話をよく聞くこと。
くどいけど、たった、上記の4点数のみである。
もっと探せばあるかもしれないけど、せいぜいあと2つか3つだと思われる。
しかも、司馬遼太郎は、長所を挙げているのか、けなしているのか、どっちかわからないという状態に陥っている。
気前がいいのは、ちんけな盗賊団の頭をやっていたから、ぶん捕った獲物を分ける按配がよくわかっている、といった評価である。
褒めるのは、一応は世知に長けているから。
愛嬌があるのは、ただ単にバカだから。
人の話をよくきくことだって、なにも考えられないバカだからそうするしかない、と言いたいのが伝わってくる。
というか、そうも書いてある。
でも、こんな人、現代でもいる気がする。
ちょっと強引にはなるけど、劉邦とその軍団を、現代で例えれるとすればなんだろう?
社長がバカなんだけど周りが優秀だから不思議なバランスがとれている会社、といった例えがしっくりくるかもしれない。
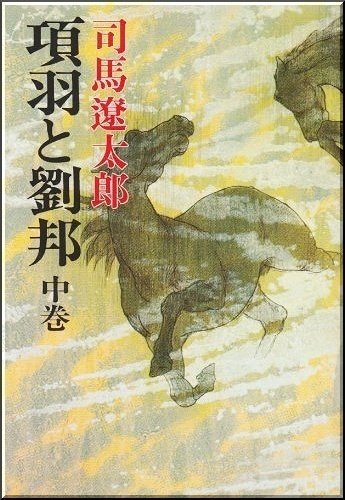
初出:『小説新潮』連載 1977年~1979年
登場人物 - 漢軍・劉邦陣営
※ 筆者註 ・・・ 以下、すべて司馬遼太郎テイスト、いわゆる “ 司馬史観 ” に沿っています。人名も地名もたくさん出てくるのですが省いてます。
劉邦(りゅうほう)
秦の帝都には一番乗りするが、項羽に咎められる。
ひらすら謝ることで、難を乗り切る。
そのあとの論功行賞では、漢の王に封じられる。
が、その僻地の流刑地だった。
漢に地についた劉邦だったが、大将に任命した韓信の進言を受けて、もう1度打って出ることを決める。
が、あっけなく大敗。
篭城してからは1年が過ぎた。
蕭何(しょうか)
劉邦軍の文官を受け持つ。
仕事熱心で、帝都の宮殿に乱入したときには、財宝に目をくれずに多数の行政文書を持ち出す。
情報を分析して、のちに漢帝国の成立に多大に関わる。
もっとも、このときは、劉邦が後に皇帝にまでなるとは思ってもないようである、と司馬遼太郎は記す。
漢王となった劉邦とは、漢の地まで同行する。
内乱となってからは後方支援をする。
この蕭何がいなかったら、劉邦などどうなっていたのかわからないとも、司馬遼太郎は記している。
長良(ちょうりょう)
元韓の貴族の生まれ。
韓の再興を望んでいる。
秦を憎んでおり、帝都に向かう劉邦軍に加わる。
兵法と老子の思想を学んでおり、軍師として様々な作戦を考え、弱かった劉邦軍を勝利の方へ形づける。
長良が実行した作戦のひとつには、ゲリラ戦がある。
小部隊を編成して、裁量権を与えて行動させる。
敵を引きつけて、その間に本隊を進ませる。
この大陸の戦史上、戦略としてのゲリラ戦は、この長良が最初ではないかと思われる、と司馬遼太郎は解説する。
韓信(かんしん)
項羽の親衛部隊の下級士官だったが、いつまでたっても評価が低いことに不満がある。
自ら作戦をたてて軍を動かしたい、という野望もある。
劉邦に賭けたのだった。
漢王となって封地へ向かう劉邦に元へ参じる。
蕭何が強く推薦した。
「おもいきった抜擢をしなければ」というので、大将とすることに劉邦は決める。
また、蕭何は、簡単に口頭で任命しようとする劉邦を咎めて、漢の地で盛大な任命式を挙げるようにする。
大将となった韓信は、項羽の至らなさを挙げて、打って出ることを進言する。
今度は、劉邦がそれに乗る格好になる。
陳平(ちんぺい)
項羽側から劉邦側に鞍替えする。
陣営に加えるのを反対するものも多かったが、毒をもって毒を制すという考えで重用する。
漢軍となってからの城郭での篭城戦となったとき、項羽の猜疑心をつく心理戦を献案。
金をバラまいて噂を流して、軍師の范増を去らせるのに成功する。
城郭からの撤退にも奇策を実行する。
登場人物 - 楚軍・項羽陣営
項羽(こうう)
秦を滅ぼしたあとの論功行賞を仕切る。
で、失敗する。
反感と恨みを買う。
あまりにも武功をたてて、物事を勇断するので、周囲はなにも言えなくなる状態になってしまう。
義帝(ぎてい)
楚の懐王から改名。
“ 鴻門の会 ” のあとの論功行賞では、18名の王の1人となる。
新たな封地へ向かう途中に、力を持つことを恐れた項羽に討たれる。
このことが、漢王となった劉邦の宣戦布告の名目となる。
范増(はんぞう)
70代前半の項羽の軍師。
劉邦を早くから危険視していた。
“ 鴻門の会 ” では、劉邦の謀殺を計画する。
計画が失敗して劉邦の命が助かると「そのうちに連中は劉邦にとりこまれる」と危機感を覚える。
その後の内乱となってからは、陳平の工作で、猜疑心を抱いた項羽から遠ざけられる。
このことで項羽に見切りをつけて、自ら陣営を去る。
故郷へ帰る途中で、憤りのため急死する。
項伯(こうはく)
項羽のもう1人のおじ。
項羽軍の将の1人。
若い頃は放浪していて、そのときに殺人犯として当局に追われて、長良にかくまってもらったことがあった。
恩を感じていたことから、長良に面会にいき、劉邦もろとも助けると約束する。
項羽には「義に背く」と説得。
このころ “ 義 ” という語句は新しい概念だったので、それを聞いた項羽は驚く。
で、“ 鴻門の会 ” で劉邦の命が助かる遠因ともなる。
司馬遼太郎は、このことを『侠の行為』と解説する。
のちの日本にも、欧州にも、類似した精神が見当たらない。
立場はちがうが、質としては、16世紀のイエズス会の殉教精神に激しさだけは似ている、とのことである。
ネタバレあらすじ
反乱軍は、秦の帝都がある西へ向かう
先に進んでいたのは、劉邦軍だった。
主力である項羽軍は、帝国軍と戦い続けていたから、自然とそうなったのだった。
劉邦軍は雑軍である。
流民や盗賊などの寄せ集めである。
ときには敗れて、ときには勝った。
酔っ払いのように頼りない。
雑軍を率いる劉邦にしても、もともとは一介の土匪である。
「わしなど馬上で居眠りしているだけだ」と笑っている。
もし、劉邦が有能であったなら、配下は命令を待って動くようになっていたのかもしれない。
忖度で疲れてしまっていたのかもしれない。
そんな劉邦から仕事を任された配下は、生き生きと動き回った。
雑軍は膨れ上がっていき、戦いにも勝つようになってきて、次々を城を抜いていく。
秦の郡県の長官から、降伏の申し出を受けもした。
こんなことは初めてでもあった。
秦の壁が崩れはじめたのだった。
秦帝国は15年で亡んだ
秦の帝都は陥落した。
いや、進軍してるだけのなのに、戦わずにして宮廷が降伏を申し出てきた。
秦の官僚制度は、平時にあってはすぐれた運営ができるが、ひとたび危機に陥ると、宮廷の官僚は我が身を保つことだけを考えて、戦って死守しようとはしない。
あっけない事態であった。
雑軍は帝都に入った。
元来が流賊あがりの劉邦だった。
天下の財宝と、天下の美女を集める都に入らなければ、なんのために秦を滅ぼしたのかわからいと思っている。
争って財物をつかみ取りして、逃げる女を追いかけた。
やりすぎたと事態を収拾したときには、宮廷はさんざんと荒らされたあとだった。
劉邦軍は、帝都の近くに宿営をすることになる。
紀元前206年、鴻門の会
項羽軍の、帝都への到着は2ヵ月遅れた。
「あの百姓が!」と項羽は激怒していた。
反乱軍は、おじの項梁がつくったのであり、項羽が鎮圧軍を負かしたのである。
劉邦などは、小部隊をつれて途中で陣借りしてきた男ではないか、と討ち取るつもりでもいる。
劉邦もそれはわかっていた。
項羽軍と劉邦軍は緊張した。
5倍もの兵力がある項羽軍を前にして、劉邦の運命を見限る者もいる。
劉邦も逃げ出したいが、こうなってはそうもいかない。
鴻門の会では、地面に這いつくばって申し開きをする劉邦だった。
その姿を目にした項羽は「こんな情けないヤツだったのか」と気勢を削がれ斬るのをやめた。
項羽は論功行賞に失敗する
鴻門の会のあと、項羽が主導して論功行賞が行われた。
新体制が決まる。
全土に18名の王が封じられたのだ。
18名の王は、楚王に臣従して、封建制度が復活した。
劉邦は、漢の王に封じられた。
が、僻地の流刑地だった。
そこへ行くには、ヒマラヤに続く海抜3000メートルの山々を越えなければならない。
道路といえるものもない。
都落ちである。
漢王となった劉邦だったが、前途を見限って逃げ出す将が続出した。
漢軍は楚に向かい進撃する
新しい体制は、半年で揺らいだ。
僻地の劉邦が「打倒項羽!」を掲げて進軍したのだ。
「東へ帰るのだ!」と、新しく “ 漢軍 ” を名乗る軍は進む。
内乱となったのだが、漢軍を中心にした勢力は、あっという間に3万に膨らんだ。
あの、項羽の論功行賞は、多くの不満を残したのだった。
基準が単純すぎた。
戦いで功績があった者しか評価されなかったのだ。
項羽は、楚の王となっている。
漢軍は、楚の中心の都を目指して進む。
ゆくにつれて兵が増えた。
信じられるだろうか?
つかの間に勢力は56万になったのである。
「敵を攻めるよりも、味方を維持するほうが難しい」と行軍をしながらの劉邦は、毎晩、諸将を招いて宴会をした。
劉邦の接待の力量は、相当なものだった。
もっとも、劉邦が好きで酒を飲んで騒いだという面もある。
漢軍の大敗北
漢軍は、押し寄せるようにして楚の都を占拠。
項羽は不在だったのだ。
10万の兵を率いて、北方の鎮圧に向かっていた。
10万の兵は、各地に展開しているので召集に時間がかかる。
項羽は3万の兵だけを集めると、楚の都へ急行した。
古来から戦いは無数にあるが、このときの項羽の勝利はすさまじいものだった。
「項羽がくる!」というだけで、たったさっきまでの56万の大軍が逃げたのだ。
木端微塵とはこういうことであろう。
もちろん、劉邦も戦わずに逃げている。
紀元前205年5月から翌5月まで篭城する
西へ向かって大敗走した漢軍は、再び集結。
10万の兵が、城郭に入り篭城作戦をとった。
すでに漢軍を見限っている者も多い。
今度は、項羽の楚軍に囲まれる事態となる。
城郭への補給路を巡る戦いが続いた。
負けては奪還してが繰り返された。
1年が経つと、補給路の維持が危うくなってきた。
この道が絶たれたら、たちまち城内は飢えてしまう。
さらに西側の城郭へ、撤退することになる。
奇策が実行された。
降伏すると見せかけて、こっそりと撤退するのだ。
