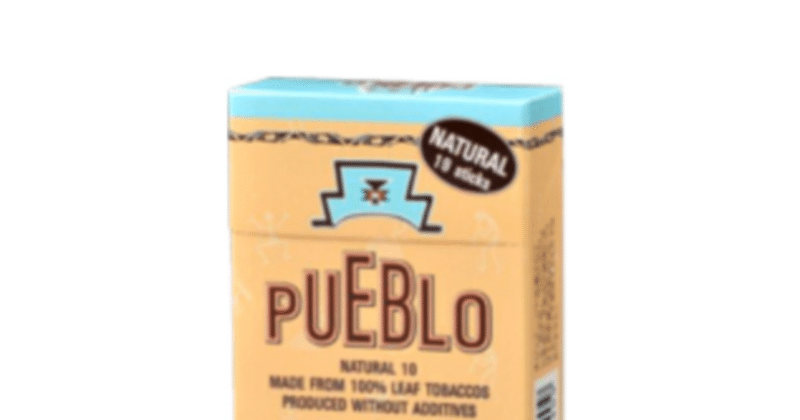
【一次創作】煙の絆
私が若かった頃、喫煙所でよく愚痴ってました。時は流れ、今はときどき、若い人から愚痴を聞く立場になりました。あのとき、先輩たちが思っていたことは。
テーマはそんなところです。そして、大部はフィクションです(今はもう喫煙していませんし。)。
「煙の絆」
執務室から、遠い遠い、仕切り壁も天井もない、野ざらしの屋外喫煙所。
オフィスビルに囲まれたこの場所は、22時をまわれば、あたりは明かりも人も少なくなる。
40をとうに過ぎたおれは、視力もまた加齢により低下し、暗い場所では、人もモノも見えにくくなった。
誰かがいることはわかるが、それが誰かを知ろうと思えば、注意深く目を凝らさないといけない。
22時をまわっても、喫煙所にはまばらではあるが人がいる。
この時間にこの場所にいる「人間のこと」は、だいたい覚えた。今日もおなじみの面子だ。
「人間の顔」と言わなかったのは、先にも述べたとおり、顔自体はよく見えないからだ。
それでも、歩き方とか足音、背格好、佇まいは当然として、たばこを吸う、煙を吐くといった所作、ペースなどにも、個性はあらわれる。銘柄が違えば、煙の臭いも違う。
見えなくたって、わかるのだ。
ライターでたばこに火を点ける。ふと「ブックマッチ」の生産が終了したという話を聞いたことを思い出した。個人的には、火をつけにくいので、好んで用いることはなかった。
しかし、ライターをなくしたとき、鞄の中や上着のポケットのなどにブックマッチが入っているのを発見すると、「たばこの神様って、いるんだなぁ。」と嬉しくなったことを覚えている。
たばこは、20歳の2か月目まで吸わなかった。特に法律のことを気にしていたわけではない。気管支の強くない自分には、縁のないものだと思っていた。
大学時代の友達に、興味本位で「一本吸わせてくれよ。」とお願いして吸わせてもらったが、煙を肺に入れた途端、喉を切るような痛みとえずきが止まらず、すぐに灰皿に投げ入れた。友達には「もったいねえことするなよ。」と叱られた。「くれ」と言われたからあげたものを、目の前で一瞬で捨てられたのだ。そりゃあ、怒るだろう。
そこからどうして、喫煙という習慣が身についたのか、記憶にない。今となっては、立派なヘビースモーカーになった中年がひとり居る、ということだけが事実だ。
*
昼過ぎから一本も吸っていなかったから、ニコチンが身体の隅から隅まで、よく染みわたる。
人によって様々だが、おれの場合は、手先の毛細血管が顕著に冷える感覚に浸される。そして、口腔と手先に感じる、心地よい刺激。鼻をとおる、絶妙な風味。さらに、軽い酩酊。歩き出せば、たたらを踏む。
この状態は、「ヤニクラ」などと呼ばれる。これが、実に気持ちいい。
目を閉じてみると、身体が平衡感覚を失っていることが理解できる。
これだよ。
この感覚が欲しくて、ここへ来たんだよ。おれはひとり満足していた。
*
最近よく見る若い子は、今日もいた。いつだったか、採用時の挨拶まわりでおれのいる部署に来ていた記憶がある。
とはいえ年が離れすぎていると、接点もそうそうない。名前だって知らない。ただ、高校生かよ、と思うくらい幼い顔をしていたことは覚えている。
若い喫煙者は珍しい。さすがにひと箱600円は安くないのだろうな、そんなことを考えた。
おれが師範代を務める空手の道場には、どうしようもないクソガキどもが何人かいるが、不良のくせに、誰もたばこは吸っていない。理由を聞けば、「高いじゃないっスか。」という。
確かに、おいそれと子供が手を出せるものではなくなった。
くだんの若い子と、目が会った気がした。軽く会釈をされた。お互い名前も知らぬだろうが、同じ会社で働く先輩、仲間、という認識は持たれているようだ。
「いつも遅い時間まで頑張ってるね。お疲れさん。」
彼が頑張っているかどうかは知らない。おれは丁寧に、社交辞令じみた挨拶をした。
「あっ…。お疲れ様です。柴田さんですよね。」
「…すまん。おれたち、どっかで一緒になったっけ?」
「いえ、その、柴田さんって、…ビッグネームですから。若い人でも大体みんな、御存知ですよ。」
お噂はかねがね、どうせろくな噂じゃねえだろ、というやりとりをしたことは何度かあったが、自分のことを、ビッグネーム、などという壮大なオブラートに包まれて表現されたのは初めてだった。彼なりに、失礼のないようにと選んだ言葉がビッグネーム、だったのだろうか。思わず笑ってしまった。
「名前、なんての。」おれは少しフランクに接した。小物なりに、ビッグネームっぽさを演出してみた。
「若竹といいます。いま、柴田さんの同期の葛城さんと同じ部屋にいます。」
若竹は、たばこを吸うのを止めておれとの会話に臨んでいるので、気にせず吸えよ、と促した。
「ありがとうございます。」というと、彼のたばこから、長い灰の塊が彼のスラックスの上に落ちた。火をつけてから、ほとんど吸っていなかったのだろう。
深く物思いに耽るときは、たばこを吸うピッチも落ちるものだ。こんな時間だ。何を考えていたかまでは分からないが、若竹も、おそらくせいぜい2年目、3年目というところだろう。
いろいろ思うこともあるはずだ。
自分が若竹くらいの年次の頃には、「若いやつは叱られるのも仕事のうちだ」なんて、上手いこと言ってるつもりのバカがいたことを思い出した。
自分もそのバカくらいの年になり、後輩や部下にあたる人間と仕事をすることも増えたが、おれの下には、叱られるのことを仕事にしている奴はいないな、と思い、安堵した。叱って出来るならいくらでも叱ればいいが、決してそういうものでもないはずだ。
おれがもの思いにふけるうちに、若竹との間には、会話がなくなった。ただ、おれがもう一本くわえると、若竹もまた、一本取り出した。若竹はおれにライターを向けてきたが、固辞した。互いに、自分で自分のたばこに、火をつける。
「若竹君は、若いのにたばこを吸うんだな。」
「ええ。子供の頃に再放送で見たドラマなんですけど。」
若竹は、昭和時代の俳優たちの、たばこを吸う仕草にかっこよさや哀愁に、ずっと色気を感じてきた、彼らのように、無言で、たばこだけで、感情を表現したり、会話をしてみたかった、という話をした。
「仕事は…嫌いか?」
「えっ!いえっ!その…ただ、楽しくないなぁと。」
まあ、好きなわけがあるまい。好きか、と聞くのは野暮だから、嫌いか?と聞いた。
「…柴田さんは、仕事、好きでしたか?今も好きですか?」
「んなわけねえだろ。」
おれは、吐き出した煙の流れを眺めながらそう即答した。
「…やる気にならないんです。やっても、叱られてばかりで。叱られれば、やる気を失って。毎日、辛いです。」
「やる気なんか、どうでもいいだろう。やる気がなければ、仕事ができないのか?」
おれは、やる気という言葉が嫌いだ。基本的に表情に乏しいおれは、若い頃から何かにつけてやる気を理由に叱られてきた。
「やる気がねえからそんなこともできねえんだよ!」
やる気があれば出来るとは思えなかった。それより、適切な指示を出せないお前が悪いとすら思っていた。
「みんな、そうでしょう。」
若竹は、少し呆れたように言った。若竹の方からヂリッという音が聞こえた。そして、吐き出された煙がおれの方にやってきた。おれに吹きかけてきたのかと思った。実際は風に流されただけだが、くだらない人間につまらないことを言った、という意思表示か、と勘繰りたくなった。
「おれは違う。ハナからやる気なんて全くない。昔から少しもない。あるのは、やらんとまずい、という思いだけだ。やれさえすれば、ここは会社だ。求められているのは成果だ。それがあれば十分だ。」
「でも、やる気のあるふりはしておけよ。会社の評価なんて、適当だ。まわりに「あいつ、てんでダメだけど、なんか頑張ってんなぁ。」と漠然と思わせておけば、そんな酷いことにはならん。その演技はお前を助けてくれる。」
ビッグネームなおれは、大物ぶって舌三寸を炸裂させた。若竹がたばこを吸ったとき、たばこの火がわずかに彼の顔を照らした。
なんだかわからないが、とても含蓄に富んだ有意義な話を聞いた、というような、満足そうな表情をしていた。
若竹は律儀におれがたばこを吸い終わるのを待ち、「いろいろお話ができて、気持ちが救われた気がします。ありがとうございました!!」と御礼をいった。おれは夜風に当たりたいからもう一本吸っていくと言うと、若竹は頭を下げて喫煙所を後にした。
*
ゆっくりと空を上っていく煙を見ながら、「こういうのを、煙に巻く、というのだろうか。」と思った。こんな話は、若竹にとって何の救いにもならんだろう。なんだか妙なテンションだった若竹だって、すぐに現実に立ち戻るはずだ。申し訳ないが、おれが若竹のために出来ることはない。
ただ、若い頃の俺は、たばこを吸いながら先輩に話を聞いてもらい、そして、どんな内容であれど、真摯に向き合ってもらえたことが、とても心強くて、嬉しかった。
今の子は、どう感じるだろうか。
22時過ぎの、喫煙所での話である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
