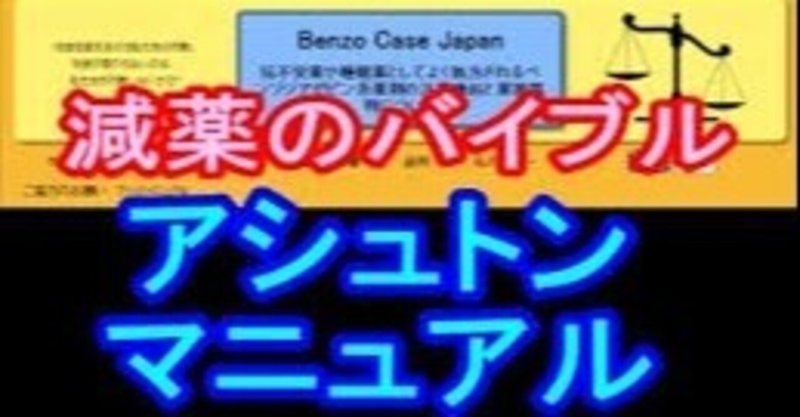
ベンゾジアゼピン系薬剤(睡眠薬・抗不安薬)の安全な離脱方法の話~通称:アシュトンマニュアルについて~
現在、私自身「ブロマゼパム」「トリアゾラム」というベンゾジアゼピン系の抗不安薬・睡眠薬の減薬を進めています。
ただ、その過程は必ずしも順調なものとは言い難いものです。既に「ブロマゼパム」の減薬中(単純に1週間に1㎎ずつ減らしていった)に離脱症状が出てしまったため、先日から通称「アシュトンマニュアル」に基づいた減薬に切り替えています。(「アシュトンマニュアル」については後述)
なお、ベンゾジアゼピン系薬剤には以下のようなものがあります。
アルプラゾラム(ソラナックス、コンスタン)・ブロマゼパム(レキソタン、セラニン)・クロルジアゼポキシド(コントール、バランス)・クロバザム(マイスタン)・クロナゼパム(リボトリール、ランドセン)・クロラゼペイト(メンドン)・ジアゼパム(セルシン・ホリゾン)・エスタゾラム(ユーロジン)・フルニトラゼパム(ロヒプノール)・フルラゼパム(ダルメート、ベノジール)・ロラゼパム(ワイパックス)・ロルメタゾラム(エバミール、ロラメット)・メダゼパム(レスミット)・ニトラゼパム(ベンザリン、ネルボン)・プラゼパム(セダプラン)・クアゼパム(ドラール)・トリアゾラム(ハルシオン)等
日本の1人当たりのベンゾジアゼピン系薬剤処方量は、他のいかなる国よりも多く、単独で短期間(2~4週間)に限って使えば、相対的に安全な薬ですが、服用が長期に及ぶと、多くの有害作用が引き起こされることがあります。(例えば、過鎮静、薬剤相互作用、記憶障害、抑うつ、感情鈍麻、耐性の形成、依存(つまり中毒)など)
また、ベンゾジアゼピン系薬剤は通常、不安や不眠に対して処方されますが、長期間の常用により、当初の効果を失います。そして不安症状は悪化し、服用前にはなかったパニック発作や広場恐怖、動悸などの身体症状、あるいは神経症状などが出現することもあります。依存は数週間、あるいは数か月の常用で起こり得ます。いったん依存に陥ると、薬からの離脱が非常に困難になる場合もあるといいます。
そういったベンゾジアゼピン系薬剤の減薬・断薬手法及びスケジュールの指針を示したのが「アシュトンマニュアル」です。このマニュアルは、イギリスのニューカッスル大学神経科学研究所教授のヘザー・アシュトン氏がベンゾジアゼピン離脱クリニックでの臨床に基づいて作成したものです。
「アシュトンマニュアル」はネットで日本語訳も公開されているので誰でも読むことが可能です。
https://www.benzo.org.uk/amisc/japan.pdf
このマニュアルに基づいて、現在、私が実践しているのは、「ブロマゼパム」という高力価、短時間作用型の薬剤の減薬を進めるにあたって、「ジアゼパム」というゆっくりと代謝される長時間作用型のベンゾジアゼピン系薬剤への置き換えです。置き換え自体にも長い時間がかかりますし、その先に「ジアゼパム」自体の減薬もあるので、だいぶ長期戦となります。
そうした置換がなぜ必要かというと、ゆっくりとした「ジアゼパム」の排出(血中濃度半減期は200時間)によって、血中濃度のスムーズで緩やかな低下がもたらされ、身体がベンゾジアゼピンの血中濃度低下にゆっくりと対応ができるようになるからだといいます。
おそらく精神疾患を患っている多くの人たちに、ベンゾジアゼピン系薬剤(睡眠薬・抗不安薬)が処方されていることと思います。場合によっては、知らぬ間に依存や離脱症状が出るレベルで長期服用されている場合もあるかと思います。
私も最初にかかった心療内科で処方され、そうした知識がないまま飲み続けてしまったため、こうした長期戦の減薬に取り組むこととなってしまいました。
知識は自身の身を守る武器です。ぜひ多くのベンゾジアゼピン系薬剤の服用者がこのマニュアルの存在を知り、きちんとした知識をふまえて医師と相談し、減薬・断薬できるようになることを祈っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
