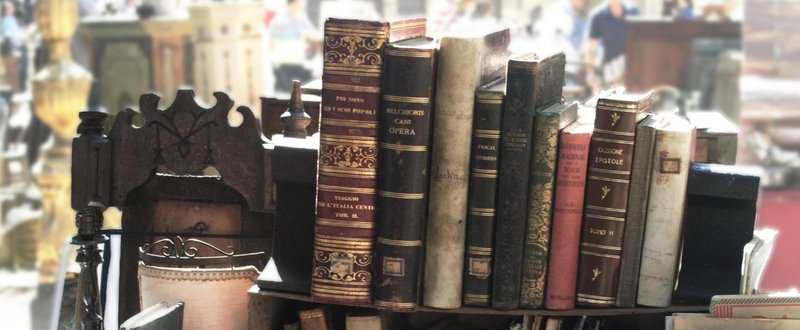
サンスクリット語の思い出
大学生の時、1年間だけサンスクリット語の授業を履修した。
記憶を頼りにかつてのシラバスを検索してみると、「初級サンスクリット語(思想)1・2」という講義。
小教室に、15人ほど学生がいただろうか。中には、聴講生と思しき高齢の紳士もいらっしゃった。
履修をしたきっかけは、恥ずかしながら「珍しい言語を学んでみたい」というものだった。そう、私は言語学習が趣味なのだ。
以下に、シラバスの記載内容を引用してみたい。
講義概要
インドの古典語であるサンスクリット語を初歩から学びます。
インドでは、学問・芸術のあらゆる分野の古典文献でサンスクリット語が用いられてきました。インドからアジア各地に伝わった仏教やヒンドゥー教を理解するためにもサンスクリット語の知識は必要です。また、ヨーロッパの諸言語と起源を同じくする古いことばで資料も豊富ですから、言語に関心を持つ人にもサンスクリット語の知識は有益でしょう。
備考
まったくの初心者を対象に、言語への興味と思想への興味の両方を想定して授業を行います。将来本格的にサンスクリット語の文献に取り組みたいという人はもちろん、なにかひとつ新しい言語を学んでみたいという人も、語学というよりは思想や歴史に関心があるという人も歓迎します。それぞれの関心に従って、積極的に参加してください。
「言語への興味と思想への興味」というコピーに惹かれたのだ。このシラバスを読み返すと、今でもあの頃のウキウキが思い出される。
サンスクリット語なのでまずは文字(デーヴァナーガリー)を学習するのだが、それは初めのほんの少し。中国語と同様、アルファベットを使った表記法があるとのことで、講義・演習は専らアルファベットを使って行われた。
扱った文献はたしか、マハーバーラタ 、バガヴァッド・ギーター 、ラーマーヤナあたり。それらから印象的な部分をピックアップし、文化的背景や思想的背景を交えながら、丁寧に読み進めていった。
使用する文法書は、まさに初学者向けの先生オリジナルのもので、ステープラで留めて冊子状になる、大変素晴らしいものだった。
「語根」という文法用語はそこで初めて知ったし、アムリタ=甘露や、アスラ=阿修羅など、現在でも目にする機会の多い言葉のルーツも知ることができた。
そして、インドカレー屋さんにはほぼ必ず飾ってあるガネーシャの誕生神話なども読んだことで、今でもカレー屋さんに行くとこの授業のことを思い出す。
教えてくださった先生は瀧川郁久先生。調べたところ、今は東海大学で准教授をされているようだ。
先生の言葉で印象的なのは、「こういった講義は、皆さんが履修しないと(=ニーズがないと)どんどん廃止されてしまいます。文学部の矜持として、古典語の授業を存続させるためにも、ぜひ積極的に学んでください」というもの。胸に響くお言葉だった。
難しいかもしれないが、機会があればぜひまた先生にサンスクリット語を教わりたいと思う、今日この頃である。
もし何かに共感していただけたら、それだけでもとても嬉しいです。いただいたお金は、他の方の応援に使わせていただきます。
