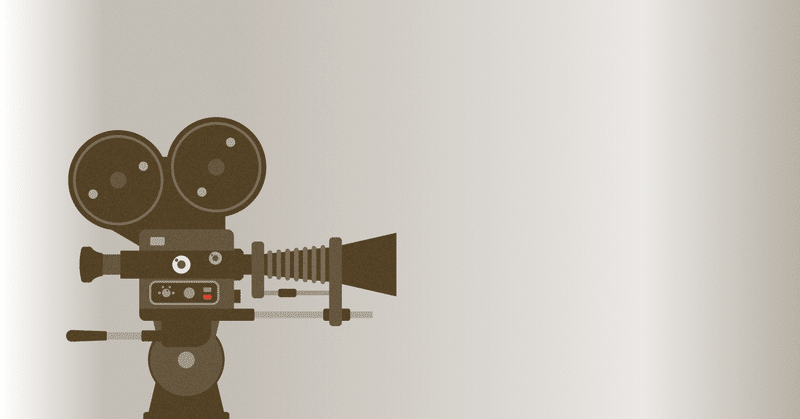
『ベニスに死す』:1971、イタリア&フランス&アメリカ
グスタフ・アッシェンバッハが客船を降りると、奇妙なメイクを施した男が笑いながら歩み寄って来た。男はグスタフに、「美しい滞在でありますように。私のことを記憶に留めてくださいますように」と告げる。
小舟に乗ったグスタフは、サンマルコの船着き場から水上バスに乗り換えてリド島へ向かう予定だった。しかし船頭が「無理だ、荷物は乗せてくれない」と言うので、彼は苛立って「口を出すな、引き返せ」と要求した。船頭は軽く受け流し、そのままリド島へ向かった。
リド島で小舟を降りたグスタフは、船着き場の係員から「あれは無免許の船頭ですよ。警官の顔を見て逃げ出した」と聞かされる。ホテルに到着したグスタフは、部屋へ案内された。作曲家で指揮者のグスタフは心臓が衰弱し、休暇を取るためにリド島へ来たのだった。
大広間へ赴いた彼は、タッジオという美少年に目を奪われた。タッジオは家庭教師や3人の妹たちと一緒にいて、後から母親がやって来た。夕食を取るため食堂へ移動した時も、グスタフはタッジオに視線を向けた。
食堂を出たグスタフは、友人のアルフリートと論争になった時のことを回想する。アルフリートに「君の過ちは人生や現実を束縛と思っていることだ」と指摘されたグスタフは、それを認めた上で「芸術家は闇で獲物を狙うハンターだ。だが、何を狙っているのか。現実は獲物を照らしてくれない。美と純潔を創造するのは精神の働きだ」と語る。
「いや違うね。美は感覚で受け止めるものだ」というアルフリートの主張に、彼は「同意できない。感覚を制御した芸術家だけが、英知と真実と気高さを手に入れられる」と反論した。
アルフリートが「それが何だ?天才は天から降臨する」と言うと、グスタフは「悪魔のような芸術には反対する」と告げる。アルフリートは「邪悪は必要だ。天才の糧だ」と口にすると、彼は「芸術家は手本であるべきだ。曖昧は許されない」と意見を述べる。
「芸術は曖昧だ。特に音楽は、最も曖昧な芸術だ」とアルフリートは告げ、部屋に置いてあるピアノを引いて和音を奏でる。彼は和音の曖昧さを語り、「これが君の音楽だ。認めろ」と声を荒らげた。
グスタフはホテルに宿泊した次の朝、食堂で再びタッジオを見つめた。ビーチへ繰り出した彼はテーブルを用意し、楽譜を書こうとする。しかしタッジオが現れたので、また彼は目で追い掛ける。
タッジオは年下の子供たちが砂の城を作っている場所へ行き、助言を送る。そこへ友人のヤシュウが現れ、タッジオの肩を抱いて「街まで散歩しよう」と誘った。彼がタッジオの耳元で囁いて頬にキスする様子を見たグスタフは、心穏やかではいられなかった。
グスタフが場所を移動して海を眺めていると、タッジオの母親や家庭教師がやって来た。泳いでいたタッジオは母親たちの元へ駆け寄り、ふざけて走り出した。そんな様子を、グスタフはじっと眺めていた。
ホテルに戻った彼がエレベーターに乗ると、大勢の子供たちが入ってきた。その中にはタッジオもいて、グスタフは彼を見つめた。部屋に戻ったグスタフは、アルフリートとの対話を回想する。グスタフはモラルを守って自分の行動も音楽も完璧を求めていたが、アルフリートは官能に屈服するよう説いた。
グスタフはミュンヘンを戻ると決めて、ホテル代を清算した。彼が朝食を済ませて食堂を出ると、タッジオが現れた。グスタフは彼とすれ違った後、「さようなら。短い出会いだったな。幸せに」と呟いた。
グスタフは列車に乗ろうとするが、手違いで荷物がコモ湖へ送られたと駅員から告げられる。腹を立てた彼は、「荷物が届くまでベニスを動かんぞ」と言う。しかしグスタフは、すぐに機嫌を直してリドのホテルへ戻ることにした。
グスタフはホテルへ戻り、ビーチで遊ぶタッジオを眺めた。しかしタッジオが自分を意識したような行動を取ると、グスタフは緊張して息が詰まりそうになってしまう。大広間でピアノを弾くタッジオを眺めていた彼は、支配人を見つけると外国の新聞に出ている伝染病の蔓延について訊く。
支配人は保健局の掲示が出ていることを認めたが、公衆衛生のための予防措置だと説明した。グスタフのタッジオに対する思いは募り、ついには家族で町へ出掛ける彼を尾行した。
グスタフはレストランで家族と食事を取るタッジオを、少し離れた場所から眺めた。両替所を訪ねた彼は、「なぜ町を消毒しているのか」と職員に質問した。すると職員は世界各地でコレラが発生しており、ベニスでも大勢の病死者が出ていることを明かした。
しかし観光都市のベニスは夏が稼ぎ時なので、住民は口をつぐんでいるのだと職員は語る。グスタフは職員から、「すぐに発った方がいい。数日後には交通が遮断されます」と忠告された…。
製作&監督はルキノ・ヴィスコンティー、原作はトーマス・マン、脚本はルキノ・ヴィスコンティー&ニコラ・バダルッコ、製作総指揮はマリオ・ガロ、製作総指揮協力はロバート・ゴードン・エドワーズ、撮影はパスクァリーノ・デ・サンティス、編集はルジェッロ・マストロヤンニ、美術はフェルディナンド・スカルフィオッティー、衣装はピエロ・トージ、音楽はグスタフ・マーラー(『交響曲第3番ニ短調』&『交響曲第5番嬰ハ短調』より)。
主演はダーク・ボガード、共演はビョルン・アンドレセン、シルヴァーナ・マンガーノ、キャロル・アンドレ、ロモロ・ヴァリ、マーク・バーンズ、ノラ・リッチ、マリサ・ベレンソン、レスリー・フレンチ、フランコ・ファブリッツィー、アントニオ・アッピチェラ、セルジオ・ガーファグノリ、シロ・クリストフォレッティー、ルイジ・バッタグリア、ドミニク・ダレル、マーシャ・プレディット他。
―――――――――
トーマス・マンの小説『ヴェニスに死す』を基にした作品。監督は『山猫』『熊座の淡き星影』のルキノ・ヴィスコンティー。脚本は『地獄に堕ちた勇者ども』のルキノ・ヴィスコンティーとニコラ・バダルッコが担当。カンヌ国際映画祭では25周年記念賞、英国アカデミー賞では撮影賞&美術賞&衣装デザイン賞&音響賞を受賞した。
グスタフをダーク・ボガード、タッジオをビョルン・アンドレセン、タッジオの母をシルヴァーナ・マンガーノ、売春婦のエスメラルダをキャロル・アンドレ、支配人をロモロ・ヴァリ、アルフリートをマーク・バーンズ、家庭教師をノラ・リッチ、グスタフの妻をマリサ・ベレンソンが演じている。
映画が始まってからグスタフがホテルへ着くまでの間は、「これは何の意味があるんだろうか」「本当に必要な描写なんだろうか」と思うシーンが幾つか続く。
客船を降りたら奇妙なメイクの男が話し掛けて来るとか、グスタフが船頭の些細な言葉に苛立つとか、船頭が無免許だと知らされるとか、そういうのは何か意味があるんだろうか。ひょっとすると奇妙なメイクの男は、何かの暗喩だったり、グスタフの裏の顔だったりという意味合いなんだろうか。
グスタフがホテルへ着くまでの経緯をバカ丁寧に描いているというだけなら、特に気にすることは無かっただろう。しかし奇妙な男の存在やグスタフと船頭の会話は、明らかに一定の引っ掛かりを抱かせるモノとなっているのだ。
ただ、芸術や文学の素養もセンスも著しく不足している私には、ハッキリした物を何も読み取ることが出来なかった。ヴィスコンティーの作品を本当の意味で堪能するには、まだまだ修業が足りないというか、レベルが違い過ぎるようだ。
映画が始まってから30分ほど経過するとタッジオが登場し、グスタフは彼に目を留める。他にも大勢の人々が大広間にいるが、グスタフにとって彼だけが特別な存在として見えている。後から母親が来ると、そこでもタッジオの時と同様、カメラがアップで捉える。
つまり、グスタフは彼女にも同じように注目したってことだ。しかし、「美人の母親に視線を奪われる」という描写になってもいいところを、まずタッジオなのだ。そして、それ以降はタッジオと母親が同列に扱われることが無く、タッジオだけが特別な存在となっている。
このタッジオを演じるビョルン・アンドレセンは、まさに「美少年」としての問答無用の説得力を持つ容姿だ。タッジオはポーランド人という設定だが、アンドレセンはスウェーデンの出身。
子役として活動していた彼はオーディションで選ばれて映画に出演し、日本でも人気となってコマーシャルにも出演した。来日した際は熱狂的な歓迎を受けたらしいが、それも納得できる。彼を見つけたことが、この映画において、とても大きな意味を持っている。
ものすごくゆったりと話は進み、現在のシーンにおける台詞の量は少ない。贅沢に時間を使い、静かに、そして上品に、グスタフの行動を追い掛ける。
大広間でクラシック演奏を聴いている宿泊客たちの様子を写すとか、ビーチにいる人々の様子を写すとか、ストーリー進行に全く関係が無いようなシーンを何度も挿入し、マッタリとした雰囲気を醸し出す。しっかりと意識を持っていないと、オツムを空っぽにしてボーッとしていたら、ずっとシエスタの中に落ちているかのような感覚になる。
現在のシーンは台詞量が少ないが、回想シーンの内容はグスタフとアルフリートの論争が大半だ。イメージとしても、「静」と「動」の対照的なモノになっている。
会話の中では、「アルフリートがグスタフの考え方を否定し、グスタフが反論するが、それも間違っていると指摘される」という手順が繰り返される。饒舌な会話劇の中で美や芸術に関する意見が交わされ、現在のシーンでは見えにくいグスタフの心情や考え方が間接的な形で表現される。
グスタフはタッジオに心を奪われて夢中になるが、そこにホモセクシャルの感情が働いていることは間違いない。そもそも原作はトーマス・マンの実体験に基づいて執筆されているのだが、バイセクシャルであるヴィスコンティーが映画化したことによって、その意識はより明確になっていると言えるかもしれない。
ただ、それよりもヴィスコンティーが強調したいのは、「美」に対する執着だ。食堂でグスタフがタッジオを見つめた後、挿入される会話の音声によって、そのことが示されている。
グスタフはアルフリートから「芸術家は美を創造できない。美は自然に生まれる。我々の努力を無視し、芸術家の想像を超えて存在する」と言われ、それに反論する。グスタフは芸術家として、美は創造できるし、自分は創造して来たと思っていた。
それをアルフリートに否定され、彼は激しく反発する。それを認めてしまったら、自分の作曲家としての人生を否定することにも繋がるからだ。しかし彼はタッジオという、「努力を無視した美」と遭遇してしまう。
エレベーターでタッジオを見つめたグスタフが部屋に戻ると、アルフリートが「恥じゃなくて恐怖だ。それを感じ取る感性が君には無い。堅苦しいモラルを守り、自分の行動も音楽も完璧を求める。過ちは堕落や汚れだと思っているからだ」と指摘する回想シーンが入る。
その後には、「私は汚れた」「汚れて何が悪い?官能に屈服しろ。芸術家の喜びだよ。健全な人生なんてつまらない」「バランスを保ちたい」「芸術はモラルを超えた物だ。君の芸術の根底には何がある?凡庸だよ」という会話が続く。
グスタフは「芸術家は手本であるべきだ」と考えているが、アルフリートは「堕落すべきだ。汚れるべきだ。そこから芸術が生まれる」と主張する。グスタフはアルフリートに反発するが、回想シーンの中では売春婦を買おうとする様子も描かれている。
結局は性交に及ばず去っているが、本人の中でも「官能に屈辱することで凡庸から脱したい」という思いがあるのだ。モラルを重視する自分が凡庸な人間だということを、グスタフは痛いほど分かっているのだ。
グスタフはタッジオへの溢れ出る思いに耐え切れなくなり、ミュンヘンへ戻ろうとする。どれだけ胸を焦がしても、希望が成就する可能性は無いと本人も分かっているからだ。グスタフは「急用が出来て戻る」と言うが、それは明らかに嘘だ。しかし荷物のトラブルが起きると、最初は憤慨するものの、すぐに「リドのホテルへ戻る」と決めている。
駅員は「荷物は数日でミュンヘンに着く」と説明しているし、本気でミュンヘンに戻りたいのなら、それを待てばいいだけだ。しかし、そのトラブルをグスタフは、「リドに戻る口実」として解釈する。本当はタッジオから離れたくないので、それは嬉しいハプニングなのだ。だから小舟でホテルへ向かう彼の姿がアップで写し出されると、その頬は分かりやすく緩んでいる。
タッジオは「美」だけでなく、今のグスタフが絶対に手に入れることの出来ない「若さ」も持っている。心臓が弱って静養に来たグスタフにとっては、何とも羨ましい存在だ。そして何事においても完璧を求めるグスタフにとって、まさにタッジオは完璧な存在だ。
しかし一方で、タッジオへの思いに溺れることは堕落であり、汚れることでもある。そこにグスタフは恐怖も抱いている。欲法と恐怖の狭間で彼は大いに葛藤するが、結局はタッジオの魅力に屈服する。
終盤、グスタフは白髪を見つけた理容師から、「外見に無関心だからですよ。どんな大物も、見た目にこだわるのは罪ではありません。むしろ問題は、年齢より老け込むことです」と言われる。理容師はグスタフの髪を切り、「これで恋も楽しめますよ」と告げる。
散髪だけだったはずなのに、なぜかグスタフはメイクも施されている。その白塗りの顔は、冒頭シーンで客船を降りた時に出会った男とそっくりだ。だから、そこに込められた深い意味があるんだろうけど、愚かな私には読み取れなかった。
回想シーンでは、楽団の指揮を終えたグスタフがブーイングを浴び、アルフリートから「君は純粋じゃない。純粋とは、痛々しい老いの対局にある。君は年老いた。この世界で老いほど醜い物は無い」と痛烈に攻撃される。それはグスタフの老いに対する不安を示す回想だ。
だから彼は、いかに白塗りメイクが不気味なのかも分からず、いや感覚が麻痺してしまい、その姿でタッジオに会おうとする。だが、幾ら無駄なあがきを見せたところで、彼は確実に老いているのだ。それは奇妙なメイクなどでは隠せない。
終盤、グスタフはタッジオの母親に疫病の蔓延を知らせ、子供たちを連れてベニスから立ち去るよう促す。しかし皮肉なことに、グスタフ自身がコレラに感染してしまう。すっかり衰弱してしまった体で、彼はビーチへフラフラと赴く。そこで彼は、老いとは無縁で、ひたすら純粋な「美」の輝きを放つタッジオの姿を見る。
波打ち際で遊ぶタッジオのまばゆさは、確実に死へ向かっているグスタフに最期の喜びをもたらす。死の間際になってようやく、グスタフはタッジオの「美」に受け入れられた気がしたのかもしれない。
なお、この映画を通じてビョルン・アンドレセンが酷い目に遭ったことが、後になって判明している。ヴィスコンティーはビョルンをオーディションで選んだ後、ゲイバーに連れ回した。ビョルンは本作品の出演で、5000ドルしかギャラを貰えなかった。
撮影後もビョルンはゲイバーに連れ回され、性的玩具にされた。撮影から1年後のカンヌ映画祭で、ヴィスコンティーはビョルンが1年で美貌を失ったと言って記者たちの前で扱き下ろした。ヴィスコンティーのクズっぷりが顕著に現れたエピソードである。
(観賞日:2018年7月4日)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
