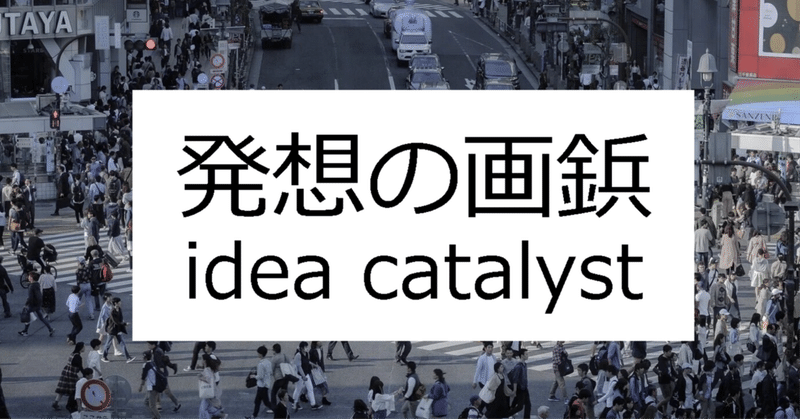
「理想」は他者目線から生まれる
vol.2
普段、一般企業の方々とブレストすると、まずは一旦現実を忘れて「理想」を語るということに抵抗を感じる方が多いと感じます。
特に成果主義が色濃い会社ですと、「実現可能性」や「利益の最大化」を追い求めて過ぎているからです。
それが上手くいっているうちは良いのですが、時に成果を目的にし過ぎてしまいますと、自社のパーパスや社会に提供すべき価値を見失ってしまう場合があります。
だからこそ我々マーケティングコンサルタントの出番なのですが、そういう場合は大抵「顧客調査」から入るパターンが多い。
顧客視点で自社のあるべき姿を顕在化する。
顧客の声は水戸黄門の印籠と同じです。
これをもってイノベーションは加速する。
…一方で…、顧客調査は時に会社によってはハードルが高い場合もあるのです…
それは予算の場合だったり、顧客の声を聞くこと自体に慎重だったり。
すると、コンサルティングが一時足踏みしてしまいます。
そんな状態になった時の解決の糸口になりそうな好事例に最近出会いました。
財務省が仮想の「未来人」に成り切って現代人に提言するという教育開発の話です。
〈JIJI.com / 2023年5月8日〉
実証実験では、会議に集まった10人のメンバーが最初に50年前の1970年の人々に対するダメ出しから始まります。
そうすると、「もっとエコを考えて」「女性就労のため環境整備を」などと、過去への不満が次々と飛び出るわけです。
理想の今日を想像し、もっとこうした取り組みをしていたら、それが叶っていたはずだと考える。
そうした未来から見るという視点を養ってから、今度は50年後の2070年の人々に成り代わって今を見つめると、現代人の判断の積み重ねが将来を形づくることに思い至るわけです。
「少子化に歯止めを」「賃金を上げないと海外移住が進む」「人工知能(AI)に詳しい人材の育成を」
などなど。
未来視点を育んだ人は多くのことが言えるわけです。
ここで大切なのは、一旦他者目線でものを見るということです。
やはり、自分事として捉えると、縮こまってしまう気持ちもある。
他人事なら好き放題言えるわけです。
そうして、本当の理想(あるべき姿)に出会う。
もちろん、未来に向けてそうですし、今現在のことも言えます。
なぜなら、70年代に問題になった環境についても、女性活躍についても、未だ解決していない問題だからです。
一旦、他者目線に移すことで理想を言いやすくし、そしてそれを自分に落とし込んでいく。
そうした方法論として、今回の事例はとても重要だと思いました。
もしも、理想に立ち返りたい時。
一つの参考として、ぜひご活用くださいませ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
