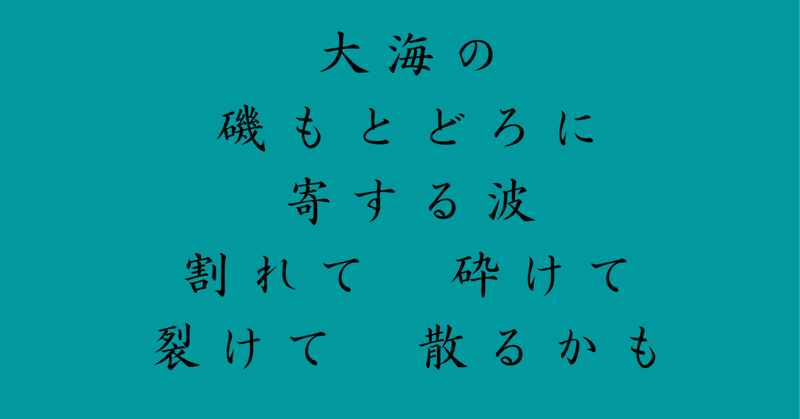
建保の騒乱 その7
五月二日、申の刻。
どんより曇った空からは今にも雨が落ちて来そうだった。湿り気を帯びた風がかすかに流れていく。和田の館の若宮大路に面した東門の前には、一族の者と与力の者共が勢揃いした。
「常盛は五十騎を従え、義時第の南門を襲え。朝盛も五十騎を従え、同じく義時第の西北の門を攻めよ。三郎義秀、四郎義直、五郎義重、六郎義信、七郎秀盛等は、残りの手勢を引き連れて横大路から幕府南門に向かえ。将軍家と義時の間を遮断するのだ。土屋、古郡、渋谷、中山、土肥、岡崎、梶原、大庭、深沢、大方、の与力の方々は、私とともにあって後詰めをお願い申す。者共、押し出しのかけ声じゃ。」
黒革威しの大鎧を着、同じく漆黒の馬に白い小房の鞦を掛け、金覆輪の鞍を置いた上にまたがった義盛の姿は、さすがに見る者を威圧するに十分な貫禄を備えていた。
「えい。えい。」義盛が鬨の声をあげる。
「おう。」義盛の左方に居並ぶ騎上の武者たちが掛け声に応じる。
「えい。えい。」「おう。」
再び義盛が鬨をあげ、今度は右方に居並ぶ者共が応じる。左は「陽」で、右は「陰」であることから、戦場作法では、必ず、左方、右方と順次に鬨をあげるのだ。
鬨の声を三度あげ、東門が開く。常盛、朝盛に率いられた百騎は、怒濤の勢いで飛び出していった。若宮大路を北に少し駆け、鶴岡八幡宮寺の赤橋の前を右折するとすぐが義時の小町の館であった。朝盛率いる五十騎は、赤橋の前を走る横大路を直進し、筋替橋のきわにある北門の前に勢揃いした。
「北条義時殿に物申す。我こそは、和田義盛が嫡孫新兵衛尉朝盛なり。日ごろのそなたの傍若無人の振る舞い、もはや許すべからず。この矢を馳走いたすゆえ、尋常に勝負つかまつるべし。」
朝盛は十二束三伏の鏑矢を弓につがえ、よっぴいてひょうど放った。続けて騎乗の五十騎も一斉に矢を放つ。櫓門を守る北条側からの応戦はほとんどなかった。
斧、鉞、掛矢をもった数人が門を打ち破り、一斉に門内になだれ込む。ほとんど同時に南門を襲った常盛の五十騎も館内に乱入し、義時の姿を追った。が、館内にはほとんど人影もなく、みなむなしく馬を駆け巡らすだけであった。
その頃、幕府南門に向かった三郎義秀等の五十騎が、波多野忠綱率いる軍勢と烈しい矢戦を行っていた。常盛、朝盛等もすぐに駆けつけ、筋替橋を渡ったあたりの政所前で激戦が展開されていった。夾板を切った物を並べ、そのすき間から矢を射、石を投げる敵方を前にして、半刻ほど合戦は続いた。
「やや、あの旗指し物は三浦義村ではないか。」
三郎義秀がうなるように叫ぶ。
「みな、みな、裏切り者の義村が出張って来たぞ。」
「うふぉー。」
獣の雄叫びのような声を発したかと思うと、三郎義秀に率いられた五十騎の軍馬は、黒い塊となって三浦義村の陣に突っ込んでいった。合力無双の三郎義秀は、手に身の丈の三倍もある一丈二尺の金砕棒を持ち、憤怒の形相で先頭を駆ける。彼の駆け抜けた後には、鉄鋲を打った六角形の金砕棒で頭を砕かれた死体がいくつも転がった。
横大路を駆け抜けた三郎義秀は、一町ほど先で反転し、再び義村の陣に突っ込んでいく。今回は、五十騎が輪となって義村の陣の真っ只中に踏みとどまり、容赦なく周囲に矢を射ていった。三郎義秀の乗る馬は、馬上の主人の性格に似てきわめて烈しい気性を持っていた。この馬があたりかまわず雑兵の腕や足を食いちぎっていく。
この攻撃に、三浦勢はたまらず御所方面に逃走を始めた。これを機に、波多野勢も陣を支えきれなくなっていく。和田方は、逃げる兵を馬で踏みつぶしながら追いかける。和田方の馬が通った後には、頭蓋骨を割られ、眼球を飛び出させた死体が累々と横たわっていった。
酉の刻になって、合戦は御所の四門に移されていった。義盛も与力の諸勢を引き連れて参陣していた。御所の内には、義時の嫡男相模修理亮泰時、次郎朝時、三郎義氏等が多くの軍勢を率いて待っていた。和田勢は、御所の四門を囲み、さかんに矢戦をしかけていった。
唐様の南門は、こうした合戦では防御の用をなさない。北条方は、南門を両側に大きく開き、そこに夾板を並べて矢を防ぎ、次々に矢を射て応戦した。朝盛は、征矢を弓につがえては射る。その矢はことごとく夾板の影に隠れている敵のしゃ首をひいっふっと射切っていった。
しばらくして応戦する敵方の矢数が減って来た。
「えい。とお。えい。とお。とお。」
「えい。とお。えい。とお。とお。」
押し出しの鬨の声とともに、漆黒の馬に乗った義盛を先頭に和田方は南門に迫っていく。矢を射て義盛を討ち取ろうとする敵方の武者は、すべて朝盛の射る矢で絶命させられてしまう。威圧的な押し出しによって、和田方の軍勢は、ついに南門を越え、御所内に乱入し始めた。
西門も、東門も、和田方を支えきれなかった。すでに寝殿前の南庭では、あちこちでお互いが四つに組んでの乱戦が行われていた。特に、三郎義秀の活躍はすさまじかった。彼に向かって、名のっては組んでいく御家人たちは、組んで数秒後にはこの世の者ではなくなっていた。
五十嵐小豊次、葛葉三郎盛重、新野左近将堅景直、禮羽蓮乗以下数人が、日頃の強力をたのんで組んではいくのだが、ただ屍をさらすだけだった。もはや誰も三郎義秀を相手に出来る者もなく、遠巻きに馬上の彼を眺めるだけになっていた。
その時だった。
「叔父御、組もうぞ。」
一人の若武者が義秀の前に立ちはだかった。それは、和田二郎義茂の子、高井三郎兵衛重茂だった。重茂は、将軍家に弓引く事に堪えられず、和田一族の中でただ一人、北条方として御所に参じていたのだった。
「うむ。」
一言うなったまま、義秀は弓を捨て、鐙に両足をかけて立ち上がると、両の手を大きく左右に開いたまま、馬を重茂の馬に体当たりさせていった。瞬間、二人は組んだまま落馬し、ごろごろと転がった。そして、ひとつの塊となって、南池にザンブと入っていった。しばらくして、池の面を鮮血が染め、義秀だけが立ち上がった。
その義秀が、自らの鴇毛の馬を見つけて乗ろうとした時、再び彼に挑む者があった。
「北条義時が次男、相模二郎朝時、和田三郎義秀と勝負仕るべし。」
朝時は、櫨の匂威しの鎧を着、星白の兜をかぶり、手には三尺もあろうかという長尺の太刀を抜いていた。憎き義時の子息と知って、義秀の両の眼にあやしい光が宿った。義秀はひらりと鴇毛の馬に跨がると、こちらも太刀を抜き、両の手でしっかりと把を握ると、朝時めがけて馬を駆けさせた。
朝時も、北条家の中で名の聞こえた剛の者。将軍家の勘気を被って駿河の国に謹慎していたものを、義時が今日の合戦のためにわざわざ呼び戻していたのだった。
二人が駆けさせた馬は、南庭中央で激突した。朝時が薙いだ太刀を義秀は臑当で受ける。同時に義秀の振り下ろした太刀が朝時の星白の兜を真っ二つに割る。朝時はもんどり打って落馬した。
主人の危うきに、朝時の家人数人が、熊手を持って義秀を馬から引きずり下ろそうとした。四方から振り下ろされた熊手の爪が、義秀の大鎧に食い込んで彼をがんじがらめにする。だが、義秀の壮力は、熊手を持つ人間ごと宙に飛ばしてしまった。が、その間に、朝時は家人等に運ばれて行き、危うく命だけは取り止めていた。
その頃、朝盛は、将軍家の姿を探し求めて、御所中を馬で駆けていた。御所に乱入してすでに一刻が過ぎようとしており、初夏の日も落ち、次第に暗闇がおとずれようとしていた。朝盛の梁の中の矢も尽きかけ、和田方の諸勢の疲れも極まってきていた。
何者かが放った火が、西侍から燃え広がり、西対屋、渡殿、寝殿と燃え移っていく。火の爆ぜる音に混じって、軍馬のいななき、武者の怒号、傷を負った者の呻き声と、御所中は阿鼻叫喚の様だった。名乗り合いもないまま、そこここで組み合う乱戦になっている。
時が経つにしたがい、足利、武田、島津といった大身の御家人たちが諸勢を引き連れて北条方に加わり、義時の嫡男泰時の指揮の下、激しく和田方に攻撃を加えはじめていた。和田方は、御所の外に退けられては、再び御所に乱入すること数度に及んだ。傷を負わぬ者もなく、さすがに一騎当千の者共とはいえ、進退に窮する姿があちこちで見受けられていた。
「父上、今日の合戦はもはやこれまで。とりあえず前浜まで下がり、横山殿の救援を待って明日の取り合いにしましょうぞ。」
常盛が義盛に近づいて言う。
「うむ。」
「殿は私が承りましょう。」
「わかった。」
常盛、朝盛、義秀、とその手勢二十数騎を殿にして、和田方は退却を始めた。足利義氏、筑後知尚、波多野経朝、潮田実季等の軍勢が、勝ちに乗じてそれを追う。筋替橋まで追ってきた彼らは、そこで激しく矢を浴びた。常盛、義秀等が、ここに踏みとどまって、味方が逃げるのを助けようとしていたのだ。
義秀は橋の中ほどで追ってくる敵勢を睨んでいた。足利義氏が名乗りをあげて義秀に挑んでいく。が、朝盛の放った上差矢が義氏の左目を射貫く。
「ぐわっ。」
悲鳴を発した義氏だったが、さすがに手綱をかいぐり、矢を片手で抜き取り、反転して味方の方に逃げ帰りはじめた。義秀は義氏を追い、その鎧の袖に手をかけた。義氏は馬に鞭を加えて、川を飛び越える。義氏の鎧の袖は、引き千切られ義秀の手に残った。義秀は川を越そうにも、その鴇毛の乗馬はすでに疲れ果てていて、川を越す余力は残されていなかった。
しばらく筋替橋で敵を支えた常盛等は、若宮大路を南に下り、再び、米町口の辺りで敵勢を待った。今度も義秀が先頭になって敵を迎え撃つ。勢い込んで進んできたのが武田信光だった。お互い名乗り合って合戦に及ぼうした時、信光の子、三郎信忠が二人の間に入って義秀に向かって行った。信忠は、義秀の合力無双を知っており、父信光を討たせまいと自ら進んで死地におもむこうとしたのだった。義秀は、信忠の親を思う気持ちに感じ入り、わざと馬首を廻らして前浜の方に去って行った。
和田方を追ってきた諸勢も、それ以上追うことを止め、中の下馬橋、下の下馬橋に旗指し物を打ち立て、陣を構築しはじめた。御所はいよいよ火勢を強めて、夜空を焦がして燃え盛っていた。
実朝は、御所の北にある山の中腹に、頼朝が建てさせた持仏堂の中にいた。出入り口は閉じられ、そのすぐ外には義時が直垂姿のままじっと坐っていた。持仏堂の周りは、北条家の家人たちによって、十重二十重に厳しく固められている。義時の元に戦況を知らせに来る者によって、実朝も合戦の詳細を逐次聞いていた。
実朝にとっては、初めて経験する合戦だった。彼が言葉を発さなくとも、御家人たちは、将軍家の命という大義を押し立てて和田一族と闘っている。ひたすらに和田一族を追いつめ、息をしなくなるまで攻め続けようとしているのだ。
実朝には何もできなかった。朝盛や義盛の爺を救うことは全く不可能だった。それどころか、御家人たちは、朝盛や義盛の首を自分の目の前に運ぶまで、命の取り合いをやめないだろう。ここにこうしてそれを待つしかない自分とはいったい何なのだろう。実朝は、今だかつて経験したことのない激しい感情に捉えられた。
実朝は立ち上がり、持仏堂の扉を開けた。御所が燃えていた。日が昇ればすべてが灰になっているのだろう。実朝の瞳に燃え上がる炎が映っていた。義時が立ち上がり実朝を持仏堂の中に押し返す。その義時の目にも、実朝の両の目に映じる炎が映し出されていた。今、この二人は、確実に時間を共有している。実朝はやっとその事に気づいていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
