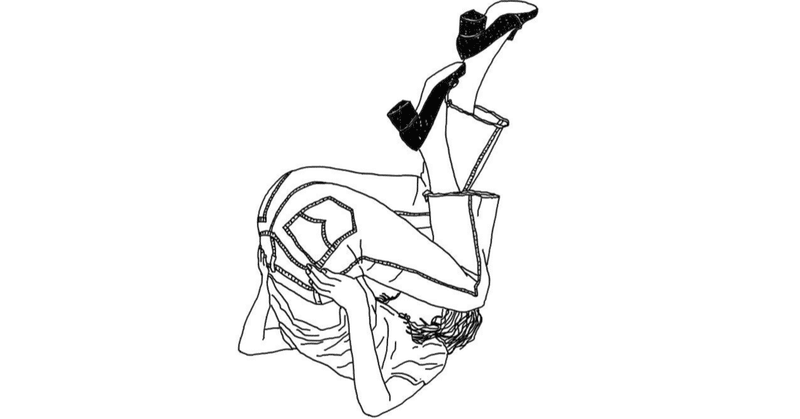
宇佐見りん『くるまの娘』
『推し燃ゆ』は未読だが、複雑な家族の環境を描く物語として惹かれた。母は記憶に問題があって(脳に疾患を抱えていて)、時折自らの心をコントロールできなくなる。父は怒りをうまくコントロールできず、時折暴力的になることがある。そんな家族に距離を取るために、三人兄妹の長兄、末弟は家を出るが、主人公であるかなこ(かんこと物語の中では語られる)は家を出ることができない。
家族に問題があるにもかかわらず、その家族を捨てることができないという物語は山ほどあるだろうし、その結末部分でその家族と残酷に別れる決意をするという物語も多く書かれているだろうが、この『くるまの娘』には90年代の岡崎京子的な要素を感じることもできる。アルコールを体内に含んだ際の母親の暴力性や、父親の時折見せる残虐な言葉のぶつけ方は当然既視感があるが、主人公かなこはその二人を拒絶することなく、受け入れることを選択する。
このどうしようもない状況のまま家の者を置きざりにすることが、自分のこととまったく同列に痛いのだということが、大人には伝わらないのだろうか。かんこにとって大人たちの言うことは、火事場で子どもを手放せと言われているのと同等だった。言われるたび、苦しかった。あのひとたちはわたしの、親であり子どもなのだ、ずっとそばにいるうちにいつからかこんがらがって、ねじれてしまった。まだ、みんな、助けを求めている。相手が大人かどうかは関係がなかった。(123)
問題はかんこがヤングケアラーであるということに収まらない。彼女自身も、精神を病んでいることが明らかになるからだ。学校では次の授業が始まって教室を移動しなければならないのに、同じ席で眠り続ける。そのようなかんこに手を差し伸べてくれる存在はこの物語の中では描かれない。救いを求める長兄や末弟は家を出ており、かんこが日常的に頼れる人物はどこにもいない。
そのような家族が父親の母の葬儀から自宅に戻る場面はリアリズムから離脱をしたように描かれる。狭い車内で末弟を含めての口論の後、かんこはいつの間にか眠りに落ちる。気づくと、運転していたはずの父親ではなく、母親がハンドルを握っている。母親が一家心中を試みているようだが、唐突に描かれるその場面はかんこや読者にとってはそれがリアリズムなのか、あるいはかんこの夢なのか判断がつかない(このあたりでかんこは何度も微睡に落ちるため)。父親も弟も母の選択を積極的に止めようとはしない。
母は冷静さを保つふりをするときにつかう声色を出した。舌っ足らずに、繰り返した。鼻息荒く、噛みしめた歯の隙から「しんじゅうする」と濁った声を出した。…… いきなり、崖なのか、山の中なのか、海のちかくなのかわからない場所に放り出されたかんこは、混乱した。うねり、たどり着いた先に、何があるのかわからなかった。弟も父も起きている。「何やってんだよ」父の声が揺れる。父は足を踏んばりながら、倒した後部席から助手席に移る。
「しんじゅうする。こんなんなったら、もう、それしかない」
叫びは、喉ばかりでなく、見ひらかれた目から、両耳から、髪の毛先から、ほとばしった。
この一家心中は未遂に終わるが、この後かんこは両親とは同じ屋根の下に暮らすことができなくなる。距離を取ることで彼女の精神はゆっくりと回復に向かうのだが、結末部分でも不穏な空気が続く。父親がかんこの暮らす車に乗り込んできて、買い物に行くと言う。その誘いにかんこは乗るが、父が運転する車はどこに向かうのかわからない。父親は自分の母との距離感に苦しんできたのだが、決定的な断絶を認識したエピソードがかんこに話されるとき、かんこがイメージするのはやはり心中である。絶望から逃れることができるのは死であるというイメージだが、その解決策に彼女/父/母が安易に乗らずに苦しみながら生きているという物語である。
かんこは、霞む視界のなかに街を見た。誰かが突っ込まなかった交差点がある。誰かが飛び降りようとしたビルがあり、飛び込めなかった線路がある。誰かが首を吊ろうと縄をかけた杉の木があり、一家心中を起こしかけた車がある。街は張り詰めていた。何かが、起こるか起こらないかの違いで、その気配は常に迫っているのに街はいやに平和に見える。むしろその突発的に起こる事件の気配まで含めて、平和そのものだった。肌が淡い陽光にひりつき、痛んだ。隣に、ここまで生きていた父がいる。生きているということは、死ななかった結果でしかない。みな、昨日の地獄を忘れて、今日の地獄を生きた。あの交差点、あの線路脇、あの窓の向こうで偶々生を選択し続け、死を拒み続けた積み重ねだけが父を生かしてきた。それだけだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
