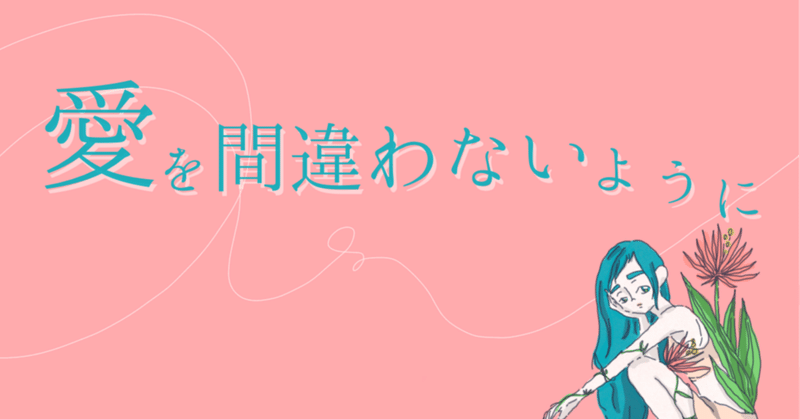
5/19文学フリマ東京38 『愛を間違わないように』アンソロジーサンプル
みなさん、こんにちは。
アンソロジー『愛を間違わないように』主催の常世田美穂です。
文学フリマ東京まであと20日。
ブースが決まりました。
今回はそのご報告と、各作品の冒頭サンプルをご紹介したいと思います。
少しでも気になった方は、スキしてくださるとうれしいです。
イベント後、通販も予定しております。
どうぞよろしくお願いします。
場所:東京流通センター
日時:2024年5月19日(日)12:00〜17:00
出店名:ねぇ、ライナス
ブース:D-42(第一展示場)
新刊はアンソロジー『愛を間違わないように』
表題のテーマを実力派の六人が紡ぎます。
文庫サイズ/220P/R-18/1000円
収録作サンプル
海月 Immortal Jellyfish/静 霧一
私はクラゲの夢を見た。
光が差す海の中で、ただ果てもなく漂い続ける、そんな夢であった。
途中、小魚の群れが私の横を通り、その勢いで起きた波に揺られ、私はどこかへと流されていく。
目的地などない。ただ流され、生きている。
波に身を委ねて、美しい水面を眺め続けるのも悪くない。そんな心地の良い夢の中で、パタパタという足音が聞こえた。
誰かが近づいてくる。不思議とその足音に嫌な感じはしなかった。次第に私の意識は海面へと引き上げられ、白い光の中へと吸い込まれていく。
ふと目が覚めると、目の前にはいくつもタスクが書かれた付箋が目に入った。ディスプレイに投影された作りかけのサイトデザインが淡い光を放っている。モニターの右端を見ると、時刻は23時35分と表示されていた。終電まであと15分。私は終電に乗り遅れるとまずいと焦り、ノートパソコンを急いでバッグにしまい、そのまま逃げるようにして社内の施錠をした。
終電の電車に揺られながら窓の外を見る。すでに住宅街は眠っており、夜の暗さが一層増したせいか、電車の窓ガラスに私の顔が鮮明に反射している。眼の下にはうっすらと影ができ、頬には赤みがなく、気力のない表情をしていた。
スマホを見ると時刻は11月25日の0時を表示している。
電車に揺られながら、私は記念すべき30歳を迎えた。
誰からも通知がない、無音の30歳であった。
硝子窓/明星
駅前のカフェは人通りも多く賑やかで、こんな暗い気持ちでここにいることを早くも後悔した。
今日、彼女と会う。
彼女と会える。
でも怖い。
怖いという思いが先行してしまって、手どころか今では足まで震えてきている。
嬉しいはずなのに、胸の痛みは最大で、引き裂かれるように苦しい。
でもこの痛みは、自分が作り上げたもの そう、全て自分のせいであった。それは分かっているのに、往生際も悪く彼女に会いに来てしまった。それが私の罪だろう。
カフェの中で待ち合わせに来た彼女を外から確認する。彼女はどんな髪だろう。どんな瞳だろう。私が好きになった彼女は、一体どんな 。いや、私には好きになる権利なんてないんだ。それでも止まらなかったこの恋は、私の人生最大の罪であるのかもしれない。
「ごめんなさい」
呟いて、頬に当たるほんの少しの雨粒を感じる。
大都会東京の空は、曇天となっていた。
「別れよう」
ホテルの一室で彼にそう告げた。
「は?」
彼氏の大地は冗談でしょ、と呟く。冗談なんかじゃない、散々悩んで、それでも私が出した答えはこれでしか無かった。
「もう、いいんじゃないかなって」
「おい環ってばそんないい加減な気持ちで付き合ってたの?なんか怒らせた?俺」
怒らせた訳じゃない。あなたが嫌いなわけでもない。
それでも、今一緒にいるのは、なんとなく自分が違う気がするだけだ。
「そういう訳じゃなくて」
「少しマンネリしたかな?俺たち」
ベッドの上で加熱式たばこをふかす彼は、天井を見て、うんうん、と頷いた。
この空虚で不穏な気持ち。どう表現したらいいのだろう。悩みつつ、大地に分かってもらう言葉を必死で探している。でも、言葉は出てこなかった。
「……居心地が悪い、いや……無気力……いや、なんだろう。上手く伝えられない」
「ああー。うん。そっか。そしたらさ」
大地はたばこを置いて言う。
「少し、距離を置こうか、しばらく会わない、メールもしない」
「ああ」
違うんだけどな、そう思いながら私は何故か頷いている。違う。あなたじゃない。それも、分かっているのに。
心の中でそう思いながら、そうだね、と無気力に返していた。
蒔き戻り/夜空知世
黄昏時の教室で鹿山奏太(かやまかなた)は真っ正面の相手を睨んだ。
「だから、一花(いちか)とは付き合わないで。わたくしと付き合いなさい」
「はぁ? なんで俺が有城(ありしろ)と付き合わないといけないんだよ。断ると言ったら?」
「わたくしがこの学園の理事長の娘って分かっているわよね。そして一花が特待生としてこの学園に通っていることも」
「だから、何なんだよ」
苛ついた声で再び睨む。
有城ひめかは、腰まで伸びた茶色に染めた髪を手でくるくるといじりながら奏太を見つめる。整った顔をしているのだが、内面から滲み出るのか、いじわるそうな顔つきに見えた。薄暗い室内にいるせいで余計にそれがきわだってくる。
「お父様に頼んで、一花を特待生から下ろすことも出来るのよ。いいのそれでも?」
「くっ……最低だな、有城」
「知っているのよ、鹿山くんが一花を好きなこと。そして一花もあなたに恋をしている。わたくしは一花だけ幸せそうにしているのって何かムカつくのよ。だから絶対恋人にはさせないんだから」
「どこまで性格が悪いんだ」
「だから一花にこのまま学園に通ってほしければ、わたくしと付き合いなさいな。そうすれば、これまで通り一花は特待生としていられるようにするわ」
「俺とお前が付き合えば一花の特待生は卒業まで続くんだろうな? 進路の邪魔もしないと約束しろ」
「約束するわ。じゃあ、わたくしの彼氏になってくれるのね」
「表面上だけだ。お前なんか絶対好きになるものか。学園を卒業するまでだ」
「了解。だけど、卒業後、半年の間は芝居は続けてもらうわ。契約完了ね」
両手を握り締める奏太の横を通り過ぎ、はしゃぎながら楽しそうにひめかは帰って行った。
その試合のヒーローは/小国風也
二球目まんなか高めのボールで、試合の主導権が相手チームに渡った。
バッターはこのあまく入った一球を見逃さず、打球は東京ドームのスタンドまで飛んだ。
『見事に打ちました、ホームランです』
一回、しかも先頭打者から試合が動いたのに、大学野球の実況はプロとくらべてあっさりしている。それだけこの試合は一方的になることが予想されていたのかもしれない。
美咲はコップのお茶をのんだ。
十畳にローテーブルとトールグラス、寝転べる広さのソファ、二十四インチのテレビにDVDプレイヤー、テレビ台のとなりには読まずに積まれた新聞がたまっている。
テレビには大学野球選手権大会の一回戦のようすが映し出されていた。巨人戦のようなプロとくらべればしずかだが、時折汗を流しながら声を張り上げる応援団や大きく体を使ってポンポンを動かすチアリーディングがアップにされ、応援の熱量が伝わってきた。
美咲は東京ドームのようすを頭にうかべた。近づくにつれて胸を震わせるように響く太鼓の音、風は通らないが居心地の悪くない空気、グラウンドは照明があたってキラキラと輝いている。ふだん応援しに行く市営の球場とはまったく異なるつくり。それぞれの良さがあるが、プレーをする選手を考えればドーム球場はこの上ない環境をしている。
そんな東京ドームで拓也がプレーしていた。
八つの大学が所属する星雪北海道学院連合のなかでリーグ戦を制し、雪峰北海大学初の選手権大会出場を決め、この日初めて全国大会の地を踏んだ。
雪峰大学が全国レベルかと問われると、まったくそんなことはない。リーグ戦も辛勝の連続で、観客も落ちついて見ていられない展開ばかり。エースの畑中はプロからも注目されていると噂されているものの、そこそこのコントロールの良さのみが売りで、他はどれも並ほどであるため、さほど優れたピッチャーとは感じない。チーム全体を見ても、安定した守備力はあるものの、攻撃もつながるときとつながらないときの波がはげしい。
ジェフ/千本松由季
暗いのに急な階段で、僕はもう少しで首の骨を折るところだった。ダンジョンを手探りで進む。僕はなにを探しているのだろう。テーブルに置いてあった、白く光る骸骨の手に腕を掴まれた。僕は飛び上がる。
「ほんとに俺のこと全然知らないんだな」
知らないといけないんですか。僕は済まなそうな顔をしてみせた。彼はそんなに長くもない自分の髪を何度も掻き上げる。芸能人みたいに。って、芸能人か。
「ですから僕は、クラシックが専門なので」
彼は平然とスコッチの氷を長い指で掻き回す。それを何度もやる。氷がぶつかる音が、うるさい音楽に消える。これでは話ができない。海に浮いた氷山は、海面に見えてる部分より、海水に沈んでる部分の方が、ずっと大きい。
それはアーネスト・ヘミングウェイの「氷山理論」によって証明されている。ほら、また彼は、とけていく氷を掻き回して、冷たくなった指を口に入れる。小説家は、氷山の浮いた部分だけ書けばいい、そうしたら読者は、氷山の全体を理解してくれる。要するに余計なことを書くなと、そういうことだろうけど、確かではない。
身体中の骨が透けて見える。彼の細くて、薄白い骸骨。博物館に吊り下げられた彼の骸骨は、側を通る度に微かに揺れる。こんなに頑丈なガラスケースに入っているのに。博物館に積もった埃が吹き上がる。それで、その骸骨は、僕に向かって笑う。骸骨を下げるワイヤーは、一見そんなことをするには頼りなく見える。
旅するアメトリン/常世田美穂
アイオライトはこうかいのみちしるべ。長年ユナは航海を後悔だと思い込んでいた。小学四年生のとき、友だちのチカにみせてもらった小説にこう記されていたのだ。タイトルは『アイオライトの果て』。チカが書いた小説である。ノートに書き記された物語をユナは夢中になって読んだ。一言一句忘れずにおぼえるくらいに。今では朧げになってしまったが、冒頭だけは声に出していえる自信がある。プロローグはみつ石ひゅうがくんの作文からはじまる。
ぼくはねむっているとき、いつでもうちゅうにいけます。いちばんはしっこのぎんがのはてにもいけます。こうぶつみたいにきらきらしているところで、ぼくはすきです。でも、ママはあぶないからいっちゃだめといいます。こうぶつは、ほうせきになるまえのきれいないしで、いしじゃないのもあります。パパとママはいっしょにけんきゅうをしています。パパはぜんもうなので、ぼくがみえません。でも、ぜったいにぼくがわかり、ぼくはうれしいです。このまえ、アイオライトはこうかいのみちしるべだっておしえてもらいました。ともだちはぼくのことをうちゅうじんといいます。うちゅうにいけるからでなく、みんなとかたちがちがうからです。ぼくはとくべつだっていいます。でもぼくはみんなのかたちはおなじだけどとくべつとおもいます。ぼくのいたほしでは(ちきゅうにくるまえ)みんなかたちがちがってわかりやすかったので、みんながとくべつとしっています。おとこどおしもけっこんできてこどももうまれます。ちきゅうみたいにかんじょうはあまりないけれどみんな、しやわせです。
チカは天才だった。男の子たちから絶大な人気を誇るほどかわいらしい容姿をしていたが、アプローチされるとその賢さでねじ伏せてしまうような女の子だった。チカのとなりには三石彪駕くんがいた。小説のなかの男の子と同じ名前。モデルは彼なのだ。ふたりはいつも一緒だった。その男の子だけがあたまの回転のはやいチカの話についていけた。天才だったのは三石彪駕くんだったのかもしれないとユナは思っている。
ユナはチカに憧れていた。髪型も服装もまねをして双子みたいだねといわれたことがある。ユナはうれしかった。ユナはチカのことがだいすきだった。容姿、言動、思想そのすべてに感銘を受けた。ついにはチカをまねて小説を書きはじめた。もちろん、主人公は三石彪駕くんだ。できた小説をクラスメイトたちにみせたとき、ユナは大バッシングをくらった。チカちゃんのパクリだ。まねっこだ。といわれたのである。ユナに不満を持っていた者は総じてユナの髪型や服装にもケチをつけ出した。
チカ本人はどんな反応をしていただろう。ユナにはそれだけが記憶にない。三石彪駕くんに味方をしてもらったことだけはおぼえている。
「チカかわいいもんな。まねしたくなるよな。大丈夫だよ、大丈夫」
いただいたサポートは執筆時のコーヒー等ドリンクにさせていただきます♡
