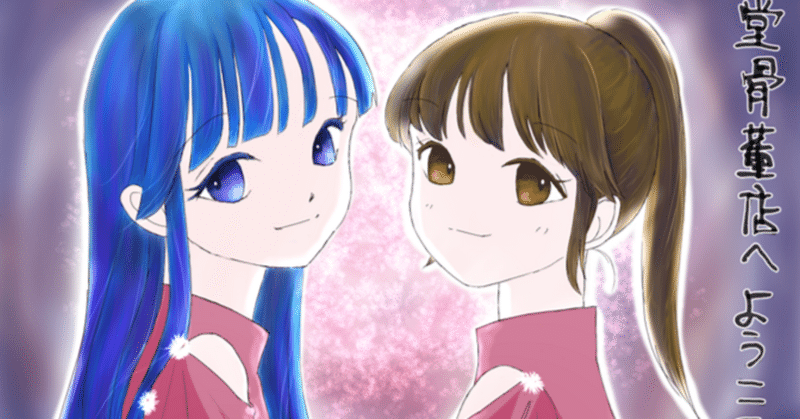
樹堂骨董店へようこそ29
那胡が気が付いた時にはふたりは再びもののけ道の中にいた。
もやもやした白い煙のような壁の、たびたび分岐している通路だった。電灯なんてどこにもないのにふんわりと明るい不思議な場所だった。
「着くぞ」
流が言うとぶわっと強い風が那胡の顔に吹き付けてきた。思わず目を閉じたが、すぐに収まり目をこわごわ開けると花をつけた桜の木がたくさんあった。
しかも花が満開だ。そらは薄明るいが月も太陽もどこにもなかった。薄紅色の海に飲み込まれたように、周囲を見回してもほかの景色がみえなかった。ぬるい風の吹く空間に空と桜しかない。
「ここは…」
その時、那胡の脳裏にある映像が流れた。満開の桜の森で泣いている子供。ママを探して泥だらけで歩いている。月も太陽もなくて、どこを歩いているのかもわからず、必死で歩いている。
「あ…」
映像は那胡の状況におかまいなしにどんどん流れる。
足をすべらせて大きな穴に落ちて力尽きた子供は眠り込んだ。しばらくすると「那胡」と声をかけられた。スーツを着た男の人。手には鎖のついた懐中時計を握っている。
「…流だ」
那胡は急速に七歳の時に失った記憶がよみがえる。
流は握っていた那胡の手をすっとはなした。
「…どうした…?…何か思い出したのか?」
なぜか流には那胡の頭の中で何が起きているのかわかるようだった。
「あの時、森の出口まで連れてってくれたのは流だったんだ…」
「…子供の頃の記憶がもどったのか…」
「うん」
流はそれについて何も言わなかったが少し微笑んだように感じた。
「向こうにみんながいる」
どこからか生温い風が吹いてくる。そのたびに桜が舞うが、いくら舞っても花が樹上から無くなることはなかった。
何か音が聴こえてくる。笛、小さな太鼓、チキチキと聞こえる金属の楽器…演奏しているようだ。聴いたことのない音楽だった。
そこには着物を着た人々がいた。桃の節句のお雛さまに飾られている、お姫様やお内裏様みたいな着物を皆着ていた。演奏したり、毬をけったり何かを食べている者もいる。那胡には宴会に見えた。
「みなさん、用意が出来ました。持ち場へ出発します」
流が大きな声で言うと
「おう…」
「あらもう?」
「ひゃひゃひゃひゃ」
「歌え歌え…」
「おや、那胡也さんかい?久しぶりだねぇ」
(ナコヤ?)
那胡がその言葉に反応した。なんとなくどこかで聞いたことがあるような気がしたのだ。
皆バラバラなことを言いながら一斉に列をつくって歩きだした。途端にどこからか強い風が巻き起こる。
「うわっ」
那胡は顔を手で隠した。息するのも苦しいくらいの風だ。ふいに体がふわりと持ち上がった。
「きゃあああっ」
びっくりして顔から手を離すともう桜の森の上空にいた。すぐ横に流がいて腕を掴まれていた。前方にはどんちゃかどんちゃか音楽を奏でながらさきほどの着物の人たちがどこかへむかって飛んでゆくのが見える。自分も飛んでるし、皆も飛んでる…という信じられない状況だったが那胡は不思議と受け入れられていた。桜の森もなにもかも夢みたいな世界だから、夢かもしれない…そんな風に感じた。
流は前方を指さしながら
「七年祭りの次の年は土地守たちが交替するんだ」
「土地守?」
「土地を支えるモノたちさ。彼らがいなければ桜杜は存在しない。大晦日は交代の日だ」
そう教えてくれた。
ふいに那胡はすぐ下の桜の森の中に見知った人影を見つけた。
「え…パパ?こんなとこでなにしてんの…?」
思わず声にする那胡に
「沙那さんがきっと帰してくれないんだろう…」
とさりげなく流が言った。
沙那とは那胡とともに行方不明になり、いまだ見つからない母の名前だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
