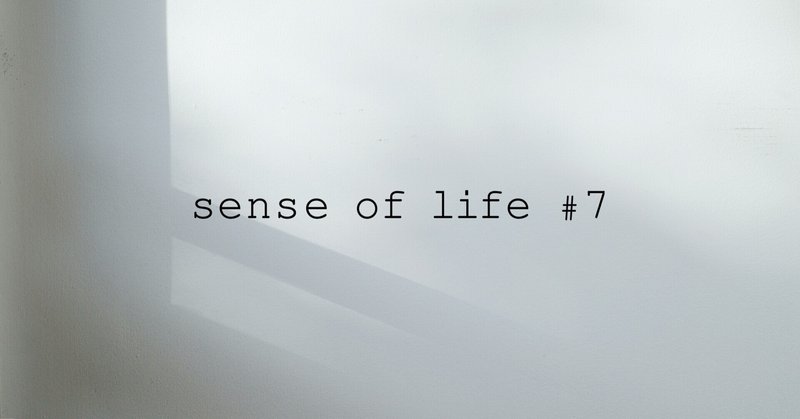
7. 感覚過敏
いったい何の修行だろうか。
何らかの感覚過敏を持っているなら、そう思ったことがあるに違いない。
視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚などの知覚が、通常よりも鋭い「感覚過敏」。この症状に悩まされている発達障害人、もしくは発達障害傾向の人は多い。
感覚過敏は、その程度や、どの感覚が突出して敏感なのかには個人差があり、他人に理解されにくい症状ともいえる。
そもそも、自分の感覚が平均と比べてどれほどなのか知ることは不可能である。感覚は、他人とシェアしようもないし比べようがない。それぞれ初期設定のレベルがバラバラで、かつ、全員それが「常態」なのである。
だから、私も自分の感覚が一般よりも鋭いと思ったことはなかった。
ただ不思議だった。突き刺すようなLED照明や液晶ビジョンの光が、換気扇の音や人の話し声が、洗剤や化粧の匂いが、不自然な調味料の味が、化学繊維の肌触りが、顔に当たって邪魔なメガネが、みんなよく平気なものだなー、と。
発達障害を知ってようやく合点。これって感覚過敏なのか!
感覚過敏は、発達障害人が家にこもりがちになる一因にもなっている。
都会はとくに五感への刺激に溢れて過酷で、人だかりの多い街中に行くと異常にぐったりするので、自分の部屋は、感覚過敏持ちの発達障害人にとって、最大の安らぎの場なのである。
と、言いたいところだが、私の場合はそうもいかないところが辛い。
現在、私の悩みの種は、家にいるのに寛げないことである。思わず冒頭の言葉が浮かぶのも主に家にいるときなのだ。
私の住居兼アトリエは、壁が薄くて機密性がほとんどない築70年の木造平屋である。建物がある場所は、幅は狭いが交通量は少なくない道路に面していて、車やバイクが薄い壁越しに至近距離で通過するので、かなりうるさい。通行人の会話も筒抜けだし、窓を開けていなくても排気ガスの匂い漂ってくる。
さらに、道路を挟んで路面電車の線路が通っているのだが、家の目と鼻の先に踏切がある。日中は一時間に10回踏切がカンカンと鳴り、ゴトゴトと電車が通る度に、音だけでなく家は振動に見舞われる。
原付バイクや作業車がひっきりなしに行き交う夕方が最もキツいが、行楽地に近いことから、爆音でエンジンをふかす大型バイクが頻繁に通る休日も休まることがない。それから、飛行機やヘリコプターの襲来、割と静かな日に限ってどこからともなく草刈機の轟音が……と、人間の活動音はキリがないのだが、それに加えて自然の音もハードである。風が吹けば建具がガタつき、トタン屋根に落ちる雨は太鼓を打つような音をたてる、といった具合。
音と振動を受け続けて、1日が終わる頃には疲れ切っていることもしばしば。
あーもう気が狂いそう、いったい何の修行なのか? と何度思ったことか。
そりゃもちろん引っ越せばいいわけだけど、いろいろと事情がある。よりによって、こんな所に仕事場兼住居があるのにも事情があるのだが、それは仕方ないとして、なぜ、こんなに苦しめられるのか。そもそも感覚過敏とは何なのか。
人が何かを感じる仕組みは、感覚器官というセンサーで情報を受信 → 神経回路を通して脳に伝え → 脳がその情報を解析する、という段階を経る。
感覚過敏はこの過程のどこかで、情報が必要以上に増幅されてしまう状態である。
発達障害とは「少数派の脳」であると前にも書いた。
発達障害の症状は、病気や欠陥というわけではなく、一定の有用性が認められていたからこそ存続し得た遺伝特性だということを前提とすると、感覚過敏も、人類の生存に必要不可欠な能力だった、という見方ができるのではないだろうか。
原始の人類にとって、敏感な感覚は、外敵や気候の変化や飢餓に対応して生き延びる上では必須のものだったのだ。
森の中で、獲物の気配や植物のわずかな匂いを嗅ぎ分けること。風景や道を視覚的に記憶すること。湿度や風の変化を感じ取ること。これらは、食糧を得るために必要な能力で、農作物の栽培や、災害回避にも欠かせない。集団の中で、敏感な感覚を持った少数派は、危機をいち早く察知し、損失を避けるための判断材料を提供する役割を担っていたといえる。対して、多数派(定型発達)の役割は、少数派から得た情報を活かして、協調して効率よく生産活動を行うこと。
これは、どちらが優れているという話ではなく、いずれも必要な役割の分担でしかない。能力を特化した個体が集団となって補い合うこと、つまり、社会を形成することで人間は発展してきたのである。
しかし、テクノロジーが驚異的に発達したおかげで、生存を脅かされる心配がなくなり、産業構造が変化するにつれ、有用性を失った少数派が追いやられていったのが近代といえる。
では、快適安全の行き渡った現代においては、感覚過敏はストレスでしかないのかといえば、そうとも言えない。
現代における感覚過敏の有用性は、文化的な洗練をもたらす、ということがある。
過敏だからこそ、わかる違い、発見できる豊かさがあるからだ。
有難いことに、現代の先進国に生きる限り「生存」を命題とする必要はなくなったわけだが、少数派と多数派の役割の本質は変わらないんじゃないだろうか。不要になったから多数派に迎合するのではなく、「よりよく生きる」という、その先のフェーズにおける役割分担の仕組みが出来ればいいのだ。
というか、もはや多数派が担ってきたことの多くも、技術によって解決されようとしている昨今、過敏さはむしろ脚光を浴び、新しい創造に繋がってゆくものに違いない。そう考えてみると、感覚過敏は悪いばかりじゃない。
何だか話が壮大になったが、現実の「家で寛げない問題」に戻ろう。
最近、以前住んでいた東京の街を訪れる機会があって、気がついたことがある。
そこは山の手の閑静な住宅街とされているエリアなのだが、久しぶりに来てみると、予想外にうるさく感じたのだ。といっても、何の音が気になるわけでもない。ひとつひとつの音が際立っているのではなく、遠くの雑踏が微かなノイズとなって漂っている感じである。住んでいる時にはあまり気にならなかったが、閑静な住宅街といえども、巨大な繁華街が地続きになっている東京は飛び交う音の総量が桁違いに多く、人工音の密度が濃い。離れてみるとそれがよくわかるのだった。
変わって今の家がある環境は、緑が多く海に近い所だ。起伏のある土地で、家が密集していることもない。人の活動が少ない早朝や夜はとても静かだ。日中だって、往来の合間に一瞬の静寂が訪れることもある。
道路と反対の家の南側には、まあまあの広さの庭がある。静けさの中で、庭の草木や空の雲の動きを見ているとき、私は至福を感じる。
建物の構造や素材上、外の動きが直に伝わってくるので、温度、雨音、風、鳥の声などの微妙に変化し続ける自然を、常に感じながら過ごしてもいる。
鉄筋コンクリートの箱の中に住んでいた時は、上階の足音や微かに漏れる隣室のテレビの音に神経質に反応していたのだが、内と外との隔たりを全く感じさせない機密性のないこの家では、鳥の声や近隣の生活音が、時としてアンビエント音楽のように聞こえることがある。
他の者と空間を共有する心地よさ。静まりかえった夜に、微かな波音や虫の声、露に湿った草の匂いを感じる喜び。私はそれを確かに感じる。
不快と快は紙一重だ。
また、何かに熱中している時は、稀に音も振動も気にならなくなることもある。
精神科医が言うには、感覚過敏を軽減するには、ストレスを溜めずリラックスした状態でいること、なるべく「不快」に注意を向けないこと、「不快」を感じている自分を客観的に見て受け流すことを意識すべし、とのこと。
言うほど簡単ではないが、注意の向け方で、感覚の感じ方が変わる余地が多少はあるということは事実らしい。
そう、必要以上の情報を捕捉してしまうセンサーを持っていたところで、不要なものをカットするフィルターがうまく機能すれば問題ないのだ。
いっそのこと、前頭葉の注意制御機能を鍛えるワークと思って、家での時間を過ごしてみるのはどうだろう。
「快」に注意を向け、「不快」情報をカットすることを、故意に、自在にコントロールできるようになったとしたら、こんなに素晴らしいことはない。
ひょっとして、これはやはり修行なのかもしれない。
鍛錬を続けてゆけば、いずれ武術の達人や仙人のように、鋭敏な感覚を持ちながらも、どんな物音にも動じることのない境地に到達することができるだろうか?
そんな妄想をしつつ、今日も私は、夕方の交通ラッシュを前にいそいそと喫茶店に避難する。ノイキャン機能付ヘッドフォンを小脇にかかえて、いつもの席の周辺に香水の匂いが漂ってこないことを願いながら。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
