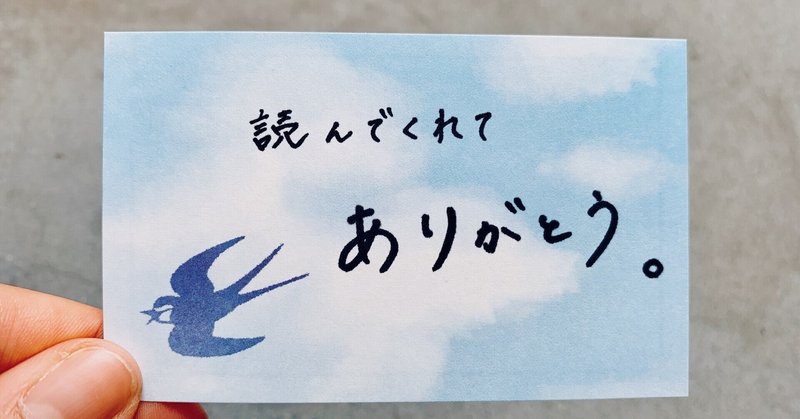
「遺贈寄付」したい人のための注意点
(*この原稿は、毎日新聞WEBでの筆者連載「百年人生を生きる」2019年3月21日の記事です)
前回、遺贈寄付の実例を紹介し、「思い」が次世代に引き継がれることで生まれる「寄付者よし、受け手よし、社会よし」の「三方よし」のお金の流れについて述べた。今回は、なぜ遺贈寄付への関心が高まっているのか、実際に寄付しようとする際にどんな点に注意したらよいのか紹介する。
遺贈寄付への関心の高まりは、寄付を受ける側の実例をみるとよく分かる。例えば、NGO「国境なき医師団日本」の場合、2012年に国内で受けた遺贈寄付(遺贈と相続財産からの寄付)は1億3990万円だったが、16年には8億3690万円に急増。18年には件数は101件になり、寄付額も過去最高になった。遺贈寄付に関するパンフレットの請求件数も12年の95件から年々増え、18年には2600件に達した。
少子高齢化や生涯未婚率の上昇で注目高まる
遺贈寄付が注目される背景には、いくつかの要因がある。一つは、遺贈寄付の土壌ともいえる、寄付そのものへの関心が高まっていることだ。寄付文化を広める活動をしている認定NPO法人「日本ファンドレイジング協会」がまとめた「寄付白書2017」によると、16年の1年間に日本人が個人でした寄付の推計総額は7756億円。寄付をしたことがある人は約4571万人で、率にして45.4%に上った。年齢が上がるにつれて割合は高くなり、60代は52%、70代は57.8%の人が寄付をしていた。東日本大震災を機に寄付市場は確実に広がっているのは下図からもみてとれる。

(出典・「寄付白書2017」)
日本財団「遺贈に関する意識調査」(17年3月)では、家族がいるかいないかで遺贈に関する意識に差があることも分かった。「子ども・配偶者なし」の場合、遺贈を意識する人が42.6%と半数近くいる一方、子どもがいる場合は20%だった。
遺贈が注目されてきた背景には、少子高齢化や生涯未婚率の上昇で、そもそも相続人がいない人が増えている事情がある。相続人が誰もいない場合、最終的に財産は国庫に納められる。その額は17年度約525億円と、12年度(約374億円)の1.4倍となっている。
また、13年に相続税法が改正されたことも影響している。15年1月1日以降の相続から基礎控除額が減額され、相続税を納めなければならない人が大幅に増えたことも見逃せない。法人に遺贈した場合は、基礎控除と同じように原則として相続税を計算する際の対象額から除外されることで、相続税が減額される可能性もあるのだ。「法定相続で課税されるぐらいなら、自分の意思で使い道を決めて社会のお役に立ちたい」と考える人も増えたのではないだろうか。

遺贈寄付の際に注意すべき点は
では、実際に遺言を作成して遺贈しようと考えたとき、どんなことに注意したらよいのか。
まずは、どこに寄付したいかについて考えることがスタートだ。最初から支援したい分野や団体がはっきりしている人は少ない。「なんとなく寄付したい」という人がほとんどだろう。
まず、遺贈先を個別に選びたいと思っているのか、遺贈先の選定は信頼できる団体や人に任せたいと思っているのか――。個別に選びたいなら、まずは「活動分野」を選ぶ。たとえば、教育やまちづくり、国際協力、災害支援、環境保全などの選択肢がある。次に「活動地域」を海外、日本全国、都道府県、市町村から選んでみる。
その後は、支援する団体の規模を選ぶ。誰もが知る有名な団体なのか、小さい団体なのか。さらに、寄付金控除の適用が受けられる公益法人や認定NPO法人がいいのか。段階を踏んで整理していくと、だんだんと絞れてくる。
また、遺贈先の選定まで任せたいのなら、NPOを支援する中間支援組織やコミュニティー財団が選択肢となる。ある程度まとまった財産もあるし、いっそ自分で財団法人をつくって思うような支援の仕組みを、という場合は公益信託の活用を考えてみてもよいだろう。
「国境なき医師団日本」が17年に実施した調査で、「遺贈をするとしたらどのような分野に役立ててほしいか」を尋ねると、「人道支援」が最も多く49.2%で、次いで「災復旧支援」(35.1%)、「教育・子育て・少子化対策に」(26.8%)と続く。
過去にもらった奨学金への恩返し
取材した中には、こんな例があった。貧しい家庭に育ち、高校進学は無理と思っていた男性が、奨学金で大学院まで進んだ。その後、教員として働き、定年退職。結婚したものの子どもはおらず、妻に先立たれ、財産の遺贈寄付を決めた。子どもの教育に関することに使ってもらう「恩返し」と男性は語っていた。自分の生き方を振り返り、遺贈先を決めるやり方もある。
大切なお金を託すのだから、できれば直接、活動内容の説明を受けたい。前回、もともと縁のあった団体が本当に信頼に足るのか、2年以上にわたりボランティアとして関わったケースを紹介した。そこまでしなくても、事務所に行けばある程度、雰囲気は分かるだろう。取材した中には、試しに少額の寄付をして対応をみて選んだケースもあった。
公正証書遺言か自筆証書遺言で遺贈先を指定
遺贈先が決まれば、次は遺言書を作成する。代表的な方法として、公正証書遺言と自筆証書遺言がある。ざっくりいえば、法律のプロである公証人の助けを得て作成するのが公正証書遺言、自分で手書きするのが自筆証書遺言だ。
公正証書は費用がかかるものの、内容が無効になる危険性が低く、公証役場で保管してもらうので紛失も考えにくい。自筆証書は形式の間違いなどで無効になる危険性が高く、紛失の危険性もある。民法が18年に改正され、自筆証書遺言の財産目録は自筆でなくパソコンで作成してもよいことになり、法務局での保管制度も20年7月から始まることになった。とはいえ、確実に遺言を残したいならやはり公正証書遺言が無難だろう。
公正証書遺言の作成件数は年々、増える傾向にあり、日本公証人連合会によると17年の作成件数は11万191件。08年には7万6436件だったから約1.4倍に増えている。
ただし公正証書遺言も万能ではない。自分の代わりに遺言を実現する「人」の問題に行き着く。遺言執行者だ。いくら遺言に問題がなくても、それを執行する人がいなければ、存在しないのと同じことだ。
相続人が遺言執行者となるケースも多いだろうが、たとえば「遺贈寄付など取りやめて身内だけで分けてしまおう」という相続人の圧力に屈することなく、誠実に遺言内容を執行する第三者に託したい。弁護士や信託銀行などだ。信頼できる遺言執行者を指定することで、「執行されないリスク」はかなり軽減できる。
法定相続人への「遺留分」に注意
最後に注意したいのは、法定相続人がいる場合の「遺留分」だ。配偶者に1円も残さないとか、特定の相続人にあまりに偏った配分をすると、他の相続人が生活できなくなってしまう可能性がある。そのため、民法は兄弟姉妹以外の法定相続人に、法定相続分の2分の1(親や祖父母のみの場合は3分の1)を、最低限の相続分である「遺留分」と規定している。自分の相続した財産が遺留分に満たない場合、不満があれば遺留分を侵害している人に対して「遺留分に足りない金額を分けてください」と請求できる。遺贈する場合は、この遺留分を侵害しない範囲で行いたい。
また、財産が不動産の場合は、できれば現金化して遺贈したほうがよい。「みなし譲渡課税」という制度が適用される可能性があるからだ。簡単にいえば、税金がかかるのだ。団体によっては不動産を活用したり、管理したりすることが難しい場合もある。だから、一部の団体を除いて、不動産の寄付をそもそも受け付けないことが多い。
前回紹介した「全国レガシーギフト協会」など、無料で遺贈寄付の相談に乗ってくれる窓口もある。活用してみてはいかがだろうか。
(*この原稿は、
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
