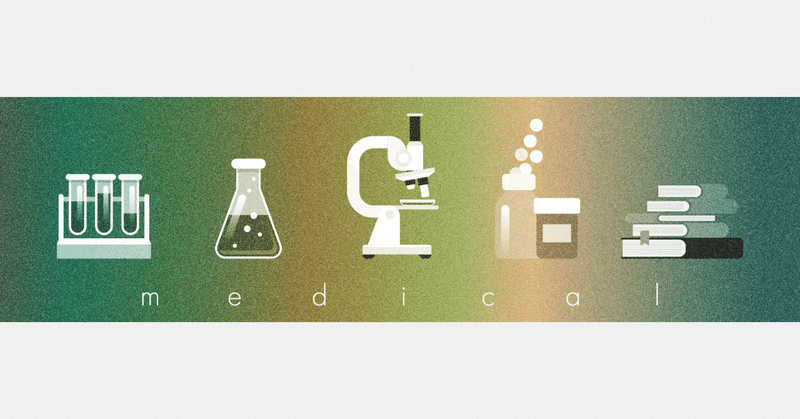
#1440 こんな研究主任は嫌だ
今現在(2023年度)、私は校内で研究主任を務めている。
研究主任は、校内研究を司るポジションである。
なので、自分の「やりたい研究」というものがなければならない。
しかし、それを押し付けるのはナンセンスである。
かつて、私が在籍していた勤務地では、自分の「やりたい研究」を押し付けてくる研究主任がいた。
私が「若手」だから、言いやすい?のか、心配?だからなのか不明だが、押し付けが激しかった。
私の主張を聞かず、「もっとこうした方がよい」「ここを直そう」と強制的に授業の構想を押し付けられたのである。
これでは、「私のやりたい授業」ではなく、「研究主任のやりたい授業」になってしまう。
しかし、実際に授業を実践するのは「研究主任」ではない。
「授業者本人」のはずである。
研究主任は「やりたい研究」を押し付けるのではなく、助言をすべきである。
授業者が困ったときに、それに耳を傾けて、相手の主張を聞き、適切な助言をすべきなのである。
授業者の主張も聞かず、一方的に「やりたい研究」を押し付けても、授業者は主体性を発揮できない。
そんな「借り物の授業」をしても、見栄えはよくなるかもしれないが、自己の成長にはつながらない。
最重要なのは「研究方針どおりの授業」をすることではなく、「授業者の主体性」である。
「授業者の主体性」のない研究授業に、未来も学びもないのである。
そんな過去をもつ私は、人生で初めての研究主任になったが、「押し付け」をしていない。
ベテランの先生方は、それなりの経験があるので、ほぼ任せている。
授業の事前検討会で「指摘」「助言」を少しするが、それを押し付けはしない。
私の指摘・助言を採用するかは、授業者本人が決めることである。
なので、指摘・助言程度に留めるようにしている。
一方、若手の先生はアドバイスを求めてくるので、それに応えるように助言している。
しかし、私の助言も強制的に押し付けずに、採用するかは本人に任せている。
これでよいのではないだろうか?
おそらく「自分のやりたい研究」を押し付けてくる研究主任は、授業者が授業を失敗するのが怖いのである。
そして、最終的に「研究主任が悪い」と言われるのを恐れているのである。
しかし、本当に研究主任が悪いのだろうか?
「何もしなかった」のであれば、研究主任に落ち度はあるだろう。
けれども、研究主任の助言に対して、それを採用したり、採用しなかったりしたのは「授業者本人」のはずである。
そしてその授業中、目の前の子どもたちに「教育」を行ったのは、紛れもなく「授業者本人」のはずである。
なので、授業がうまくいかなかった落ち度は、研究主任よりも授業者本人にあるのではないだろうか。
研究主任はそんなに怖がる必要はないのだ。
できるだけの助言は必要だ。
あとは、授業者の主体性に任せればよいのである。
私は過去に出会った「押し付けてくる研究主任」を反面教師にし、的確な助言をする研究主任を目指していきたい。
では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
