
昔の道具からわかる、今の私たちに大事なこと。
2200字くらいです。写真多め。昔の道具に興味はありませんか。
こんにちわ!! 民俗資料館をみていくのが趣味なわたしです。
今回は、昔の道具の問題を出していきます!
さあ、みなさんが知ってるのはありますか?
またはぜひ、推理してみてください。
第一問!

今は家電です。
正解は、
洗濯機!
では、第二問。

ノーヒントで使い方を考えてみませう。
正解は、
ワープロ!ワードで文字を打つ機械ですね。
日本語は英語と違い、アルファベットの組み合わせでなく、ひらがな、カタカナ、漢字の組み合わせで、そのせいで活版印刷などは難しかった。
けどまあ、気合いと根性で、文字すべてを版画で彫って版木を作ってましたがね。
ワープロもひらがなカタカナはできるでしょうが、星の数ほどある漢字変換とか難しそうです。
第三問。

箪笥(タンス)のもうひとつの使い方です。
正解は、
階段!箱階段といいますが、棚を階段にしている家はいまでもあるのでは?
昔の階段は、「急」です!
第四問。

正解は、
トイレ!江戸の長屋のもの。上から下から、丸見えです。
ちなみに、紙は浅草紙など粗末な紙は高級で、糞箆(くそべら)とか木のへら、わらや縄とかも。
昭和最初まで新聞紙なので、やわらかいトイレットペーパーは幸せな道具なのです。
第五問。

正解は、
張り板。洗濯物の衣類を、パーツごとに分解し、洗ったあとに、糊をつけて張り、乾かします。
アイロンは「ひのし」てもので、器に炭を入れ、その底でシワをのばしましたが、よりパリッとするためにノリでのばしてました。
分解してましたから、あとで縫い合わせるのは一苦労でしょう。
第六問。

正解は、
木樋。江戸時代の水道管で、上水という水路から、各町の井戸へ水を送ってました。
第七問。
ここからややマニアック!

ヒントは梵字とか、宗教ぽいですね。
以下、再び与野郷土資料館です。
正解は、
板碑。昔のお墓や卒塔婆ですね。
第八問。

正解は、
算盤。
江戸時代の人々の趣味に数学(和算)があり、自分がつくった数学の問題を、神社に奉納します。
近現代の数学の定理に近いものがあるらしく、すごい!
第九問。

正解は、
綿花です。
このあと、綿の中の種をとり、糸車で紡績、機織りで布にし、衣服を繕います。
昔は布は高級で、一枚つくるのにかなりかかり。同じ服を修理しながらずっと着ていました。
洗濯すると(手でごしごし)布がいたむので、何日も来ていたとか。
肌が荒れますね。
第十問。

何に使うのでしょうか。
食べ物ではありません。
正解は、
肥料。ニシンなどは搾(しぼ)り、魚油と別に搾り粕を肥料として使ってました。
第十一問。

ヒントは何かの原料。あるものがくっついてますね。
正解は、
鉄鉱石。
草加市のとなり、川口市は鉄を型に流して鉄器をつくる鋳物の産地。
鉄を冷やす水、土砂が流れてたまった良い砂や土(鋳型や砂鉄もとれるのか)、さらに川による舟運でいろんな道具が集まるところ。
戦争の大砲や砲弾、銃剣などのサーベルも作ってた。

第十二問。

形やらから推理できました?
正解は、
行火(あんか)。
猫行火ともいい、布団のなかで足を暖めていました。
第十三問。

蹄鉄ではありません。
正解は、
牛の鞍。背中にのせて、物や人を載せる部分。
人が座ると、お尻は痛いのでしょうね。
最後、第十四問。

正解は、
携帯の薬箱です。
さて、ちょっとマニアックでしたか?
こんなの期待してましたか?







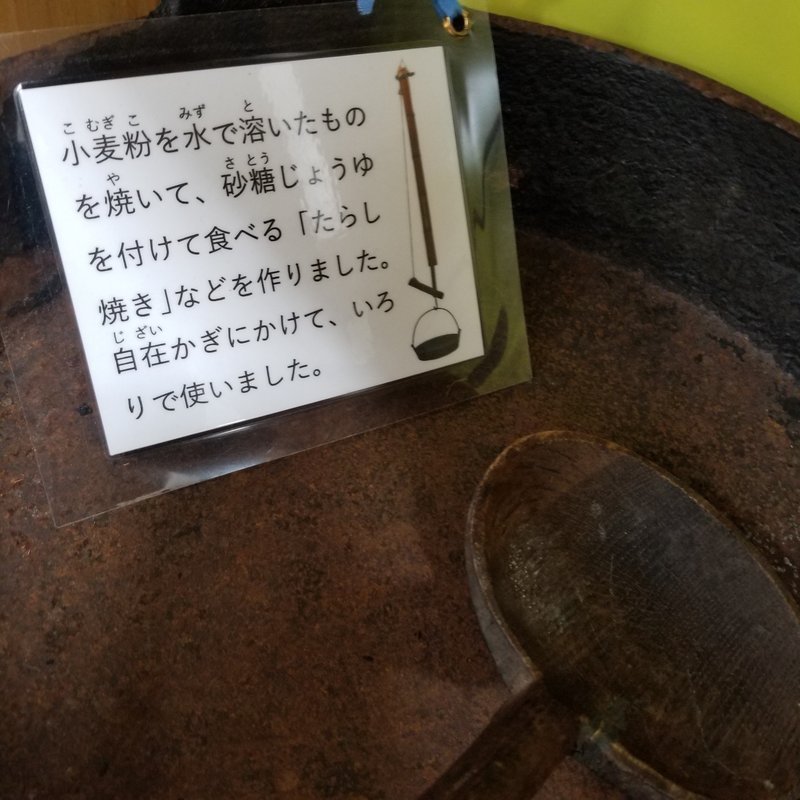






さて、最後の問題です。
これらが今や、新しい「便利な道具」に改良され、私たち現代人は、昔の人とくらべ、
何を獲得し恵まれるようになったのでしょう。
ヒントは、「便利」とは何か。
効率とは、よけいなあるものをかけなくなったこと。
正解は、
「時間」です。
私たちは、水道の蛇口をひねるだけで、あふれるように水が手に入るが、昔は近くの川や井戸から水をくんでは運び、水瓶に蓄えていました。田舎まで水道が届いたのは、ここ50年くらいでしょうか。
さらに、移動は江戸時代までは徒歩中心。明治になり鉄道ができるも、本数少なく、鈍(のろ)い。
私たちは、便利な道具を開発することで、ふだんの行動が高速で、そして広い範囲でできるようになりました。
昔は、ご飯をつくり食べるのも、水をくんで飲むのも、ひとつの家事をすることも、相当な時間がかかったわけです。
では、昔の人が不幸なのか。もちろん、このように自分の手で、家をつくり服を仕立て、食材から食事をつくり、食べて寝る。こういうのも幸せなのでしょうが、それで終わっていたのも事実。だから、先人たちは、便利な道具を開発し、時間がかかった行為を簡単に、かつ広い範囲でできるようにしてくれた。
この積み重ねで、わたしたちは「生活する以外の時間」、仕事や生活を簡単に快適に過ごせるようになったのです。
医療制度の発達で、わたしたちは平均寿命も伸びました。
「生きる」には「暇すぎる」時間もとれるようになったかも。
だからこそ、「自分は何をして、この長く生きる時間を楽しんで暮らせるのか」充実できるように先人たちが作ってくれたのでしょうね。
個人的に、母から「昭和30~40年ぐらいは、トイレの紙は新聞紙だった」と聞いて、トイレットペーパーの紙の柔らかさに幸福を感じています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
