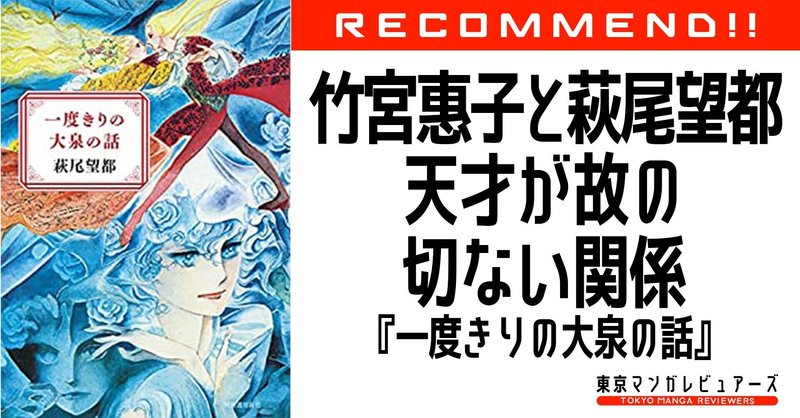
竹宮惠子と萩尾望都。ふたりの天才少女漫画家の、誰も知らない友情と嫉妬、羨望『一度きりの大泉の話』
【レビュアー・兎来栄寿】
1970年代以降の「少女漫画」が別次元の高みへと発展していった転換点の中心として、誰もが挙げるであろ二つの名前、「竹宮惠子」と「萩尾望都」。
これまで、その二人の過去については基本的に萩尾さんから語られたものはなく、竹宮さんの視点のみから語られたものが世に出ていました。2016年に上梓された『少年の名はジルベール』、及び2020年に読売新聞で連載され2021年に書籍化された『扉はひらく いくたびも』はその中でも特に重要なものです。
『少年の名はジルベール』は、紛れもない天才である竹宮惠子さんがひとりの作家として、またひとりの人間として漫画創作や人生にまつわる苦悩や失敗、悦びや成功を赤裸々に綴った単体で読んでも極上の一冊なのですが、その5年後、今回発刊された萩尾さんの『一度きりの大泉の話』と併読することによって更にその価値が無限に高まったように感じられました。そして、竹宮さんの両親や祖父母の話などより詳細な過去、そして現在の活動に至るまでが書かれた『扉はひらく いくたびも』を読むことで、更にその解像度を上げて俯瞰することが可能になります。
なぜ、「大泉サロン」は2年で終わったのか。どのようにして終わったのか。その顛末はどうだったのか。
双方の視点からの記述を辿ることで、狂おしく遣る瀬ない感情に支配されます。読了してから数日間、心がどうしようもない状態に持っていかれたままでした。
ふたりの天才
私は、萩尾さんと竹宮さん二人の関係性について『ガラスの仮面』の作中に登場する二人の天才、北島マヤと姫川亜弓を想起しました。
姫川亜弓は、自分が持たず北島マヤだけが持つ圧倒的天才性やそれに対する評価に、灼けつくような悔しい思いを滲ませ続けていました。
しかし、一方で北島マヤにとってはまさかあの亜弓さんが、輝くような美貌を持ち素晴らしい両親と大豪邸で育った、演技にとどまらず何をやってもハイレベルにこなす大スター・姫川亜弓が、中華料理屋で住み込みで働いていたドジでおっちょこちょいで演技に関しても素人同然の平凡な自分に対して嫉妬や羨望といった感情を持つなどということは、想像だにできなかったわけです。
そして、マヤがそんな風にしているからこそ、自分が抱えるような苦悩とは無縁でありそうな超然とした存在であるからこそ、そして憎めるような人格も持っていないからこそ、より一層居た堪れない想いは深くなるのです。
それと似た状況が萩尾さんと竹宮さんの間にも見受けられました。
『少年の名はジルベール』及び『扉はひらく いくたびも』では、はっきりと竹宮さんが萩尾さんに抱いた嫉妬と羨望の焔の激しい燻りが、克明に描かれていました。
自分はネームも原稿も間に合わないので編集者が取りに来たとき、時にはカンヅメにもされたが、萩尾さんは真面目で根気強くスケジュールも遅れない優等生だったこと。
デビューして間もないころから既に、家に泊めてくれるようなファンがついていること。
自分が好きに描いた作品はなかなか載せてもらえず、いつ仕事が途切れるかもわからないという不安に駆られる一方で、「萩尾の作品だったら何ページだろうと好きに描かせて必ず載せる」「萩尾は売りやすい」と編集者が言っていたこと。
「いきなり何かの事件の最中を見せてしまう」という話の作り方や斬新な演出方法など、美しい絵のみならず映画のように漫画を描くそれまでになかった清新な才能。
萩尾作品の背景の美しさに感動した一条ゆかりさんがその背景を描いたアシスタントを雇いたいと竹宮さんに電話してきたが、それを描いたのも萩尾さん自身であったと説明させられたこと。
「そういう描き方、作品の世の中への出し方、理想だよ……」
「脅威に感じた」
「称賛と恐れがないまぜになった」
「私が認めたくない不安や焦りをはっきりと認識させられてしまう」
「私は中学、高校時代の読書量や映画を見た量が、圧倒的に少ない(中略)そういう文化的な差みたいなものに劣等感をおぼえ、ストレスになっていました」
など、渦巻く嫉妬と羨望、コンプレックスが随所に吐露されていました。
きちんと毎日定時に仕事をこなす萩尾さんに対して、朝から鬱々としながらボウリングやパチンコに興じていた時間や、酷い時にはスランプとストレスにより悪夢を見て泣き叫んだ経験も赤裸々に綴られています。
そして、恐らくはこれらもほんの一角に過ぎず、現実には萩尾望都という超大な才能と一つ屋根の下で暮らす中で日々どれだけ辛く惨めな想いに晒されたかを想像するに胸が苦しくなります。
大好きだった憧れの竹宮先生
ひるがえって、今回発売された『一度きりの大泉の話』を読むと、萩尾さんの方からの竹宮さんへの高い評価が書き連ねられます。
そして竹宮さんの評価や想いとは裏腹に、萩尾さん自身は自分のことをノロマで幼稚だと思っており、自己評価を高くできていなかったのだということもわかります。
担当編集からは「お前なんか、もういらねえよ」と言われ、その原因を分析してみれば1年執筆してもアンケートで点数を取れない巻末作家であること。
編集部の中でも竹宮さんファンがいて、予告カットをもらって宝物のようにしている編集者がいること。
ささやななえこさんの原稿を竹宮さんが手伝ったら、モブが上手すぎて皆がそのページを見に集まったこと。
世間で絶賛される『ポーの一族』も、最初は佐藤史生さんから「なんでこんなの描いたの?」と言われ、読者からの反応も今ひとつだったこと。
『トーマの心臓』も連載1回目が掲載された後に「連載をやめてくれ」と編集者から言われたこと。
『一度きりの大泉の話』の巻末には、現在は萩尾さんのマネージャーを務め大泉の時代からの関連人物と交流も深い城章子さんの証言もあるのですが、そちらでも、「傍から見ていても竹宮さんは自信たっぷりに暮らしていて萩尾さんに嫉妬するとは思いも寄らなかった、アシスタントへの指示も竹宮さんは非常に的確だったが萩尾さんは感覚的で抽象的だった、ただ一度だけ「モーさまが怖い」と竹宮さんが言うに至ったエピソードがあった」、と書かれていました。
この第三者の証言も非常に貴重です(もうひとり重要な人物である増山法恵さんに関して、城さんから見た増山さんの話も重要なピースであると感じました)。
上述したような竹宮さんの抱える苦悩は、竹宮さんがそのように見せなかったという部分も大きいでしょうが、萩尾さんも周囲の人も想像だにしなかった、できなかった。
つくづく「隣の芝は青い」であり、人間という生き物は自分の領域と基準でしか物事を判断できないし、当人の真の想いは実際に訊いてみないと解らないという示唆でもありました。そして、たとえそのことが解っていたとしてもその実践がどれだけ難しいかということも……。
萩尾さんは、語るのも辛いはずの思い出であるにも関わらず、それでも田舎から出てきたばかりの自分に優しく接してくれた竹宮先生への称賛の言葉を惜しみません。
「美人で明るくて親切で才女」
「穏やかで人間的にも立派。こんなに若いのに完璧な人がいるのだなあ、と感心しました」
「本当に絵がうまい方でした」
「竹宮先生の青空のような明るさは、私にはないものでした。いつも仕事にも描くものにも、前向きでした。心が伸びやかな方だったのです」
「竹宮先生の聡明さ、公平さ、明るさなどをどんどん好きになり、尊敬し、こんないい人に出会えて私は幸福だと思いました」
これほどまでに大好きで尊敬していて、互いの感性の素晴らしさを認め合い、向こうから「結婚するなら萩尾さんのような才能を持った人」とまで言われて、苦しい修羅場の数々も共に乗り越え、一緒に少女漫画の新時代を切り拓いていた竹宮さん。
そんな人から、ある日突然に無情な別離を宣告された萩尾さんの心境を考えると涙が止まりませんでした。
萩尾さんのその後
当時は病名は意識していなかったものの、そのことが原因で萩尾さんは心因性視覚障害や鬱のような症状を発症したそうです。そして、大泉での記憶は永久凍土に閉じ込めて静かに穏やかに生きようと、永遠に竹宮さんやその作品から離れることにしたそうです。
当然、まともに漫画を描けるような状態でもなくなったのですが、それでも
「自分を好きでいるためには、自分に正直でいないといけない。毎晩浮かぶ物語を、これからも描き続けたい。それが一番やりたいこと」
と、漫画の執筆を続ける選択に至ってくださったことは、世界にとって大いなる幸福でした。
しかし、そうならなかった未来も大いに有り得たことを知らしめられました。
奇しくも、萩尾さん自身は嫉妬という感情を知識として知ってはいても、本質的には理解できないということも今回詳しく綴られていました。
「排他的独占願望」という言葉を用い、自分が、美少年の出る寄宿舎ものを竹宮さんや増山さんとは違う解釈で描いたことが地雷で、気に障ってしまったのだろう、ファンレターでも盗作疑惑の噂があると届いていた、と回顧しますが、それは本当に些細なことで、スランプに陥り自律神経失調症になるまでに追い込まれていた竹宮さんの嫉妬と羨望こそが問題の本質である、ということを萩尾さんが理解するのは非常に難しいことなのでしょう。
しかし、嫉妬できるのもやはり竹宮さんが才気溢れる方であったからであることは疑いがありません。感性の乏しい人であれば、同じものを見ても何も感じず何の感情も抱かなかったでしょうから。
「私や萩尾さんは1回観ただけで、映像をそのまま丸ごと、視覚的に記憶できたので、互いに興味を持った画面構成の面白さを確認し合うことができる」
こんなことをさらりと言えてしまう竹宮さんもやはり紛れもなく天才です。同じ時代に生まれた傑出した才能同士が出逢って、ひとつ屋根の下で衣食住を共にしながら切磋琢磨したことは、奇跡という言葉を用いるのに相応しいでしょう。
若干20歳同士で、漫画を描くのが呼吸と同義であるふたりが、初めて出逢い原稿作業をしながらマンガやSFについて熱く語らい、物語を創り出した夜。萩尾さんにとってだけでなく、徳島から単身出てきた竹宮さんにとっても同年代の女性でそんなことをできる相手がまず初めてで、それがどれだけ嬉しく尊いことだったかが述べられています。その夜から、常人には計り知れないほどの密度で魂を通わせる時間が存在したことでしょう。
少女漫画の既成の枠を破り、新しいものを生み出したいという強い情念は共通していて、道を違えた後もそれは間違いなく果たされていきました。
萩尾さんは決して竹宮さんの描いたものを読まなかったそうですが、奇しくも近似点のある作品はいくつも挙げられます。
「事実は小説より奇なり」と言われますが、これらはもはや並の創作では及ばない領域の崇高な物語です。それだけに、あまりにも悲劇的なふたりのすれ違いが痛切に過ぎます。
禁じられた大泉の話
竹宮さんは、2016年『少年の名はジルベール』を上梓した際にそれを本人の名義で萩尾さんに送ったそうです。そして、大泉にまつわる企画や対談なども萩尾さんさえ良ければ私は構いませんという態度を通しているそうです。
しかしながら、『一度きりの大泉の話』を読了した後ではそれがどんなに萩尾さんにとって至難で残酷な話か、そして『少年の名はジルベール』を決して読むことはない萩尾さんとは違い、恐らく竹宮さんは『一度きりの大泉の話』を読むであろう、その時の心境たるやいかばかりか、と涙淵に沈み慨嘆するのみです。
私も、これまではお二方の一ファンとして、それこそ『まんが道』のような大泉サロンのドラマや漫画があったら良いなと軽率に思っていました。
しかし、そんな不明を恥じて止まない切実な述懐でした。筆舌に尽くし難いであろう経験と思いを、よくぞここまで表出させてくださったものだと思います。
そして、齢70を超えた萩尾さんが、さまざまな障害を排して未だに素晴らしい『ポーの一族』の続きを描いてくださっていることの有り難さを改めて噛み締めました。深い感謝と畏敬を捧げると共に、萩尾さんが静かに心穏やかに暮らせることを願って止みません。
『少年の名はジルベール』と『一度きりの大泉の話』、そして『扉はひらく いくたびも』。これから読む方はどれから読んでも良いのですが、必ずこの3冊は併せて読んで欲しいです。
いずれも、胸を圧搾される部分もありながらふたりの天才作家の作家性が如実に現れており、紡ぐ言の葉の美しさや巧さ、そしてあらゆる創作や人生に通ずる魂の在り方がちりばめられた、稀有な書です。
なお、後書きにて
「このような話を聞いて、読者の方は混乱したり、漫画界に失望したり、漫画から遠ざかってしまうかもしれない」
という危惧を萩尾さんは書かれていましたが、それだけはなかったと、むしろこの本を読んだことでまた遠い異国の少年たちや、宇宙の星々の向こうを描いた遠大な物語に再び触れ直したいという欲求はかつてなく高まり、漫画の持つ力の大きさと素晴らしさに改めて思いを馳せました。
「私は漫画とその世界に、子供のころから救われてきました」
という萩尾さんの作品に子供のころから触れて救われてきた私は、そう伝えさせていただきたいです。
