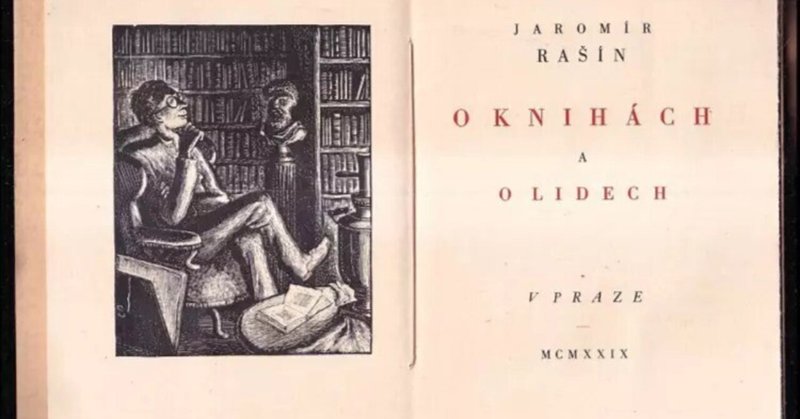
ヤロミール・ラシーン「書物について、人について」(1929年)
親愛なる友人のみなさま!
本に対する愛、美しい本を望む心が私たちを結びつけている、この《チェコ愛書協会》において、今年の連続講演の幕を切って落とす光栄に浴することとなりました。ここで私は書物と人について、お話ししたいのですが、いきなり、中世の神学者の顰みに倣って区別と分類から話し始めるからといって、何とぞ私を非難しないで下さい。私たちは本を、その内在する価値によって文学性の長大な尺度の上に――主観的見解と客観的事実、印象と思想、感受と無関心、親愛の情と悪感情、流派、影響関係、従属関係、過大評価と過小評価、宗教的な倫理と社交的な不道徳との興味深い混淆にほかならぬ尺度の上に――位置づけます。こうした評価は、私たちの人生と同様、多種多様で不完全なものであり、各々が各々の教皇、大司教、主教、大修道院長、教区司祭、チャプレン、寺男、侍者(アコライト)らを作り出します。誰もが熱心に、書物のことをよく理解しているかのように――いや、それどころか誰よりも本を理解しているかのような顔をして本を評価、分類します。愛書協会員の私たちは、その外面によって本をただの本と美しい本に分けます。それから人を、学校を出てから一度も本を手に取ったことがなく、せいぜい新聞を読むくらいの人々をより分けます。これこそが最大多数派であり、人間社会のあらゆる状態がこのグループに顕現しています。次に多いのが読書好きの人々で、この人たちは本を借りて読み、本の中身に泣き笑いをし、本を持ったまま夕食を摂ります。こうした読書好きは、本を買うのは単なる娯楽のためにお金を浪費することだと考えているので、読後、本を手許に取り置くことはしません。書籍を一個の趣味の対象として愛する人々がいちばんの少数派で、愛書家と呼ばれる人々です。そして、我が友なる皆さんはその一員というわけです。あなた方は、それぞれの人生において大切なものとして本を愛し、本と共に、本のために生きておられ、本が増え、美しい蔵書へと育っていくことを、家族がふえたかのようによろこびます。美しく、芸術的に装丁された書物を愛し、用紙と活字組を仔細に吟味し、凝った挿絵で飾るだけでなく、表紙にも同様の注意を払います。その本はあなた方の手の下で芸術作品へと成長し、内容の美しさがそれに相応しい優美な外観と結びつく―このことこそ、書籍の分野において発達した古代ギリシアの「カロカガティア(善美)」の理想なのです。
愛書家には敵対者が少なくありません。まずはお金のない人々です。彼らは言います―我々が買えないことが分かっていながら、どうして美しくて高価な本を出版するのか、と。お金持ちの敵対者もいます。何をいったいどうすれば、高価な書物に私たちの金を使えと慇懃に要求するなどという真似ができるのか、というのがこの人たちの言い分です。それは作家たちなのでしょうか?往々にして作家たちは、権威と影響力を欲するあまり、万民の日々の糧になりたがるところがあります。自分たちの言葉の力で人々を屈服させ、精神の軛で隷属させようと望みがちなのです。彼らは美しい書物を、女々しい翫弄物、欺瞞的な風潮と考えていますが、それは美しい書物が何万、何十万部単位で拡散していくことなどあり得ず、作家の野心を満足させ得ないからでしょう。二百部かそこいらしか出さないのでは我々の儲けにならないではないか、というのが作家たちの言い分です。もしも皆さんが、コメニウス(コメンスキー)の漂泊の旅のように、人間社会のありとあらゆる状態を通りぬけ、世界という迷宮を彷徨ってみたとしても、美しい書物の愛好者をほとんど見つけることができず、あなた方の心は悲しくなることでしょう――美しくデザインされた書物は思想に捧げられた最高のオマージュであり、美への捧げ物、理想の形式、美しい身体に宿った美しい精神であるにもかかわらず。
画家が古新聞に絵を描かず、彫刻家が自らの夢をこね上げてジャムにすることなどないというのに、書物を愛する者が、よしんば人間精神のもっとも崇高な思想であったとしても、すでに湿って崩れかけて悪臭のする、灰色や緑がかった古紙の塊として提供される思想を歓迎するなんてことがあるでしょうか?王様が襤褸ではなく正装で出でますように、思想の担い手であり、精神の揺り籠である書物、物質と結びついた非物質的な知性としての書物は何か王にふさわしいものを内に宿していますが、だからと言って、そのことが書物を助けてくれるわけではありません。なぜなら王の時代が終わり、今は平等化の、おしなべての平準化の絶頂期であり、平等と集合住宅の時代なのですから。
友人諸氏よ、精神と肉体から人が成りたっているように思考と紙が書物を作りあげているのだと、書物の成熟が民族の成熟にほかならないのだと、書物のお陰でいにしえの人々の文化が我々の許に保存されているのだ、と思えないでしょうか?私はそう思いますし、人が自分の体に気を遣って手入れするのと同じくらい本に対しても気遣いが必要だと、私も思います。しかし、現実にはそうではありません。新聞は読んでは捨てられ、図書は貸し出されては返却されています。もし愛書家が実際にそうであるほど珍しい存在でなかったとしたら、さまざまな風刺歌謡、ユーモア新聞、オペレッタのレパートリーにとって欠くべからざる要素のひとつになっていたにちがいありません。つい先日も『国民新聞』紙上で、いかにも愛書家(ビブリオフィル)好みの装丁でマハル[Josef Svatopluk Machar(1864–1942)はチェコの詩人、随筆家。反オーストリアの政治グループの重要人物としても知られ、詩の多くには社会風刺が込められている]まで上梓されてしまったと、文化活動家としても知られるさる有名作家が嘲笑したばかりです。ほかの作家にしても、愛書家について何か特別に作品を書かねばらぬ仕儀に立ち至ったとしたら、彼らに書けるのはせいぜい、オークションで狂ったように手当たり次第に買いまくる書痴(ビブリオマニア)、高く競り落とした低俗な本の支払いのために貴重な本を売り払う破目になった収集狂の話ぐらいでしょう。愛書家は一度本に噛みついたらもう二度と離さないブルドッグのように描かれたり、ふらふらと古書店を回る幽霊として描写されたりするのが常です。しかし、友人諸氏よ、我々はかくも善良な人間なのですから、我々をモデルに書かれた風刺文(カリカチュア)をこころよく進んで刊行しています。
本に美しい装丁を着せてやりたいという欲求は、歯ブラシがそれほど長く使われてきたわけではないのと同様、さほど古いものではありません。1880年代、90年代の我らが尊敬すべき出版者諸氏は、我が国の詩人たちの精神が生み出した素晴らしい作物を見るのも恥ずかしいような安っぽい装丁で刊行したおかげで一財産を築き、家屋敷や別荘をあがない、娘たちに大した持参金を持たせたのでした。彼らは自分とその娘たちに良かれと願ったのに対し、もし無欲な人間である私だったら、自分よりも本に良かれと願ったと思うのですが。
どうやら私は本に対してこのような独特の考え方を持ち、書物は儲け主義からではなく愛情から出版されるべきだと、台所にエジプト風の鍋をたくさん備え付けるためや細君に毛皮のコートを着せるために本から搾取するのは罪作りなことだ、と考えています。とはいえ、事の成り行きは私の正しさを証明してくれています。人々が物質的に貧しくとも愛に溢れ、その生涯を本に捧げ、彼らの情熱の炎が後に続く人々のために道を照らし出す時に初めて、書籍の美術が育ち、開花し出すのです。ここで私は、出版界の司祭長とも言うべき存在、スタラー・ジーシェ生まれのヨゼフ・フロリアンを――「ビブリオフィル」と呼ばれて気色ばんだフロリアンを思い起こしていただきたいのです。その次に名を挙げたいのが、類い稀な出版者にして愛書家であったタソフ生まれのヤクブ・デムル。眠る間もないほど働き、「チェコのフランチェスコ」と称せられたデムルは、価値ある内容の本を数多く、しかもとびきり素晴らしい装丁でもって出版しました。福音主義的な清貧に安んじる『安息日の平安』誌を出版する一方、ヴァーハル自身の挿絵で飾られた詩集を手にすることに智天使のような純粋な悦びを味わったフランチシェク・カシュパルや、信奉者や友人たちを糾合して、古代ギリシアのプラトンやエピクロスのように一家をなした、雑誌『モダン・レヴュー』の創刊者アルノシュト・プロハースカのことも忘れずにおきましょう。そして最後に、出版に携わったがために困窮し、六人の娘から富と財産を奪い取る結果になったルドヴィーク・ブラダーチの名を挙げたいと思います。賞賛に値する出版者たちであるにもかかわらず、ここでその名に言及しなかった人々が、美しい本の価値を軽んじていたなどと言うつもりは、毛頭ありません。あえて名を挙げたのは、彼らが実際に美しい本を刊行し得たというにとどまらず、そのために苦しい目に遭うのを承知で犠牲を払った人々だからです。
私たちのような愛書家がいる一方で、本を愛さぬ人々がいるのはなぜなのでしょう?多分それはリチャード・ド・ベリー主教が言う通りなのであり、本が怒ったり叱ったりしない先生だから――棒やムチでぶたず、馬鹿にせず、根気よく教えてくれる先生、いつも君のために十分な時間を割いてくれる先生だからなのです。多分それはペトラルカが書いた通り、本がさまざまな国、さまざまな時代からやって来るからであり、私たちの疑問に答えることを、自然の神秘を私たちに明かすことを厭わないからです。偉大なる精神とは、すべからく書物に対する特別な愛によって、書物に対する高い評価によって際立っていることを忘れずにおきましょう。ペイシストラトスがアテナイを支配できたのは、その書物愛のおかげだと言われていますし、プラトンとアリストテレスは哲学書を書いただけでなく、体系的に収集しました。プトレマイオス一世は有名な古代アレクサンドリア図書館の礎を据えたし、ルクッルスは伝説的な宴で知られているだけでなく、その素晴らしい蔵書でも有名でした。カエサルは本を愛しもしたし、書きもしましたし、ローマ皇帝アウグスティヌス、ティベリウス、ウェスパシアヌス、ドミティアヌス、トラヤヌスらは図書館を建設しました。キケロ同様、セネカも多くの蔵書を持っていましたが、肉欲のため書物なしに過ごされる時間を死と、生ける人間の墓だと考えていました。偉大な軍人たちも、古代におけるアレクサンドロス大王とコンスタンティノスから近い過去においてはナポレオンまで、本好きで知られ、ナポレオンは軍隊の遠征にも恋のロマンスにも本を持ってこさせるほどでした。教父たちと神秘主義的な夢想家たちのどちらもが本を愛しましたし、書籍を魂の精髄と見なしていたショーペンハウアーは、人との個人的接触よりも書物を好んでいました。『マハーバーラタ』が今も偉大なインドの国民文学であり続けているのと同様、『聖書』はヨーロッパ諸民族の文学となっています。ハーフィズはペルシアを、セルバンテスはスペインを有名にしました。もし英国が何一つ成し遂げることがなかったとしても、その名をなすためにはシェークスピアとミルトンの名だけで十分でしょう。古代ギリシアはホメロス、ヘロドトス、プルタルコス、プラトンの著作以上に崇高なものを残し得たでしょうか?アイスキュロスやイプセンに作品以上に、悲劇が頂点を極めたことがあったでしょうか?ドストエフスキーほど、圧倒的な力をもって預言をした詩人がいたでしょうか?いにしえのヘラスの太陽が、ゲーテにおけるほど明るく蘇ったことがありますか?トルストイの作品ほど真実を希求する宗教的熱意と願望が成熟している芸術作品はどこにもありません。孔子の叡智、モーセの正統性、仏陀の言葉、ソクラテスの友愛、イエス・キリストの愛、ムハンマドの熱狂を我々に伝える書物が存在しました。この世に存在する唯一無二の富は魂の富であり、図書館はその宝庫なのです。そのことをエマソンは的確に言い表しました――「小さいながらも選び抜かれた蔵書を持つよう心がけなさい。あらゆる文明国から選び出され得る賢明にして機知に富む人々の社会とも言うべき蔵書は、その学識と叡智の過日を最良の形で何千年にもわたって伝えてきた。それらの人々が自ら俗世を離れた、近寄りがたい隠者であったにもかかわらず」と。さらにその先では「それはひとり跪いて読むべき書物だ」とも語っています。彼の友人にして魂の兄弟、そして不滅の作品『森の生活』の著者、ソローも次のように書いています――「アレクサンドロス大王が豪華なケースに入った『イーリアス』を携えて遠征に出たことは、驚くには当たらない。書かれた言葉はかけがえのない記念物だ。それは、他のいかなる芸術作品よりも身近であると同時に普遍的でもある。文学は、ひとりひとりの暮らしにもっとも近い芸術作品――書物は世界の貯蔵庫であり、世代と民族の伝承にとって最適の依り代なのである。サー・ジョン・ラボックは熱を込めてこう語っている――「図書館こそはこの世の楽園だ。しかも誰も私たちをそこから追放できない。図書館では何ごとも好みにまかせて自由に――かつて人類の母なるイヴが、そのために楽園でのあらゆる悦びを犠牲にした、善悪を知る木の実さえ私たちの自由になるのである。ここで私たちは重大事件について学び、遠方への旅行や探検についての胸躍るようなニュースを知り、興味深い歴史や美しい詩を読む。偉大な思想家と語り合ったり、人間精神のもっとも高貴な作品を楽しむことが、図書館ではできるのである」
知的な人を特徴づけるのは丁重さ、何より書物に対する態度です。ボジェナ・ニェムツォヴァーは、そんなインテリの部屋に足を踏みいれると、まずどこに蔵書があり、その中のどれを読んでいるかを見るのが常でした。無知が人格を下げるのは富と結びついた場合に限ると、古典的な警句を吐いたショーペンハウアーは、次のように語っています――「貧しい人は貧困に縛られており、その肉体的活動は知識に取って代わり、全ての思考を占めている。だが、悪徳に耽溺している無知な金持ちは、人間と呼ぶに値しない」と。高名な哲学者は、傲慢な富者を知性の欠如のゆえに手厳しく批判したわけですが、それはいささか不公平な難癖でした。なぜなら、人生に価値を与えるものは魂の陶冶か、あるいは神秘主義者が言うように神の探究だけであり、そのための時間とお金があるのに胃袋でだけ生きているとしたら、その人は人間という名を持つに値しない。肉体的快楽が身体を疲弊させ、魂を滅ぼすのに対して書物は、秘教の奥義の美酒に酔った東洋の詩人が言う通り、精神世界を飛翔することを可能にしてくれるのです。
書物は天の王国の息子たちの秘密の知恵を、さらには全ての存在の統一と神聖な火についてのいにしえのブラーフマナの深遠な教えを私たちが知ることを可能ならしめてくれますし、仏教の涅槃とムハンマドの天国に近づけてくれるのも本、福音書の真率さと愛で私たちの魂を満たしてくれるのも本なのです。異教的で素朴な生命観を持っていた古代ギリシア人は、熟れた葡萄の芳香と永遠に微笑むその太陽の暖かさを今なお放射し続けていますし、哲学者たちの庭を散策したり、詩人たちの永遠に人間的であると同時に、人間にとって乗り越えることのできない悲劇の叫びに劇場で耳を傾けるように、あるいは暗示的な台詞を辞さぬ彼らの喜劇に戯れ笑うよう、今も誘っているのです。もしも私たちが隠された真理を見いだしたいのであれば、もっとも深い認識の古代のエジプトやバビロン、カルデアやシリアの人々の著わした書物が、私たちを知識の深淵に至る足跡へと導いて行ってくれる書物がある。『タルムード』と『聖書』は倫理的正義と公正な道徳を、パピニアヌスやウルピアヌスら古代ローマの法学者たちは、法的正義の基礎を教えてくれる。たとえばホメロスを読んでいる時には、自分たちが血と肉とで出来ているのを感じるでしょうし、ウェルギリウスを読んでいる時は、自分たちが善と謙遜の力の認識できることを喜ばしく思うでしょう。アウグスティヌスとテルトゥリアヌスは、私たちに古代世界を破壊しようとする人の魂を――独善的に上品ぶる雰囲気の中で身もだえしている人の魂を垣間見せてくれますし、神秘主義者のロイスブルークは、私たちの魂を不可思議な震えで満たし、パスカルは我々を神へと導いていきます。ショーペンハウアーのペシミズムは私たちを打ちのめしそうになりますし、その継承者であるニーチェは超人の理想を唱道しました。超人などと勿体ぶってと申し上げましたが、私の場合、人間とは超越されなければならない存在ということです。超越するため、あなた方は何をしてきたのでしょう。蛆虫から人間に至る長い旅路を辿ってきたわけですが、それでもあなた方の中にはありとあらゆる蛆虫がまだいるのです。かつてあなた方は猿でしたが、今も人間は猿、少しはましな猿に過ぎません。そしてダンテが教え示してくれたように、人間自身が蛆虫であるのみならず、蛆虫に食い尽くされる――自らの感情や欲望や地獄の蛆虫に食いつくされる存在なのです。この蛆虫人間、猿人間、少しは猿よりマシな人間は、ドストエフスキーにより、スメルジャコフの中に嫌になるほど忠実に描破されています。
書物の中には何と貴重な宝物が秘められていることでしょう!何という精神の高み!私たちがこの世界にあるさまざまな物をただ欲するだけで、大旅行家たちに伴われて見知った風景、見知らぬ風景の中をモンゴロイドやニグロイドの土地まで旅して行くことも出来れば、インディアンたちと共に川を越えたり、ジャングルで鹿狩りをしたりもできるのですから。私たちは、フンボルトやフラマリオンやハーシェルと共に太陽や星まで上昇していったり、天の川の神秘の深みに有頂天になったりもするのです。他の著者たちと共に、遠い過去の世代についての知識を身につけたり、また別の著者たちの導きで地殻や山岳に分け入ったり、あるいは他の著者と共に水晶の信じがたいほど美しい生態に見入ったり、細胞の構造に驚き入ったりするのです。書物は海や砂漠、天空や星の神秘を探究し、その全ての知識を、キャラヴァンが支配者の足下に宝物を置くのと同じように、恭しくあなた方に差し出します。私といたしましては、たとえばとても独創的な人物であるシャーニカ氏のような、美しい本を愛好する多くの仲間たちと語らうことは楽しいことではあるのですが、それにもかかわらず(どうか信じていただきたいのですが)ヘルチツキーのキリスト者としての峻厳さとコメンスキーの平穏な叡智の方により深い感嘆の念を抱くものです。コメンスキーの『現世の迷路と魂の天国』を携えて、私は今の暮らしの迷路に入り込んで行きます。自分の蔵書に『安心の中心』を見出し、『隠者と聖人と修道士の生活』に敬虔な忍耐と粘り強い熱意を教えられるのです。
みなさんの中に本と共に生きていくことを望まぬ方がいらっしゃるでしょうか?薔薇の多い庭と蔵書に富んだ書斎は、詩人の理想にほかなりません。だからと言って、薔薇がいつも咲いているとは限らぬように、私たちはいつも本を読んでいられる訳ではありません。土壌が薔薇を覆い隠して、冬の寒さから守っているのと同じように、仕事が私たちを書物から遠ざけてくれているのです。なぜなら、愛情の深い女性が色恋を職業にしないのと同じで、真の本好きは自分の愛情を職業にはしないものですから。
私は多くの時間と愛情を本に捧げてきたので、本たちのことを良く存じています。何が良書か、最良の書物は何か、何を読むべきかと、もし尋ねられたとしたら、こう答えるでしょう――聖書、タルムード、コーラン、福音書、教父たち、マルクス・アウレリウス、エピクテトス、セネカ、アイスキュロス、エウリピデス、アリストファネス、クセノフォン、プラトン、ヴェルギリウス、ホラティウス、ルキアノス、オヴィディウス、パスカル、シェークスピア、ダンテ、デフォーの『ロビンソン・クルーソー』、セルバンテスの『ドン・キホーテ』、ゲーテの『ファウスト』、ロシア文学ではプーシキン、レールモントフ、チェーホフ、ゴーリキー、ツルゲーネフ、トルストイ、ドストエフスキー、我が国の文学ではシュチートニー、ヘルチツキー、フス、コメンスキー、コラール、シャファジーク、パラツキー、ヴルフリツキー、ブジェジナ。タゴール、ガンディー、ロマン・ロラン、チェスタトンを読んでくださいと。これらの書物に包蔵されている思想に出会って親しんだあと、もしそうしたいのだったら、新しい本を、最新の書物を読みましょう。それらの本を読み、理解し、出版するのです。そして図書館全体を、博物館全体を読破するまでになったなら、あなた方の人生行路を照らしてくれるであろう、人間のありとあらゆる叡智――信頼に足る先達にして保護者、助手、刎頸の友になってくれるであろう叡智――の精髄が宿った要約を作ることを自分に課しましょう。そうすれば、この叡智が次の二つの単語に要約できることを知ることでしょう――
祈りと労働
なぜなら祈りは精神の状態を、労働は身体の状態をあらわし、魂と肉体は全人格をあらわすのですから。
本は私たちにあらゆる事について語って聞かせてくれ、あらゆる事を教えてくれます。いつどこでも私たちの導き手となってくれるし、楽しませてもくれます。しかし本でも一つの疑問にだけは答えることができなかったし、今後も答えることはできないでしょう。それは人生の意味という古くからの、しかし永久に残る疑問です。「何のために私たちは生きているのですか?」と釈迦の弟子たちが尋ねたのですが、シャカは黙ったままでした。なぜなら、くだくだしい返答は拷問に等しいのですから。私たちが生きていることにどんな意味があるのか、とトルストイは自問し、それが自分の内側から来るにせよ外界から来るにせよ、答えを待ち続けました。では、我々は何のために生きているのでしょう?誰にも分かりません。本も知らないし、私たちも知りません。たぶん、自分たちの蔵書を読むため、それをよろこぶためになのでしょう。蔵書の中で智天使が私たちのこめかみに触れ、悦ばしい熱中の瞬間に、純粋な見識の深淵を――計り知れないほど深い、しかし明らかな深淵を――一瞬の間、私たちの心の眼には明かされるが、次の瞬間には閉ざされ闇に覆われてしまう深淵をのぞき見させてくれるのです。その後私たちは、太陽の下で行うありとあらゆる仕事から、人はどのような利益を得ているのだろうと問うのです。さらに私たちは、あらゆる存在の無益さを感じ、全ての物質が今にも壊れそうな恐ろしさに身震いします。それゆえ物質的な形をとった愛はすべて――女性に対する愛も、本への愛も、郷土愛も――物質化されていて重力によって落下するからには、痛みを与えるのです。私たちを無限にまで上昇させくれるのは、神に対する愛だけなのです。本は旅路、旅を愛するものは、道行くことを好みます。そして日が傾き、晩鐘の静かな声が谷に響く頃、歩き疲れた旅人は、一休みするための居酒屋を探すため進んで道を離れます。この後、しかし、高みへと導いてくれるこの道を離れ、本たちと別れを告げることになったら、と考えるだけで、私たちは悲しくなります。私の念頭にあるのは、十八世紀のロシアに生きた有名な愛書家スチェファン・ヤヴォルスキーのことです。彼は一七二二年に亡くなりましたが、「傑出せるリャザンの府主教ステパヌス・ヤウォルスキが死を前にして編んだ、自らの蔵書についてのエレジー」と題されたラテン語の詩を詠むことで、本に別れを告げました。こんなふうにです。
さあ行くが良い、再々この手で触れたる書巻たち!行け、我が光、我が奇跡、我が悦びよ!行くが良い!汝らは幸せ者、他者をしてその美を愛でさせよ、汝の香り高いネクタルを注ぎやれ。やんぬる哉、汝ら書巻を見やることの叶わぬ我がまなこは、もはや我が心を満たすことあたわず。往時、汝は全き甘露、蜂蜜、ネクタル――共にし暮らすことが、我が悦びなりし。我が富、我が名誉、我が偉業、我が桃源郷、我が愛、我が悦楽なりし書巻ら、この世の大いなるものに惹かれたるも汝らのお陰ならん。しかるに今や我に大いなる痛みあり。運命は許さじ、汝と共に一点の雲なき空のごとき幸いなる日々を送ることを。夜のごと、永遠の闇のごと、我がまなこは閉じんとす。我が手をもてなれに触れることも最早なし。もう一冊の書巻、永遠の書巻が我が目交かいに開かれ、読み始めんと神は我に望む。万人の言葉と行いが書き留められているこの書で、万人は己が美点とその報いを悟る。自らひもどきし書のおぞましきかな。あぁ、恐ろしき書巻よ、汝は審判者の前に自らを開き、全ての人の罪を明らかにする。この書について己が思案を凝らす時、我は身震いし、固い弾丸が心臓を引き裂く。神よ、我らの父よ!至高の愛の深淵よ、慈悲の山よ、敬神の泉よ、善の頂よ、さらに未来の水に軛を課し、賢明に星辰の環を操る海陸の支配者たちよ、最高峰の支配者たちよ!汝にあたわぬ蛆虫、御前では取るに足らぬ空虚な蛆虫なれど、乞い願わくば生の書を一覧し、キリスト教的博愛のゆえ我が名と我が生とその救いをそこに書き記せかし。だらば、我が写本、我が書巻、我が蔵書。我が手の働きによって作りあげてきた汝らに別れを告げよう。ごきげんよう、市民たちよ、国民たちよ、同胞たちよ、兄弟たちよ、長老たちよ。母なる国よ、やさしいあなたに別れを告げよう。さようなら、そして我が身を抱きたまえ、我が魂を神に委ねたまえ。
十八世紀ロシアの愛書家スチェファン・ヤヴォルスキーは、このようにして本と分かれ、理性と美と愛と内面の幸福と平安、徳育の道が全て本へと至ることを、そして本からは一本道が、天国にまで伸びていることを、示してくれたのです。
どうかお元気で!
