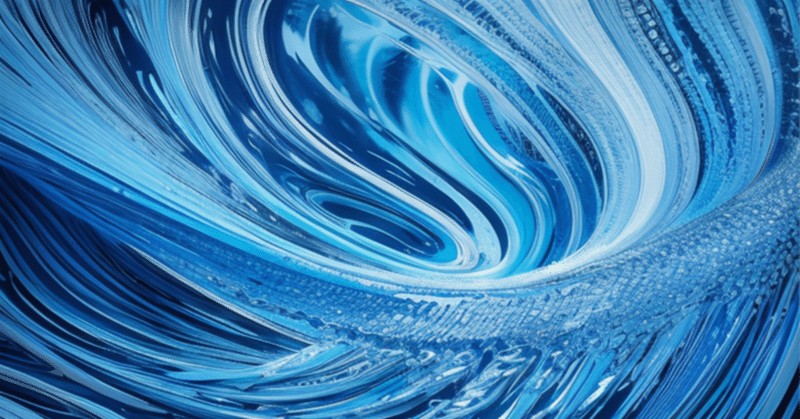
教科書を使って歴史の授業をする
「世界史B」が廃止され「世界史探究」となった高校指導要領改訂の中で、授業の時間数は減少しました。また内容についても細かな知識事項を網羅することではなく、それを通じてテーマを設定して考えることに力点が置かれています。
「世界史探究」の教科書は、古代→現代の順に記述されています。世界史は、一国史である日本史とは異なり複数の国と地域の歴史を追う学問であるため、教科書の記述も当然複線的になります。そのため、何を、どの順で配置するか、またどこで区切って別の歴史を語るか、が重要となります。
旧指導要領(「世界史B」)においてはこの流れが定められており、教科書各社における差もありませんでした。しかし新しい指導要領は「生徒の興味関心に応じて」内容が変動しうる指導要領であるため、教科書での掲載順序・区切りの位置が会社によって異なる事態が生じています。
このことが世界史教員の中で、大きな議論とならず、「世界史B」からなめらかに変化しているように見えるところが、注目に値します。なぜ、全国の世界史教員は教科書の根本的な構造の変化に、これほど無反応でいられるのか。おそらく、日本の世界史教員のうち、教科書をベースとした授業を展開している割合は、決して多くないからでしょう。多くの教員が自前のプリントに基づく講義を展開しており、教科書は辞書的な活用に留まったり、中には使用しない授業があったりする実態があります。
かつて全国研究大会の授業者として協議を行った際に、私が授業で教科書を使用していたことに驚きをもったフィードバックを受け取ったことがあります。そこでの議論で見えてきたのは、世界史教員の間では、教えるべき語句・概念がチェックポイントとして共有され、それらのチェックポイントをどのように経由して講義とするかは教員の個性の発揮として理解されているということでした。語句・概念のチェックポイントをトークに含みながら、よどみなく話せるように”筋書”を設計し、それを一部ワークシート化して教材とする。世界史教員の多くにとっての「授業準備」とは、このようなトーク設計を指すものでした。「授業準備」がこうした「教員にとってよどみなく語れるストーリー作り」として受け取られている限りにおいて、それ自体に物語性を持つ教科書は使いづらい書物であり、辞書的に文言を確認したり、写真や図表を確認したりする「参考書」としての用法に限定されます。
また、歴史教員の中には、国の検定済み教科書を用いることへの抵抗感も少なくない。歴史教科書の記載を巡る圧力や、歴史修正主義に基づく「新しい歴史教科書」を標榜する団体の活動は、既にその問題が指摘されて久しいものです。歴史教科書の記述は、何を掲載し、何を掲載しないか、どのように記載するかを巡って、政治的問題となり続けています。そうした問題に対しての意見表明として、歴史教員の中には教科書の記述内容に立ち入らず、むしろそれを相対化する人もいます。「歴史の解釈は1つではないから、教科書を信じてはいけない」と指導しつつ、その教員の歴史観に基づくストーリー展開を(歴史解釈の1つの例とすることで)正当化する手段を取る人もいます。教科書の歴史観と教員の歴史観を踏まえ、最後は生徒が自分の歴史観を形成するんだよ、と促すわけです。
私は、教科書検定や歴史修正主義の諸問題を十分に認識しつつも、教科書の相対化は生徒の学びに困難をもたらすと考えています。ほとんどの生徒にとって、教科書は手元にある唯一の体系的な教材であり、自学自習を進めるうえでの羅針盤となるものです。
地歴公民科の特徴として、すべての教授内容があらかじめ書物として生徒の手元にある点が挙げられます。例えば、国語や英語の教科書には、文法や語句の解説を伴いつつ、教材である文章が記載されています。それらの理解・解釈は授業で行われますが、その内容までは記載されていません。数学や理科については、その教授内容は(網羅的ではないが)全て掲載されているものの、それらが一貫した論理的文章で記述されているわけではありません。地歴公民科においては、一冊の書物として生徒に教科書が与えられており、理論上は生徒が授業を受けずとも、その内容を予め学ぶことが可能です。世の中の大人たちに向けて、地歴公民科の教科書を一般書として編みなおした「もう一度学ぶシリーズ」が一定の人気を博しているのも、一人で読破できる書物であるためです。
ここにおいて、地歴公民科の授業の新たな側面が見いだせます。自分で読めば分かる一冊の書物を、あえて生徒と教師とが持ち寄り読解する営みが、授業なのです。極端に言えば、「授業とは輪読である」ともいえるでしょう。共通した一冊の書物を読み、解釈を巡って意見を交わす輪読は、視野の異なる他者や、理解度の異なる者どうしの対話を伴いつつ進行します。教師から生徒への一方的な教授とは異なり、時には生徒が新たな解釈を発見し、知の地平を切り開くことも、輪読が持つ可能性の1つです。
このような授業観に立つと、教科書を「信じてはいけない」と相対化したり、参考書扱いにするなどして活用しなかったりすることは、「輪読」を不可能とし、学びを困難にする方針であるといえます。教員が”筋書”に基づいて講義する授業は、いかにそのトークが面白く、またよどみなかったとしても、そこには学びの共同性はなく、授業は伝達へと変質します。生徒に「○○先生の授業が面白い」という印象を持たれても、それは学びが豊穣であったかどうかとは異なる評価軸の話であるわけです。
教科書がその背景に政治的問題を持つという認識を述べました。「輪読」を授業の本質であるととらえれば、政治的問題を持つからこそ教材としてふさわしい、という見方も可能になります。前述のとおり、「輪読」は視野の異なる他者や、理解度の異なる者どうしの対話を伴います。そのような対話の場においては、教科書の記述を額面通り受け取ることよりも、むしろ論争的な主題を認識しながら、多角的な分析をすることに向かいます。既に歴史教科書の記述を巡る報道や意見表明は広く行われているため、生徒たちもそれらの事実を踏まえたうえで授業に向かっています。読む生徒のバックグラウンドによって、また読む生徒が生きる世相によって、そして生徒集団の構成によって、教科書の読解は変動する。それが、一人で教科書を読んでは得られないダイナミックな学びであり、授業の意義です。
ここにおいて、教員の歴史観は教室という共同体における1意見としての役割を持ちます。「教科書と教員の歴史観を併置し、生徒がそこから新たな歴史観を持てばよい」という発想は、教員の歴史観を過度に特権化しています。なぜ、生徒は教員の歴史観をスタート地点として学ばなくてはならないのか、どこにも正当性はありません。教員が教科書の歴史観を拒絶することが、教員が持つ歴史観を肯定してくれるわけではない。それにもかかわらず、教員が自ら用意したストーリーを、その妥当性を裏付けないまま生徒たちに伝達するとすれば、それは歴史観の「押し付け」に他ならないでしょう。
教員と生徒の間には知識・経験の大きな開きがあり、そのことが教員を教員たらしめています。授業の前提は、生徒たちがこれから歴史を学ぶ、ということにあるのであり、歴史観を受け入れるかどうかの判断についても、学習中の間は十分にはできないという前提を持たねばなりません。そのため、教員の展開するストーリーの歴史観を受け容れるかどうかについてだけ、生徒に成熟した判断を予め求めることは、授業の前提を無視しているという見方もできます。
ここまで、地歴公民科の授業(特に歴史)において「輪読」が授業の意義であることを整理しました。そのような授業観に立つと、教科書は輪読する共通の書物であり、教員と生徒とが対話を通じてその解釈を深め、批判し、歴史を学んでいく下地の役割を果たしているといえるわけです。
この発想は、それでもしばらく少数派のままでしょう。受験に出る知識をチェックポイントとして網羅した先生のトークによる授業は、一度準備したらその後は微調整で済むという簡便さから、なかなか駆逐されるものではないでしょう。1人の教員が仕事をする数十年間の中で、ウナギのたれのように微調整を継ぎ足した古式ゆかしい講義を続ける限り、教科書の変化は対岸の火事としての受け取られ方をするものではないわけです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
