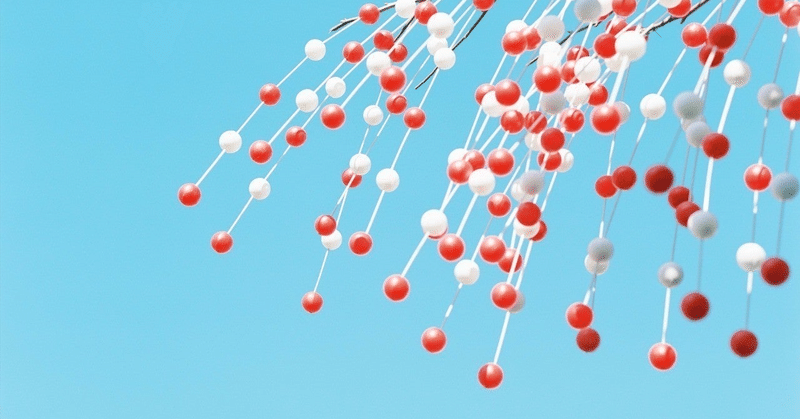
ツバメの来る日 第9章 正月の見合い
(前章までのあらすじ~ 一方、母親が由美に手紙を出し、息子と会ってほしいと頼んだと知る。青木は母親を批判し詫びの電話を由美に入れる。由美はまた電話をくれという。やがて母親は病気で入院し、青木は病気が突飛な行動の原因だったのかと思う。また電話すると由美は彼氏と結婚すると言う。青木は片恋の終わりを感じる。その反動か、万里と電話のやりとりをする。秋山は高齢の母親が入院し、心を痛める。加えて友人が交通事故で死亡し、右往左往する。実家の縁談を聞き流す。相談所のクルージング・パーティに参加するが、東京湾周遊で女性より風景の方が印象的に感じる。
しばらく由美への追慕にとらわれる。妊婦姿の由美が目の前に現れ、息の止まる思いがする。福祉課の元の女性課長が退職の涙を流すのを見る。万里に電話し、最近結婚したことを知る。二重の打撃でうつむく日々が続く。実家の縁談で相手のことを聞き、会ってみる気になる。パリ事務所勤務の打診を受けるが、失恋の痛手で気が進まずに見送る。相談所のパーティに参加し、社長秘書の女性と気があったが、電話の連絡が付かなくなりデート前に断られる。)
正月、青木は打合せの通り久美子と見合いした。8才年下の容姿の良い女性と思えた。
近頃、見合いでは緊張して、コーヒーカップを持つ手が震えてしまう。それで、早めに待ち合わせのレストランに行った。
「青木さんですか?」
久美子が元気な声で聞いてきた。さばけた感じだった。
青木をなんとなく自然に受け入れている感じがした。自由恋愛であんなに苦労したのに、見合いで簡単に話がまとまってしまうような気がする。
仲人の事前の話では、久美子は都心のブティックに勤めている。両親とも大卒で、娘を東京から地元に戻したいらしい。
青木の車に久美子は乗った。隣町の地元では有名な神社に初詣でしてから、近くのレストランに回り、秋山とよく行く喫茶店に入った。
久美子は、デートの時、自分から帰るとは言い出さなかった。
ブランド品志向なのか、流行の香水をつけていた。青木がうろ覚えで尋ねた。
「プワゾンですか?」
「サンローランです」
久美子は、さらりと答えた。
毛皮のコート、ミニのワンピース、ハイヒール、スカーフと行った出で立ちで、おしゃれだった。
結婚相手の条件には、健康であること、賢いこと、温和であること、付き合っている相手がいないこと、などが挙げられる。今年あたり久美子と結婚してしまうのも、悪くないかと、ふと思う。万里の事件の冷却期間も過ぎないうちに、そんなことになってしまうのか。
青木は珍しく、また会いたいと、母に返事を出した。
向こうが断れば終わりだ。しかし、青木の親も先方の親も乗り気のようだ。
青木は思った。久美子は、初めての見合いの相手にどうして、あんなになじんできたのか。久美子の魅力に惹かれていきそうだ。健全な家庭に育っているような気がする。
久美子の母親は、久美子の東京の電話番号を教えてきた。
夜の10時半に、青木は自分の母にせかされて、久美子に電話した。デパート勤務で、水木曜が休みになり、今まで地元には月1回帰っている。仲人の話では、久美子もとりあえず付き合うつもりらしい。
間違い電話がかかった。怪電話ではない。名を言われて、違うと答えた。まさか久美子ではないだろうと思う。
久美子は、気の強い一面も見せるが、こちらの心証を害するほどでもない。
そう思いながら、青木は感じる。また今度も、女性との間で男女の駆け引きが始まっている。かつての万里とそうしたように。
苦笑いしながら思う。人生って面白い。青春て最高だ。世の中はうまく行かないが、そこが面白い。
青木は、この月末、仕事で中国地方に行く予定でいる。その時、東京で会いたいと思っていることを、久美子に伝えたかった。しかし、電話は留守だった。久美子の留守録に用件を入れた。
そのうち、仲人から実家に電話があった。交際はどんな具合かと。母が職場の青木に電話してよこした。
東京と地元はは少し離れている。1月は双方とも仕事が忙しい。休日がすぐには合わない。そう話すと、母は、自分から休みを取って会いに行ったらいいという。青木は確かにずっと残業している。
その日、雪が結構降っていた。
久美子には、また電話したが留守電だった。
こんな時でも、怪電話が鳴った。こちらが出たら切れた。その後の祝日、仕事休みの日、夕方また、怪電話。こちらが出ると切れた。
久美子は、何度電話しても留守電になっている。
青木は久美子の反応が気になって、彼女の母親に電話した。
「夜分失礼します」
「どうも、この度はお世話になります」
「あのう、ちょっとお聞きしたいんですが、久美子さんは、お付き合いしている人はいるんですか?」
「そういう人はいません」
「何度か電話したんですが、なかなか出ないんです」
「それは失礼ですね」
母親は電話の向こうで苦笑いしたようだった。
「余り見込みがないようだと、僕も考えてしまいます。僕のこと、どう言っていましたか?」
「写真と違っていい人だったと言っていました」
「僕は、どこといって悪いところのない、いいお嬢さんだと思いました。一応オーケーのお返事だったので、何度かお付き合いしてみたいと思っています」
「すぐに結婚がどうのとかにはならないとは娘にも言ってあります」
「僕も同じ気持ちです」
「ただ1つ問題がありまして……。久美子は、東京に未練があるんです」
「はあ、都会の生活は色々と面白いから、僕も学生時代は東京に住んでいましたから、その気持ちは分かります」
「大した仕事、やっているわけでもないのに、帰りが遅いんですよ」
「そうですか。どうも、もし余り反応が鈍いようだったら……」
「その時は、押しの一手ですね。私は女だから分かります。悪からず思っている人から強く押されると、女の心は動きます」
「お母さんにそう言われても困りますねえ」
青木は電話口で笑った。頭の片隅で、もし彼女の気持ちを得られたら、少なくとも母親の承諾を得るために苦労することはなさそうだと思った。そう言えば、うちの母親も、同じようなことを言っていたな。
「久美子さんは、東京でいい人見つからなかったんですか?」
率直に聞いてみた。
「実は、学生の時にお付き合いしている人がいたんですよ。尊敬できると本人も言っていました。結婚も考えたようでした。でも、相手方に障害者の人がいて、後々のことを考えて諦めたようなんです」
「僕も今まで色々ありました。好きになったり、好きになられたりしました。それで、最近、好きだった人に結婚されてしまって……。まあ、今回のお話は、乗りかかった船だから、やることはやろうと思っています」
「私どもも、結婚して3年くらい東京に住んでいて、こちらに戻ったんです。この前、久美子には、ちゃんとお付き合いしなさいと言っておきました。話題がない、なんて言ってましたけど……。明日、東京で知人に会うから、その時に久美子の所に行ってみます。もう一度電話してもらえませんか?」
その後、青木は、今日は仕事は休みだろうと思って、久美子に電話を入れた。
「今食事中だから、後でいいですか?」
そう言われて、電話を切って待った。しかし、1時間経って電話しても、いくら呼んでも出なかった。
そんな電話のやりとりで、万里のことを思い出した。万里は、最終的に残念な言葉を送ってよこしたが、電話の受け答えは礼儀正しかった。しかし、久美子はイエス・ノーがはっきり言えないらしい。
この人生で、女でこんなに苦労するとは思わなかった。気持ちを整理する暇もなく、別の女に心を移していく。気持ちのやりとりは機械的に運んでいかない。
一方、見たばかりのテレビの番組を思い出した。中東では、湾岸戦争で人々が血を流している。自分は日本列島の片隅にいる。恋愛の悩みは贅沢で幸せな悩みだ。
その後、青木の母親は電話をよこした。出張するんなら、久美子とその母親に贈り物にブローチでも買って来たら良いという。青木は久美子の母親と自分が話したこと、久美子があまり乗り気でないことを伝えた。
久美子が望むなら、青木が東京に住んだらどうかと、母親は事情を適切に理解しているのかどうか、訳の分からないことを言った。住む場所を変える必要があるのか。そこまでしても、その先にまた別の問題があるかもしれない。
やっと久美子と電話で話すことが出来た。今度、中国地方に羽田空港から飛行機で出発すると伝えた。前日の晩、都心のホテルに泊まり、久美子と会うことになった。
ふと久美子と男女関係を結ぶことを想像する。良心に背くようにも感じるが、万里を忘れて、久美子を好きになることも出来る。
恋の悩みは贅沢で幸せだ。最近、遠くの中東では、武力攻撃で人々が殺されている。連日の報道は、そればかりだ。自分の私生活と世界情勢はかけ離れている。
その後、出張の予定が早まり、久美子に連絡したが、向こうの都合は無理だった。そこで後日、出張の後に東京で待ち合わせる場所と時間を決めて、留守録に入れておいた。すると、久美子が10時過ぎに電話をよこした。突っ慳貪な話し方だった。待ち合わせの場所に、ある喫茶店を提案すると、別の喫茶店を指定してきた。
約束の日に青木は上京し、久美子とあった。出張先で買ってきたプレゼントのブローチを久美子に渡した。夕食に繁華街でしゃぶしゃぶ料理を選んだ。鍋をつつくと、青木は2人が夫婦みたいな気がした。失恋の心の整理もできず、新しい女性に心を移して行く自分を感じた。
その数日後に、久美子に電話した。
「今、お風呂に入っているから、後でいいですか?」
数日後、午後、久美子の母親が断りの返事を伝えてきた。
青木はその日、仕事に走り回り、早めに帰宅した。実家に行って様子を聞いた。父母は、期待していたのか、落胆して大騒ぎしていた。
出張先で、仲人と久美子と久美子の母親へのプレゼントを買ってきた。それを青木の母親が仲人の所に持って行った。
「実は、だめなんですよ」
と、そこで言われたらしい。
青木は、事実を自分で確かめるため、久美子の母親に電話した。
「本当に申し訳ありません」
電話口で頭を下げているのかもしれない、と青木は想像した。
「青木さんのどこが悪いと言うことではないって。ただ、東京に住んでいたいと娘は言っているんです」
「そうですか。僕も内心で、いつ断ってくるのかと思っていました。久美子さんは、僕と会っていても、楽しそうじゃなかったですからねえ。東京の生活が染みついているように見えました」
「長引かせると悪いからって言ってたんですよ。友だちも結婚していないし、まだ焦りがないのかもしれません」
青木は思った。また、だめだった。何がだめなんだろう。
気の進まない久美子と会っても仕方がない。中途半端な相手で妥協せず、やはり本当に自分の望む女性を見つけるべきだ。
青木は思った。久美子には、そのうち偶然再会することもあるかもしれない。
終わってしまったが、2回のデートは楽しかった。今までの見合いと違って、この人も1つの選択だと自分が思えた。
元々、強い執着はなかった。あの無口で無愛想な久美子と、これ以上デートする気にはなれない。あの素っ気ない電話の受け答えに、これ以上付き合う気にはなれない。
久美子は元々結婚する気もないし、地元に戻る気もなかったのかもしれない。それでも、親に言われて仕方なく見合いしたのだろう。
由美と万里に続く傷心の連続。落胆の恋愛遍歴。激動の時代。恋愛の激流に飲み込まれて、押し流されていく時代か。
後日、青木は久美子の職場のデパートの売り場に行き、久美子の顔を見つめてきた。前日、母から、久美子をもう一度押してみてはどうかと言われたからだった。
眼鏡をかけた久美子は近くに行っても、視線を合わせようとしなかった。他の女子店員よりきれいだった。諦めるべきか、追うべきか。
その後、私鉄に乗って、自宅のアパートを見てきた。彼女の言ったとおり、親戚の寿司店の3階だった。入り口の表札には、弟の名も書かれていた。男の名を書いておけば、防犯のためになると言ってた。
そこにはやはり、都会の慌ただしさがあった。彼女は、自分との束の間の心の交流は忘れたのだろうと感じた。
自分は今、出来事の終わりを自分の目で確かめているんだなと思った。久美子の母親とは別れの言葉を交わしたが、本人とは交わしていない。
帰宅してから、久美子本人に電話して、直接別れのあいさつをした。
「先週、返事が届いたようで……、やっぱりだめだったんだ?」
「すみません」
「そっちで頑張るわけ?」
「ええ」
「もう返事は来ちゃったんだけど、一応、あいさつしておこうと思って……。一昨日だったか、職場に行ったんだよね。じゃあ、この頃寒いから、体に気をつけて」
「本当にどうもすみません」
「さよなら」
それ以上、余計なことは言わなかった。これも恋、1ヶ月の恋だった。
12月中旬、また都心のホテルでクリスマス・パーティーに、青木は出席した。
立食パーティーで顔を見知っている男性会員と再会した。
「活動の方は、うまくいっていますか?」
青木は尋ねると、その男は小声で言った。
「ちょっと、そのう、2,3人と付き合ってしまって、その場の雰囲気で、ちょっと関係が進んだ人がいたんですよ」
「ええ? そんな付き合いは、あまり良くないんじゃないですか?」
「ええ、それは、相手も分かっていたと思うんですが……」
「進んでしまったんですか?」
「まあ、進んだ人もいて…。でも、こちらも、気持ちが固まらなくて…。そうこうしているうちに、他の人とも出会ってしまうんじゃないですか?」
「まあ、その気になれば、持てる人だと相手を持て余すかもしれませんね」
「そうなんですよ」
その男は、確かにハンサムで、女性たちの目をひきそうだった。
「それで、男と女の関係になってしまったわけですか?」
「まあ、そんなところです」
「そういう女性が、パーティーの中にも混じっているんですね」
男は黙って頷いた。
「そしたら、その女性が僕のことを不誠実だって言うんですよ」
「はあ」
青木は、あきれて苦笑いした。
「会の方に連絡してもいいんですかって、聞くんですね」
「要するに、悪く言えば遊ばれたって言うか、傷つけられたというか、そういう意味ですか? 」
「まあ、そんな感じで…。まあ、不誠実ってことになると、退会させられるでしょう? でもねえ、向こうだって、子どもじゃないんだから、そんなこと言われてもねえ。それは、男と女だから、色々ありますよね。会に言うって言ったって、自分だって恥をかくわけじゃないですか?」
「それは、持てる人の悩みですかね。確かに、同時に複数と交際してもいいということには、最初からなっていますからねえ。多くの出会いを会で見つけてくださいって触れ込みですから……」
男は困り顔をして、そのうちパーティーの会場の他のテーブルに行ってしまった。
青木はとりあえず、このパーティーでは2,3人希望し、その中のひとりが向こうからも希望してきた。
初めて電話で話すと、昭子は快活に言った。
「あたし、希望が来るとは思わなかったから、うれしかったんです」
駅前で待ち合わて近くの大きな公園へと歩いた。それから、子どものように動物園の中を見て回り、お好み焼きを一緒に食べた。
昭子は生まれも育ちも東京だった。
「父が転勤で関西にいて、時々遊びに行きます」
目が大きくて、時々きれいだと思える表情を見せた。ほっそりした体つきで、町の中を歩いていれば、魅力的に見える女性のひとりかも知れなかった。おっちょこちょいで、陽気だった。
甘えん坊で、年齢のわりに子どもっぽいところはあったが、自分と同じ33才という年齢が、青木にとって難点だった。
しかし、一日中、ふたりで楽しく遊んだ気がした。
2週間、間をあけて、今後のことを迷いながら電話してみると、昭子も迷っている様子だった。
「青木さん、あまり気がなさそうに見えたから、また会うのは考えたいんです。毎週、電話してくる人もいて、今まで、その人と何度か会ってるんです」
「僕は、自分の気持ちが本気になれないのは、確かだよ。その人は、その気があるんだろうから、大切にした方がいいな」
電話口でも、昭子は明るく元気で、よくしゃべった。あと一押しすれば、青木についてきそうな気配だった。
「最近いろいろあって、疲れちゃって。33才は、もう若くないよ」
青木は、由美や万里に翻弄された過去を重荷に感じていた。
「男の33才なんて、まだまだじゃないですか。同じ年の女のあたしがこんなに元気なのに…」
世間話はいつまでも続けられるが、結論は出さなければならない。
「やっぱり、おれ、だめだと思うから…」
「ええ、でも、残念」
「また、パーティーで会えるといいね」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
