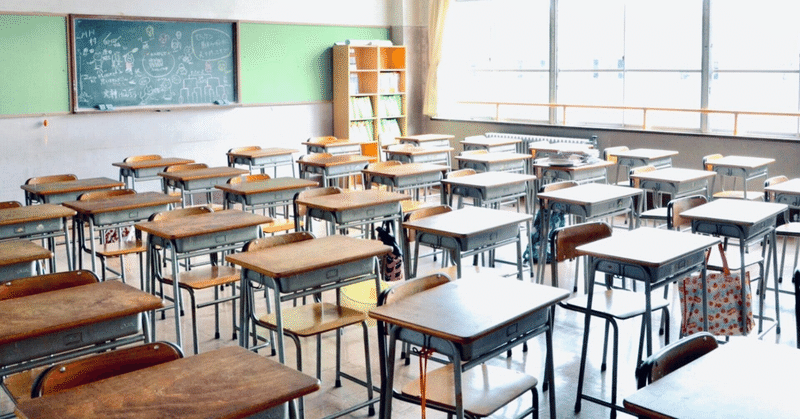
心がエリートな人とは
人は成長するにつれ、価値観だったり志すものだったり、自分と何かしらの共通点を持った人と人間関係を構築していくものだ。そうでない場合であっても、まあいずれにせよ自分で関わる人を選べるようになってくる。
一方、幼馴染とは家族のように血が繋がっている訳でもない上に、自分で選んで関わり始めるような存在でもない。
人格形成が十分にできていない時期から「たまたま生まれ育った場所が同じ」というだけで関係が始まるのだ。
だからこそよく喧嘩をするし、簡単に疎遠にもなる。それだけ不安定な関係性だと思う。
こうした幼馴染ならではの関係性の特殊さを描いた、映画『クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園』を少し前に視聴した。
あらすじ:
全寮制の超エリート校「私立天下統一カスカベ学園」通称・天カス学園に1週間体験入学する事となったしんのすけ達。体験入学時の成績や生活態度により"エリートポイント"が溜まると、正式入学ができるシステムになっている。風間は密かにこのシステムを利用して、全員で正式入学することを目指していた。しかしそのような風間の目論見も知らずに足を引っ張るしんのすけ達に風間は苛立ちを抑えきれず、大喧嘩の末に寮から飛び出してしまった。しんのすけ達が探しに行ったところ、ある怪事件が起こる。
この作品は、エリートになりたい風間と、そうでないしんのすけ達が将来確実に訪れるであろう環境の違いを、サザエさん時空ながらも"体験入学"という形で垣間見せてくれるものである。
風間は絵に描いたようなエリートである。
小学校のお受験を控えており、複数の塾に通うほどの英才教育を受けており、まあ恐らくこのままいけば普通に東大とかに行くのだろう。
一方、しんのすけは全くエリートじゃないどころか大問題児で、将来どういう人間に育つか全く検討もつかない子供である。
かすかべ防衛隊の中でも、風間としんのすけは最も対照的な2人であり、おそらく育った環境が異なっていれば一生交わることはなかっただろう。
そのことに風間自身も5歳児にして自覚していて、卒園後の関係性に危機感を感じていたのだ。
■エリート街道を突き進むということ
風間が感じている不安とは、単にお互いが別々の道を歩んでいくことだけではない。
自分が歩んでいく「エリート」というガチガチに敷かれたレールにしんのすけが付いてきて来なくなることに対する不安だ。
エリートとはある意味最も分かりやすい人生の歩み方である。ひとたびレールに乗っかって努力し続けられさえいれば、ある程度は自分が予想していた将来の通りに進んでいくことができる。
すなわち、本作の風間の願いはこういうことだ。
「しんのすけも頑張り続ければエリートになれて、将来が約束されている。そうすれば幼稚園を卒業してもずっと一緒にいられるのに」
敢えて強調しておきたいが、風間の感情は「自分のようなエリートでないと関わりたくない」といった選民思想的な発想ではなく、ただただ「しんのすけともっと一緒にいたい」というピュアな感情に過ぎないことが重要である。
ここに幼馴染が疎遠になるか否かの分岐点があると私は考えている。
▫️異なるレールでどう歩むのか
互いの環境が次第に変わっていきながらも、時には交わっていけるにはどうすれば良いのだろうか。
違いを受け入れて、相手が歩んでいくレールならではの景色を自分も楽しめば良いのだ。
つまり、自分のレールに交友関係を縛られたり、損得勘定で人を判断しない心が大切である。
人は大人になると生きていくことに必死で、「何者かになりたい」といった願望が強くなるあまり、「今の自分に利益をもたらすか」といった価値基準で交友関係を築いてしまいがちだ。
一方、しんのすけはヤンキーだろうがギャルだろうがインテリだろうがしんのすけには関係ないのだ。一緒にいて面白ければそれで良いし、もはやその面白ささえも、しんのすけは自分で見出すことができる。
このように立場や肩書きに囚われすぎずフラットに人と接する姿勢こそ、成績などだけでは判断できない真の意味でのエリートと言えるし、風間がしんのすけを評価している所以だろう。
それはエリート校では必ずしも得られるとはかぎらないし、むしろエリート街道を突き進むほど見失ってしまうかもしれないと考えているからこそ、本当は心がエリートなしんのすけについてきてほしかったのだ。
幼馴染はひとたびレールが違ってしまうとそのまま疎遠になってしまいがちだが、風間としんのすけのように、自己の相互理解を持てると、時に離れながらもふとした時に交わることができるだろう。
風間は初めての経験だから、このまましんのすけと疎遠になってしまうのではないかと危惧しているが、我々視聴者が安心して見ていられるのは、彼らは大きくなっても、損得勘定に縛られずに互いが自分にない価値観を楽しめる人間性を持ち続けられると確信できるからだろう。
もちろん、無理に仲良くし続ける必要は無いと思うが、「自分は相手の個性にどれだけ歩み寄っ
ているか」「変なフィルターを掛けていないか」を意識できると人として一歩成長できるのではないか。
「幼馴染」とは、このような人間関係の出発点であるにもかかわらず、その大切さに気づかず、手遅れになってしまうことが多いのだ。
私も幼馴染を始めとした友人たちと末永い仲でいられるよう、時には失敗しながら正面から向き合っていき、本当の意味での「エリートさ」を磨く努力を惜しまずに生きていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
