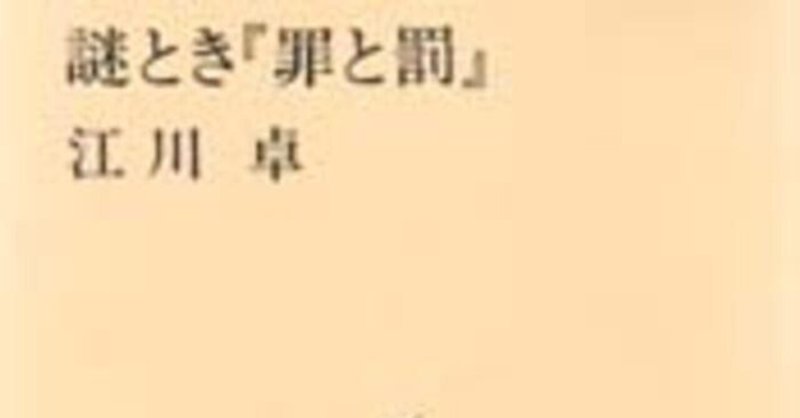
「哄笑する人形師の影」 江川卓『謎とき『罪と罰』』
■江川卓『謎とき『罪と罰』』1986年2月20日・新潮選書。
■¥880。
■長篇評論(ロシア文学)。
■1986年度讀賣文学賞(評論・伝記賞)受賞。
■①1987年11月18日読了、②1992年10月19日再読了、③2021年12月30日三読了。
■採点 ★★★☆☆。

1 ドストエフスキー像を一変
本書を始めとして江川卓のドストエフスキー論の卓抜さというのは、ドストエフスキー像を一変させてしまったことにある。すなわち、従来、借金取りと原稿の締め切りに追われて、書き殴った、悪文の見本のような作品だという見方を、それとは全く正反対で、一文、一語疎かに出来ぬ入念な執筆による原稿なのだと明示して見せたのだ。
題名にもある「謎とき」の「謎」というのはひとえに、そこにかかっている。ドストエフスキーの書いたテキストの、その語、その表現は何故、それが選ばれているのか、何故、そう書かねばならなかったのか。一見無意味に思える言葉、言い方、表現にも重大な意味があるというのだ。
2 「ナスーシチヌイな仕事」とは何か?
例えば例を挙げてみよう。江川が第1章の冒頭に掲げた例である。『罪と罰』の冒頭に次の一節がある。
彼(引用者註・ラスコーリニコフのこと)は貧乏に押しひしがれていた。だが近頃では、この窮迫した状態ですらいっこう苦にならなくなった。自分のナスーシチヌイな仕事もすっかりやめてしまい、どだいその気がなかった。( [江川, 『謎とき『罪と罰』』, 1986]p.15・下線部引用者)
さて、問題なのが下線部を引いた「ナスーシチヌイな仕事」である。江川本人の訳本では「アルバイト」になっている( [ドストエフスキー フ. ミ., 『罪と罰』, 1867]江川訳,上巻,p.8)。この「ナスーシチヌイ」という形容詞の元の意味は「その日その日の」、「しなければならない当面の」ということなので、学生、と言ってもラスコーリニコフは元学生だが、その彼にとっては「アルバイト」という和訳が間違っている訳ではない。試みに他の訳者のものを比べてみよう。
① 「その日その日の当面の仕事」(米川正夫訳・1951年・新潮文庫・上・p.6)
② 「アルバイト」(江川卓・1966年・旺文社文庫・上・p.8)
③ 「毎日の自分の仕事」(工藤精一郎訳・1978年・『ドストエフスキー全集』7・新潮社・p.7)
④ 「毎日のさしせまった仕事」(亀山郁夫訳・2008年・光文社古典新訳文庫・1・p.10)
こう見てくると、江川の訳が一番日常的な訳語になっている。『罪と罰』の和訳は江川によると全部で10種にも及ぶ( [江川, 『謎とき『罪と罰』』, 1986]p.294)ということなので、それらも検討せねばならぬが、今わたしの手元にあるのは先の4種なので、一旦、これで議論を進めて行こう。いささか問題なのが、江川自身の訳本が実は3種類ある*[1]ことで、これも含めて後日にはなるが確認せねばならない。
さて、何故、江川は、この「ナスーシチヌイ」に首を捻らねばならなかったのか。それは「この「ナスーシチヌイ」という形容詞が、日常にはめったに使われない、ほとんど文語的な語感をもった言葉だ」からだ( [江川, 『謎とき『罪と罰』』, 1986]p.16)。そこで江川は「マタイ福音書」の「われらの日用の糧を今日も与えたまえ」という一節に着目する( [江川, 『謎とき『罪と罰』』, 1986]p.16)。ここで出てくる「日用の」という言葉がロシア語では「ナスーシチヌイ」なのである。ということはこういうことにならないか。
いまのラスコーリニコフは、 この言葉で表わされる「日用の糧」をかせぐ仕事さえやめようとしている。これは彼が、自身の幼時体験、無意識のお祈りの世界をも振り捨てようとしていることを意味してはいないだろうか。ドストエフスキーは、あえて聖書起源のこの言葉を使うことで、言外にそのことを暗示したかったのである。 ( [江川, 『謎とき『罪と罰』』, 1986]p.16)
ドストエフスキーが例のシベリア流刑時代に深く『聖書』を耽読したことは広く知られているが、それのロシア語版の問題になると、一般の日本の読者には生中なことでは、作家の真意に辿り着くのは難しいが、江川によれば、恐らくドストエフスキーの作品全編に渡って、同様な言葉の選択の配慮がなされているというのだ。
3 ラスコーリニコフの名前の意味とは?
先に挙げた例は、あるいはロシア人であれば、ああそうそう、と簡単に理解できるものかも知れない。しかし、次の例は、ご存知の方も多いかもしれぬが、恐らく、ロシア人も気付かなかった、江川卓独自の発見のようである。 それは『罪と罰』主人公と目されるラスコーリニコフの名前に込められた意味についてである。
ドストエフスキーが自身の作中人物の命名に、或る意味では戯画的な意味を込めたことは、本書でも述べられているが、では当のラスコーリニコフはどうか。彼のフルネイムは「ロジオーン・ロマーヌイチ・ラスコーリニコフ」という。まず「ラスコーリニコフ」という名字は「ラスコーリニキ」すなわち1666年にロシア正教会から分裂した「分離派」を意味する( [江川, 『謎とき『罪と罰』』, 1986]p.38)。これは動詞「ラスコローチ」(割裂く)に由来する( [江川, 『謎とき『罪と罰』』, 1986]p.40)。したがって、彼は名前の中に「分裂」という主題を掲げ持っているのだ。従って、彼には「割崎」なる日本名が与えられる( [江川, 『謎とき『罪と罰』』, 1986]p.39)。
さて、問題になるのが、創作ノートの段階ではワシーリーという名前が第三稿になって、それが、現行の「ロジオーン」に改められた( [江川, 『謎とき『罪と罰』』, 1986]p.47)。一体そこにどんな理由があったのか。「ロジオーン・ロマーヌイチ・ラスコーリニコフ」をロシア語の表記にすると「Родиoн Романыч PасколЪников」となり、イニシャルは「PPP」である。ロシア語のR音はPで表される。これを逆転して後ろから見ると「666」が浮かびあがってくる仕掛けだ。無論、この「666」は「ヨハネ黙示録」の第13章にあるように悪魔の化身たる獣には刻印があり、「その数字は六百六十六である」とされている、その数字、つまり悪魔を示す数字ということになる( [江川, 『謎とき『罪と罰』』, 1986]p.p.46-49)。そんなのは単なる偶然ではないか、とおっしゃる方もいるだろうが、江川の計算によると、およそ600万分の1の確率であるとのことだ( [江川, 『謎とき『罪と罰』』, 1986]p.47)。仮にこれが偶然だとしても、ドストエフスキーのテキストは、このような事例で溢れかえっているとのことだ。
4 デビュー作『貧しき人々』に仕掛けられた謎
では、それは『罪と罰』に特別なことだったのかというと、そんなことはないと江川は言う。
例えば、ドストエフスキーのデビュー作である『貧しい人々』 [ドストエフスキー フ. ミ., 『貧しき人々』, 1846]。題名通り貧しい人々の素朴な日常と最終的にもたらされる小さな悲劇を書簡の往復という形で描いた、言ってみれば裏も表もないと考えられている作品ではある。当時の大物評論家べリンスキーは「写実主義的なヒューマニズム小説の傑作」と激賞したとされるが( [江川, 『謎とき『罪と罰』』, 1986]p.25)、実は全くそんなことはなく、この最初の作品から相当作為に満ちた技巧を凝らしたものになっていると江川は言う( [江川, 『謎とき『罪と罰』』, 1986]p.25)。
この作品が実はゴーゴリやプーシキンらの一種のパロディになっていることは、『ドストエフスキー』 [江川, 『ドストエフスキー』, 1984]でも明らかにされていたが、本書でも瞠目の分析がされている。一つだけ挙げてみると、小説の冒頭で、主人公ジェーヴシキンがワルワーラにキスをした時の喜びを綴っているが、その後、その件については全くなかったかのように何の進展もない。これは何故なのか。問題は日付にあった。最初の手紙は4月8日付であるが、この二週間前が復活祭に当たり、ロシアでは、この復活祭の日曜日の午前0時に初対面同士でも接吻を交わす習慣がある。従って、二人の間に男女関係の進展が見られないのも当然という訳だ。ここでは省略するが、この小説が9月30日に終わっていることも大変重要な意味があることを江川は恐るべき推理力で示している( [江川, 『謎とき『罪と罰』』, 1986]p.p.27-29)。いずれにしても日付、あるいは数字に重大な意味があることは言うまでもない。
5 「哄笑する人形師の影」
さて、そうすると、何故、ほとんどの読者が読み飛ばすであろう数多の謎をテキストに潜めたのか。また、そのことを仄めかすような発言も一切見られないが、それは何故なのか、ということになる。
江川は、これらの数多の謎は「作者が設定したもののように見えながら、実は作者を超えるだれかから与えられたものではなかったか」( [江川, 『謎とき『罪と罰』』, 1986]P.29。下線部引用者)という言葉とともに、ドストエフスキーの小文「詩と散文でつづるペテルブルグの夢」の一節を引用する。
……あたりを注意して見まわすと、ふいに何やら奇妙な人たちが見えてきた。どれもこれも奇妙で不可思議な人物たち、あくまでも散文的な人物たちで、けっしてドン・カルロスやポーザ (シラーの『ドン・カルロス』の登場人物)などではなく、完璧な九等官たちなのだが、それでいながら何やらファンタスチックな九等官たちである。ふと見ると、だれやら、このファンタスチックな群像のかげに隠れて、しかめ面をして見せるものがあり、彼が糸だかゼンマイだかを引っぱると、 これらの人形たちが動きだす。そしてそのだれやらはげらげらと笑いだし、いつまでも哄笑をつづけるのだ! すると、そのとき、私の脳裏には別の物語が浮びはじめた。どこかの暗い間借部屋の片隅に、だれやら九等官らしき心根の男がいる。清廉潔白、志操堅固で、上司に忠勤をはげむタイプ、そして彼といっしょに一人の少女がいる。辱しめられた、悲しげな少女。そしてこの二人の物語の一部始終が私の心を深く引裂いた。あのとき私が夢に見た群像を全部集めたら、 さぞかしみごとな仮面(マス)舞踏会(カラード)ができたことだろう。(ドストエフスキー「詩と散文でつづるペテルブルグの夢」/ [江川, 『謎とき『罪と罰』』, 1986]p.p.29-30より援引。カッコ内註原文。下線部引用者)
つまり、ここで夢想? されている「哄笑する人形師」こそ「作者を超えるだれか」に他ならない訳だ。このドストエフスキーの奇妙な言葉について、江川は次のように解説する。
引用の後半が、十七年前に書かれた自身の処女作(引用者註・『貧しき人々』)を念頭に置いていることは容易に見てとれる。しかし問題は、作者が二人の物語の一部始終を「仮面舞踏会」のひとこまとして捉えていたことにある。作者の心を「深く引裂いた」物語の背後に、ドストエフスキーは、だれともわからぬ人形師の哄笑を聞きとっていた。そしてこの人形師こそ(中略)作者を超える存在だったのである。神であれ悪魔であれ、その存在がしかと認識できるのであれば、ドストエフスキーはこれほどまで手のこんだ、それでいなから読み解かれるはずのない無用のからくりをテキストに仕掛ける必要はなかった。 いや、そもそも小説などという形式でものを書かなかったにちがいない。しかし、その認識がかなわぬものであれば、ドストエフスキーはあくまでも幻想の人形師にあやかり、自身をその人形師に擬してまで、彼の哄笑に支配されるこの現実世界のせめてひながたを、自分の作品の中に構築しなければならない。そのためにこそ、ファンタスチックとも見える小説のからくり構造も必要になるのである。( [江川, 『謎とき『罪と罰』』, 1986]p.30。下線部引用者)
なるほど、とも思えるが、では、その「哄笑する人形師」であるところの「作者を超える存在」とは一体何なのか。よもやドストエフスキーは悪魔と魂の契約を結んでいたのか。あるいは、彼には神が見えて、対話することが可能だったのであろうか。あるいは彼の表層的な意識を深奥から支える無意識か何かのことであろうか。
いずれにしても、わたしの知る限りでは、この問題について江川が語ることはなかった。
仮にそのような根拠のない不明確な存在を仮定しなくても、ドストフスキーが自身の小説の細部に渡って入念な細工を施していたことは揺るがない。しかし、一体何が作家をしてそこまでさせたのかという問題は十分検討の余地があると思われる。
残念ながら、この不世出のロシア文学者・江川卓は数多くの翻訳書と、そして、たったの5冊の単著*[2]を残して、わずか74歳でこの世を去った。惜しむらくは、最後の著書となり得たかも知れぬ「謎とき『悪霊』」が連載半ば、というより2回目で中断していることである*[3]。「謎とき」シリーズは亀山郁夫に引き継がれたものの*[4]、もちろん、発想も方法論も異なった二人である。少なくとも江川自身による「謎とき『悪霊』」だけでも完成をみていたら、と残念でならない。
もう一点だけ、ここではほとんど触れなかったが、ロシア正教における異端派、分離派の問題を大掛かりに取り上げたのも江川の功績だと思う*[5]。これについてはまた別稿にて触れることになるであろう。
20220116 1546
※以下は、江川卓『謎とき『罪と罰』』についての書評というか読書ノートの初稿に当たる。しかし、余りにも本筋から離れたことを書き過ぎたために没にして、上に掲げた新版を書き直した。ここから派生してきた問題もあるので、これまた単なるわたし個人の覚書として、おまけの第6項として付け足しておくことをご寛恕せられよ。
6 江川卓『謎とき『罪と罰』』書評(初稿)
本書の裏表紙に小説家・評論家である丸谷才一の推薦文が掲載されている。全文を引く。
ロシア文学では江川卓がよく出来る。/その評判はまへまへから耳にしてゐたけれど、 疑り深いわたしは、ロシア語が出来るだけだらうと高をくくつてゐた。/しかし、岩波新書の『ドストエフスキー』とこの『謎とき「罪と罰」』を読んで、予想がまつたくはづれてゐたことがわかった。江川さんはどうやら、語学の才と文学の感覚の双方を身に備へた、つまりしつかりと読んで深く考へることのできる、理想的な外国文学研究者らしい。/江川さんは紋切り型のドストエフスキーの肖像を焼き捨てて、彼の本当の姿を二十世紀の後半に生かす。深刻に硬直した『罪と罰』は現代人のための古典として相貌を改め、われわれが今ここで読むに価するものとなる。/大事なこと、清新な説がいつぱい詰まつてゐるおもしろい本が、こんなにやさしく、わかりやすく書いてあるのは、不思議な話だ。 丸谷才ー」( [江川, 1986]裏表紙)
辛口で知られた丸谷からすればかなり激賞の部類だろうか。つまり語学的に優れているだけかと思っていたら、「文学の感覚」も備えていた、と褒めている訳だが、ここで丸谷が言っている「文学の感覚」というのが一癖も二癖もある代物なのは言うまでもない。
丁度、本書の連載が『新潮』誌上で開始されたのが1983年の3月のこと。以降隔月連載で終了したのが85年の8月。で、選書の形で刊行されたのが、翌1986年の2月のことである。
丁度、これと軌を一にして、という訳ではないが、丸谷の古典評論の代表作とも言うべき『忠臣藏とは何か』 [丸谷, 『忠臣藏とは何か』, 1984]が書下ろしで刊行されたのがこの翌年に当たる1984年の10月のことだった。
別に影響関係云々を言う心算はない。先程言及した、丸谷言うところの「文学の感覚」というものが、いわゆる実存的な意味での、というのはどういうことかというと、青春の最中(さなか)でなんだか絶望して、ああ一体どうすりゃいいんだ的な文学のことではない、ということだ。
何時のころから、文学と言えば、小説のことであり、小説と言えば、青春小説であり、青春とくれば、そこには恋愛があり、という概念、縛りができてしまっているが、多くの諭者が指摘するようにそのような事態は近代に入って成立した、たかだか200年から100年の歴史しか持たないものである。
丸谷と江川を結ぶ線は、無論そんなところ(だけ)にはない。
丸谷は自らが影響を受けた3人*[6]の1人としてミハイル・バフチンの名を挙げている [丸谷, 『思考のレッスン』, 1999]。バフチンについては言うまでもなく、カーニヴァル論、あるいはポリフォニー論などでドストエフスキーの作品の読み直しを提唱した訳だが*[7]、先に挙げた丸谷の『忠臣藏とは何か』にその影響がとりわけ「第6章 祭りとしての反乱」に強く見られるのは言うまでもない。このようにバフチンの射程範囲と方法論が当然、先に述べた近代的な文学の概念を越境、逸脱するものであり、江川のそれらも広く、その流れにあると言える。
さて、元々の記憶を辿れば、『新潮』誌上に連載されていた「謎解き『罪と罰』」の第1回「哄笑する人形師の影」*[8]を読んだことが、わたしのドストエフスキーのと付き合いの始まりだった*[9]。その頃は、正直言って、よく分かっていなかったのだと思う。無論今でも分かっていないが。
ロシア文学やドストエフスキー学の世界のことは分らぬが、恐らく、本書あるいは江川卓の数少ない著書は「異端の書」として遇されているのではないか。それは後続する位置にいる亀山郁夫もあるいは同じかも知れない。
要は彼らは所詮、翻訳家であって、厳密な意味でのロシア文学者、ドストエフスキー学者ではない、翻訳家があること、ないこと、根拠もなく書き散らしているのだ、と見られているのかもしれない。当然、そんなことは誰も口に出しては言わない。基本、無視する、ということになるのか。
これは、分野は異なるし、また文脈が異なるかも知れぬが、文字学、漢字学の泰斗・白川静の置かれた位置と相似形をなす気がする。白川の「字書」三部作*[10]を始めとする漢字成立の根源を追究する、まさに鬼気迫る業績は、小学生から老人に至るまで国民的に受け入れられたといってよいが、漢字学の世界での黙殺ぶりは広く知られるところである。この辺りの経緯と、その意味については評論家の三浦雅士が「白川静問題」として論評している*[11]。
恐らく、江川―亀山というラインで言えば、全く方法論が違うのだが、この場合、とりわけ、白川との相似性を感じさせるのが誰あろう江川卓その人の方である。
言葉は良くないかもしれぬが、白川への風評として、あたかも見てきたかのようなことを書いているという。つまり、言われてみればそうかも知れぬが、何故、そんなことが分かるのか、それは詩人の感覚ではあろうが、学問ではない、というような批判が江川の場合も少なからずあったのではなかろうか。
もちろん、文学作品が学問であろうとなかろうと、そんなことは実は全くどうでもいいことである。
いま、わたしが書きつけたことも、あるいは余計なことだったかもしれない。すいません。
本書を手に取るのは、実は三回目である。読むたびに、よくもまあそんなことまで思いついて調べたものだ、と驚嘆すること一再ならずというところではあるが、それはそれとして、『罪と罰』そのものも今回三読目となったが、何と三読目にして初めて面白い、それも途轍もなく面白いと思えた。一体何を読んでいたのであろう、以前は。と言っても30年ぐらい前の話ではあるが。
奇妙なことだが、今回『罪と罰』を読んでみて、様々な点で興味深かったのだが、とりわけ、主人公と目されるラスコーリニコフの若さ*[12]からくると読める挙動不審さに心惹かれた、というか撃たれた。要するに、最後のの「回心」とされる場面に至っても、お前ら(世間一般の人達ですね)に何が分かるんだ! とでも言いたい気分だったように思う。
という訳で、3周か30周遅れぐらいで、やっと青年*[13]の気持ちが幾ばくかでもわかるようになったのか。
で、そういうベクトルで言うと、残念ながら、江川の所論は、大変興味深い、極めて参考になるとは思わせられたが、なんというか、本丸から相当離れた外堀をあちらから、またこちらから埋めていく作業であって、無論、これはこれで重要な作業ではあるが、本丸ので呻き苦しんでいる城主であるラスコーリニコフの懐にいきなり飛び込んで切りかかる、といったことは当然ない。それは方法論とフィールドが違うためで致し方がないことだ。
今のわたしが求めているのは文学の研究ではなくて、恐らく文芸批評なのだろう。
これは江川等のロシア文学者の皆さんを貶めるために書いている訳ではない。江川の著書から多くのことを学び、これからも学び続けるであろうことは言うまでもない。
本書の内容についても触れるべきではあるが、いささか事情があって、後日を期す。スマソ(´;ω;`)。
【文献一覧】
エリオット・スターンズ,トーマス. (1920). 「ハムレットとその問題」 Hamlet and His Problems. 著: 『聖なる森』 The Sacred Wood.
シェイクスピアウィリアム. (1601?). 『ハムレット』.
ドストエフスキーミハイロヴィチフョードル. (1846). 『貧しき人々』.
ドストエフスキーミハイロヴィチフョードル. (1866). 『罪と罰』. (亀山郁夫, 訳) サンクトペテルブルグ, ロシア.
ドストエフスキーミハイロヴィチフョードル. (1867). 『罪と罰』. (江川卓, 訳)
ドストエフスキーミハイロヴィッチフョードル. (1861). 「詩と散文でつづるペテルブルグの夢」. サンクトペテルブルグ.
丸谷才一. (1984). 『忠臣藏とは何か』. 東京: 講談社.
丸谷才一. (1999). 『思考のレッスン』. 東京: 文藝春秋.
亀山郁夫. (2007). 『ドストエフスキー――謎とちから』. 東京: 文春新書(文藝春秋).
江川卓. (1984). 『ドストエフスキー』. 東京: 岩波新書(岩波書店).
江川卓. (1986). 『謎とき『罪と罰』』. 東京: 新潮選書.
三浦雅士. (2010). 『人生という作品』. 東京: NTT出版.
柄谷行人. (1992,2017). 「意識と自然」. 著: 柄谷行人, 『新版 漱石論集成』. 東京: 第三文明社,岩波現代文庫(岩波書店).
20220114 1557
📓ノート
l 江川訳『罪と罰』学研版では作品舞台、人名、神話、民俗などについて、従来のものとは決定的に異なる型破りな訳者注解が付いた p.11
l 何故、『罪と罰』という題名なのか? P.12
l 何故、『罪と罰』は全6編+エピローグなのか? P.12
l 『罪と罰』が近代小説の極限を極めたものだとすれば、この作品の研究は小説とは何か、それが現代において果たしうる機能は、などの問題の手がかりになる p.13
l 『罪と罰』の原テキストの読まれ方には大きな盲点があった p.14
l 「ドストエフスキイの翻訳にかけては、吾が国は、恐らく世界一である。といふ事は、ドストエフスキイにからかはれてゐる事にかけても世界一だといふ事になるかも知れない」(小林秀雄「『罪と罰』について」)p.14
l ナスーシチヌイは学生隠語でアルバイトのことを「日用(ナスー)の(チ)糧(ヌイ)の仕事」と呼んでいたのでは p.17
l またぐ、踏み越える ペレストゥピーチ p.19
l 730歩 歩数 p.21
l 敷居 階段 踊り場 カーニバル的空間 バフチン p.21
l 罪の女 グレーシニツァ グレーフの女 ソーニャは自分の売春行為を良心の咎める行為と理解していた p.23
l 罪 プレストプレーニエ 人間の定めた掟を越える行為/罪 グレーフ 神の掟に背く行為 p.20
l 作者を越える存在 p.25
l 『貧しい人々』 なぜ9月30日で終わっているのか? 翌日10月1日はポクロフ祭(聖母祭) 冬の始まり ポクルイチ(覆う) 大地(女性名詞)が雪あるいは落ち葉で覆う←ポクロフ(男性名詞) 「ポクロフのおやじさま、母なる大地を覆っておくれ、そして若い身空のわたしをば、婿がねで覆っておくれ」という諺 ワルワーラは願いがかなった p.28
l ワルワーラの病死した元カレはポクロフスキー p.27
l ポクルイチ 家畜を交尾させる、雄と雌をつがわせるという意味もあるワルワーラを連れ去る地主はブイコフ ←ブイク 牡牛 p.28
l グロテスク・リアリズム p.29
l からくり装置 p.30
l マルメラードフ(甘井聞(あまいもん)太(だ)) 「変わった名前ですな」 p.31
l 帝が沼地の上に石(ペトラ)で築いた人工的な都ペテルブルグ p.33
l 他者を意識するとき素顔と仮面の区別がつかない p.36
l 「名前のない主人公」の発明 p.37
l 後期の作品にはほとんど分離派が登場する p.39
l ラスコーリニコフは峰打ちで老婆を殺害した=自分の顔を割ったのだ(ゲオルギー・メイエル) p.40
l 分裂者 ラスコーリニコフ p.41
l 犯行当日、太陽が出ていない p.42
l ポルフィーリーの謎の言葉「太陽になれ」 ラスコーリニコフ自身が太陽だった p.43
l 「いったい僕は婆さんを殺したんだろうか? ぼくが殺したのは自分自身で、婆さんじゃないのさ! あのときぼくは、ひと思いに自分をウフローパチしたんだ(パシリとやった)、永遠にね!……」p.44
l 凡人と非凡人と区別 何かしるしでもあるのか? P.49
l 7は完全数 過去・現在・未来を表す3+地水火風(あるいは東西南北)の4 p.53
l S横町=ストリヤーヌルイ(指物師)横町=狂人横町 ゴーゴリ『狂人日記』に登場 p.p.57-59
l ドイツしゃっぽ! P.67 こっけいさ p.68
l 豌豆ゴロフ王 p.70
l 「主よ、あなたが私を創られたのは、この世に短い生を与え、長の年月を地獄で苦しめるためだったのですか? いまあなたの愛する者たち、私の子孫らは、暗黒の中に座し、地獄の底でうめき悲しみ、おのれの目と瞳を涙で洗っております。ほんの束の間、あなたの太陽を目にすることができただけで、あれからもう何年もの間、私たちは明るい太陽を仰ぐこともなく、風の騒ぐ音を聞くこともなしに過してきました。私は他のだれよりも大きな罪を犯したのだから、この報いは当然かもしれません。けれどあなたの像に似せて創られたこの私が、いま悪魔にあざけられ、責めさいなまれているのが口惜しいのです……主よ、早く私たちのもとへ来られて、地獄を救い悪魔を縛りあげ、きびしい姿を拝させてください……」最初の人間アダムは大罪を犯して地獄にいる 『地獄にあるアダムよりラザロへの言葉』16世紀以前の作と指定されるロシアのアポクリファ(偽経) p.p.85-87
l ラスコーリニコフの地獄巡り(4日間) p.86
l ところがマルメラードフの「キリスト」は、知者、賢者の反対を押しきってまで、彼を天国に迎えようとされる。 となれば、彼が思い描くキリストは、 アンチクリスト、 悪魔をまで赦される、無限に「心の大きい方」ということにならざるをえない。ここであらためて強調しておくと、 このようなキリスト観こそ、 現世の苦しみにあえぎうめいていたロシアの民衆の救済願望そのものの表現であり、同時にそれは、 ドストエフスキー自身のキリスト観の最重要な特質をなすものでもあった。小説に即して言えば、 666の刻印をひそめたラスコーリニコフその人にさえ、 キリストへの道は閉ざされていないということである。P.94
l カチェリーナが高官に投げつけたインキ壺 『カラマーゾフの兄弟』のイワンと悪魔の対話に出てくるように、「インキ壺」は、聖書を翻訳していたマルチン・ルターがか、うるさく邪魔を入れる悪魔に、苛立ちのあまり投げつけたと伝えられる小道具である。 →カチェリーナにとってはその高官は悪魔だった p.95
l
p.99
l 蠅が全てを見ていたのか p.195
l クレオパトラの治世を終末期と見ていた p.207
l 私の考えでは、おそらくこのあと、二人は、ソーニャの「願望」のとおり、完全に心と肉体をひとつにすることができたのだと思う。むろん、ドストエフスキーは直接にはなんの描写も与えていない。しかし、ソーニャの「ええ、行ってよ! 行ってよ!」につづく段落は、次のように始まっている。
l 「二人は、あたかも嵐のあと、無人の岸辺に二人だけ打ちあげられでもしたように悲しげにうちしおれて、並んで坐っていた。彼はソーニャを見やり、自分に注がれている彼女の愛情がいかに大きなものであるかを感じていた……」p.222 二人の性関係の有無は?
l 創作ノートには、 ラスコーリニコフの言葉として、 「ぼくらは二人とも呪われている、 社会の被(パ)差別(ーリ)民(ア)なんだ」 という書きこみが見られる。「パーリア」という言葉は完成稿からは除かれたが、 ドストエフスキーがほの暗い蠟燭に照らされる「殺人者」と「淫婦」を描いたとき、農奴制からようやく脱け出ようとしていたロシアの現実に充満する、 被差別民衆の大集団を視野に納めていたことは、 ほとんどなんの疑いもないことだと思われる。 その最も無力な代表者がソーニャであり、 彼女に肉体を売ることを強いねばならぬほどの貧しさに追い込まれた、 マルメラードフ家の人びとであった。 これらの人びとが「新しきエルサレム」 に入ることを許されるようにすることこそ、 ラスコーリニコフがわが身に引受けた十字架だったのである。 P.226
l 「……」に意味がある。 なぜ、そこで言い淀むのか? P.251
l 小説の冒頭は7月8日、老婆殺害は1865年7月10日午後7時過ぎ、7月20日に自首(13日目) p.273
13620字(34枚)
🐦
20220117 1836
【註】
*[1] 江川卓訳による『罪と罰』は以下の3点。①1965年-66年・全2巻・旺文社文庫。②1977年・学習研究社。③1999年・全3巻・岩波文庫。
*[2] ①『現代ソビエト文学の世界』(晶文社、1968年)、②『ドストエフスキー』(岩波新書、1984年)、③『謎とき『罪と罰』』(新潮選書、1986年)、④『謎とき『カラマーゾフの兄弟』』(新潮選書、1991年)、⑤『謎とき『白痴』』(新潮選書、1994年)。
*[3] 第1回「椋鳥の里の惨劇」(『新潮』1996年1月号)、第2回「覇を競う父と子」(『新潮』1996年3月号)。
*[4] 亀山郁夫『謎とき『悪霊』』2012年・新潮選書。
*[5]「ドストエフスキーについてはこれまで星の数ほど本や論文か書かれているが、異端派との関わりをめぐって書かれた論考はきわめて数少なく、故江川卓による世界的な仕事『謎とき』シリーズ(新潮社) にその記述があるのみで、 ロシア内外の研究も最近ようやく彼のレベルに追いついて来たというのか、実情である。」( [亀山, 2007]p.258)
*[6] 正確にいうと「私の考え方を励ましてくれた三人」。他の二人は中村真一郎、山崎正和。
*[7] ミハイル・バフチン(1895年~1975年)は、ロシアの哲学者、思想家、文芸批評家、記号論者で、対話理論・ポリフォニー論の創始者として知られる。ドストエフスキーについては次の2著で知られる。①『ドストエフスキーの詩学』(望月哲男・鈴木淳一共訳、ちくま学芸文庫、1995年)②『ドストエフスキーの創作の問題』(桑野隆訳、平凡社ライブラリー、2013年)初訳は『ドストエフスキー論 創作問題の諸問題』(新谷敬三郎訳、冬樹社、1974年)。
*[8] 「哄笑する人形師の影」は雑誌初出時の題名。選書化に当たって「精巧なからくり装置」と改められたが、この「哄笑する人形師の影」というイメージはドストエフスキー自身が小文「詩と散文でつづるペテルブルグの夢」 [ドストエフスキー フ. ミ., 1861]の中に書きつけた重要な創作概念だと思われる。江川自身も残念がっているようにも感じられるが、恐らく選書編集部の意向による措置かとは思われる。その意味でもいささか残念ではある。
*[9] 全くどうでもいいことだが、何故、「謎解き『罪と罰』」の第一回が掲載された『新潮』1983年3月号をわたしは買ったのだろうか? 探せば実家のどこかにあるはずだが、探せない。仕方がないので、国会図書館の蔵書目録で調べてみると、なんと驚くなかれ、いや驚かないか、北杜夫の「輝ける碧き空の下で」の第二部の新連載の第一回に当たっていたのだ。この当時は北杜夫のファンだったんだね( ´∀` )。
*[10] 白川静・字書三部作『字統』(各・平凡社、1984年)、『字訓』(1987年)、『字通』(1996年)。
*[11] 三浦雅士「白川静問題――グラマトロジーの射程・ノート1」・「起源の忘却――グラマトロジーの射程・ノート2」/ [三浦, 2010] 。
*[12] 本当のところは「若さ」とか、という年齢的なことは関係ない。人間の本質に根差したものが若い時ほど露出し易いということかと思う。
*[13] 註の12と同じで「青年」云々は、本当は関係ない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
