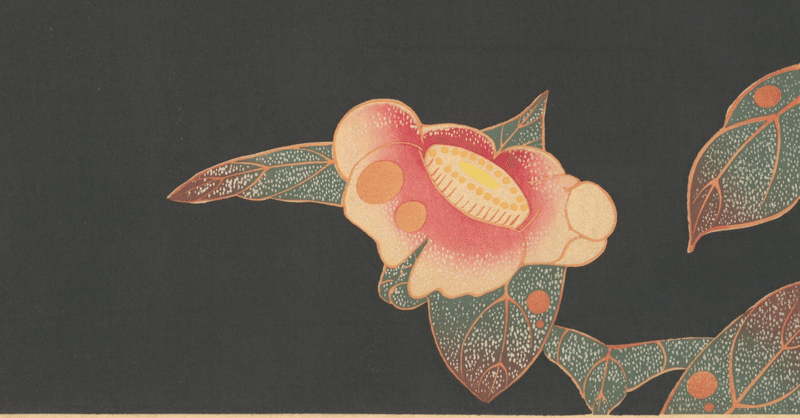
【小説】握り潰された花の名は(4)
結局、何もできずにアニタを送り出すことしかできなかったセーバ。失意に沈む中、新たな生き神のお披露目がひらかれる。セーバは降臨した神に何をみるのか。
上記から続く生き神の器の少女と若き僧の、どうしようもない運命に翻弄される話。これで完結します。
儀式は恙なく終わったと聞いた。
喜びにわく人々の声は、セーバにとっては呪いだ。浮かれた喧騒や街に飾りつけられた花々が、己の体に重い鉛を注ぐ。
あの子が勇気を出して伸ばした手を、とってやれなかった。見殺しにした。事情を知っている分、呑気に祝いあっている民衆よりも性質が悪い。
(神が人殺しなら、俺は殺人ほう助か)
セーバにはもうわからなくなっていた。何が正しいのか。何が幸福なのか。神は何を望んでいるのか。
己が神仕えに選ばれたことも、アニタが神の器として選ばれたのも、セーバには何もわからなかった。ただ一つわかることは、信仰が己を救ってくれるわけではないということだ。少なくともこの国の宗教は救ってくれない。何の道も指し示してくれない。
年中暖かな太陽に照らされていようとも、ひとたび下をみれば、この国の根幹は醜く歪んで、見るに堪えないほど腐敗している。
通いつめた煉瓦造りの館をみるたびに、厳かな寺院の姿をみるたびに、底に折り重なった少女たちの死体が透けてみえるようで吐き気がした。
セーバは寺院を出ることにした。このまま僧として籍を置いていればきっと気が狂う。アニタを見捨てておいて、今までの生活を送れるほど面の皮は厚くなかった。
寺院に入った理由も、僧ならば少なくとも明日の飯には困らぬという単純かつ低俗な理由である。もう無力な少年の齢は過ぎた。知恵も体力もついた。ここにこだわる必要はどこにもない。
荘厳な門をくぐる。初めて見たときは威厳溢れる大きさと装飾に気後れした門も、今では煉瓦を積み上げた、無駄に大きいだけのつまらぬ塊にしか見えなかった。
棄教しても世界が一変するわけではない。彼女がいなくなっても日々は回り、人々は生活を続けていく。
寺院を出たら職につけないのではないかと、一抹の不安があったが、意外にも近所の者たちは優しかった。内職の仕事を割り当ててくれ、一人でいるとほとんど食事をとろうとしないセーバに食事に誘ったり、差し入れをもってきてくれたりした。
それでも胸にはぽっかりと虚ろな穴が空いたままだった。時おりこのまま何もせずに干からびてしまいたくなる。だがそれでは神でなかった頃の彼女を、神の器と崇められながらただの少女であった頃の彼女を覚えている者が誰もいなくなってしまうのではないか。そう思うと、無理やりにでも固形物を喉に流し通すしかなかった。
この日も近所の老婆が香辛料で煮こんだスープと漬物、米を詰めこんだ缶を片手に押しかけてきていた。
「そういえば、聞いたかいセーバ」
相変わらず噂好きな彼女はこちらの顔色など気にも留めずにべらべら喋り続ける。
「ついにニドサータさまがお披露目されるそうだ。お前も見に行ったらどうだい? 寺院を出てから、まるで抜け殻じゃないか。ニドサータさまに触れられなくても、一目みれば、活力がわいてくるかもしれないよ」
虚ろな目にわずかに光が宿った。
「……それはどこで行われるんだ?」
「やだねえ、もうぼけちゃったのかい? ニドサータさまのお披露目といったら、館から始まってぐるりと大通りから一周するじゃないか。館の前は混むだろうから、通りのほうからみたほうがいいだろうね。わたしゃ、いいところを知っているんだ。明日は朝早く起きるんだよ」
「あす……」
セーバはぼんやりと呟いた。
「そう、明日さ。いいかい、明日は朝早いんだからね。覚えておきな。寝ていたら叩き起こしてやるんだからね」
セーバの返事も聞かず、一方的に約束を押しつけると、老婆はよたよたとおぼつかない足取りで去っていった。
じりじりと眩い太陽の光が街路を照らしている。道の端に真っ白な蝶が死んでいた。誰の目にも留まることなく、土煙に汚される小さな死骸。
なぜだか直視することが憚られて、セーバはそっと目を背けた。
老婆に手を引かれて大通りへと向かう。朝早く出たというのに、既に道の両脇は大勢の民衆が詰めかけていた。
「まったく、これじゃ一目拝むどころか進むのにもひと苦労だよ。ほらどいたどいた! 弱っちいばばあが通るんだ。道をおあけ!」
老婆が声を張り上げれば、人々は訝しげに振り返る。しかしみすぼらしい老婆と、明らかに顔色のよくないやせ細った男が立っていれば、事情を察した顔で道をあける。
「今日ばかりはお前の格好に感謝しなきゃねえ。勝手に老人と病人だと哀れんで、道を譲ってくれるってんだからさ」
ひひひ、と欠けた歯を覗かせて老婆は囁いた。セーバは曖昧に相づちを打って、老婆の後をついていった。
「ああ、ここだここだ。ここならまだあんまり人は来ていないねえ」
老婆がたどり着いたのは館から一番離れた地点だった。街の端なので、館前や中央の大通りほど掃き清められていない。女神が来るので花はまかれていたが、大通りと比べてしまえばどこか色がくすみ、盛り上がりに欠けていた。
「ま、最後に回るってわけでもなし、のんびり待つさね」
そう言って老婆は地面にどっかりと座りこんだ。
日が高くなったころ、ようやくざわめきが広がってきた。人通りが増えはじめ、セーバたちの前にもいつしか人の壁ができていた。
「お、そろそろじゃないかい? ほらやってくるよ。ああ、横入りするんじゃないよ! ちょっとおどき! 見えないじゃないか」
老婆が指差した先には屈強な男たちが今にも殺到しようとしている群衆たちを威嚇しながら歩いてくるところだった。その後ろには太陽の光を反射する眩い金の屋根が見える。
間違いない。ニドサータの輿だ。
セーバは目の前の人々を押しのけようとしたが、すっかり細くなった腕はなかなか塞がる壁をどかすことができない。どいてくれ、と大声を上げても興奮した彼らの耳には届かないようだった。
と、そのとき、ふいに壁が軽くなった。先ほどまでびくともしなかった垣根がいともたやすく割れる。まるで何者かが導いているかのように。気づけばセーバは人々を押しのけ、顔を突き出していた。
飛びこんできたのはあの日見たものと同じ、金の屋根と最高級の木材でこしらえた華やかな輿。あの日とは違い、絹の薄布はあげられ、中の様子がはっきりと見えた。
どこまでも真っ直ぐ前を見据える目は、目の前の光景を見ているようで見ておらず、人とは思えぬ神秘的な超然さが漂っていた。
それはまさしく神であった。あの日の神が今、目の前を通り過ぎていく。
脳裏に彼女と過ごした日々がくるくると回った。
子どもっぽく頬を膨らませた横顔や咲き誇る花のような笑顔。本を読み聞かせてやったときの好奇心に輝く顔や、かたくるしいマムタの顔真似と称して変顔を披露したときの顔。
それらが砂のように徐々にこぼれ落ちていく。
ふいに少女がこちらをみた。そして微かに口元を緩ませて笑った。
瞬間、セーバのうなじの毛が逆立った。
そうだ、あの日、先代ニドサータを見たときも、彼女はこちらを見ていた。歓喜にわく人々から一歩離れたところで眺めている、自分をはっきりと見つめていた。
もしや、あのとき既に――
だが何のためにニドサータは自分を選んだのだろう。残酷な運命を見せつけて、いびつな世界を変えてほしかったのか。はたまた不信仰な自分に罰を与えたかったのか。神は何も答えず再び前を向いた。口元の微笑みは消えていた。
「どうだい、セーバ。新しいニドサータさまは? これで少しは元気が……セーバ? おい、どうしたね」
喧騒が戻ってきたとき、輿は既に通り過ぎてしまっていた。
(ただ一つわかるのは、)
もうアニタはいない。陽だまりの中で無邪気に笑う彼女はいやしない。永遠にこの世から消えてしまったのだ。
涙が両の目からとめどなくあふれだし、頬をぬらす。体を揺さぶる老婆だけでなく、周囲も驚いて声をかけてきたが、セーバは拭うこともせず、ただ呆然と行列を見送った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
