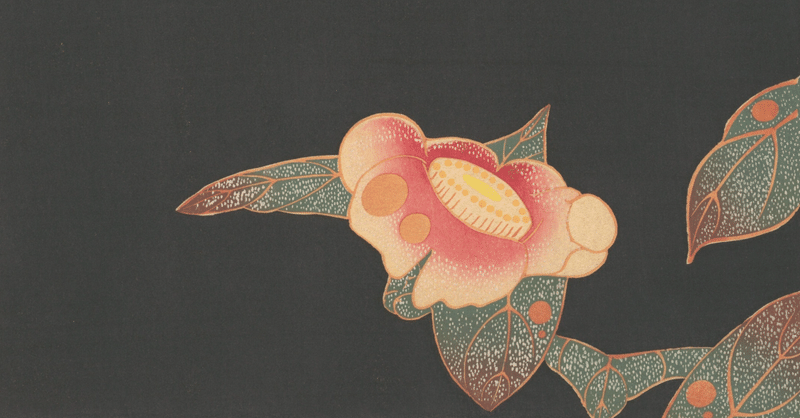
【小説】握り潰された花の名は(1)
神が人の心をわかるわけもなし。
生き神の器として選ばれた少女とその世話役に選ばれた若い僧の話。3~4話で終わる予定です。
雑踏の中、どけどけ、道を譲れ、と怒鳴る男どもの声が聞こえる。人波をかき分けて顔を出せば、豪奢な輿が男たちに担がれて運ばれていくところだった。屋根は傷一つない金。柱は最高級の木材を用い、美しい木目はもはや芸術品だった。輿には絹の薄布がかけられ、中をうかがい知ることはできない。
ふいに歓声が上がる。一陣の風が吹き、輿にかけられた薄布がめくれて中の人物の顔があらわになった。
乗っていたのは一人の女だった。真紅の衣を身にまとい、腕や首には金の輪が何個も巻かれ、頭にはこれまた真っ赤な花たちが孔雀のように花弁を広げている。豊かな黒髪には白髪一つなく、褐色の額には神聖さを示す赤い筋が一筋、描かれていた。
だが何よりも目を惹くのはその瞳だ。黒真珠のようにまるまるとした目の奥は霞がかったようでありながら、全てを見透かすような透明さがある。その目で見つめられた者は誰でもたじろいでしまうほどだ。浮世離れしたそれは、人間というより神と呼んだほうがしっくりきた。
「おお、ニドサータ! 美しき幸福の女神よ!」
「どうか御手を! 哀れな私めにお慈悲を!」
悲鳴まじりの声があちらこちらから飛び、無数の手が女に向かって伸ばされる。輿を担ぐ男たちが怒号を飛ばしても怯みもしない。それを無表情で見やった女は、ふと思いついたように、その細い手を民衆へと近づけた。
一層狂喜は渦を巻き、群衆は雪崩を起こす寸前まで輿に詰め寄った。男たちが押しのけようにも人数差がありすぎる。遠くのほうで、一人の男が駆け出していった。恐らく応援を呼びに行ったのだろう。
汗と埃にまみれた衣をまとう群衆たちと、豪華絢爛な輿に乗る女。まるでゴミ溜めに気まぐれにとまった蝶みたいだ。そんなことを思っていると、ふいに、女と目が合った。
黒は真っ直ぐこちらを貫いていた。瞬間、足が縫い付けられたかのように動けなくなり、頭のてっぺんから足の爪先の隅々まで見通されているような、奇妙な視線を受けているのを膜一枚隔てた向こうで感じた。
ごくりと唾を飲みこむ音がする。己のものであるはずなのに、どこか他人事だった。
女はじい、とこちらを見ていたが、突然顔を引っこめて、薄布の向こうに消えてしまった。それでも民衆の熱狂が収まることはない。
どん、と鈍い音がし、視界が傾く。咄嗟に足を踏み出したおかげで地面に口づけせずにすんだものの、前の人を押してしまい、罵声が飛んできた。
唾を飛ばす男に軽く頭を下げて、後ろを振り返る。しかし視界いっぱいに映るのは、日に焼け、薄汚れた顔、顔、顔、顔。犯人はさっぱり見当もつかなかった。
前方から悲鳴が上がった。応援が到着したのだ。屈強な男たちは、追いすがる民衆を力づくで押しのけ、道を作った。
輿が遠ざかっていく。それを追って民衆たちが尾をひくように並ぶ。太陽がじりじりと照りつけ、世界から色が消えていく。それをただ木偶の棒のように突っ立って、少年は見つめ続けていた。
「喜べ、お前に神仕えの任が命じられたぞセーバ」
「……は?」
セーバはぽかんと先輩の顔を見つめた。
「だから神仕えが命じられたと言っているんだ。いつまでも間抜け面を晒しているんじゃない。さっさと準備にとりかかれ」
まったくどうしてこんな奴が、とぼやきながら先輩は背を向けた。明るい日差しが差しこむ廊下に、先輩の橙の衣がひらめく。
白昼夢をみているのかと思った。頬をつねれば、きちんと痛みが走る。が、未だに現実味がない。足が床についていないような感覚だった。
どん、と衝撃が走る。すれ違った別の男が肩をぶつけたようだった。が、一瞬交わった目には冷たい憎悪が浮かんでいた。ついでに薄汚いネズミが、との悪態もセーバの良い耳は拾った。
周りを見渡せば、無数の視線が突き刺さっていることに気づく。巻物を抱えながらこちらに向かってくる男、談笑している二人、庭に立つ人々。そのどれもが、嫉妬と憎しみにまみれた仄暗い視線を送ってきていた。上にどんな媚びを売ったんだか、と聞こえよがしな陰口もささやかれている。
(べつに俺が何をしたってわけでもないんだが……)
そもそも後ろ盾も何もない庶民の出が、上に媚びを売ったところでどうにかなるものでもあるまい。自分ですら、選ばれた意味が理解できないというのに。
頭をかこうとして、指先が虚しく肌の上をもがく。この道に入った際に、すっかり剃ってしまったのだ。
しかしふさふさとした黒髪が居座っていた時代の癖が抜けず、気を抜くと、こうして間抜けな様を晒してしまうのだった。
嘆息を落とし、セーバは足早にその場を後にした。
神仕えとは生き神ニドサータの世話役を指す。
ニドサータはこの国で信仰されている女神で、けがれなき少女の体に宿るとされる。触れたものに幸福を与え、また国の安寧を保つと言われている。
ただ、やはり神に選ばれたといえども、器はただの少女。多くは短命だ。それでも先代は長くもった。なにせ三十を超えてもその体に神を宿したのだから。
だがついに限界が訪れた。
ひと月前に彼女は眠るように息を引き取った。日が短くなり、朝晩は肌寒さを感じる、温暖なこの国の冬の朝のことだった。
色とりどりの花に囲まれて、彼女の体は火にくべられた。こわばった冷えた顔には、いつかの日にみた神秘性はどこにも感じられなかった。
もはや神がいない抜け殻はただの肉と骨の塊でしかないのだ。むせび泣く声を背景に、葬儀の列が伸びていく。日差しは薄く、されどあの日のようにふとした瞬間に何度もよみがえるような奇妙な引力は存在しなかった。
(そういや、この前新たな器が見つかったんだったか)
熱に浮かされたように話し続けていた近所の老婆を思い出し、重苦しい息を吐いた。
誰かが置き忘れたのか窓辺に桃が転がっていた。愛らしい薄紅色はすっかり黒ずみ、溶けている箇所もみえる。気分が悪くなるほどの甘ったるい匂いを放出する果実に、無数のハエが群がっていた。
まるでいつかの日の群衆のようだった。だが自分も例外ではない。こうして神にへりくだる僧の一人なのだから。
セーバはかぶりを振って歩き出す。いつまでもまとわりつく甘さは知らぬ振りをした。
「それで、なぜお……私が栄えある神仕えに選ばれたので?」
うっかり普段の一人称が口から漏れた途端、高僧からじろりと睨まれる。慌てて口調を直したが、彼の眼差しは冷たいままであった。
「知らぬ。だが女官長が言うには、ニドサータさまがお前を指名したとのことだ。私はそれに従っただけのこと」
高僧のすました顔には珍しく苦々しさが滲む。だがたとえこの国の権力者であろうとも神の言うことは絶対である。何者も歯向かうことはできない。
「とにかく、神仕えは基本女官たちが行うが、お前が直々に選ばれてしまったのならば、仕方がない。明日から女神の館に向かうといい」
異論は認めぬ、と締めくくり、高僧は背を向けた。
まるでこの前の先輩とのやり取りのようだ。しかし自分に許された行為は一つだけ。
セーバは静かに腰を折った。
ニドサータが住まう館はこの国でもっとも金がかけられている館だ。どっしりとした煉瓦造りの館は、一見すると国王や貴族の館のような煌びやかさは感じない。
が、よくよく見れば巧みに積まれた煉瓦には職人の技巧が見えるし、何より国王の館より少し小さい程度の館を、一つ一つ人の手で積み上げたのだ。そこにかかった労力は計り知れない。等間隔に並んだ大きな金属の窓は堅牢ながら細やかな植物の模様が彫ってあり、材質のわりに女性的だ。
豊かなたてがみをたくわえた東の国の幻獣が、鋭い眼光で門をくぐる人間たちを睨んでいる。その冷たい面差しに見下ろされると居心地が悪く、一対の石像から逃れるように門を足早にくぐった。
門の先には中庭があり、池には蓮が浮いていた。花は咲いていなかったが、どこかで香を焚いているのか花のような匂いが体にまとわりつく。よい香りのはずなのにどこか粘っこく、セーバは眉をひそめた。
女神を祀っているだけあって、すれ違うのはみな女官だ。じろじろと不躾な視線を送られながら、セーバは階段を上がった。
高僧が伝えた集合場所は二階のつきあたりの部屋だ。木製の扉は今までみた中で一番重厚な扉だった。黒の木材は長い年月を感じさせたが、それは決して古臭くはなく、むしろ深みを増している。
恐らくこの先にニドサータがいる。あの日見た生き神が。セーバは一度深呼吸し、扉を叩いた。
「僧のセーバです。高僧シェカンより命じられ、はせ参じました」
「入れ」
「失礼します」
低い女の声が許可を下す。セーバは一礼して扉を開けた。
「来たか」
出迎えたのは女官長のマムタと、その横の椅子に腰掛ける一人の少女だった。
(これが、次のニドサータ)
少女に視線を移して絶句した。少女は身なりこそ綺麗なものであったが、いつか見た先代のような神々しさはどこにもない。むしろその辺の街角にいる子どもを捕まえて、ここに持ってきましたと言われたほうがまだ納得できる。共通しているのは性別と豊かな黒髪くらいだ。
くりくりとした目がこちらを向いた。幼い目だった。
「マムタ、この人は?」
「今日からあなたの遊び相手のセーバですよ、アニタ」
「えっ」
そんなことは一言も聞かされていないが。いやたしかに世話役の範疇なのかもしれないが、遊び相手? 自分が? 小さい子どもの遊び相手などしたこともないのに。
しかしマムタの極寒の眼差しにより黙らざるをえない。
アニタと呼ばれた少女は首をかしげた。
「この人が相手してくれるの?」
「ええ、その通りです。彼は僧の中で一番遊びに通じている者ですからね。遠慮なく何でもきいていいのですよ」
そうでしょう? と話を振られたセーバは乾いた笑いを貼りつけるしかなかった。そうでもしなければ、女官長殿に眼光だけで殺されていたことだろう。
「ただ、今日は予定が詰まっていますから、遊ぶのは明日からにしましょう」
マムタが手を叩くとすぐに別の女官たちが入ってきて、アニタの手をとった。
「そうなの? じゃあまた明日ね、セーバ」
アニタはすぐに女官たちとともに歩き出そうとはせず、セーバを見上げて笑った。可憐な花が咲いたような笑みだった。神の厳かな空気は欠片もなかった。
セーバは咄嗟に言葉を返せなかった。ただ今の感情を突き詰めていけば、きっとよくないことになるだろうと、おぼろげな警鐘が鳴り響いた。
口を開いたときには、女官たちに寄り添われながら少女が扉の向こうに消えていくところだった。
気まずさを取り繕うように咳払いをし、マムタに向き合う。
「今日は顔合わせということですか、女官長さま」
「待ちなさい。まだあなたには話があります」
今すぐにでも踵を返しそうなセーバをマムタはこわばった顔で呼び止めた。
「なんでしょうか」
「あなたは気づいていますか?」
先ほどの違和感が頭をよぎった。
「……もしやニドサータはまだ君臨されておられない?」
「ええ、その通りです」
「まさか、アニタは器になれないと」
「馬鹿なことをおっしゃらないで!」
壁まで震える怒鳴り声にセーバは体を震わせた。気まずげに視線をそらし、マムタは押し殺した声で言った。
「アニタが次のニドサータさまになることは確実なのです。なぜなら先代が直々に指名したのだから」
「ではなぜニドサータはおりられていない」
「これは寺院の中でも限られた者しか知らない秘密なのですが、あなたには教えなければなりませんね。いいですか、今から言うことは決して他言なさりませぬように」
じろりとねめつけられ、セーバは何度も首を縦に振った。マムタは深く息をつくと、重々しく口を開いた。
「ニドサータさまがおりられるまでには準備が必要なのです。まず先代が亡くなってから一年以上経過していること」
「喪に服すというわけですか」
硬い表情のままマムタは続けた。
「その通りです。そして器が十三になったとき、ニドサータさまは器の中におりられる」
「ああ、だからいつも器が見つかってから、ニドサータとして公の場に姿を現すまで時間があるのですね」
そういえば子どもの頃から疑問に思っていたのだ。なぜ次の器が決まっても、生き神として姿を現すまでに間が空くのか。
「ええ。アニタはまだ十。あと三年はおりられません」
「なるほど。ところで、なぜお……私が選ばれたのですか? 正直、私は庶民の出で、僧の位も下から数えたほうが早い。ニドサータの器に関わるような身分の者でもなければ、子どもの遊び相手としても不適です」
庶民ならば、同じ年ごろの子どもと遊んでいて、子ども相手に最適だと思ったら大間違いだ。日々の生活にあえぐ平民にとって、子どもの時代はお偉い方々が想像するよりもずっと短い。
無慈悲に肌を焼けつくす太陽の光に追い立てられながら、何度空きっ腹をかかえたものか。
マムタは薄い唇を引き結んだ。
「そんなことはわかっています。ですが、先代が息を引き取られる間際にあなたを指名したのです。ニドサータさまのお言葉は絶対。わかったら、早く神仕えの任を果たせるよう勉強なさい」
叩きつけるように置かれたのは、どこから持ってきたのか分厚い本の山。一番上の題には「庶民の文化史」と仰々しい文字が踊っている。どこぞの暇人こと高名な学者がわざわざ平民たちの暮らしぶりをまとめてくれたらしかった。
正直、こんなものを読むくらいならさっさと街に出て、外を駆け回る子どもたちを観察したほうがマシだ。
「あ、ありがとうございます」
もちろん心の声をそのまま舌にのせるほど馬鹿ではないため、セーバは頬を引きつらせながら礼を述べた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
