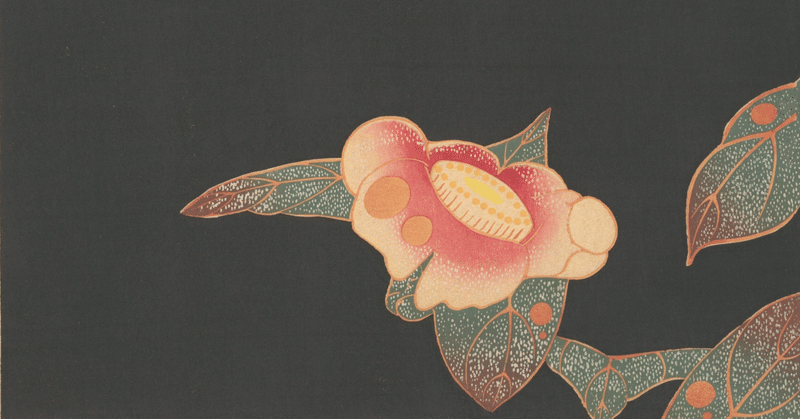
【小説】握り潰された花の名は(3)
神と器の衝撃の真実を知ってしまったセーバ。しかしどうすることもできずに、いたずらに時間だけが過ぎていくだけ。セーバが出した答えは、そして神の器であるアニタの運命はどうなるのか。
上記の話から続く生き神の器の少女と若き僧の、どうしようもない運命に翻弄される話。次で終わります。
三年が経った。国をとるか、アニタをとるか。未だセーバの答えは出ていない。
「ねえ、セーバ」
アニタはまだ少女の域を抜け出していなかったが、ここ三年で背が伸び、輪郭もしゅっとして大人びた雰囲気を醸し出すようになった。まるで蛹から蝶が羽化するように、少女から美しい女へと変わっていく過渡期だった。
「どうしました、アニタ」
視線を少女のほうに戻すと、いつもこちらの顔を真っ直ぐ見て話す少女は、珍しく窓の外を向いたままだった。
窓からは遊び場となっていた芝生が見える。やわらかな日差しが草花の上に降り注ぎ、心なしか草花も生き生きとしているようだった。寂しい冬は遠ざかり、新たな生命が産声を上げる春の気配が近づいてきていた。
「そろそろ神降ろしの時期よね」
「……ええ、そうですね」
その言葉にセーバの心は一層暗さを増した。
神降ろしというのは、器にニドサータをおろす儀式のことだ。この儀式が終わったとき、この世にアニタはいなくなる。代わりに国民から愛される幸福の女神が誕生するのだ。
「この体にニドサータさまがおりたとき、私はどうなるのかな」
窓の外にどこからきたのか一匹の蝶がひらひらと舞っていた。今空の上を流れていく雲のように真っ白な蝶だ。この時期に蝶が舞うのは珍しい。蝶の最盛期はもう少し暖かくなってからだからだ。
「ううん、答えはもう知っているの。きっとニドサータさまがおりられたとき、私はこの世からいなくなるわ」
薄紅色の衣が風にそよいだ。心の傷をこするような乾いた風だった。
アニタは形のよい唇を引き結んだ。
「それでもいいって納得したつもりだった。マムタに私の役目を伝えられたときから、覚悟していたつもりだった。だって、みんな望んでいたんだもの。お父さんもお母さんも私がニドサータさまの器に選ばれたって言われたとき、とても喜んでいたから。私がニドサータさまになることで、みんなが幸せになるんだって。私にしかできないことなんだって。だから、みんなが笑顔になれるならそれでもいいかなって思ってたの。でもね」
アニタが振り返った。大きな黒い瞳は、水気を含んでゆらゆら揺れていた。
「私、ここにきてなりたくないって思っちゃったの。だってまだやりたいことたくさんある! もっといろんなもの見てみたいし、いろんなお話を知りたいし、セーバとだってもっといっしょに遊びたいわ!」
言い終わるや否や、アニタの手がセーバの指を掴んだ。やわらかで小さな手は小刻みに震えていた。
「それは……」
セーバは地面に視線を落とした。
今すぐこの手を引いて館を飛び出してしまいたい。しかし衝動に任せて飛び出せるほど、セーバは若くなかった。
この国を支えているのは美しき幸福の女神と彼女への信仰心だ。器が儀式前に失踪したとなれば、ニドサータがおりることはない。篤い信仰心はひとたび支柱が外れてしまえば、砂上の城よりもあっけなく崩れ去るだろう。
「ごめんなさい。こんなこと言われても困っちゃうだけよね」
眉を下げてアニタは手を離した。風の冷たさがやけに肌を刺す。
「……儀式を遅らせることができないか、できる限りのことは――」
「いいの!」
セーバの言葉を遮ってアニタが叫んだ。血を吐くような叫びだった。
「いいの。そんなことしなくていいわ」
セーバは口を開きかけたが、いっそ悲壮なまでに強い眼差しに口を閉じざるをえなかった。
「かわりに約束してちょうだい、セーバ。私が私でいられる最後まで、ただの遊び相手でいてくれるって。あなただけは、私を神の器ではなく、ただ一人の少女としてみてくれるって」
セーバは何も言えず、ただ頷くことしかできなかった。
「お前、変なこと考えているんじゃないだろうな」
突然呼び止められ、セーバは緩慢な動作で振り返った。そこには険しい顔つきの先輩僧が立っていた。
「変なこととは?」
先輩に構っていられるほどの時間も余裕もないが、ここで無視したほうが後々面倒なことになる。
だが表情こそ平静を保ったものの、声には隠しきれない険が乗った。
「お前が一番わかっていることだろう」
「さあ? 私にはわかりかねますが」
荒っぽく首を振って、先輩はため息をついた。
「ニドサータさまの器のことだ。――まさかとは思うが、連れ出そうなんて思ってはいないだろうな」
最後の言葉は限界までひそめたため、セーバ以外は誰も聞き取ることができなかっただろう。
セーバは無言で先輩の顔を見つめた。先輩の顔はますます険しくなり、眉間の皺はそびえ立つ山脈の谷間もかくやというほどまで深く刻みこまれた。
「以前にもあったのだ。ニドサータさまをおろすな、と。女神をおろさずとも済む方法があるのではないか、と主張する愚か者がな。全員器の近くの者だった。馬鹿なことはやめろ。そんなことをしたところで器は救われんぞ。それどころか国中から追われ、家族からも非難され、どこにも居場所がなくなるのだ。もちろんお前もな」
「では、先輩はこのままでいいと考えているのですか。まだ十三の少女に犠牲を強いて、この国の礎になれと、人身御供になれと、それが正しい国の在り方でしょうか!」
「口を慎めセーバ!」
ついに先輩が怒声を上げた。が、セーバも黙ってはいられない。周囲からちらほらと窺う視線が飛んだが、セーバにはどうでもよいことだった。
「慎むものか! どこが幸福の女神だ! 一人の少女を殺してなりたつ女神など、神ではない。ただの人殺しだ!」
先輩は鼻白んで一歩後ずさったが、ふいに顔を背けて低い声で言った。
「もういい。こうなればシェカンさまに進言して、お前を神仕えから外してもらう。神仕えが儀式直前で変更など前例のないことだが、危険な思想をもつ者をそばに置いておくことはできん」
「っ、それは……」
『約束してちょうだい、セーバ。私が私でいられる最後まで、ただの遊び相手でいてくれるって』
アニタの笑顔と言葉がちらついた。並々ならぬ覚悟で器としての任を果たそうとする彼女との約束を破るわけにはいかない。
「それは、それだけはどうかご勘弁を」
腸がねじ切れるような思いで、セーバは頭を下げた。先輩が嘲笑を浮かべる気配がした。
「だが先ほども言ったように、危険な思想をもつお前を放置することはできん」
「ですからっ」
顔を上げた瞬間、侮蔑を多分に含んだ目と合った。
「だからここで誓え。神仕えの任を全うし、決して儀式の邪魔だてをするような愚かな真似はしないと。ニドサータさまの名において誓うがいい」
口内はすっかり乾いているのに、背中にはびっしょりと冷たい汗をかいていた。
「そ、れは……」
「なんだ? 誓えぬのか? では仕方がないな。心苦しいが、シェカンさまに報告せねばなるまい」
先輩はくるりと背を向けた。
「待て!」
「なんだ?」
わざとらしく振り返った先輩に、セーバはぎこちなく舌を動かした。
「誓う。ニドサータの名に誓って何もしない。儀式の邪魔だては絶対にしない。だからどうか、どうか……」
「先輩に対する口のききかたがなってないな。それにニドサータさまを呼び捨てにするとは何という不敬」
「ニドサータさまの名において誓います! 俺は神仕えの任を全うし、儀式の邪魔だてをすることも、愚かな計画を練ることもしません!」
寺院中に響き渡ったのではないかと錯覚を覚えるほど、大きな声が出た。先輩はゆっくりと笑みを浮かべた。
「いいだろう。ここにいる者が証人だ。降臨の儀までもうまもなくだが、最後まで気を抜かぬことだ」
はっと周りを見渡せば、周囲にいたのは先輩と仲の良い僧たちばかりであった。
(まさかはじめから――)
しかしそれを確かめるすべはない。元々身分の低い上に、突然神仕えに選ばれたセーバに味方してくれる者はあまりいないのだ。
腹に鉛のように重いものが溜まる。それを抱えたままセーバは早足で去るしかなかった。
「ついに明日ね」
アニタは凪いだ面持ちで呟いた。
「そんな顔しないで。ね? せっかく一番楽しみにしている時間なんだから、そんな顔されると心が暗くなっちゃうわ」
にっこりとアニタは笑った。いつもと同じ、可憐な花がほころぶような笑みだった。
「そうですね。失礼いたしました」
セーバも無理やり笑みを作った。
年下の、まだ少女の域を出ない子どもに気遣われている。しかももっとも辛い立場にあるのは自分ではない。彼女だ。
自分が悲哀を醸し出したところでどうにもならない。最後ならば笑って見送らねば。
「それでは今日は何をしましょうか」
「決まっているでしょ。ルンガよ」
初めて会ったときの笑顔が目の前の彼女に重なった。
「ずいぶん上手くなりましたねえ」
「そうでしょ! でも結局セーバには勝てなかったけど」
顔を輝かせたアニタは、次の瞬間にはぶすっと唇をとがらせていた。
「今日くらい勝ちたかったのになあ」
「俺とアニタじゃ手の大きさが違いますからね。俺のほうが有利になるのは当たり前かと」
アニタは後ろに倒れた。せっかく整えられた髪が草の上に散らばる。常ならば一応口頭での注意をいれるところだが、セーバは軽く眉をひそめるだけにとどめた。
「それでも、こういろいろ工夫すればいけるでしょ。素早さとか手の器用さで勝てると思ったんだもん」
「素早さでも手の器用さでも、俺に勝ったことはなかったように思いますがね」
「ちょっと! それは思っても心の中にしまっておくものよ」
たちまち眦を吊り上げたアニタに、セーバは思わず吹き出してしまった。
いつもと何一つ変わらぬ応酬。明日も同じ日々が続いていくのだと錯角してしまうほどの気安い空気が流れていた。
「ねえ、セーバ」
「なんですか」
ふいに真剣な顔つきになったアニタにセーバも姿勢を正す。
「あのね、最後に一つだけお願いがあるの」
「なんでしょうか」
上半身を起こしてアニタは真っ直ぐセーバを見上げた。
「あのね、明日儀式の前の見送りに来てほしいの」
「それは……」
セーバは返答に窮した。
つい先日、先輩僧に釘を刺されたばかりなのだ。任は降ろされていないのでシェカンまでは話はいっていないだろうが、マムタの耳に届いていないとは限らない。そうでなくとも降臨の儀の前に身分の低い自分が会うことなど可能なのだろうか。
「ね、お願い。これで最後なの。マムタにも許可はもらったわ」
よくよくみれば握りしめた拳が小さく震えている。
「私の友達として見送って。最後にセーバの顔をみれば、儀式も怖くなくなるから。きっと満足していけると思うから」
アニタは口角を上げた。瞼は不自然にひきつり、今にも泣き出しそうな下手くそな作り笑いだったが、それを指摘してやることなどできなかった。
「……わかりました。明日アニタを見届けます。あなたの友として」
「ありがとう。ほんとうにあなたに会えてよかった。ニドサータさまがあなたを選んでくれてよかった。あなたが最後の友だちでほんとうによかった」
アニタはそう言って力いっぱいに抱きついた。布が湿っていく感触など気にもとめず、セーバも同じ力で抱きしめ返した。
翌日、アニタはかつてみた先代ニドサータのように真紅の衣、孔雀のような花の頭飾り、首と腕には金の輪っかを何個もはめて、額に赤い筋を垂らしていた。
この国一番の晴れ着姿は誰もが振り返ってしまうほど美しい。セーバもアニタでなければ、手放しで褒めていただろう。
「どう? 似合ってる?」
「ええ。とてもお似合いです」
心にもないことを吐いた。だがアニタは心の底から嬉しそうに笑った。目尻にたまった水の玉がきらりと光る。それに気づかぬふりをすることだけが、セーバに許された唯一だった。
「ありがとう。……じゃあね。さようなら」
セーバは唇をかみしめて、ただ深く頭を下げた。
女官たちが館の奥にある儀式への間へとアニタを促す。小さな背が重々しい扉の向こうに消えてしまった後もしばらくの間、セーバは頭を下げ続けていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
