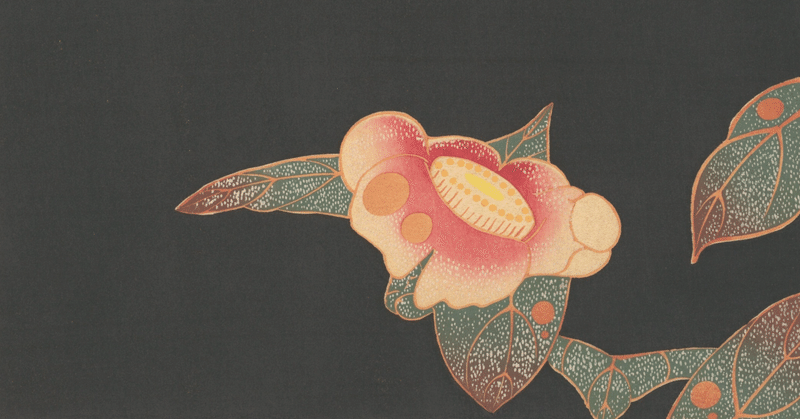
【小説】握り潰された花の名は(2)
理由もわからぬままに先代生き神ニドサータより任命された神仕えをまっとうするため、若い僧セーバは次期神の器となる少女、アニタの遊び相手となることに。
上記の話から続く生き神の器の少女と若き僧の、どうしようもない運命に翻弄される話。
次の日、案内されたのは昨日のかしこまった部屋ではなく、その二つ隣の部屋だった。中は柔らかい座布団がいくつも置かれ、おもちゃらしきものも散らばっている。その窓際に少女は座っていた。
「はじめまして、アニタさま。今日からあなたの遊び相手を務めさせていただきます、セーバと申します」
「さまはつけなくていいわ」
甲高い声がセーバの言葉を遮った。幼さが色濃く残る声だった。日に焼けた肌に白い朝日が落ちる。
「ねえ、セーバ」
「はい、なんでしょう」
子牛のように長いまつ毛が震えた。純粋さを形にしたような目が見る。
見透かそうとしていると思った。しかしあの日のような奇妙な力はなく、緊張も畏れも感じなかった。
「セーバは遊びの達人なのでしょう? だったらそんなにかたーい感じで話さないでよ」
砕けたもの言いにセーバは目を瞬いた。
「はあ、しかしですね……」
𠮟られるのは自分のほうなのだ。勘弁してもらいたい。
セーバは渋い顔で言葉を濁した。
「ね、おねがい。もしマムタや他の女官がきたらいつもの言葉づかいにするから。ずっとこのへんてこな言葉つかっていたら、体かたまっちゃう。それに」
一足飛びにアニタはセーバの目の前までやってきた。手招きされて、反射的に背をかがめる。耳元に温かい息が触れた。
「セーバだって似たようなものでしょう」
セーバは目を丸くした。言外に己の出自と同じなのだ、と彼女はささやいたのだ。
磨かれた一対の黒真珠にいたずらっぽい光が宿る。
「だってどうみても、丁寧な感じ似合わないもん。私といっしょで、そとで育ってきたんでしょ?」
セーバは深く息を吐き出した。
「……わかりました。でも最低限の敬語はつけます。誰かに聞かれて怒られるのは俺のほうですので」
アニタは大きな目をぱちぱちと瞬いて、突然、蕾がほころんだように笑った。
「わかったわ。じゃあ今日からよろしくね、セーバ」
「それで、何をして遊びましょうか」
アニタは器だ。立派な神の器になるために、やらなければならないことは山積みである。その中でセーバとの時間はもっとも優先順位の低いものだ。なぜなら神がおりた後は子どもの時間は一切なくなり、神をこの世にとどめるための入れ物となるからだ。
ではなぜ、このような時間が設けられているのかというと、他ならぬニドサータの要望である。幸福の女神はどうも器に年頃らしさを求めるらしい。神は大人たちによって作られた人工物ではなく、天然物がお好きなようだ。もっとも器に選ばれた時点で大人が介入するので、完全な天然物ではなく、天然物の形をとった養殖物なのだろうが。
つらつらと川のように流れる考えは袖を引っ張る緩やかな主張によって中断された。
「あら、私の話を聞かないの? ほら、私がここにくるまでになにしていたのかな、とか」
きいて、きいてと言わんばかりに瞳が輝いている。自分の要望が断られるなど一切考えていないような、幼子特有の甘えだった。
小さな子どもたちが兄姉の袖を引いて、甘えた声を上げる。壁に伸びる影は多く、自分の足元の影は一つしかなかった。
セーバはかぶりを振って、感傷にも満たない、つまらない記憶を追い出した。どの道、自分の選択肢は一つしかないのだから。
「ええ、それでアニタは昔どのような子どもだったのですか?」
「やだ、ぜんぜん興味なさそう」
アニタは頬を膨らませる。セーバは笑みを貼りつけた。
「まさか。とっても興味ありますよ、ええ」
「いや、ぜったい興味ないでしょ。もしかしてセーバって子ども苦手?」
「苦手ではないですが……」
好きでもなければ嫌いでもない。それが本音だ。年下の子どもと遊ぶ機会がほとんどなかったため、手に余っているともいう。
「思ったけど、セーバって子ども好きでもなければ、遊びにくわしいわけでもないでしょ。顔がそう言っているもん」
誤魔化そうと思ったが、アニタの目は真剣そのもので、煙に巻くのも憚られた。
(遊び相手に心を開かれないというのも酷だろうしな。まあもしこれで気分を害して、神仕えの任を解かれたとしても寺院に戻るだけだ。嫉妬や嫌がらせもなくなるだろうし、どちらに転んでも益がある)
心の中で言い訳を並びたて、セーバは貼りつけた笑みを消した。
「まあ、そうですね。べつに俺は遊びに詳しくもなければ、特別子どもが好きってわけでもありませんよ、ええ。アニタだって俺と同じ庶民だったならば、わかるでしょう。子どもには子どもの仕事があって、意外と子どもの時間はとれないってことに」
ましてや親の庇護を受けられない子どもなどは。それは心の中にとどめておく。年端もいかない子どもに同情をかけられたくはない。口にしたところで、過去が変わるわけでもない。泥は底に押しとどめるに限る。
アニタは面食らったようにぽかんと口を開けた。そこでようやく返答が十の子どもに返すには不適切なものであることに気づいた。
一気に血の気が下がる。
いくらまだ神がおりてきてないとはいえ、これから蝶よ花よと大事に育てられる身だ。これは不敬、いや下手したら磔刑ものであるのではないだろうか。
「ふ、ふふふ」
混乱していた脳内に、軽やかな笑い声が割りこんできた。
「まさかこんなにはっきりいってくれるなんて思ってなかったわ」
アニタは体を震わせて笑っていた。目尻に真珠ほどの水の玉が光った。
「そうね、そうよね。私も家事とかいろいろやることがあって、遊ぶ時間なんてほとんどなかったもの」
ふいにアニタは窓に目を向けた。
「懐かしいなあ。でもいま振りかえると、そんなにわるいものだと思えないの。いまよりもずっとボロボロの家だったのに、草むしりとかいやな仕事もたくさんあったのに、たくさんのハエに追いまわされることも小さい弟妹たちに毛布をとられる心配もしなくていいのに。でもなんでかあの日々にもどりたいの」
それはどきりとするほどの寂寥だった。何か声をかけてあげなければならなかった。でも何を?
「私、なんでニドサータさまの器に選ばれたのかよくわかってないわ」
「俺もなぜ神仕えに選ばれたのかよくわかってないんだ。ただ先代に指名されたってだけで」
口をついて出た言葉はなんとも幼稚なもので、しかも言葉尻を奪うように前のめりに答えてしまった。かっと頬が熱くなった。
「じゃあ私たちおそろいね!」
アニタは弾けるように笑った。つられて先ほどまで顔を真っ赤にしていたのに、セーバも表情を緩めてしまった。
「あ、わらった。ねえその顔でいてよ。そっちのほうがさっきのかたくるしい顔よりずっといいわ」
「はあ」
「あ、戻さないでよ。ここの人たちってみんな恐い顔しているんだもの。セーバは笑ってよ。遊び相手までそんな顔じゃきゅうくつだわ」
眉間に指を押しつけて、こーんな顔、とアニタは思いきりしかめっ面を作った。
「善処します」
「ぜんぜんゼンショしてないわよ」
ぷくっと膨らませた頬がまったくもって神に選ばれた器と思えなくて、セーバはついに声を上げて笑った。
「もう! 笑わないでよ」
天に小さな拳が突き上げられるが、その仕草でさえも彼女の幼さを浮き彫りにする。
「笑えと言ったり笑うなと言ったり、どっちなんですか」
「セーバのいじわる!」
ついに顔を背けてしまった少女に、セーバは片膝をついて視線を合わせた。
「はいはい、すみませんね。それでアニタはどこ出身なんですか? 俺はこの街で育ちましたけど」
途端にアニタは振り返って、顔を輝かせた。
「そうなの? じゃあセーバはずっとこの街にいたの?」
「ええ、まあ。……街ほど華やかな生活ではありませんでしたが」
「そうなのね。私、この街より北の山あいの村に住んでいたの。畑のほかには牛かニワトリしかいないような田舎で、夜になってもハエや牛がうるさいの」
山の急な斜面に広がる段々畑。そして草を食む牛や作物を背負う村人たちの姿が頭に浮かんだ。
「ずいぶん田舎から来たんですね」
「うん、そうなの。でもある日とつぜん、マムタと兵士さんがやってきて、私がニドサータさまの器に選ばれたんだって、腕をひいたの」
「それでここに来たってわけですか」
少女はこくりと頷いた。
「そういえばセーバはどうして僧を――」
問いは最後まで紡がれることはなかった。
「アニタさま!」
扉が勢いよく開き、女官が衣をひらめかせて入ってきた。息を切らしてこそいないが、急ぎの用であることは明白だった。
「お話の途中失礼しますが、次のご予定が迫っていますので……」
その瞬間、アニタは幼いながらも神の器としての仮面をかぶっていた。
「わかったわ。セーバ、ごめんね。じゃあまた明日」
セーバは黙って少女の背を見送ることしかできなかった。
「昨日はごめんね。もっと話したかったんだけど」
椅子に座るアニタは申し訳なさそうに眉を下げた。
「いえ、おつとめもありましょうから」
「あーもう! だからセーバ、その話し方なんとかしてよ」
「敬語は外せないと言ったはずですが」
さすがにアニタと同じ口調では話せない。自分はただの神仕えであり、遊び相手に過ぎないからだ。アニタは昨日のように頬を膨らませたが、すぐに表情を明るくして、椅子から飛び降りた。
「ね、今日はちゃんと遊びましょ。昨日みたいにお話だけで終わるのいやよ」
「そうですね。ではこの部屋にあるおもちゃで……と言いたいところですが、俺は中で上品に遊ぶやり方を知らないので、外に出ましょうか」
アニタはにんまりと口角を上げた。
「うちの中の遊びを知らないなんて遊びの達人のいう台詞とは思えないわね」
「この国には中で遊ぶなんて大人しいもの似合っちゃいません。子どもならやはり外にでなければ」
すまし顔でセーバは歩き出した。後ろから軽やかな足音が追いかけてくる。
今日は事前にアニタの予定を聞いてあるので、昨日のようにはならないはずだ。移動時間と建物の見取り図を頭の中に広げているうちに、自然と歩みが早くなっていった。
館の中庭は人が多く通るので、そこを抜けて、南に抜ける。そこにはまた別の細長い建物が囲っているが、それは四角い館から少し離れたところに建っているため、細長い光の絨毯ができていた。
元々人の往来が激しいのは館内部と出入口だけだ。囲う建物は物置のような場所であり、滅多に人がくることはない。
穏やかな日差しが草花の上に温もりを注いでいた。
「ここはどうでしょうか」
「すてき! で、今日はなにするの?」
「毬も考えたんですけど」
たしかにあの部屋の中には毬があった。しかし金糸や鮮やかに染め上げられた絹糸で織られた美しい毬は、遠い東の国からわざわざ取り寄せられたものだ。そのような高級品は外遊びには相応しくない。
「これでどうでしょう」
しゃがんでとったのは小石たちだ。アニタの大きな目のきらめきが増した。
「ルンガね! 懐かしいわ」
ルンガというのは複数の石を用意し、一つの石を上に投げ、それが落ちるまでに決まった数の小石をとる遊びである。ただし拾うのは投げた手と同じ手のみで、両手を使ってはいけない。とても単純な決まり事だが、やってみると石が着地するまでの時間が短く、たくさん拾うのは案外難しい。
「どちらからやりますか」
「じゃあ私から。これ得意なのよ。三つまではよゆうでとれるんだから」
「ほう、ではお手並み拝見といきましょうか」
小石が青空に向かって放り投げられた。
「すごい! すごい! 六つもとるなんて初めてみたわ」
「まあ、昔取った杵柄というやつですね」
ぴょんぴょんと飛び跳ねるアニタにセーバは苦笑をこぼした。
こんなものとったところで何かあるわけではないのだが、少女にとっては驚くべき技に映るらしい。
これは石があればできるのが良いところである。どんなに貧しい者でも、地面に転がっている石を使えば、タダでやれる。国民の誰もが知っている遊びだから、道端で子どもが宙に石を投げていたって気にもとめない。
「でもすごいわ。ぽんと投げたと思ったら、ぱっととっているんだもの。さすが遊びの達人ね」
「まあ一応そういうことになっていますので」
やや含みのある返しにアニタはくすくすと笑った。
「どうです、アニタの様子は」
「今日も楽しく過ごしておられましたが」
「それはようございました」
一切感情の乗らぬ顔でマムタは頷いた。
セーバの仕事は順調だった。ルンガの日もあったし、部屋においてあったコマでコマ回しをしたこともある。雨水が滴る日は本を読み、それが飽きれば輪っかと玉を複雑に組み合わせた幾何学玩具を二人で頭を悩ませながら、解いた。もちろん、寺院に戻れば、同僚たちの冷たい眼差しが突き刺さるが、セーバの心はもうそれほど痛みはしなかった。
「ところでニドサータがおりてくるのが十三であるならば、三年の空白はどうするのですか?」
「ああ、それは私たちがアニタを通してニドサータさまから預言をたまわるのです。まだおりられていないといえど、心をこめて祈祷を行えば、ニドサータさまはいつだって私たちに道を示してくれるのです」
思い返せば、たしかに歴代のニドサータの器たちも姿を現すまでに間が空いた代もあったが、そのときは彼女のお言葉が定期的に国民の前に開示されていた。
どこか恍惚とした光がマムタの目に宿る。それをセーバは一歩引いたところで眺めていた。セーバの冷めた眼差しを察したのか、マムタはみるみるうちに眦を吊り上げた。
「まったくそれにしてもニドサータさまも何を考えているのやら。ほんの数年のためだけにわざわざ遊び係まで指名して」
言外に自分の身分まで当て擦られているのを感じ、セーバは苦く笑った。
「そういえばニドサータがおりられたあとは、アニタはもうニドサータの器としての仕事しかしないのですか。十三の子にいきなり神事のみを強制するのは……」
「なにを言っているのです? ニドサータさまがおりられれば器の人格など不要。そもそも神がおりられた時点で人の心がもつはずがないでしょう」
時が止まった。
「……いま、なんと?」
絞り出した声は驚くほどかすれていた。
「ですから、ニドサータさまがおりられればアニタの人格はもう必要ないということです。必要なのは、ニドサータさまに選ばれた体だけ」
「そんな、一人の少女を殺すというのですか!?」
きょとんとした顔でマムタはセーバを見つめた。
「殺すなどと物騒なことをおっしゃらないで。器に選ばれた少女の命はニドサータさま自らが天にあげてくださいます。最上級の名誉ではないですか」
その顔になんの疑問はなかった。心の底から最高の幸福だと思っている。ぞっと背筋に冷たいものが走った。
霞がかった神秘的な眼差しが記憶の彼方から自分を見つめている。彼女の顔はいつの間にかアニタの顔に変わっていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
