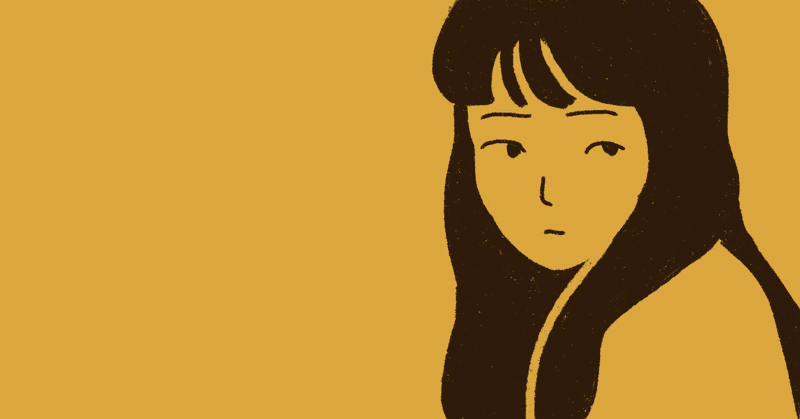
恋と学問 第29夜、告白は歌にのせて。
今夜から、本居宣長33才の作、「紫文要領」(西暦1763年成立)の、結論部分(岩波文庫版、162-184頁)の読み解きを始めます。私たちの旅は予定された目的地を持ちません。読み解いた先に、どんな景色が待っているのか?すべては宣長の筆と、それを読んだ時の私たちの想像力にかかっています。
手始めに結論部分のタイトルについて触れておきましょう。いわく、「歌人此の物語を見る心ばへの事」。
・・・え?
本文の流れをていねいに追ってきた私たちには、驚くべきタイトルです。歌人が、源氏物語を読む際の、心構えについて?
この戸惑いは、本論部分との齟齬に由来します。私たちの歩みを振り返ってみましょう。私たちは本論「大意の事」を、認識論であり、人間論であり、芸術論であり、広義の「哲学」でもあるところの、「もののあはれ論」を中心に、どの時代の、どんな人間にも通用する、客観的かつ普遍的な思想を述べた文章として扱ってきました。それがいきなり、「歌人」という「主語の限定」を受けて、なおかつ、彼/彼女が源氏物語という特定の作品を読んだ時の「心構え」という、これまた特定の状況に条件付けられた事柄についての論述が、本来「結論」が置かれるべき位置に置かれている。・・・これは一体、何を意味しているのか?
さらに、本文に進むと、早々に謎めいた言葉に出くわします。
此の物語の外に歌道なく、歌道の外に此の物語なし。歌道と此の物語とは全く其のおもむき同じ事也。されば前に此の物語の事を論弁したるは即ち歌道の論としるべし(163頁)
【現代語訳】
源氏物語の他に歌道はなく、歌道の他に源氏物語はない。歌道と源氏物語は、その趣において、全く同じである。よって、これまで私が源氏物語について論じてきたことは、そのまま歌道論であったと思ってください。
これではまるで、ちゃぶ台がえしされたようなものです。明らかに人生哲学としか読めなかった本論と、和歌の本質を述べてゆく結論との整合性が見通せないかぎり、私たち読者は途方に暮れて立ち尽くすことになります。
前後のつながりが分からない文章に出くわした時の対処法としては、これをひとつの独立した固まりとして、ひとまず理解しておくことです。そして、理解された内容を、事後的に前段の内容と突き合わせることで、はじめて脈絡が理解されることがあります。今はその方法に一縷の望みを託すことにして、結論部分の要約を試みます。
【結論部分の要約】
源氏物語を読むことは、和歌の本質(歌道)を理解する上で必須の作業である。なぜならば、源氏物語は古代人の生活感と心情を詳しく描いているために、古代の歌がどんな条件の下で歌われたか、その発生起源を読者に教えてくれるからだ。古代の歌の発生起源を知らずして和歌は詠めない。そのわけは、今も和歌というものは、古今和歌集をはじめとする三代集の風情を模倣する決まりになっているからだ。三代集の時代を生きた古代人が、どんな生活感と心情を持っていたか?これを歌の姿だけから知るのは困難である。歌物語には古代人が歌を生み出す瞬間の事情が詳しく描かれている。歌物語の中でも、源氏物語が最も詳しく描いている。だから、源氏物語のほかに歌道なし、と言うのである。
以上が、結論部分のかんたんな要約です。やはり、本論で述べられていた思想との「接続」がよく見えません。源氏物語から抽出された、紫式部の「もののあはれ」の思想は、どこに消えてしまったのでしょう?
問ひて云はく、此の物語を見て、古への歌の出できたる本をしるとはいかなる故ぞや。答へて云はく、古への歌は事にふれて物のあはれをしるより出できたる物也。されば出できたる本といふは、ものの哀れをしる事也。その古への人の物の哀れのしり様はいかなるものぞといふ事をよくしるを、出できたる所の本をよくしるといふなり(166頁)
【現代語訳】
質問がありました。「この物語を読むことで古代の歌の発生起源を知るとは、どういう意味なのか」私は次のように答えました。「古代の歌は事に触れて物の哀れを知ることから生み出されたものだ。だから、歌の発生起源とは物の哀れを知ることである。その古代人の物の哀れの知りようは、どういうものだったかを知ることを、歌の発生起源をよく知るというのである」と。
このように、結論における「もののあはれ」は、「歌の発生起源」という役割を負わされたものとして姿を現します。古代人は何かのきっかけがあって物の哀れを知った時に、はじめて歌を歌ったものなのだ。だから、古代の歌にならって歌を詠もうとするなら、古代人がどんな時に物の哀れを知ったのかを知る必要があるじゃないか。それを知るのに最適な書物が源氏物語なのである、と。
言いたいことは分かります。この主張に異論があるわけではない。しかし、私たちがまだ納得が行かないのは、いかんせん、本論との「接続」の悪さです。本論で「もののあはれ」が負わされた役割を思い出してください。浮舟という女は、二人の男の物の哀れを全く知ろうとして、宇治川に身を投げたのではなかったですか?むろん、浮舟のことは極端な例かも知れませんが、少なくとも、本論における物の哀れを知ることは、そのために損得や善悪を度外視し、時には己の幸福まで犠牲にするほどに、私たちが豊かに生きるための必須条件として、重大な役割を負わされていました。それに比べて、結論における「もののあはれ」は、歌の発生起源という、あまりにも小さな役割しか負わされていないように見えます。そして改めて、なぜ物の哀れを知る主体が「歌人」に限定されているのか?これもまた、本論で行われた議論の矮小化に思えます。
さて、疑問が噴出したところで、いったん「紫文要領」を離れて、宣長の同じ時期の作品、「石上私淑言」(いそのかみささめごと)を取り上げてみます。そうすることが、解決の糸口になると思われるからです。
まず、「石上私淑言」の、宣長のキャリアにおける位置について整理します。宣長の作品は数多くありますが、私が勝手に「5大作品」に数えるのは以下の5冊です。
1.排蘆小船、25才、和歌の本質について
2.紫文要領、33才、源氏物語について
3.石上私淑言、33才、和歌の本質について
4.古事記伝、34-68才、古事記について
5.うひ山ぶみ、68才、学問の方法について
以上の位置関係から分かることがふたつあります。ひとつは、「石上私淑言」の執筆が、同じく和歌論だった処女作、「排蘆小船」の語り直しを意味したということ。しかも、「紫文要領」を間に挟むことで、「もののあはれ論」を踏まえた和歌論として発展したということ。もうひとつは、「石上私淑言」が「古事記伝」という35年におよぶ大研究の直前に置かれているということ。このことは、宣長が「紫文要領」から「古事記伝」へ、直接にジャンプしようとしたが果たせず、「石上私淑言」という「跳躍台」を必要としたということを暗示します。
「石上私淑言」は「紫文要領」と同年の成立とされています。しかし、本文中に「紫文要領に詳しく言へり」とあるように、前後関係は明らかで、「石上私淑言」は仮に「紫文要領」と同時に書き始めたとしても、その脱稿は「紫文要領」完成のあとだったのは間違いありません。
以上のことから、私たちが今見ている「紫文要領」の結論部分が、唐突な歌道論であることの理由が分かります。つまり、「紫文要領」の結論部分は、「石上私淑言」の導入部分を兼ねているのです。ありていに言えば、両者は「姉妹篇」の関係にあります。したがって、「石上私淑言」に書かれた内容から、「紫文要領」の結論部分を読み解くことは、その位置関係から言っても正当かつ有効なのです。
では、この「石上私淑言」の本文を使って、先ほど噴出した疑問に答えていきましょう。まず、「もののあはれを知る主体が歌人に限定されているのは何故か」について。
人のみにもあらず、禽獣に至るまで、有情のものはみな其声に歌ある也。・・・鳥虫なども、其鳴声の程よくととのひておのづからあやあるはみな歌也。・・・いける物はみな情有りて、みづから声をいだすなれば、其情より出でてあやある声則ち歌也
(本居宣長「排蘆小船・石上私淑言」岩波文庫、2003年、158-159頁)
【現代語訳】
人間のみならず、禽獣に至るまで、心を持った生き物はすべて、その声に歌があります。鳥や虫なども、その鳴き声が程よく調っていて、自然とリズムがあるものは、すべて歌です。生き物には心があって、その心が声を出させるのですから、その心から出ていて、独特のリズムがある声は即ち歌なのです
宣長はここで、誰もが、動物も含めて、己の歌を歌っているという、素朴な事実を指摘します。私たちは誰もが歌人なのです。したがって、「歌人此の物語を見る心ばへの事」というタイトルは、実は主体を限定しているわけではなかったのです。ここで言う「歌人」とは、「人間、この歌う存在」というような意味合いです。すべての人間に備わっている本質的性格という意味で、「歌人」の言葉は選ばれています。
人間という、歌わずには済まされない存在が、源氏物語を読む際の、心構えについて。結論部分のタイトルは、このようにとらえ直され、「主語の限定」の謎は解消しました。
続けて解かねばならない謎は、なぜ「もののあはれ論」が、豊かに生きるための条件から、歌の発生起源へと、その役割を変更したのか?一見するとこれは、役割の限定・縮小のように思えるのですが、「石上私淑言」の議論は私たちに、歌が人生に対して果たす役割の大きさについて、考え直させるきっかけを与えます。
さて于多(うた)といひ、于多布(うたふ)といふ言の意は、一説にうつたふる也、心のうちに思ふ事を告訴(つげうた)ふる意也といふ。今按ずるに、常にはうつたふといへども、刑部省を和名抄に宇多倍多々須都加佐(うたへただすつかさ)とあれば、于多布留(うたふる)が本語にて、于都多布(うつたふ)といふは俗語也(203-204頁)
【現代語訳】
さて、「ウタフ」という言葉の語源は、一説によると「ウッタフル」で、心の内に思うことを告げ知らせることだと言います。この説を検討してみますと、今の世では「ウッタフ」と言いますけど、「和名抄」という本には、刑部省という官庁のことを「ウタヘタダスツカサ」と読んでいるので、古くは「ウタフル」と言っていたものが、後世になって「ウッタフル」に音便変化したのでしょう
非常に刺激的な主張です。いわく、「歌う」と「訴える」は、元々同じ言葉だった。そして、「訴える」の原義は己の内面を人に告げ知らすこと、つまり「告白すること」だった、と。ならば、歌を歌うことは単なる趣味事ではないことになります。心の奥底に秘めた根本感情を、誰にも知らせず生きることなど、誰に出来るでしょうか?仮に出来たとしても、それは辛いことです。人は歌いたいから歌うのではない、歌わずにはいられないから歌うのです。それが「歌う=訴える=告白する」の意味です。
告白することとして捉え直された歌うことは、「もののあはれを知ること」を発生起源に持ちます。物の哀れを知るたびに、人は歌わずにいられなくなる。心の奥底に秘めた思いを、思わず人に告白してしまう。その行為は、人間に限らず、感情を持つ動物なら皆が皆、日々行っていることです。私たちは、歌わずには豊かに生きられません。
心の奥底に秘めた思いは、最も人に伝えにくいことです。しかし同時に、それは最も人に伝えたいことでもあります。この難題を説くのは、客観的で非の打ちどころのない、「論理の言葉」ではありません。「歌う=訴える=告白する言葉」です。
以上で私たちは、「もののあはれの役割が縮小したのは何故か」という謎に、答えたことになります。実のところ、物の哀れの役割は縮小などしていなかった。物の哀れを知った先には、必ず歌が待っているから。だから、歌の本質を述べる結論が、物の哀れを知る重要性を説いた本論のあとに置かれていることは、それほど不思議なことではなかったのです。・・・もちろん、それを理解するために、こうして長々と読み解かなければならないのですから、宣長の議論には相当の飛躍があるのも確かですが。
さて、今夜はこのへんにしておきましょう。
私たちは今夜、結論部分の重要な主張を、あえて触れませんでした。それは、「歌人は古い歌を手本にすべきで、そのために源氏物語を参考にせよ」という主張です。この解釈は次回の宿題とします。
それではまた。
おやすみなさい。
【以下、蛇足】
今回は、紫文要領の結論部分が、唐突な歌道論として始まる理由について考えました。歌は歌うことが好きな人の趣味事に過ぎないという通俗的な考えに、宣長は真っ向から対決します。誰もが歌人なのだ。歌わずに済ませられる人生などないのだ。と、力強く論ずることで、宣長は本論部分の中心的なテーマだった「もののあはれを知ること」に、新しい光を当てたのです。
このような議論は、当然のことながら、歌うという行為に「普遍的な生の営み」という地位を与えることになるのですが、一方で宣長は、歌は古今和歌集を手本として詠むべきこと、そのために源氏物語を参考にすべきことを主張します。普遍から特殊へ。この「逆走」は何を意味するのでしょうか?
謎解きはまだ終わっていません。
次回もお楽しみに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
