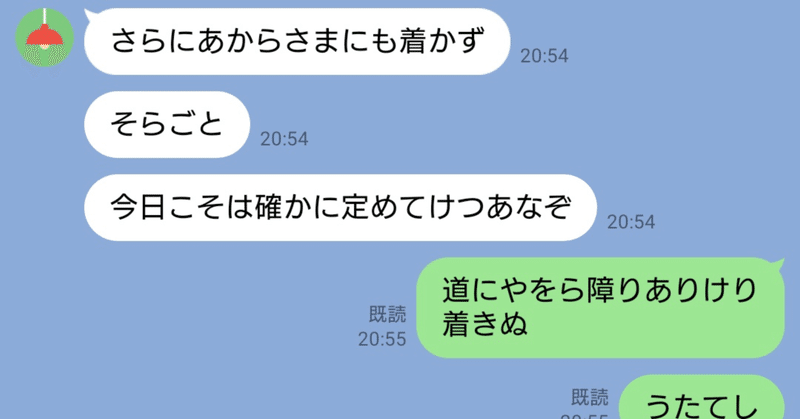
『未読の哲学』 〜実存的観点からの現代的再考〜
現代というものを定義するときに、さてそれはどこからが現代と言えるだろうか。
近代は個人主義の時代であった。デカルトが「我思う、ゆえに我あり。」と言ったことが近代という時代を世界史から分節化し、駆動させた。近代は個人というものの実在を疑わない。いま、ここにアプリオリな自己というものがいて、それは認識の範疇にあるということが自明である。そんな条件の下に、近代は展開した。
であるから、近代の関心というものは自己に対しての他者であった。それは他人というよりかは、広く全ての外在物をいうのである。例えば、社会体制である。アダム・スミスは原始資本主義を、マルクスは市民社会成立以後の資本主義を分析したし、ルソーは社会というものがどう成り立つのかというプロセスを社会契約によって説明しようとした。
近代は「個人の実在」を疑わずに、人間が培い広げゆく、世界というものを解き明かそうとした。では、現代は?果たして、現代は何をしているのか。
個人主義の時代。現代はそう定義することができるのではないか。ここにおいて大きな意味を持つのが実存主義である。実存主義哲学は個人とは何か、万物の一般真理ではない、「わたしの真理」を求めた。そしてそのことは、個人というものの存在を明確たらしめた。現代を個人主義の時代というならば、実存主義と現代には切っても切れないものがある。実存主義は大きな潮流で言えば、キェルケゴールからということになるのだろうが、私はそう言いたくない。「現代はニーチェから始まった。」、と定義したいのだ。ニーチェ ー ハイデッガー ー サルトル というこの系譜が実存主義の姿を明らかにした。彼らは"神の死んだ"無神論的世界観としての現代を描き出したのだ。
他方、一般に実存主義は死んだと言われる。構造主義者によって徹底的な批判をされたのち、思想界においては落日を見ることとなった。ポストモダン以降の思想に少なからぬ影響はあるにしろ、分析哲学と言語哲学がもはや主流研究分野となった今の哲学界において純粋哲学は長らく日の目を見なくなっている。(ドイツのマルクス・ガブリエルが「新実存主義」を掲げているものの理解者が少なく、研究の進展が望まれるところである。)
さて、個人の現代である。個人の現代とは、ただ個人が世界から分別されて存在することではない。その逆である。あなたとわたしの関係が無限に連関することによる、現代である。わたしとあなた。一般的に言えば、この世界の関係性というのは「わたしとあなたとそれ以外」なのだろうが、実は違う。三人称というものはなくて、あくまで二人称、つまり「"わたし"以外の全て」がこの世界に広がっている。家族や友人はもちろんのこと、ペットの犬から今ここにあるピアノ、椅子、魚の切り身、空気、社会。有機無機を問わず"わたし"以外の実在すべてを"あなた"と捉える。
"わたし"は嫌が応にも"あなた"と関わらなければならない。『ドラゴンボール』の精神と時の部屋のような外界から遮断された極限空間はこの世の中にはない。絶えず、わたしは外在するなにかに寄りかかり、寄り掛かられている。いま、どこかでこの文章を読んでいる時でさえ、椅子に座るやら、床に座るやらしている。あるいは、空気に触れてすらいる。
人間実存においてもそれは全く同じことだ。"わたし"と"あなた"の連関は実存的一般のわたしとあなたにおいても成り立ち、そしてそれは現代のもっとも重要な特徴なのだ。
すなわち、古代〜中世までの実存的交わりはあくまで構造主義的なものであった。交通や情報の網が限定されており、あくまでローカルなコミニュティに人が閉じ込められていたからこそ、関わらなければいけない実存というものは極端に制限されていた。要するに、出会う人間を自分で選択することはできなかった。結婚するにもやはりこれは年頃の相手は限定されるだろうし、ましてや中世では特に身分制社会において、貴賤結婚が忌避されたことも思い出される。このように自身の意思とは無関係な超越的外在によって、人生が確定していったのだ。
近代はこのような構造主義的な人間関係に対して、構造を破壊していく方向性を打ち出した。というのもそれは、先ほど述べたように自己に対して外在するものに対する興味が近代の通奏低音であることは、技術的障壁を破壊することで、決して乗り越えることのできなかったはずの実存間の交流を可能にした。交通革命、あるいは資本主義的な生産関係による都市への人口集中、国際的な報道網の整備が主たる例だろう。本来なら交わるはずもなかった個人と個人が、近代的技術によって対面することになったのだ。
近代的技術はある意味で実存に対して自由を与えたのかもしれない。意志さえあれば誰とでも関わることのできるだけの手段が我々に渡されたのである。しかし、封建的人間関係、固定化された人間社会は近代においても依然として根強く残り続けていた。手段と意志はあっても、「あの人とはきっと一生交わる機会がないのだろう、"住む世界が違う"から」と一言で諦めてしまう。これが近代という世界の矛盾であった。"見える"障壁がなくなってすぐそこにいるはずのあの人は、"見えない"障壁によって遮られてしまっていた。
そんな近代の不完全性を補完するように現代は、"見えない"障壁を打破した。いや、完了形を用いるのはナンセンスかもしれない。正しくは言うなれば、「打破しようとしている。」。いずれにせよ段々と"見えない"障壁がなくなっていることは事実だろう。代表例をあげるならば、ここ50年間の女性の権利の向上には凄まじいものがある。あるいは、少数民族、性的少数者などの一般的に近代において社会の外に配置されていたマイノリティが社会的な権利の面においては確実に対等な権利を確立しつつある。はたまた、グローバリズムは二つの大戦時には、絶望的なまでの深さを思い知らされたナショナリズムと国民という強いアイデンティティさえも乗り越えたコミュニティ形成を促している。
そしてーこれが最も重要なのだがー近代の流れを汲んだ技術の発展と現代のこの個人主義的な"見えない"障壁を取り払うという二つの潮流は巨大なムーブメントを巻き起こした。それこそが、SNSである。
SNSはすごい。本当にすごい。私自身、そこまでITというものに精通しているわけではないい。むしろ、同世代からすれば疎い方かもしれない。しかし、それでも一人間として、あるいは哲学人として、この新たな革新的ツールを称賛せずにはいられない。
SNSは"見えない"壁をまったく過去のものにしてしまったように見える。今ここで"見える"とあえて含みを持たせたのにはもちろん理由がある。
さて、SNSの最大の特徴はなにか。それは同一平面に全てのアカウントが表現されることである。貴賤問わず、国会議員だろうが世界的アーティストだろうが、一介の地方公務員から大学生果ては小学生まで、例えばTwitterや Instagram、Facebook、あるいはnote、という同じコミュニティ上に生息する。たった一つのアカウントさえ作れば、世界への容易なコネクトを可能にするのがSNSなのである。
しかし、かといって完全に誰でも彼でも岸田文雄総理にコンタクトが取れるわけではない。片方向的なコンタクトはリジェクトされる可能性があるのが現代のSNS社会だ。だからこそ、壁が完全に取り払われていないと言ったのである。むしろ、現代は技術によって完全に破壊し尽くされた実存間の壁を自分の意思で作り直す権利を与えたのではないか。その壁は薄くも厚くも、あるいは全く取り払うこともできる。私たちの関わりは全く自由になった。
これはTwitterのような「わたしとあなた」という個人対他者一般の関わりに関してだけでなく、LINEのような実存と実存がより密接に、限定的な状況で関わり合う場においても同じことである。
LINE型、あるいはショートメッセージ型のSNSはその本質を「対面の再現」に置く。技術的には以前からCメールなどで可能だった短文型メッセンジャーは過去には普及しなかったにもかかわらず、今になってからLINEなどのSNSによって大衆に膾炙している。この状況は一見奇妙に思える。実は、ここに現代というが作用しているのである。現代の気概ーつまりそれは個人主義ーは、手紙やEメールのような明らかに対面とは隔絶されたコミュニケーションツールを乗り越えようとする。あくまで実存的実存連関を求めるのだ。この現代の志向に見事に応じたのが、LINEを始めとするメッセンジャーアプリだった。
人は、あたかも目の前に人がいるかのようにメッセージを送る。脊髄反射のように素早くレスポンスを送り、言葉のキャッチボールのような短文の受け答えが繰り広げられる。まさに現実の会話の本質がそこに投射されている。
とはいえ反論を思い浮かべた人も多いのではないか。会話そのものになれるはずないじゃないか、LINEと日常会話はまったくもって異なるものだ、と。いくら対面を意識したとしても、生身の肉体でないなにかに媒介された意思疎通を行なっている限りそれはあくまでも会話っぽいなにかでしかない。"会話自体"にはなりうるわけがないのである。つまり、会話というものはあなたの喉から出る声と、私の喉から出る声の物理的交わりでなければならない、ということだとも言える。
この見方は、「実存的交わりが肉体の紐付けによって初めて成り立つ」という前提によって支配されている。裸の付き合い、とでも言おうか。人の肌身暖かさを感じるような今ここにある関わり、今現実に肉体を通してengageしている関係性のみを実存的だとみなすような狭小で卑猥な見方。これこそが私たちのコミュニケーション世界を支配している底律ではなかろうか。
私はトランスヒューマニズム的観点からこの底律を完全に否定したい。技術は進歩した。技術の進歩は、一見人間実存そのものとどんどん乖離していくかのように見える。ロウソクは誰にでも作れるが、LED電球は誰にでも作れはしまい。しかしながら、技術の進歩は進めば進むほど実存と一体化していく。いや、実存が技術にengage(アンガジェ)していっているのだ。たった十数年前まで未開部族だった者たちでさえ、スマホを持ち、画面に映る名前もわからないハリウッド女優の美しさに見惚れている。あるいは、ICチップを体内に埋め込むことで手をかざすだけで電子決済が可能になっている。技術は人間社会を覆い尽くすだけでは飽き足らず、人間実存の中に入り込もうとし、人間もまたその技術を取り込もうとしている。実存的幸福のためにはtechnicalengagemntをしなければならない状況が出来上がっている。
であるからに、LINEのようなメッセンジャーアプリは会話の写像というよりかは、その技術が実存に取り込まれたと考えるべきではないだろうか。つまり、"会話自体"が縮尺的に存在しているのではなく、"会話自体"が技術的進化を遂げた形としてLINEを捉えるということである。新しいコミュニケーションの形、それがLINEであって決して対面の代用品ではないのだ。
「LINEは会話の進化形態である」という命題は明白に真だ。しかし、それが共通認識かどうかはまた別の問題である。
LINEをしていれば、あるいは他のメッセンジャーアプリにしても、誰しもが「未読」、「既読無視」に接したり、することがあるだろう。なぜかはわからないが、既着のメッセージをいつまでも返そうとせず、放置する。こんな経験は多くの人にあるだろう。では、なぜ我々はこんな行動をとってしまうのか。これは多くの人にとって喉から声が出るほど知りたい真理なのではないか。
皆の欲しい真理は、先ほどまでの議論が完全にアナロジーされて描かれる。LINEは"新たな会話の形態"だと定義した。これが真理である、と言ってしまえばそれはそれで正解にしていいのだろうが、あまりに漠然としているのでもう少し詳しく言おう。さて、会話の新たな形態であるLINEは、私たちの実存的交わりにおいて一体なにを進化させたのだろうか。これまた漠然としているが「自由」を与えたとは言えないだろうか。
LINEは日常会話と違い、「レスポンスしない自由」を与えた。うなづくことも、あるいは話しかけられて必ず聞かなければならないこともない。LINEというSNS世界はレスポンスをするかしないか、という今までの会話では考えられなかった選択を可能にしたのである。これは会話革命である。肉体的実存主義者の観点から言えば、それは会話の条件を満たさない不十分さの最たるものであると非難を受ける点なのだろうが、進歩的実存主義の観点から言えば、LINEは会話に「自由」を与えたといえる。
しかし、この「自由」は我々に会話の利便性を向上させた一方で、歪みを生んでいる。
世の中はやはりLINEを「会話の延長線上」と捉えがちだ。あくまでそこにあるルールは日常会話かあるいは古典的なEメールのものが適用されると思っている。確実な思いがなくとも、これはある種の現代的道徳として私たちの心の奥底に定着しているものだ。「早く返信をすることは当たり前」この道徳がLINEの会話革命に重い影を落とさせている。
「早く返信することは当たり前」という道徳はそれ自体に問題はない。つまり、例えばそれが会社の常務とか目上の人だったり、親だったりあるいは友人だった場合、この国に古くからある儒教道徳の延長としてこの「早く返信することで礼を尽くす」という道徳は論理的正当性が担保されるからである。
厄介なのはかかる命題の対偶だ。「早く返信しないことは当たり前でない」という命題は必ず真になるわけだが、この命題に問題がある。すなわちそれは、「当たり前でない」ということの解釈に関わる問題である。「早く返信することが当たり前だ」と思えば思うほど、未読や既読無視が行われた時に、その状態を「異常」と捉える気持ちは大きくなる。それは先の対偶も真であるという事実からくるものだ。人は「異常」に思いを馳せる。果たしてこの人はなぜいつもと違う対応をとってしまうのだろう?と。これは未読の必然だ。そういう場合、人はものすごい恐怖を抱くか、あるいはその恐怖が怒りに媒介される蓋然性が高い。自分の悪を疑い、相手に申し訳なくなるか、相手の一方的な悪に対して憤慨するかの二択である。
そうなると、実存的交わりは破綻の色彩を帯びることになる。「早く返信はするもの」と思っている人にとって、遅読未読は実存的裏切りに他ならないからである。LINEの普及によって、多くの友情が、未読によって破綻の色彩を表現され、あるいは破綻の色彩が未読により湧き出てくるようになった。
これは大問題だ。しかし、LINEを会話の延長線上に捉え、儒教道徳の伝統的価値観がそこに当てはめられ続けていく限り、なにも状況は変わらないだろう。
なぜ、我々が未読をするのか、といえばそれは権利だからである。技術の発展が会話に及ぼした"レスポンスの自由化"という会話革命が我々に権利を与えた。権利は行使が本来自由なはずである。しかし、伝統的価値観はその行使を悪とみなし、自制させようと強いる。これがLINEの未読の構図ではなかろうか。
何度でも言うが、未読は権利の行使である。なにものにも縛られない完全に自由なはずの権利である。古い価値観に固執する旧人だけがこれに心地を悪くする。さて、君は旧人だろうか、頻繁に権利を行使する諸君、決して罪悪感を被ることなかれ。あくまで悪いのは旧態依然とした価値観を保持し続ける人の方にあるのだろうから。
もうすこし内容を深めたいが、それはまたいずれの機会にしよう。なにか疑問反論があれば是非聞きたいものだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
