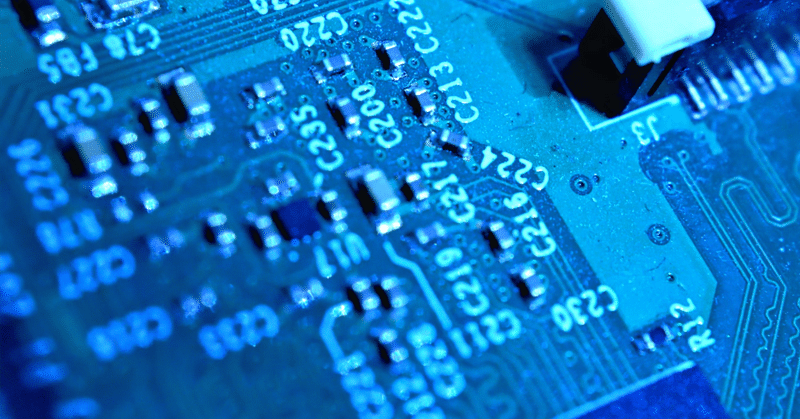
人事制度はなぜ精緻化に向かうのか?~人事制度を活かせるか?制度設計時に陥りがちな罠
”実務協業型”人事制度構築・導入支援を行う株式会社Trigger 代表の安松です。
人事制度の“完全性”をどこまで追求すべきか?
人事評価の透明性や従業員の納得感をいかに高めるか?おそらく非常に多くの、もしかしたらすべての会社・組織が、何らかの悩みや問題意識を持っている領域でしょう。
人事制度構築や組織力強化のご支援をしていると、この領域のご相談はとても多く、そして課題や解決へのアプローチも各社各様で、経営者や人事担当者の腐心がうかがわれます。
例えば多くの企業様から、「職種ごとの詳細/精緻な職務内容や能力評価基準を作ったが、異なる職種間でのレベルが合っているのかがわからない。どう合わせたら良いかがわからない。」というご相談を受けることがあります。
この問題は果たして解決できるのか?そして、人事制度の“完全性”はどこまで追求できるのでしょうか?
“完全性”を追求したA社の悩みと、その後の発想転換
A社からのご相談の事例を紹介します。
A社では、3つの主要事業において約20種類の職種があり、その職種ごとに職務内容と習得すべき能力のレベルを書き分けた「ジョブ・スキルマップ」を作り、評価制度に組み込み、活用を志向していらっしゃいました。
非常によく検討された詳細な記述内容で、それ自体はとても素晴らしいものである反面、お悩みは「異なる職種間・同レイヤーに期待する成果や能力の基準が果たして揃っているのだろうか?どう揃えたら良いのだろうか?」というもの。
人事担当者なら直面する可能性が高い課題かもしれません。皆さんならどう考えますか?
世の中には、いわゆる職務評価(Job Evaluation)のメソッドは幾つか存在しており、名のある人事コンサルティングファームがサービス提供しているものや、研究機関などが公表しているものがあります。これらのサービスを購入したり活用したりすることによって、異なる職種間での職務や必要な能力レベルの違いを判断していくというアプローチはありえます。ただ、私自身も事業会社の人事担当者としてこの種のメソッドを活用して人事制度構築をした経験に照らして言えば、これらのメソッドは判断に一定の客観性・論拠を与えはするものの、やはりどこまで突き詰めても最終的には組織(経営者)の主観的な判断・重みづけによって決まる(判定結果が変わる)、元来そういう代物であるということを理解することが肝要です。
A社の例に戻ると、20種類の異なる職種について、何らかの基準を以って“真に”正確なレベル判定を行うことは不可能であるということです。やっている仕事が異なるわけですから、これを突き詰め、合わせ切ることは現実的には不可能であるということを割り切らなければなりません。まずはそのことを提言し、共通認識を持つことから行いました。
ただ、上述したとおり、職種ごとの「ジョブ・スキルマップ」自体は非常によく練られた良いものであるため、これを活用しない手はありません。
A社では各職種のジョブやスキルを通じて期待される組織における役割や成果を役割等級という形で包括的に言語化し、職種ごとの「ジョブ・スキルマップ」は役割等級定義を補完するものという位置づけに整理することにしました(細則しかなかったところに、本則を作ったようなイメージです)。
この事例を通じ、改めて感じたことがあります。
なぜ私たちは「基準の精緻化」に向かうのでしょうか?
基準の精微化に気持ちが向かってしまう心理
おそらく、作り手の深層心理として、人事制度を、「守るべきルール」という感覚で検討すると、その要件は「できるだけ例外を作らないこと」となり、ルールとしての完全性を追求するマインドに陥ります。しかし、いくら人材を要素分化して詳細に要件定義したとしても、そもそも人材(人間)は多様であり、人材が働く状況も多様であり、完璧に合致することなどありえません。
では、基準は無くて良いのか?あるいは基準はアバウトで良いのか?というと、そうとも言えません。制度には「守るべきルール」という側面は必ず存在し、そしてその有効性もあるからです。例えば人事評価の基準があってそれが守られることは、機会の公平性を担保したり、評価者の恣意性を薄めたりするためには有効です。
したがって私たちは、「制度ルール」という側面の必要性を理解しながらも、言い古された表現ではありますが、「制度はツール」(ある目的実現のための枠組み)であるという志向を持ち、「ルール」と「ツール」の間で、自分たちの立脚する立ち位置をきちんと認識する必要があるのではないでしょうか。
人事制度の価値を高めるために必要なマインド
昨今、この認識の重要性が改めて感じられる事例が多くなっているように思います。例えば従来の目標管理(MBO)に変わるパフォーマンスマネジメントの手法として注目されているOKR(Objectives & Key Result)や、No Rating(従業員のランク付けを行わない人事評価手法)は、「制度はツールゆえ、より合目的的にその使い方を工夫する」という志向の中から生まれてきたように感じられます。ここでいう“合目的的”とは、人材のパフォーマンスを真に高め、組織成果の創出と従業員のキャリア・市場価値をより高めていくことです。形ではなく実を取りにいくスタイル、とも見えます。
まずは、 「管理のためのルール」 から 「人材を生かす/パフォーマンスをあげるためのツール」に意識を転換する。そうすることで、組織・マネジメントにとって人事評価制度は、 「管理者として人材を正確に判定するためのモノサシ」 から 「支援者としてメンバーのパフォーマンスや力量を上げるための材料」に変わります。また、従業員にとっては、 「管理されるための箍(たが)/自分を縛るもの」 から「成果や能力向上など自身のパフォーマンスを立証するもの/自分の価値を提示するもの」に変わります。
制度設計のマインドセットが、モニタリング指標の見方も変える
そして、「ルール」と「ツール」、どちらのマインドに立脚するか?は、組織・人事に関する指標やデータの見方にも影響を与えます。つまり、ルールであれば「守られているか?」が問題となり、ツールであれば「どう使われているか?」が問題となります。このことは、昨今のトピックスである人的資本情報の開示に対する取り組み方にも影響を与えるはずです。
「いま自分たちは「ルール」と「ツール」、どちらのマインドに立脚して考えているのか?」
「現案はどちらの性格が強調されていて、それで良いのか?」
人事制度や各種施策・取り組みを検討している経営者の方や人事担当の方にあっては、このことを自問し、自分たちの立ち位置をきちんと意識しながら最終的なスタンスを判断していくことが、出来上がるものと効果・成果に重要な影響を与えるポイントの1つなのではないでしょうか。
人事制度をルールと考えるのかツールと捉えるのか。
皆さまの会社・組織ではどのように考えられますか?
※本稿はCHROFY株式会社のウェブサイトへの私の寄稿を、運営会社の許可を得て転載したものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
