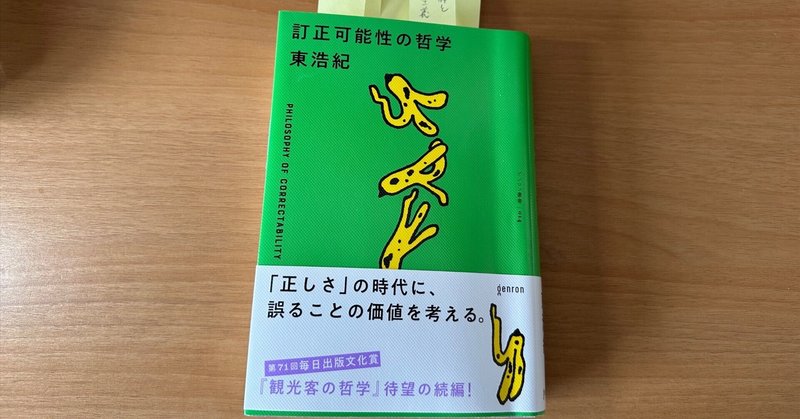
「訂正可能性の哲学」東浩紀著
手元に常においておき、繰り返し読みたくなる本と出会うことは、とても嬉しいことだ。自分の知的好奇心を常に刺激し、考えること、考え続けることを促してくれる。そして、また別の本への興味も掻き立ててくれる。
東浩紀さんの「訂正可能性の哲学」(ゲンロン)はわたし自身が考えてきたこと、疑問に思ってきたことに対して、新たな道筋を付けてくれる極めて優れた本である。
「家族」の再定義
「家族」の問題は、子供の頃から個人的な問題であり続けた。具体的に言えば、父親との関係である。それはわたしのメンタル面で常に大きな影を落とし続けてきた。
わたしの父親は2年ほど前に亡くなっている。亡くなる2年ほど前からアルツハイマー型の認知症を発症し、それ以降は一気に症状が進行して、最後は眠るようにして亡くなった。雪の季節を目前に控え、足が悪い母と、認知症の父の二人きりでは豪雪地帯の冬を越せない、そういうわたしの判断から、それまでデイサービス的な利用しかしていなかった施設に、宿泊利用の形で入所する前日の午後のことだった。わたしの母が、入所前の準備として縫い物などをしていたときで、朝食をほんの少しだけ食べたあと、昼食に声をかけても起きなかったので、そのままにしておいたらしい。しばらくして、寒いだろうからと父に帽子を被せようとして頭を触ったら、あまりに冷たくてようやく母は異変に気づいたらしく、そういう意味では最期は本当に穏やかに、そして自分が頑張って働いて建てた家の自室で亡くなったのだから、本望だったのではないか、と思っている。
わたしは次男である。長男である兄は、かなり以前に両親との同居をやめて関東地方で家族と共に暮らしている。両親とは同居していなくても、わたしが地理的に一番近くに住んでおり、アルツハイマー発症後は特に、病院のことや施設の事など、一番関わってきた。なお、父が亡くなった直後、母は長男家族と一緒に暮らすことになって、わたしがクルマで送っていった。
父親が亡くなったとことで、自分にとっての重石のようなものが失くなった気がしていた。しかし、物事はそれほど単純ではない。
一言で言えば、わたしは子どもの頃から、父親に否定されることばかりが続き、父親に対する反発と、自己肯定感の低さを常に抱えてきたのだ。
今となっては、父親自身がパーソナリティ障害的な性格だったと考えている。それが息子に対する接し方に影響を与えていたのだろうと。
もう一つは、娘3人と息子3人の6人兄弟姉妹の末っ子三男のして生まれ育ち、実家を離れて家族を持ったにも関わらず、自分を起点として「直系家族」を作ろとした。しかし、父にとって姉夫妻が経営する小さな町工場の取締役だったとは言え、自分の長男を跡継ぎとしてその会社に入社させたことが、わたしの兄にとっても様々な軋轢をもたらした。結果として兄は身体を壊して会社を辞め、遠方に引っ越して全く違う仕事をしている。
自分自身の問題意識に対して様々な知識や、考える切っ掛けを与えてくれたのが、ゲンロンでありシラスであった。特に、わたしが考えている家族の問題に関して、最初に知見を与えてくれたのが、シラスのチャンネル、「鹿島茂のナンポルトクワ」で取り上げられた家族人類学者エマニュエル・トッドの家族類型理論である。ちなみに、鹿島茂さんには「エマニュエル・トッドで読み解く 世界史の深層」(ベスト新書)という著書もあり、トッドの家族人類学の入門書として優れている。
ようやく本題にたどり着いた。
わたし自身が家族の問題として捉えていることは、すなわち「直系家族」、特に「父方直系家族」のイデオロギーに起因するところが大きいということだ。
家族類型とイデオロギーには相関関係がある、というのがトッド理論の核心部分の一つである。この視点を持つと、かなり色々なことがクリアに見えてくるようになった。これは、トッド理論を分かりやすく噛み砕いて説明している鹿島茂さんの文章や配信でのトークによるところが大きい。
そして、東浩紀さんもエマニュエル・トッドの家族人類学の理論を踏まえた上で、このように議論を展開している。
家族とは閉じた共同体だと考えられてきた。けれども本論では、家族を、閉ざされた人間関係ではなく、訂正可能性に支えられる持続的な共同体を意味するものとして再定義したい。
そしてその理由を第1章の最後に、トッド理論を踏まえた議論をした上で以下のように書いている。
プラトンも共産主義者もポパーもみな、家族を否定し、自由な個人が集う開かれた社会を構想しようとした。にもかかわらず、みな別の家族のイデオロギーのなかでしか動けなかった。家族という言葉には、そのようにとても強い支配力がある。
家族は狭い。そして小さい。だからぼくたちは家族を超えて社会をつくる。公共をつくる。多くの人がそう信じている。
けれども、これまでの議論は示唆するのは、もしかしたらそんなものはすべて幻で、ぼくたち人間はしょせんは家族をモデルにした人間関係しか作れないのではないかという疑いである。家族のかたちが異なるだけで。
訂正可能性と持続性
持続性は訂正可能性によって担保される必要がある。次のような例がわかりやすいだろう。
前述のような「父方直系家族」が存続の危機にさられるのは、その家族に息子が生まれなかったときである。直系家族において、養子や娘婿も認めない男系の血筋を絶対視していたら、その家族はそこで終わる。そういう意味で、現在の日本の天皇家は持続性の危機にあることは様々な場で語られているとおりである。
また、いわゆる「ミツカン事件」もその文脈で捉えると、非常に象徴的かつ残酷な事例だと言えるだろう。原告である娘婿が敗訴したことも、日本における「直系家族」信仰の強さを物語っていると思わる。
つまり、極端に言うと自分自身の家族に限定しても、家族の定義を訂正しなければ持続不可能になるということだ。
更にいうと、上述の引用に示したとおり、「人間はしょせんは家族をモデルにした人間関係しか作れない」としたら、「家族」を再定義しないとあらゆる組織は持続性を失ってしまう。少子高齢化と人口減少という危機に直面した日本においては、喫緊の課題だと言えるだろう。
ただ、当然ながら「父方直系家族」のイデオロギーを悪だと言うのではない。それを否定したところで、なにも生まれない。だからすなわち、「訂正可能性」の方向に開いていこう、という議論なのである。
家族の再定義というと、わたしが真っ先に思い浮かべるのは、是枝裕和監督の映画「万引き家族」である。是枝裕和監督が描く家族は、常に異形である。この映画で描かれる家族は特に、いわゆる「血の繋がった家族」が絶対的に善で、それ以外はだめなのか、という問題に対して根本的な疑問を投げつけており、とても素晴らしい映画だ。
昨年の映画「怪物」で描かれる家族も異形の家族しか出てこないが、「万引き家族」ほど突き抜けたものではない。映画「怪物」に関しては改めて書こうと思っているが、異形に見える家族は果たして本当に異形だと言い切れるのか、家族としてあり得る形の一つに過ぎないのではないか、そんな疑問を投げかけている。
社会の状況が変わると、家族のあり方も変わっていかなければ、矛盾や軋轢は増すばかりである。
現代は政治に溢れた時代である。地球規模の環境問題から国家間の紛争、個人間のハラスメントまで、毎日のように新しい政治的な問題が提起され、当事者や専門家がそれぞれの立場から正義を叫んでいる。あらゆる問題が論争の対象となり、人々は友と敵に分かれ争っているが、マルクス主義のような大きな枠組みはもはや存在しないので、現実は調べれば調べるほどわからなくなる。それゆえに多くの人々は、すべてを単純な陰謀論で切り取り心の平安を保つか、あるいはすべてに無関心になって麻痺するか、どちらかの状態に陥っているように思われる。それがポピュリズムとフェイクニュースに溢れた現代社会の基本的な条件だ。
今日の正義は、明日の不義になり、誰かの正義は別の誰かの不義である。絶対的な正義にしがみつけば、他の絶対的正義と衝突する。
だからこそ、訂正可能性を常に考えていこう、というのが東浩紀さんの主張だ。つまり、人は常に間違いを犯し、そして訂正してく、その繰り返しの中でしか、個人も家族も、社会や国家ですらも持続しない。
現代社会で生きていく上で直面する様々な問題に対して考える上での論考がこの「訂正可能性の哲学」で、その実践となるのが姉妹書と言える「訂正する力」(朝日新書)である。
過去の自分との対話
哲学とはなにか、と問いながらこの本を書いた。本書の主題である「訂正可能性」は、その問いに対する現時点での回答である。哲学とは、過去の哲学を「訂正」する営みの連鎖であり、ぼくたちはそのようにしてしか「正義」や「真理」や「愛」といった超越的な概念を生きることができない。それが本書の結論だ。
わたしが一般的な意味で「哲学」を学んだのは、大学の一般教育の一科目としてでしかなかった。工学部の電気電子工学科における一般教育の「哲学」は全くわたしには響かなかった。しかし、この「訂正可能性の哲学」や、その前書にあたる「観光客の哲学 増補版」(ゲンロン)に関しては、複数の哲学者の名前やその思想が東浩紀さんによって噛み砕かれ、とても読みやすく、理解しやすく、そしてなにより読むのが楽しい文章になっている。どんな文章を読んで楽しいと思うかは人それぞれであるが、面白く楽しく読める「哲学」があり、自分の知的好奇心や思考をドライブしてくれる本と58歳にして出会えたことは、とてもワクワクする出来事だった。
だからいま、このnoteの場を使って「訂正可能性の哲学」を読んで考えたことを文章にしている。そして、わたしがシラスにチャンネルを開設したことと直接繋がっていることだ。
だから、わたしはこの本によって「哲学」に対する認識を「遡行的に」訂正したと言える。
本書はその意味では、五二歳のぼくから二七歳のぼくに宛てた長い手紙でもある。四半世紀前のぼくは、はたしてこの返信に満足してくれるだろうか。
過去の自分と対話することでしか、自分自身の過ちを受け入れ訂正することはできない。自分の過去をいわゆる「黒歴史」として否定して消し去ろうとしても、逆に黒歴史として固着してしまうだけである。黒歴史だとしても、それも自分自身が歩んできた道だとして受け入れ、遡行的に訂正しなければ黒歴史を黒歴史でなくすことはできない。
上に引用した「訂正可能性の哲学」の締めの一文で、わたしも過去のわたしと対話して、訂正し続けることができるのではないか、そんな気がしている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
