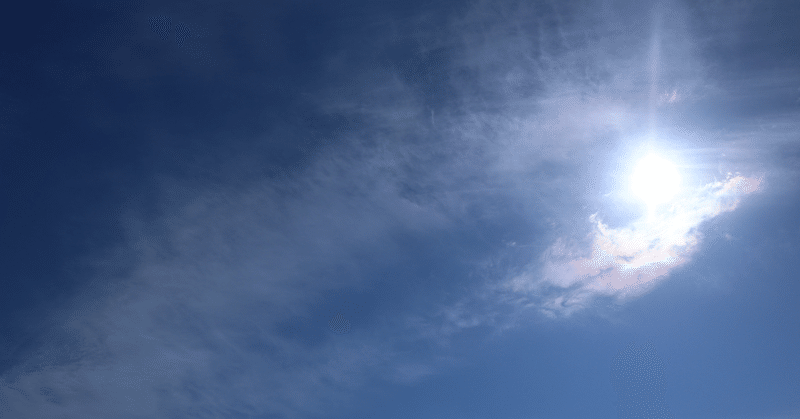
【短編小説】「あんた」に殺された
ゆっくりと瞼を開く。微睡んでいた私の脳内が、ありとあらゆる刺激物に一瞬にして晒されてしまった。否が応でも現実に引き戻される。いつの間にか布団から出てしまっていたらしい、足の指先を擦り合わせた。
20数年酷使した結果、固くなってしまったその皮膚の感触が、確かに自分の肉体であることを指し示している。
そこまで思い至り、ようやく私は完全に睡魔と決別し、目の前の出来事と直面することとなった。
淡く黄色い、蛍光灯。薄い敷布団の上に、申し訳程度にかけられた使い古された薄っぺらい毛布。
かさついた自分の頬に触れる。化粧水まだあったっけ。そうだ、買いに行こうと思ってたのだった。
その思考に辿り着いた瞬間、頭の中でぱちぱちと、あの子の声がした。
**************
「恋人ができた」
へえ、と私は答えた。おめでとう、とも付け加える。気の利いた言葉は私には持ち合わせていない。きっと、生まれた時から決まっているのだ。他人に対してどれだけの言葉を送れるのかは、自分自身ではコントロールできない。
自分の中にどれだけの感情が降り積もっていたとしても、それを言葉にできるかどうかは、まるっきり別の話だ。それを教えてくれたのは、誰でもない、目の前に座っていたあの子だ。
「あんたは?」
不躾な物言いにも、女性ではまだまだ珍しいベリーショートの髪型も、あの子は全てをうまく自分の中に取り込んでいるように見えた。少なくとも、私には。
お金がないなりに、ファストファッションのブランドで、できるだけ「可愛い」の平均値に乗っかるような服を必死になって探す私とは、まるで違う人間だ。
だからこそ、あの子が——彼女のことが大好きだった。
「私に恋人なんて、いるわけない」
「決めつけてんじゃないよ。まして自分のことなのに」
「自分のことだから、尚更でしょ」
その瞬間の、彼女の瞳が忘れられない。侮蔑を含んだ色をしている。最初はそう思ったけれど、本当は私を憐れんでいたのかもしれなかった。
「前にも言っただろ。あんた、そうやって毎回毎回、自分を殺すのいい加減やめな。グロテスクにもほどがある」
私はその言葉に視線を落とした。何年も着古しているシャツがくたびれていることに、急にどうしようもなく恥かしさを覚えた。彼女の洗練された衣服が、私の口を湿らせる。
僅かに持っていたはずの矜持すら、絞り取られてしまったような気持ちに襲われた私は、目の前のストレートティーを一気に飲み干した。
「おめでとう、本当に。お幸せにね」
「ありがとう。あんたには一度会わせたいなと思ってる」
私は薄く笑った。笑ったように、見えていればいい。飲み干しきったカップの不自然なほどにつるりとした表面を、誤魔化すようにして指先で撫でつける。
「そうね。実現したら嬉しい。――いつになるか分からないけれど」
**************
時計の針が、怠惰な私を急き立てる。動かなければいけない。立ち上がらなければいけない。部屋の掃除をしなければならないし、食料品を買わなければならないし、メールをしなければならない相手もいる。
日常は私に対して容赦がない。どんどん浸食し続け、いつの間にか私自身を押しつぶす。
彼女の名前を呟いてみた。世界で一番きれいで、透き通るような美しさの響き。
「すきだったの」
言葉の泡が、私の口の端から漏れた。
私の中に降り積もる言葉は、手垢にまみれきった、陳腐なものしか存在していない。だから、最も近しい言葉を探すなら、きっとそれは「すき」という、ただ一言に過ぎない。
「すき、だったの。そう」
確認するようにして再度口を開く。乾ききった口内に、干からびたような舌先で、軽々しい言葉が躍る。
「私のこと、いつか救い出してほしかった」
瞳を閉じた。自らが作り出せる暗闇の中で、私はひっそりと泣いた。
自分を殺すな。そう言った彼女の言葉の先に立っていた私は、これからどこに佇んでいいのかが分からない。
何もかも溶けてなくなってしまえばいい。そう願っても残る自身の肉体の中に思考を溶かすために、私は再度眠りについた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
