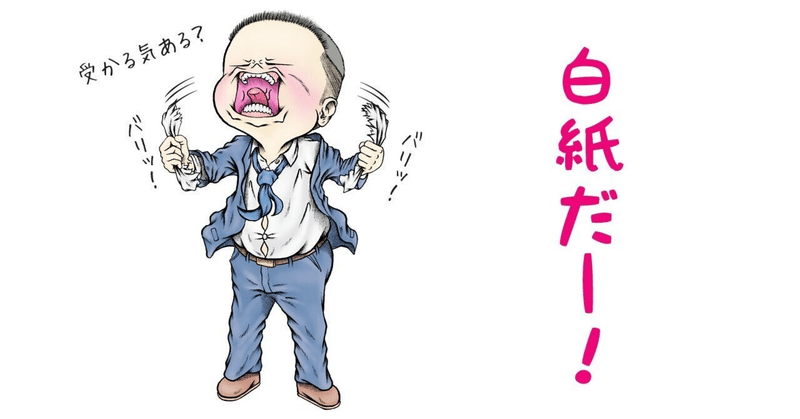
政治(歴史)講座ⅴ1577「秦の始皇帝の政治体制と現代の中国共産党の類似性」
秦の政治体制は画期的な部分があった。
「人治から法治」「文字の統一」「度量衡の統一」「貨幣の統一」の変換は見事なものである。
しかし、統一から15年で滅亡した。
始皇帝もそんなに早く国が亡びるなどとは思ってもいなかったことであろう。しかし実際には始皇帝がこの世を去ったことが世の中に知れ渡った後、国内の各地で反乱の動きが起こり、最終的には反乱勢力に秦が降伏、国が無くなった。
強かったはずの秦。どうしてこうなってしまったのであろうか。様々な理由が指摘されているようですが、一般の人々の間でかなりの不満がたまっていたことや、秦の政権内で出世した特定の人物に相当な問題があったということが秦滅亡の理由として挙げられる。それと国家財政を費用対効果の少ないインフラ工事(万里の長城、兵馬俑、始皇帝陵など)に費やして財政がひっ迫していたと思われる。そのために過酷な税を課したと思われ、同時に違反者には過酷な刑が科されて暴動・反逆を招いた。白紙革命で政変の危機にあった習近平政権は組織防衛のために、益々、締め付けが厳しくなっている。秦の始皇帝時代の政治を彷彿とさせる。
今回は始皇帝の政治体制と習近平政権の類似性に迫ってみる。
皇紀2684年1月2日
さいたま市桜区
政治研究者 田村 司
はじめに
なにしろ、紀元前221年前の事であり、推測を入れなければならないところが多い歴史である。滅亡後の漢の勝者によりつくられた歴史である可能性も多々ある。そこで自己流に現代の中国の政治とその歴史の類似性の解釈をしてみた。
秦の滅亡の要因と現在の中国共産党の類似
大規模な土木工事
始皇帝は、自身の墓、阿房宮、万里の長城の建設に着手し、多くの人々を強制的に動員した。これにより、民衆の不満が高まり、秦王朝は短期間で崩壊した。
現在の中国共産党の指導する中国は、GDPかさ上げのために、過剰不動産投資により、多額の債務をつくっている。その資金は費用対効果にあわない、鬼城マンション(ゴーストタウン)を無数に立てて、融資平台などの外郭団体を使った資金調達が焦げ付いて返済不能に陥ている。不動産崩壊が金融崩壊へと連鎖崩壊している。住宅ローンを借りてマンションを買ったはいいが未完成物件で住めない状態で、住民の不満が溜まっている。そのために、住宅ローンの返済を拒絶する不満を持つ多数の住民が警察により弾圧されている、人民には不満が溜まっていると思われるが情報隠蔽と情報操作で不満を内容に見せている。
法律の強制施行
秦は厳格な法律を採用し、法を破ると王族でも処罰され、法を守り手柄を立てると、どんなに卑しい身分でも褒美があった。しかし、秦以外の六国の法律は、秦とはまるで違った。秦は、いきなり秦の法律を六国の民に押しつけ、多くの人民が処罰された。不満の蓄積の要因となった。
現在の中国共産党の指導する習近平政権はスパイ法や国家安全保安法などで治安を乱すものとして取り締まりを強化している。言論の自由もなく、思想教育の徹底し弾圧している。焚書坑儒と同じことをしている。不正撲滅と称して綱紀粛正を断行し、今までの共産党幹部も粛清の渦中にある。多数の幹部が獄中にある。一説では毛沢東時代に祖先返りしているとか旧ソ連化しているとも言われている。組織防衛に必死なのであろう。
度重なる暗殺未遂
始皇帝は、3回の暗殺未遂に遭遇し、度重なる暗殺未遂により、他人を信用しなくなり、宦官、趙高のようなお気に入りばかりと会うようになりました。それが、最後には、遺言書を趙高に書き換えられる事に繋がり、趙高の保身による、皇族や重臣、将軍の大粛清へ突き進んでいきました。始皇帝が「間違った欲」と「甘言」によって大敵を作ってしまったと指摘しています。また、始皇帝は度重なる暗殺未遂で疑心暗鬼になり、諌める儒家を抹殺し、後継者の育成にも失敗したことが、秦が短期間で滅んだ原因とされている。
今の中国において、習近平氏は暗殺を恐れて、多数の護衛を引き連れて国内や海外に出ている。側近も信用せず、外務大臣や防衛大臣も粛清しているようである。その他、綱紀粛正の名のもとに習近平により大多数の粛清が行われているようである。残念ながら、情報が隠蔽されて全容が不明でる。
中央集権制の弊害
秦は、中国史上初めて、各地に王を置かない、中央集権制を採用し、中国は、一人の皇帝が独裁的な権力を握る帝国になりました。ところが、いざ、反乱が起きると、郡と県の長官は軍を動かす権利がないので、反乱軍と戦う事が出来ませんでした。そればかりか、皇帝と何の血縁もない役人達は、援軍が無いと分ると進んで反乱軍に協力して、自分達も秦に背いたのです。以上のような理由から、秦王朝は短期間で崩壊した。
今の中国の習近平の独裁政権は部下の忖度の弊害があり、意見具申されずに、経済や世界からの信頼が毀損されてきている。そして、海外に対する外交は戦狼外交という悪たれ外交に徹しており、まともに話し合える環境にない。そして、近隣の諸外国には領土拡張の意図を持ち、侵略を繰り返している。
この様に、秦が滅びた理由と現在の中国に共通点が起因となって中国共産党の結末がみえるのである。
今の中国の経済が破綻する可能性を秘めている。その原因はゼロコロナ以降、雇用、消費、輸出入の減少、半導体を巡る米中対立、「一帯一路」(覇権構築)の「債務の罠」と酷評され、反スパイ法の実施で拘束される者がいて、中国への投資リスクにより、それらの投資資金が中国から逃げ出している。このように、組織の権力乱用と横領などでその組織が内部から腐敗していく。その腐敗防止と綱紀粛正で成り立っている習近平政権であるが、独裁色が強すぎて、経済はボロボロになってもまだ、綱紀粛正が強すぎて、粛清される者が多く、結果、忖度や責任転嫁の組織になり下がって、経済破綻まで追い詰められているのである。「水清ければ魚棲まず」である。
「黒い猫でも白い猫でも鼠を捕るのが良い猫だ」と鄧小平は言った。計画経済であれ市場経済であれ資源配分の手段の一つに過ぎず、政治制度とは関係がない。資本主義にも計画はあり、社会主義にも市場はある。生産力の発展に役立つのであれば、実践の中で使用すればよい。この言葉はおおむねこのような意味である。習近平政権は綱紀粛正が過ぎて、粛清の嵐の最中であるが、国民経済の心配はしている気配はなく、中国共産党の組織防衛ばかりしているようであり、そのうち国民による反乱か解放軍からクーデターでも起きるかの権力闘争の気配がするのである。まさに、秦の滅亡と同じ轍を踏んでいるように見えるのである。
(安能 務 著)『始皇帝 中華帝国の開祖』
文:冨谷 至 (京都大学名誉教授)

紀元前二二一年、現在の陝西省の西方地域を本拠地として覇権を争ってきた秦は、東方の諸侯国を平定して全国統一を果たした。
秦が統一する以前の中国は、殷周時代、春秋戦国時代という時代名称で区分されている。その時代は、各地に周王から領地を与えられ周王朝の藩屏の役割を担った独立した国(これを諸侯国という)が存在した。
それは、ちょうど我が日本の室町時代から戦国時代への流れと似ている。つまり京都に足利将軍がいて、そのもとに領土の所有を安堵され自国の兵と法をもつ戦国大名が各地方に存在した。大名の力は次第に強くなり互いに覇権を争い、足利将軍は名目上の存在となってしまい、親族もしくは家来にその地位を奪われる大名も存在した。下克上が出来した時代である。
将軍を周王、戦国大名を斉、晋、楚などの封建諸侯国に置き換えた構図、それが中原に鹿を逐った統一前の情勢にほかならない。
ただし、同じ戦国時代という名称をもつ日本と中国、その後の両国の歴史には大きな違いがある。
日本の戦国時代は、織豊政権へとすすんでいくが、そこでも封建制は継承され地方分権のもと大名は無くならない。しかし、紀元前二二一年統一を完成した秦は、独立した諸侯国を認めず、全国に郡、その下に県をおき、長官は中央から派遣した。換言すれば、郡県制を基盤とする中央集権国家を誕生させたのである。
秦王政は、これまで使っていた「王」に代わって「皇帝」という新しい称号を作り、また死後あたえられる諡(おくりな)をやめて、自らを第一番目の皇帝という意味で「始皇帝」と名のった。ここに、中国史は、以後二千年以上にわたって続く皇帝による中央集権的統一帝国(これを帝政中国と歴史学では呼んでいる)が始まることになる。
帝政中国の共通する制度、それは、皇帝を頂点としたピラミッド状に築かれた官僚制、成文法(律と令)による法治、文書で行われる行政システム、中央に直属した地方行政組織などであり、それらは内容の変化を伴いつつ、二千年の長きにわたって基本構造を変えることがなかった。
かかる中央集権国家体制が、秦によって紀元前三世紀に登場したのだが、現在の甘粛省以西と自治区を除いて今とほとんど変わらない広大な領域に中央集権体制を施行したということ、考えてみれば驚異と言うほかない。
画期的と言ってよい新体制が、始皇帝一人の類(たぐい)まれな才能によって創成され可能となったのか、小説の世界ではそれは面白い題材となるだろうが、歴史学の立場、否、起こるべき常識からすれば、ことがらは、個人の力量では達成できるものではない。
かの万里の長城は、秦一代で築かれたのではなく、戦国時代に北方に位置していた各諸侯国がすでに築いていた対匈奴の防壁をつなぎ合わせ、長城の形を作り上げたのだが、郡県制、成文法、租税制度などの諸制度もこれと同じである。統一に先立って秦をはじめとした諸侯国においてすでに行われつつあったものを統一後、全国に敷いたのであり、始皇帝による「文字の統一」「度量衡の統一」「貨幣の統一」など行政面での統一の命令は、異なる基準をもっていた諸制度を整合するために最初に取らねばならない政策だったのである。
なるほど、既存の建造物をつないだだけの長城なら、さほど困難さを伴わないかもしれない。しかし、こと政治にかんしては、それほどたやすいものではない。「馬上で天下を取ることはできても、馬上で天下を治めることはできない」、これは漢高祖への臣下の忠告だが、旧政権を打倒したものが新しい政治体制を作りそれを進めていくことは至難である。しかし、秦はそれを成し遂げたのである。中央集権化がどうして確立し、また可能だったのか、いまそれを人体に例えて述べるとこうなろう。人体には血液とそれを流す血管があり、心臓から送られる血液は身体の末端まで届き、末端から血液は心臓に還流する。血液そのものに支障が生じたり、体の隅々まで張り巡らされている血管が詰まり硬化すれば、健康体を維持することができず、ひいては死へとつながる。これを国家に置き換えると、中央集権国家(身体)を創成し維持する(健全な身体を保つ)には、皇帝の命令(血液)が地方(身体末端)に行き届き確実に施行されたかどうかの報告(還流血液)が逓伝システム(血管)にのって確(しか)と機能することで、可能となる。それがどこかで不具合が生じると国家は衰退・滅亡(身体の衰弱と死)してしまう。
こういった身体にもたとえられる政治制度を完成させたのが秦であり、この制度さえ構築すれば、個人の力量に頼らずとも政治は行える。それが中央集権国家の誕生を可能ならしめた事由であり、そこに秦王朝の傑出性があると言えよう。
なお、一つ付言しておきたいことがある。それは、皇帝の命令、臣下からの上奏はすべて口頭ではなく、文書でもって執り行われ、また文書の伝達も副本が残されたうえ文書で報告されたということである。文字によって伝達し、文字によって記録が残されることは、検証が可能でありまた責任の所在もはっきりする。文書による行政は、それをおこなう役所と役人の掌握にまことに有効であったのだ。始皇帝は日夜膨大な文書の処理に時間を費やしたとあるのも、あながち誇張とはいえない。秦帝国および始皇帝の事績を知るための史料としては、司馬遷『史記』がもっとも有効と言って過言ではない。このほかには、近年陸続として出土する考古資料があり、それらは、『史記』の記述の確かさを証明していった。さきに述べた始皇帝の文書処理の記事も、出土する膨大な木簡竹簡の行政文書が全く捏造ではないことを示し、『史記』に見える始皇帝驪山陵の内容――広大な地下宮殿、庭園を造り、地下には水銀で河水を作り、魚脂をもって燈火を絶やさず明かりを保った、など――がかの兵馬俑、地下庭園遺跡の出現により、全くの出鱈目ではないことが証明され、また驪山陵の地下の水銀含有量が陵墓域に近づくにしたがって、高い数値を示したという調査結果も『史記』の記事の傍証となっている。
かく、『史記』の史料性は定評があり、始皇帝の政治、事績についての記事は史実性が高いといってもよいが、登場する人間の行動と評価、彼らの人となりに関しては、それを知る術はなかなか見つからない。ここで、『史記』が記す以下の有名な事件を紹介して、史実とはなにかを考える「資料」を提供しよう。
それは、本書『始皇帝』にも書かれている始皇帝臨終の事件である。紀元前二一〇年、始皇帝は外遊先で発病して死亡する。彼には二十人余りの子がいた。長男の扶蘇は人格者であったが、しばしば始皇帝の法治政治に異を唱えたことから、長城の守備隊長として左遷されていた。対して第十八番目の子、胡亥は特別に可愛がられて、外遊にも同行が許されていた。臨終に際して、始皇帝は、一通の遺書を長男扶蘇に残した。
「兵を蒙恬にゆだねて、急ぎ咸陽にもどり、棺を迎えて葬儀をとりおこなえ」と。
扶蘇に葬儀を命じたということは、皇位の継承を認めたことに他ならず、始皇帝は扶蘇の才能を認めて判断を下したとも言えよう。
件の遺書は、封をされたが、まだ使者に手渡されないうちに始皇帝は息を引きとってしまう。遺言書と封に使う皇帝の印は秘書官の趙高の手に残った。この微妙な状況が、以後の歴史を大きく変えてしまう原因をつくる。
遺言書をおのが手に納めて、趙高は胡亥に耳打ちする。
「お上は逝去されました。扶蘇さまに遺言を残されただけで、他のお子様にはなにひとつご配慮がありません。さて、いかが致したものでしょうな。いまや、天下の去就は、私と丞相と、そしてあなたさまの胸ひとつ。ここは、ひとつよくお考えを」胡亥という男は、実に暗愚な人物であり、老獪な趙高にとっては、赤子の手を捻るようなもの、わけなく甘言に乗ってしまう。しかしいまひとり遺言書の内容を知っていた李斯は、ひと筋縄ではいかない。なんといっても国家を代表する重臣であり、秦の法治主義の政策は全て彼によって推進されたのだった。
「お上は崩御されました。ご長男に手紙を送られ、咸陽で棺を迎えて跡継ぎになれとのことです。ただ遺書はまだ発送せず、印とともに胡亥様の下にございます。如何致したものでしょうか」
聡明な李斯にして、趙高のこの言葉が何を意味するのか、瞬時に理解できた。
「そなた、亡国の言を吐くか! 臣下たる者のとやかく言う筋合いではない」
「殿、お考えいただきたい。ご自分と蒙恬、才はどちらが勝っておられるとお思いか?功績はどちらが勝っておられるか? 遠謀熟慮はどちらが勝っておられるのか? 人気はどちらが勝っておられるのか? 扶蘇様のお覚えはどちらが勝っておられるのか?」
「確かに、蒙恬にはおよばぬ。しかし、そなた何故にかくも儂に畳みかける?」
「扶蘇様は、剛毅で武勇が優れて、人望を得ておられます。位につかれれば、蒙恬を丞相にされること間違いなく、貴方様は今の立場に留まることはできますまい。私め、教育係として胡亥様にお仕え致して参りましたが、胡亥様は過失なく、仁愛に富み、聡明で軽薄なことは口にされません。御公子のなかでも希有な人材かと。お世継ぎとして、どうかご賢察を」
「もうよい、さがれ! 某、なき主君の遺詔を奉じ、天の命に従うのみ。他に考えることなどない!」趙高の恐るべき企みを聞かされた李斯は、当然のごとくにはねつける。しかしながら、それで引き下がる趙高ではない。『史記』には、趙高と李斯の息詰まる応酬がなおも展開されて、李斯列伝の圧巻となっているが、強い意志をもった李斯も結局は趙高の説得に屈し、陰謀に荷担してしまうことになる。李斯をしてそうさせたのは、焚書坑儒に代表される始皇帝の苛酷な政治、その推進の責任者は李斯であり、扶蘇は李斯のやり方に反対していたいわば政敵だという事情である。扶蘇が皇位についた暁には、李斯の命とて保証の限りではないかもしれない、趙高のこれが殺し文句であった。
ここに初めの遺言書は握りつぶされ、趙高ら三人による偽の遺言書が作られ、扶蘇のもとに届けられる。偽書の内容は、扶蘇に自殺を命ずるものであり、受け取った扶蘇は、参謀の蒙恬の制止を聞かずに、父の命令ということで命を絶ってしまうのである。かくして、跡継ぎには、趙高・李斯に擁立された胡亥が二世皇帝として即位する。
以上の話は、『史記』秦始皇本紀、李斯列伝に記され、描写が与える臨場感が読者にことがらの信憑性を強く印象づけるのだが、冷静に考えてみれば、腑に落ちないことが多い。趙高の陰謀は、そもそも極秘裏に進められたもの、三人しか目にせずに握りつぶされたはずの遺言書の内容をどうして百年後の司馬遷が知ることができたのか。さらに趙高と李斯の密室の激論を、どうして生き生きと再現することができたのか。『史記』の記述をそのまま事実として信ずることには、やはり躊躇があると言わねばならない。
漢は秦を打倒して成立した王朝である。特に秦の法家主義は、漢が採用した儒学とは真っ向から対立する。いや、対立すればこそ、漢は儒学思想を国家のイデオロギーとして取り上げたのである。秦の儒家弾圧、それは焚書坑儒に代表されるのだが、政策の推進者は李斯であり、それにただひとり、敢然と抗したのが扶蘇であった。このふたりの役回りをもとに、漢代に入って、ことさら秦の暴政とそれによる滅亡を誇張する風潮によって、法家思想に反対する側から作られた話が、始皇帝遺書偽造事件であったと考えられないのか。
ならば、ここで改めて『史記』のフィクション性、歴史の真実とは何かを問わねばならないだろう。そして歴史家司馬遷の『史記』編纂の意図も。
歴史家は史書に記された歴史事象を分析することには長けているかもしれないが、歴史上の人物の実像の描写は、やはり想像と筆致に優れた小説家の後塵を拝することは認めねばならない。
「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算
2022年02月16日 公開 2022年02月17日 更新
石平(評論家)

始皇帝が戦国時代の中国を統一し、自らを皇帝と称して建国した秦は、実はそれまでの王朝とはまったく違う中央集権国家だった。しかし、強大なはずの秦はわずか15年で滅んでしまう。始皇帝の誤算とは何だったのか?
嬴政による「皇帝独裁の中央集権制」の新造
「商鞅(しょうおう)の変法」で富国強兵に成功した秦国は、国王嬴政(えいせい)の指揮下で、前226年から「戦国七雄」の他の6カ国を次から次へと滅ぼして天下統一を果たした。
それに伴って、中国史上最初の統一帝国が創建されたのだが、この新しい統一帝国の主となった嬴政は当然、「国王」という従来の称号に満足せず、自らの新しい称号として「皇帝」を採用した。それは、古来の最高神である「天皇」「地皇」「泰皇」という「三皇」から「皇」という1文字を取り、さらに上古の伝説中の聖君である黄帝や堯・舜などの「五帝」から「帝」の1文字を取って新造した称号である。
この称号を採択した秦王の意図は、宇宙の最高神であり万物の総宰者である「皇皇(こうこう=煌煌)たる上帝」に自らを比擬し、それまで地上に現れたどの君主(帝、天子、王)よりもはるかに優越した地位と権威を天下に示すことにあったと考えられる。これにより、「皇帝」というものが中国史上で誕生したのである。
皇帝となった嬴政はまた、それまでに秦国のなかで原型を整えた郡県制をモデルに、皇帝独裁中央集権制の統治システムをつくり上げて全国で実施した。
全国の土地を諸侯たちに領地として分け与える封建制とは違って、中央集権性の下では、全国の土地と人民はすべて皇帝の領有となり、王朝の直接支配下に置かれる。そして以前の諸侯たちに代わって、各地方の統治にあたるのは皇帝の手足として朝廷から任命される官僚である。
命令はすべて都にある朝廷から発せられ、権力はすべて朝廷に集中していることから、それを「中央集権制」と呼ぶ。そして朝廷の唯一の主はすなわち皇帝であり、意思決定の最終権限は皇帝の手にあることから、筆者はそれを「皇帝独裁の中央集権制」と名付けている。
「一君万民」の政治体制の完成
秦の始皇帝がつくり上げたこのような皇帝独裁中央集権制は、1つの重要な点において、封建制時代すなわち「王の時代」の政治システムと根本的に異なっている。
「王の時代」の封建制においては、殷王朝や周王朝の王は名目上、全国の最高支配者ではあるが、当時の中国すなわち天下は実際、諸侯となった多くの氏族集団によって分割統治されている。
周王朝の王は天下の主権者ではあるが、唯一の主ではない。各地方では、公・侯・伯・子・男の爵位をもつ氏族集団の長が貴族としてそれぞれの領地を治めている。
しかし皇帝独裁の中央主権制の下では、各地方を治める氏族集団はもはや存在しない。秦の始皇帝は天下を統一したのち、滅ぼされた6カ国の貴族たちを全員、首都の咸陽(かんよう)に移住させて統治システムから排除した。そして、排除された貴族たちに代わって各方を統治するのはすなわち、守・令・尉など、皇帝の任命で朝廷から派遣された官僚である。
つまり「皇帝は唯一の主、人民と官僚のすべては僕である」という、いわば「一君万民」の政治体制が秦王朝において出来上がったのである。
政治のリスクをすべて背負うことに
このような政治体制の下では、皇帝が唯一の主として全国の人民を直接支配下に置いておくから、皇帝は当然、人民の生活と全国の政治に対して全責任を負う立場となってしまう。
良き政治が行なわれて人民の生活が安定して国が安泰であれば、それが「皇帝の徳」の表れと見られて皇帝が「聖君」と賛美されるが、政治が乱れて人民の生活が苦しくなると、皇帝が逆に「昏君」と思われて不平不満が皇帝のほうに集まってくるのである。
「王の時代」の封建制においては、殷や周王朝の王の代わりに全国の各地方を実際に治めるのは諸侯となる貴族たちであるから、政治に対する責任が分散されている。失政に対する人民の不平不満は王に対してよりも、人民を直接に支配している各諸侯のほうに集まってくるであろう。
つまり、封建制においては政治に対する責任が分散される一方、失政のリスクも各諸侯によって分担されている。だが、中央集権制の下では皇帝が唯一の主人と支配者であるから、皇帝自身が政治に対する全責任を持ち、すべてのリスクを背負うことになっているのである。皇帝は政治の全責任を負わされる代わりに、絶対的な権力と権威も手に入れている。
わずか15年で滅亡した秦王朝
しかし後述のように、皇帝が手に入れたこのような絶対的権威と権力こそ、皇帝と彼の王朝を破滅へ陥れる深い罠になっていくのである。
上述のように、秦の始皇帝が創建した中央集権の政治体制においては、「王の時代」の王とは比べにならないほど皇帝の権威と権力が極度に強化され、すべての政治権力が皇帝に集中させられた。このような体制が出来上がると一見、人民に対する皇帝の政治支配が盤石なものとなり、皇帝独裁が揺るぎのない永久のものとなっているかのように見える。
実際、秦の始皇帝が自らを「始皇帝」と称するのも、自分の死後に子孫たちの皇帝独裁が「二世皇帝」「三世皇帝」へと永遠に続くことを念頭に置いているからである。
しかしのちの歴史の展開は、この絶対的な権力者の意にまったく反するものであった。陰謀で王朝を握った趙高
秦王朝の驚くべき早い滅亡は、いったいどういうものだったのか。ここで、王朝が崩壊していくプロセスをもう少し詳しく見てみよう。
前述のように、秦の始皇帝が死去したのは前209年であるが、じつはその時、彼は地方視察の道中にいた。彼の死後、宦官の趙高(ちょうこう)と丞相の李斯(りし)が共謀して皇帝の死を伏せておき、皇帝の詔書を偽造した。
本来なら皇位を継ぐべき太子の扶蘇(ふそ)に対しては亡き皇帝の命令として死を賜わる一方、始皇帝の遺言と偽り、末子の胡亥(こがい)を新しい皇帝に擁立した。
この陰謀を主導したのは趙高である。胡亥は太子の扶蘇よりはるかに暗愚であることと、趙高自身が胡亥の教育係を務めたことがその理由であろう。つまり趙高にとって、胡亥はたいへん御しやすい存在だったのである。
はたして胡亥が秦二世となって即位すると、王朝の全権は趙高が握ることとなった。前述のように、秦の始皇帝がつくり上げた皇帝独裁の中央集権制において、皇帝は絶対的な権威と無制限の権力を持つ存在となっている。
だが、肝心の皇帝自身が暗愚で操られやすい人間である場合、臣下の誰かが皇帝を精神的に支配してしまえば、皇帝の持つ無制限の権力がこの臣下の手に丸ごと移ってしまうこともある。
じつはそれは秦の時代以来の中国史上、無数の弊害をもたらした「皇帝の落とし穴」の1つであった。その始まりは、まさに趙高と胡亥の関係にある。
中国史上初の農民反乱「陳勝・呉広の乱」
皇帝の胡亥を完全に操ることによって、趙高は権力の頂点に登り詰めてわが世の春を迎えた。だがまさにその時、王朝の土台を根底から揺るがす大事件が起きた。
前209年7月、現在の安徽(あんき)省宿州(すくしゅう)市付近の大沢郷で、強制的に徴兵されて北部国境の防衛に向かうはずの農民900人が、陳勝と呉広をリーダーにして反乱を起こした。
道中に大雨に遭い、定められた期日通りに目的地に到着することができず、処刑される恐れがあったことから、どうせ死ぬならいっそのこと、と思い切って決起した。すなわち、中国史上最初の農民反乱「陳勝・呉広の乱」の勃発である。
反乱軍は直ちに大沢郷を占領したのちに周辺の諸県を攻略して、戦国時代の楚の国の首都であった陳を占領した。その時、反乱軍はすでに騎兵1000余、兵卒数万の大勢力に膨らんでいた。
そして乱の飛び火が直ちに全国に広がり、各地で農民を中心とした民衆が秦の官吏を殺して蜂起し、全国に及ぶ秦王朝の中央集権的支配が音を立て崩れていった。
あっけなく帝国が滅亡
秦王朝の政権中枢はすでに末期状態であった。全権を握った宦官の趙高が丞相の李斯を殺したのち、自分の操り人形である秦二世にもついに手を下した。秦二世の死後、趙高は秦三世として皇族の公子嬰を擁立することにしたが、公子嬰が即位する直前にまず趙高を殺して、その一族を滅ぼした。
しかし公子嬰は、咸陽の城下に迫ってきた反乱軍に対してもはやなすすべもない。前206年の年明けから間もなく、公子嬰は皇帝のシンボルである玉璽を首に掛けて城外に出て、それを劉邦軍に献じて降伏した。全国統一を果たしてから15年、陳勝・呉広の乱が起きてからわずか2年半、あれほど強大にして盤石のように見えた秦帝国があっけなく滅亡したのである。
権力の逆説
秦王朝の滅亡を招いた人民の大量徴用を主とする秦の始皇帝の暴政を見ると、それを可能にしたのは、まさに彼自身がつくり上げた皇帝独裁の中央集権制の政治システムである。つまり「王の時代」の政治支配と根本的に異なる秦王朝独自の政治体制にこそ、秦王朝の早すぎた崩壊・滅亡の最大の原因があるのである。
本来、「王の時代」の殷王朝や周王朝の王の権力と比べれば、秦の始皇帝が創建した中央集権制において皇帝の権力は絶大であり、全国の官僚組織と軍隊をその手足として駆使できるほど強固なものとなっている。
しかし、まさにここにおいてこそ権力の逆説が生じてくるのである。「王の時代」とは比べものにならないほど皇帝の権力が強固で絶対的だからこそ、皇帝は人民を苦しめるような暴政を思う存分、行なうことができた。しかしその結果、暴政に苦しむ人民の反乱が起きて秦王朝が滅亡への道を辿ったわけである。
始皇帝による皇帝政治の確立こそ災いの始まり
じつは秦王朝が全国を統一して成立した当初、王朝のなかでは「殷王朝や周王朝と同様の封建制を採用すべきではないか」との意見もあった。しかし宰相の李斯がこれに猛反対し、秦の始皇帝自身も封建制の復活にあまり興味がなかった。結局、皇帝自身の権力の絶大化につながる中央集権制が創建された。
歴史にイフはない、とよくいわれるが、もしその時点で始皇帝が中央集権制ではなく封建制を帝国の政治システムとして採用していたら、その後の秦王朝の歴史はどうなっていただろうか。少なくとも、わずか15年で滅ぶようなことはなかったのではないか。
しかし、結果的に秦王朝は皇帝独裁の中央集権制を採用してしまった。その結果、王朝創建から15年後、始皇帝自身の死去からわずか2年半後、彼のつくった秦王朝は、中国史上最も短命な王朝の1つとして滅んでしまった。こうして見ると、秦の始皇帝による皇帝と皇帝政治の確立は、まさに秦王朝にとっての災いの始まりだったのである。
参考文献・参考資料
始皇帝は“暴君”ではなく“名君”だった!? 驚きの政治体制とは 『始皇帝 中華帝国の開祖』(安能 務 著) | 書評 - 本の話 (bunshun.jp)
「皇帝政治」が災いの始まりだった?わずか15年で秦を滅亡させた始皇帝の誤算 | Web Voice|新しい日本を創るオピニオンサイト (php.co.jp)
政治講座ⅴ1508「盛者必衰の支那、秦の始皇帝と同じ短命の運命」|tsukasa_tamura (note.com)
政治講座ⅴ1553「秦の滅びた理由と組織の寿命」|tsukasa_tamura (note.com)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

