
本の落ち穂をためつすがめつ【エッセイ】
二十代のとき、私は埼玉県にある会社の寮に住んでいた。職場の二階に六畳のスペースを与えられ、すべての家財をそこに詰め込んで数年間暮らした。
本好きだった私の部屋は、いくつかの衣裳ケースとパイプベッド、14インチのブラウン管テレビとミニコンポ以外は、すべて本とCDと雑誌にまみれていた。
ある日、後輩のK森くんが私の部屋をノックした。K森くんは、青森県出身で映画と洋楽を愛好する純朴な青年だった。私の部屋に彼が訪ねてくるのは珍しいことだった。
ちょうど私は、小さな折りたたみ式のテーブルに向かって小説を読んでいた。自分にとっては日常であり、何も特別なことをしているわけではなかったが、K森くんにはそうは見えなかったらしい。
「どうぞ」という私の声に、ドアを開けて顔を出したK森くんは、テーブルに向かっていた私と目が合った瞬間、「ええーっ!」と声を上げてたじろぐ様子をみせた。
何をそんなに驚いているのか訊ねると、K森くんから意外な答えが返ってきた。
「だって、海亀湾さん、本を読んでるんだもの。本を読む人って、自殺する人じゃないですか」
私は仰天した。何かしらの深遠な誤解が根本に生じていて、勉強以外で普段から本を読む人は、もうじき自殺を図る人だという思い込みが彼にはあったようなのだ。
私は破顔した。ひとしきり笑ったあと、大丈夫だ、心配ない、と彼に伝えた。いったいどのような経緯で小説と自殺を結びつける誤解が起きたのかはわからなかった。玉川上水で女性と情死した津軽出身のあの有名作家とK森くんが同郷であることと何か関係があるだろうか、とも思ったが、本当の理由を訊ねないでいるうちに、彼は退社して故郷に帰ってしまった。
今でも、私はこのときのK森くんの言葉をときどき思い出す。世の中には本を読んで絶望を知り、実際に命を絶った人もいるだろう。しかしそれ以上に、世の中には本によって救われた人がたくさんいるように思うのだが。
さて、あちこちに散らかしている読み終わった本の感想文、それを拾い集めたのがこの「本の落ち穂」である。興味が向いたものだけでも拾えるように目次を設定した。
最近の新しい本は少ないが、そこは温かい目でみてもらいたい。
■今回拾い集めた十冊
1.『河童・或阿呆の一生』
芥川龍之介 新潮文庫 1968

この作品集を最初に手に取ったきっかけは、たしか宇多田ヒカルが芥川龍之介の『河童』が面白いと話しているのを、何かで読んで知ったからというミーハーな理由だったと記憶している。
芥川の後期の作品が集められているせいか、収録作には妙に印象に残るものが多かった。アフォリズムやいくつもの断章で構成されている『或阿呆の一生』は逐一格好いいし、友人や妻と三人で浜辺を歩く『蜃気楼』は読み返すたびに味わいがある。だが、もっとも精神をわしづかみにされてしまうのは『歯車』だ。この作品は怖い。非常に危険物である。わるいことは言わない、心が弱っているときは読まない方がいい。
2.『素粒子』
ミシェル・ウエルベック 野崎歓訳 ちくま文庫 2006

ミシェル・ウエルベックという名はそれまで聞いたこともなかったのだが「文學界」2007年5月号に掲載された『ミシェル・ウエルベック、不可能の探求者』という記事を読んで興味を持った。中原昌也氏に「ウエルベックは毎回、読みたくないけど、読んでしまう作家なんです」と語らせてしまう作者が書くものとは、いったどういう小説なのか興味が湧いたからだ。
最初に読んでみたのが当時唯一文庫で購入できたこの『素粒子』だった。正直、私はぶっ飛んだ。性格の違う異父兄弟の家庭環境、子供時代、性の遍歴、人生の光と影を、微塵も飽きさせることなく読ませてしまう筆力と斬新な手法の数々に圧倒されてしまったのだ。そして終盤は時代が近未来に移りSFのテイストで驚きのビジョンを見せてくれる。最後のページを閉じた私は、強い衝撃を受けて放心したような状態と、途轍もない傑作を読んだときの興奮した状態だった。
これ以降、私はウエルベックを無視することができない体になってしまった。
3.『ヴィヨンの妻』
太宰治 新潮文庫 1950

太宰治の中で一番好きな作品は何かと訊ねられたとき、『魚服記』と迷うが私はこの『ヴィヨンの妻』を最終的に選ぶような気がする。個人的にもっとも太宰らしい小説だと思うからだ。自分の身辺を題材にした私小説めいた作品だが、実は作り事であることをしっかりと意識して書いている気がする。この本には収録されてないが、太宰の『メリイクリスマス』という短編も同様の印象がある。
『トカトントン』は奇妙な小説だが、強く印象に残った。この作品の最後にある某作家の返信は、一度では理解できなくて何度も繰り返し読んだが、未だに消化できていない自分がいる。
4.『樽』
F.W.クロフツ 霜島義明訳 創元推理文庫 2013
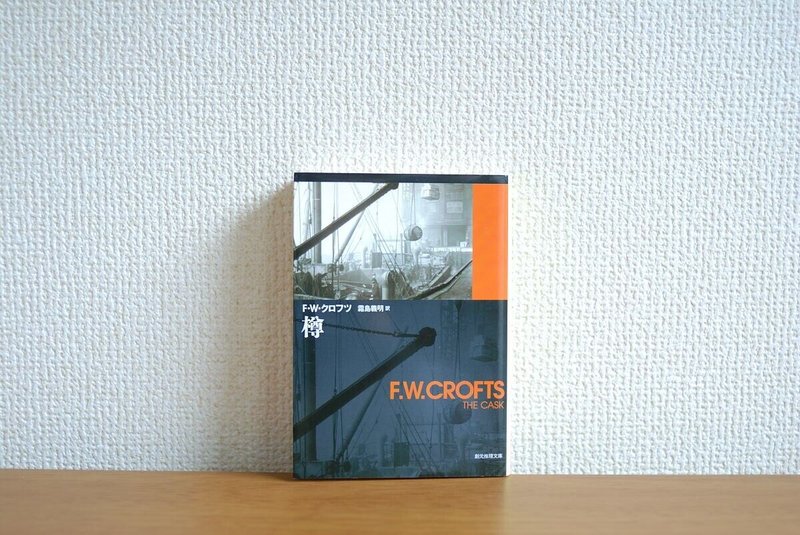
小説を読んでいて、その中に登場する小説が気になって実際手に取ってしまうことがある。『ノルウェーの森』を読んでいてトーマス・マンの『魔の山』が気になったり、『ライ麦畑でつかまえて』の最初に出てくるディケンズの「デーヴィッド・カパーフィールド」に興味を覚えたり。
堀江敏幸の『河岸忘日抄』を読んでいたらクロフツ の『樽』が気になったので、実際に読んでみたくなった。久しぶりの海外ミステリーの古典。そして、アリバイトリックの名作。
横溝正史の『蝶々殺人事件』はこの作品に影響をうけたものだと小耳に挟んだことがある。なるほど、と思う。
『樽』はアリバイのトリックも面白いが、死体の登場の仕方が最高に美しいと思った。まさにトレビアン。
5.『罪と罰』
ドストエフスキー 工藤精一郎訳 新潮文庫 1987
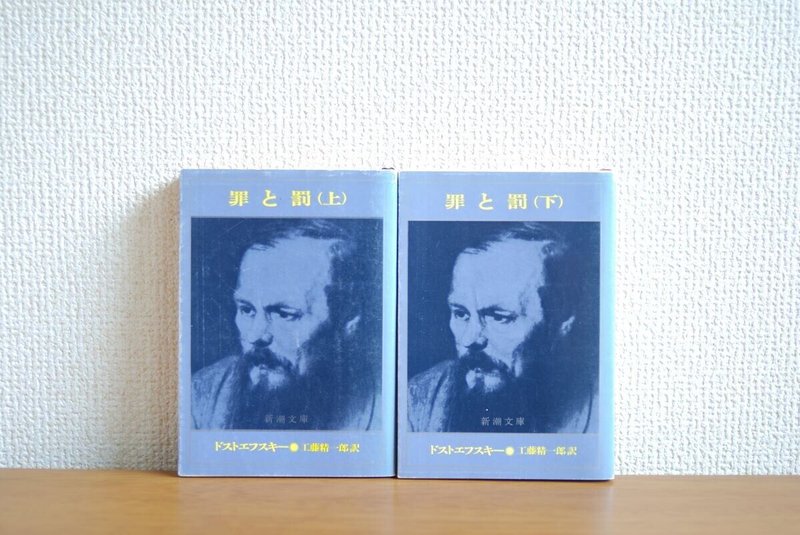
露西亜文学とドストエフスキーに初めて挑戦したのは二十代の後半だった。
最初に戸惑ったのは名前の変化だった。知らないうちに人物が増えて、それが同一人物だと気付かずにしばらく読んでいた。
会話文が長いことにも戸惑った。ひとりで延々と語り倒し、いったいこの人物のおしゃべりはいつ終わるのだろうと思った。
でも事件が起こると面白いと感じることはあり、読むページが進んだ。だが依然として名前での混乱は続き、一人語りも長く、たびたび読書は中断した。
そんな調子で読んでいたら読了に三年かかってしまった。あまりに長い時間をかけてしまうと、どういう内容の小説を読んでいるのか自分でもわからなくなってくる。
三年はかかり過ぎだと反省した。
6.『桜の森の満開の下・白痴』
坂口安吾 岩波文庫 2008

全部で十四篇の作品が収録されているが、坂口安吾の小説を堪能できる一冊としては、岩波文庫のこの作品集が一番バランスがいいと感じる。
まずは表題作の『桜の森の満開の下』『白痴』だが、言うまでもなくこの二つは安吾の代表作だ。
執筆に難渋したと言われている『女体』『恋をしにいく』という続きものの作品も入っているし、GHQの検閲を受けた『戦争と一人の女』『続戦争と一人の女』という男女で視点を交代させた傑作も読める。
『風博士』『アンゴウ』でミステリーの風味を味わい、『青鬼の褌を洗う女』という安定の名作も外していない。
何より個人的に安吾の中で一番好きな『夜長姫と耳男』を読めることが嬉しい。狂人、化け物、蛇、流行り病。出てくるものは禍々しいが、最後は愛が頂点に達する。ああ、自分もこんな風なエンディングの小説を書けたらなあと思う。
7.『羊と鋼の森』
宮下奈都 文春文庫 2018

宮下奈都『羊と鋼の森』は、単行本のときから本屋に行くと目立つ場所に並んでいる本だった。気になっていたので、文庫が刊行されると飛びつくように買ってしまった。
前知識がない状態で読んだのだが、ページを繰る手を休ませない筋の運びと文章力がまず素晴らしい。黒いピアノと鍵盤を弾く音が森のイメージに収斂して、主人公の原風景と重なる丁寧な筆致に感心した。
私がこの小説で注目したのは、前半、主人公が尊敬する調律師に、どんな音を目指すのか訊ねる場面だ。調律師はそこで原民喜の言葉を引き合いに出すのだが、それはそのままこの作品を書き進める作者の姿勢に共振しているように感じられた。原民喜が憧れる文体を、作者はこの作品で体現していると思った。
8.『スティル・ライフ』
池澤夏樹 中央公論社 1988

昭和の終わり頃に書かれた小説だが、冒頭の警句のようなあるいは詩のような文章は今読んでも格好良く、つい真似をしたくなる。だが本当に真似をすると赤っ恥をかくことになるだろう。雰囲気は真似ることができても、この洗練までは真似ができないと思うからだ。
実際『スティル・ライフ』は真似をしたくなる小説だ。この作品を読んだあと、すぐに酒場のカウンターに座って水の入ったグラスをじっと見つめてみようと思った人はいるのではないだろうか。実は私がそうだった。
「何を見ている?」
「ひょっとしてチェレンコフ光が見えないかと思って」
私は『スティル・ライフ』このやり取りに、強烈に憧れたのだった。
また、冬の季節に軒先で除雪作業をしているとき、真っ直ぐに牡丹雪が降っている静かな日は、作業の手を止めて、雪の落ちてくる上空を見つめていたくなる。そして、雪が降るのではなく、自分がこの空間を上昇しているような感覚になるまでじっと佇むのだ。私はこれに『スティル・ライフごっこ』と名付けているのだが、誰からも理解されたことはない。
9.『私はあなたの瞳の林檎』
舞城王太郎 講談社文庫 2021

舞城王太郎の純愛小説『私はあなたの瞳の林檎』他二篇。
私は表題作で、主人公の戸ヶ崎直紀と同級生の鹿野林檎が、小学校最後の春休みに濃密な二週間を過ごすエピソードが好きだ。
クラスの中で距離を取っていた二人が、急に毎日会い続けて積み上げる思い出の日々。この挿話にノスタルジー以上のものを感じてしまう。
人によってはどうということのない内容かも知れないが、すれ違いの過程も含めて、このエピソード全体が心の琴線に触れてしまった私は、折あるごとにこの作品を読み返している。好き過ぎる。
10.『詩人と女たち』
チャールズ・ブコウスキー 中川五郎訳 河出文庫 1996

失業中に訪れた市内の図書館にその本はあった。
『詩人と女たち』。魅力的なタイトル。作者はチャールズ・ブコウスキー。
単行本は上下巻があり、私はまず、上巻を手に取った。最初のページから引き込まれた。書架の前で立ち読みしたまま一時間は経っていた。途中でやめられなくて、近くにあった脚立に座って読んだ。図書館の窓に午後の日差しが傾いて、夕方の気配を帯びてきた。気付いたら、上巻を一気に読んでしまっていた。長らく読書をしてきたが、こんなにも憑かれたように読み耽ったのは初めてだった。
作者の名前をもう一度確かめる。
チャールズ・ブコウスキー。
出会ってしまったと思った。これがブコウスキーか。
書架には下巻もあったが、手には取らなかった。
上巻を戻して、急いで図書館を出た。そのまま本屋に向かう。こういう凄い本は、自分の手元においておくべきだ。
本屋で見つけた『詩人と女たち』は、一冊にまとまった文庫本になっていた。
急いでレジで支払い、包装のカバーは断った。なるべく早く家に帰って続きを読みたかったのだ。
あれから二十年以上が過ぎた。私は今でもこの小説と出会ったときのことを忘れられない。
今回の「本の落ち穂シリーズ」は以上です。
拾い読みして下さった方、十冊全部のレビューを読んで下さった方、ありがとうございます。
また懲りずに投稿するかも知れません。
前回の「本の落ち穂」のリンクを図々しくも下に置いておきます。筆者
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
